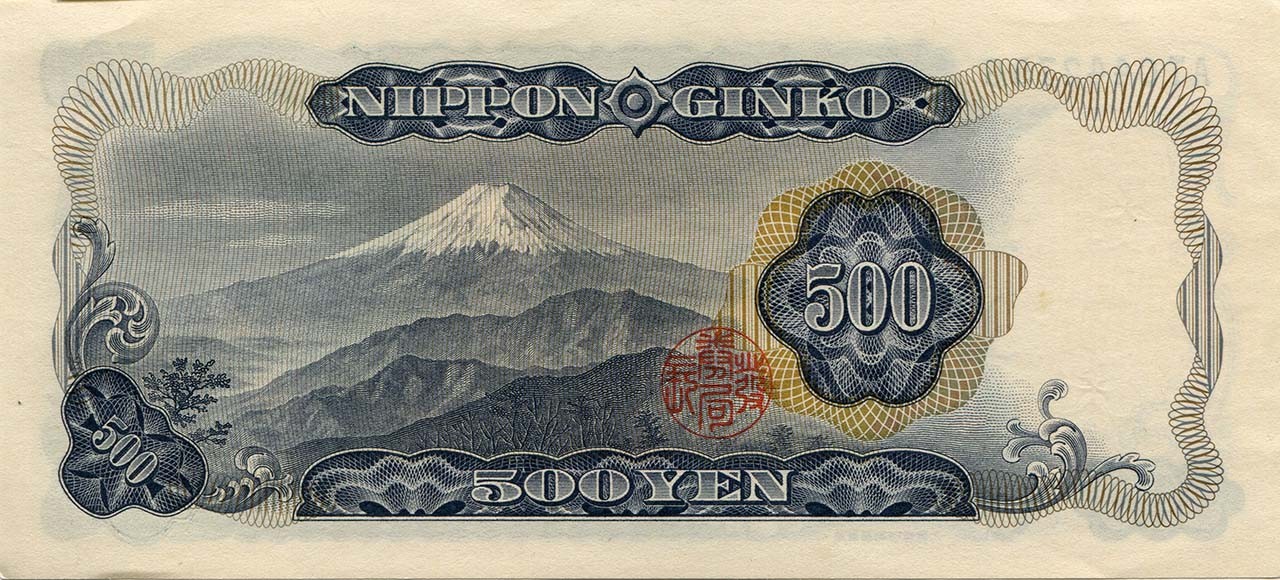1911年(明治44年)のこの日、日本橋が木橋から現在の石橋に架け替えられ、その開通式が行われた。
開通式は午後1時から行われ、天候は小雨にも関わらず、大勢の見物客が押し寄せた。その数は100万人とも言われ、あまり群集が殺到したため、ケガ人が出るほどの騒動だった。
日本橋について
日本橋は、江戸時代に東海道・中山道・日光街道・奥州街道・甲州街道の五街道の起点となった橋である。初代の木造の日本橋は1603年(慶長8年)に架けられた。
日本橋は地名にもなっているが、江戸の中心にあり、街道の起点であることから、その名前が付けられたといわれている。また、江戸の中で最も賑わう場所として、浮世絵による風景画に多く描かれた。
江戸は火事が多く、木造の日本橋は幾度も焼け落ち、現在の石造の日本橋は20代目に当たるとされる。その日本橋は石造りのアーチを2つ並べた形で、道路橋梁としての技術的な完成度の高さと、欄干部に施された和漢洋折衷の装飾が評価されて、1999年(平成11年)に国の重要文化財に指定された。
橋の中央には「日本国道路元標」の文字が埋め込まれており、裏側には当時の内閣総理大臣・佐藤栄作(さとう えいさく、1901~1975年)の名前が刻まれている。