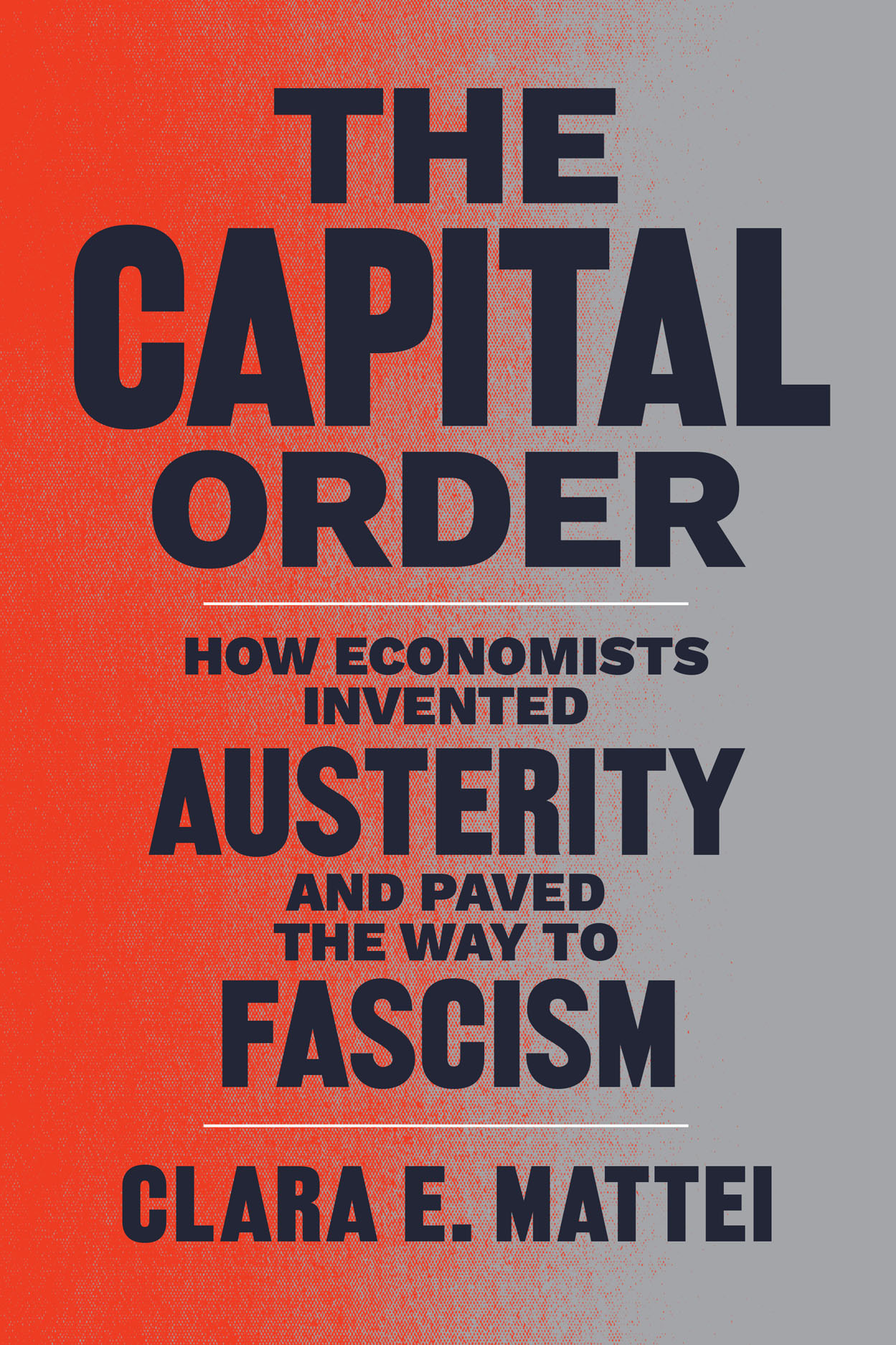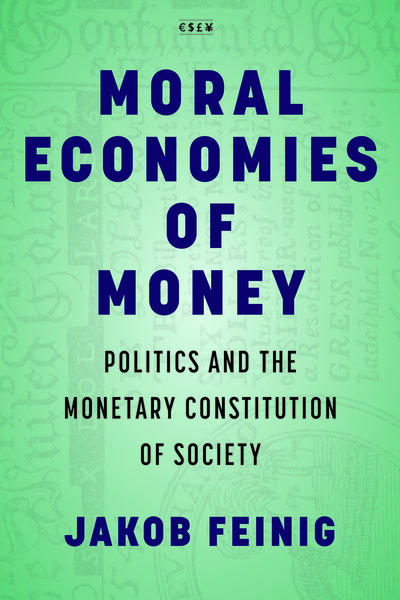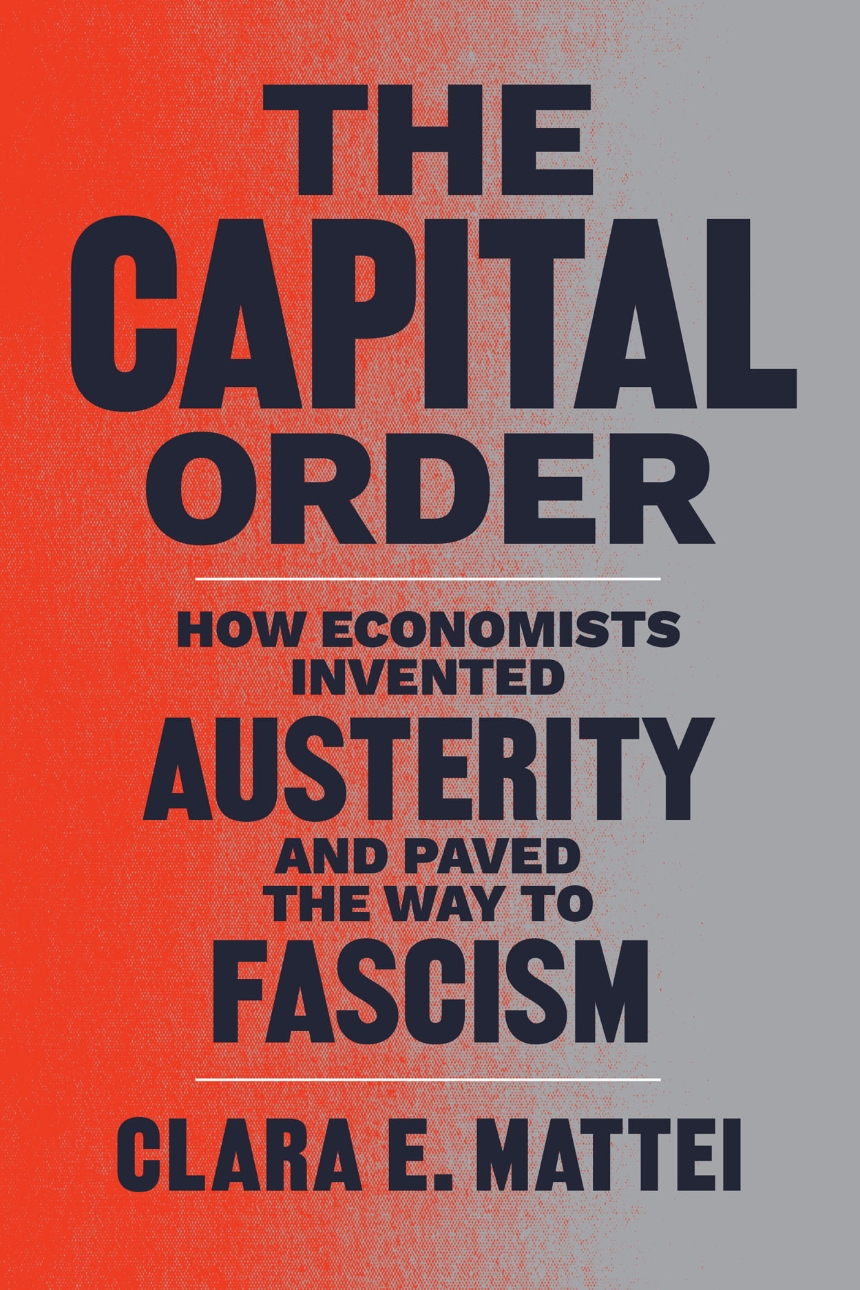
資本命令
経済学者はどのようにして緊縮財政を発明し、ファシズムへの道を切り開いたのか
クララ・マテイ
「将来への重要な教訓を含む必読の書」―トーマ・ピケティ
緊縮政策の暗い知的起源についての画期的な考察
昔も今も緊縮財政
戦間期の英国における金本位制の復活と緊縮財政は、
特定の政治家や経済学者の決断の結果であると示唆する最近の報告とは対照的に
マテイは、この歴史を国家と階級の対立で蘇らせている。
マテイは新古典派経済学のイデオロギー的基礎を前景化し
資本主義の財産関係を守るために国家権力と密接に絡み合っていることを実証する。
この意味で、『資本命令』は緊縮財政に関する最近の学術文献の進歩を表しており
緊縮財政の思想的および技術的特徴が、その広範な政治的および
社会的基盤から抽象化されることがよくある。
マテイの研究は 緊縮財政の起源を明らかにするという点で最高のものであるが
現在に至るまでのその驚くべき耐久性を説明する点ではあまり役に立たない。
マテイは今日の緊縮財政に関する最終章で、20世紀の経済史をケインズ主義と
マネタリズムの対立として語るという一般的な傾向を見事に打破している。
むしろ、私たちの現代は戦間期との根本的な連続性によって定義されていると
彼女は示唆する。
これを一貫して説明するために、マッテイは、緊縮財政を強化し
資本主義の財産関係を民主政治から守るための
最良の政治メカニズムであり続けているテクノクラシーの存続を強調している。
マテイがテクノクラシーを強調するのは適切である。
パンデミック以降の金融引き締めの最新サイクルが示しているように
選挙で選ばれていない中央銀行のテクノクラートが
依然として緊縮財政の執行の指揮を執っている。
実際、英国とイタリアの政治における最近の出来事は
マッテイの理論を裏付けている。
英国では、2022年末のリズ・トラスの疑似サッチャリズム実験を受けて
テクノクラート権力の驚くべき回復が見られた一方
イタリアでは、政治的リーダーシップがドラギのテクノクラシーから
緊縮財政へのコミットメントを肯定した真のポスト・ファシストへと揺れ動いている
マテイは、本の終わりの方で読者に「古い習慣の中には、消えないものもあります」
と思い出させてくれる。
それでも、1920 年代から 2020 年代までの緊縮財政の政治経済を、途切れることのないテクノクラートの反革命として概念化するのは、まったく正確ではない。
緊縮財政を明確にするための正統性と大衆政治のメカニズムは
1920 年以来大幅な変化を遂げた。
戦間期の緊縮財政の押し付けは、主に金本位制の構築とそれに伴う均衡予算の命令を通じて強制されたが、国民の監視や監視のチャンネルはほとんどなかった。
『資本秩序』は、この秩序に対する戦闘的な民衆の反対運動の
爆発を追跡しているが、この時期は多くの点で
未来の青写真というよりも、民主主義以前の時代の頂点と
反資本主義左翼の衰退を示していた。
この時期、緊縮財政はしばしば資本と労働者のあからさまな対立を引き起こし
資本主義と民主主義の間の将来の解決が非常に疑わしいものとなった。
このような状況では、緊縮財政は、一部の支配階級が行使する
階級支配の武器であることがより明白であった。
しかし、ファシストの空位時代、大恐慌、第二次世界大戦による破壊の余波で
ヨーロッパと北アメリカの資本主義民主主義は大幅な見直しを経験した。
戦後のアメリカの覇権の後援の下でフォーディズム的資本主義が植え付けられると
経済政策は大衆政治の仲介機関を通じて屈折し
緊縮財政の階級的性格が曖昧になり、政治的支持と反対の新たな軸が生み出された。
戦後を通じて、西側諸国の政党は戦間期の政治的急進主義の多くを脱ぎ捨て
成長、福祉協定、企業主義的な資本労働協定を中心に再編を行った。
政治家が戦後復興に伴う社会改革を徐々に認めるにつれ
民主主義資本主義の支配的なイデオロギー構造として「イデオロギーの終焉」が
階級闘争に取って代わり、政治的対立はより拡散した。
この期間はおそらく、現在の緊縮財政の耐久性を評価するための
より有望な出発点を提供するだろう。
金本位制の時代とは対照的に、大衆の権利が存在せず
労働者階級の男性にまで広がったのはごく最近のことだったが
戦後の「民主的資本主義」は大衆の政治
(決して平等ではないが)と経済の道を広げた。
政策は国民とより緊密に一致するようになった。
西洋における大衆政治の時代、緊縮財政にはより強固な基盤が必要だった。
寡頭自由主義の残滓は、特に中央銀行の役割において
戦後を通じ、経済政策を形成し続けたが
今日の緊縮政治に関する説得力のある理論は、それが現代の自由民主主義制度の中でどのように再生産されているかを説明しなければならない。
彼らは今、新自由主義者の猛攻撃の余波の中にいるかもしれない。
マテイは、緊縮財政は不合理な政策原理ではなく
階級支配のメカニズムとして理解されなければならないことを重要視しているが
新古典派経済学の役割とマクロ経済政策に対するテクノクラート権力の
持続的な集中に対する彼女の強調は、今日の緊縮財政の回復力を
部分的に説明しているにすぎない。
日本の左派・左翼は、「ザイム真理教」に洗脳され
「財源は」と問われて、右往左往し、緊縮財政を支持してしまっている。
ポピュリスト左派が出てきたけれども
その「れいわ新選組」の支持は、あまり広がっていない。
立憲民主党は、超がつくほど緊縮財政だし
共産党は、財源を細かく出しているが、それは緊縮財政そのものだ。
財政政策をめぐる問題は、思いのほか根深く
もはや階級闘争になっているのかと思わされる。
日本の左派・左翼の人々の政治的論点は、実に多岐にわたり
経済政策、財政政策を転換、特に積極財政への関心が薄い。
これでは有権者も困り果ててしまう。
自民・公明が嫌でも、投票先がない。
特に、年金財政をなんとかするのが左派・左翼の役割なはずだが
これを言っているのは、日本じゃ保守派なんだよな。
財政政策が、もう階級闘争になってしまっているなら
左派・左翼の出番なのに、この人たちが「ザイム真理教」に入信している点が
日本の大問題なのだと思ってしまう。
#森永卓郎 氏が 財務省や緊縮派が吹聴する嘘を暴露
— 桃太郎+ (@momotro018) July 25, 2023
『必要があって増税してるわけではまったく無い。#ザイム真理教 の教義で「増税しないとハイパーインフレが起きる」と言ってるが、日本に借金なんかないんです「貯金してるのに借金で首が回らないんで増税させろ」と訳の分からない理論を言っている』 pic.twitter.com/nXoamCNlF0