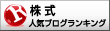トレードの本を読むと、必ず、損切りが大切だと書いてありますね。
「エントリーしたら、必ず、すぐに逆指値を入れなさい」
「あらかじめ損切りポイントを決めておいて、そこまで下がったら、問答無用で損切りしなさい」
など、とても強い口調で「絶対に損切りしなければならない」と教えていることも多いです。
でも、損切りって、どうして必要なのでしょうか?
ちょっと予想に反して下がっただけで、何故、わざわざ損を確定させないといけないのでしょうか?
良く言われるのが、
「損切りするのは、これ以上、損が拡大することを防ぐため」
という理由です。
ストップロス(これ以上のロスをストップする)、という訳ですね。
でも、たいていの場合は、株価はそのうちに戻ってきて、損せずに済むことも多いです(^^;
例えば、150円で買った株が、もし、140円まで下落したら損切りする、と決めたとしましょう。

確かに、その後も株価が下がってしまうのなら、傷が浅いうちに、140円で損切りするのは分かります。

でも、その後にまた150円に戻ってくることも多いです。
それなら、わざわざ140円で売らずに、150円まで戻ってきてから売った方が良いですよね。

時には、150円まで戻るだけでなく、180円、200円と、上昇してしまうこともあります。
これでは、140円で売ってしまうのは、最悪の結果になってしまいます。

ストップロス(損が拡大することを防ぐ)のために損切りする、という考え方には、問題があります。
損切りに、正解と失敗ができてしまうからです。
もし、140円で損切りした後に、株価が130円、120円、と下がってしまったのなら、損切りは正解だったことになります。
ですが、140円で損切りした後に、すぐに株価が戻って、200円まで上昇してしまったら、損切りは失敗だったことになってしまいます。
これは、損切りする時に、迷いを生じます。
「140円まで下落したけれども、ここで損切りするべきなのか?」
「今回はもっと下落するのだろうか?それとも、すぐに戻るのだろうか?」
という判断を迫られてしまいます。
また、損切りした後に株価が戻ったら、「失敗した!」という後悔の感情も生まれてしまいます。
損切りは、ストップロス(損が拡大することを防ぐ)のためにするのではありません。
トレード手法を遵守するためにするのです。
あなたのトレード手法は、勝てる手法ですよね?
そうであれば、トレード手法に従って、エントリーするべき時にエントリーし、手仕舞いするべき時に手仕舞いするだけです。
そうすれば、トータルで勝てます。
勝てる手法なのですから、その通りにやれば良いのです。
利益が出ていても、損していても、同じ手仕舞いです。
たまたま、買った時よりも株価が上がってから手仕舞いしたら、利食いに見えますし、たまたま、買った時よりも株価が下がってから手仕舞いしたら、損切りに見えるだけです。
この考え方であれば、損切りを躊躇うことは無くなります。
また、損切りした後に株価が戻っても、後悔することは無くなります。
トレード手法の通りに手仕舞いできた時点で、損切りはすべて正解になるからです。