ゆう@子育てパパ
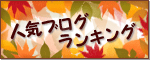
人気ブログランキングへ
マツダの乗用車試乗会で自動ブレーキ機能が作動せず発生した衝突事故が波紋を呼んでいる。事故原因については操作ミスか、構造上の欠陥かは現時点で不明だが、新たな安全技術として期待される「自動ブレーキ」の普及に水を差したのは間違いない。今回の衝突事故は“未来のクルマ”といわれる自動運転技術の実用化にも影響を及ぼす可能性もある。
想像してもらいたい。障害物に向かって走行する乗用車。ブレーキを踏まなくても自動的に停止する瞬間は、止まると分かっていても本当に怖いものだろう。しかし、それが予想に反して止まらず、そのまま障害物に激突。それは想像を絶する恐怖のはずだ。そんな事故が11月10日、埼玉県で開かれた自動ブレーキ機能を体験する試乗会で発生し、運転手と助手席に乗車していた男性2人が重軽傷を負った。
車は、マツダのスポーツ多目的車(SUV)「CX-5」。自動ブレーキ機能を体験するため、7メートル先の障害物に見立てたウレタン製マットに向かって走行したが、停止せず、さらに前方の金網フェンスに衝突した。
マツダの自動ブレーキ機能「スマート・シティ・ブレーキ・サポート」は、時速4~30キロで走行中、前方の障害物を検知して作動する。同社が事故後に公表した資料によると「障害物の大きさや種類・距離、周囲の環境、車速、ドライバーの運転操作により正常に作動しない場合がある」としており、具体的には雨や霧などで前の車を感知できないとき、アクセルを強く踏み込んだときなどだ。
現在、埼玉県警が調査を進めており、一部には「運転者によるスピードの出し過ぎ」という報道もあるが、現時点で事故が運転操作のミスなのか、それともシステム上の欠陥なのか明らかになっていない。とはいえ、重軽傷者を出したことで、「原因が何であろうと新たな安全技術として脚光を浴びる自動ブレーキの普及に水を差したのは間違いない」とある業界関係者は話す。
マツダだけでなく、トヨタ自動車、富士重工業など自動車各社は、「衝突回避システム」と呼ばれる自動ブレーキ機能を開発。一部車種への標準およびオプション搭載を始め、新たな付加価値と位置付けている。それだけに今回の衝突事故は「もしも運転手の操作ミスが原因だったとしても自動ブレーキ機能に対するイメージは間違いなく低下する」と前出の関係者は指摘する。
自動ブレーキ機能については、テレビCMなどで一躍脚光を浴びるようになったが、実は不具合も少なくない。6月には、トヨタ自動車と三菱自動車が相次ぎ自動ブレーキについてリコール(回収・無償修理)を国土交通省に届け出た。
高級セダン「クラウン」など約2万台をリコールしたトヨタによると、前方車両との距離や速度は車のレーダーから発せられる電波によって検出されるが、電波の乱反射で前方ではなく、並走する車両について誤って認識し、ブレーキ機能が作動してしまう恐れがあるという。つまり、自動ブレーキ機能が作動せず衝突したマツダ車のケースとは反対に、隣の車にも反応し、誤作動で止まってしまうというのだ。ブレーキは、人間を守るという自動車の中でも最も重要な安全装置。それが自動ブレーキに進化した途端、ブレーキが作動せず衝突したり、突然ブレーキが作動して後方車両に追突されるとは皮肉な話だ。
ただ、業界内には「今回の事故で自動ブレーキについて補助機能という正しい認識が広まるきっかけとなることを期待したい」(自動車メーカー担当者)との声もある。つまり、自動ブレーキは「運転支援」と位置付けられており、あくまでもドライバーの安全運転が大前提。それは自動ブレーキ機能が周囲の環境、車速、ドライバーの運転操作など、さまざまな制約を受けるためで、「ぜひ過信しないでほしい」(同)というわけだ。
実際、ある外資系自動車メーカーが日本で放送した自動ブレーキ機能をアピールしたCMには苦情が殺到したという。これは車を運転中の有名ミュージシャンが街中で知人を見つけて脇見運転をしてしまうが、自動でブレーキがかかり、衝突を回避。自動ブレーキを搭載した車ならば、脇見運転をしても大丈夫ととられかねない内容に仕上がっていた。
「何も知らずにあのCMを見れば、自動ブレーキは絶対安全と思い込んでしまう。実際にそう思っている一般の人も少なくないはずだ」。自動車業界をよく知るアナリストはこう説明した上で「それだけに事故に遭った2人は災難だったが、今回の衝突事故で自動ブレーキに対する過大な期待が変われば同じような事故は減る」と指摘する。
自動車業界では今、各社による「自動運転技術」の開発競争が激しさを増している。自動ブレーキも自動運転を実現するための基幹技術のひとつだが、今回の衝突事故で分かったようにまだ発展途上の補助技術という域を脱しない。自動運転技術の実用化にむけては、各社ともスピード感をもって取り組んでおり、「(今回の事故が)大きな影響を及ぼすことはないだろう。ただ、利用者の意識は『まだ自動技術には頼れない』という風に変わったかもしれない。メーカー、ドライバーの意識が同じように上がって、自動車の安全性が高まっていくことが重要だろう」とメーカー関係者は話している。
- 「危険感じるほど速い」と噂のスーパーカー 限界攻めるベンツ「AMGブラック」
- 社会変える日本発の「自動運転車」 圧巻…人間では不可能な反応速度
- 前代未聞だった現代自の欠陥新型車 雨漏り、燃費水増し…お粗末なクルマづくり
- 首相、自動運転車に試乗 「日本の技術は世界一」
- ITで車の安全向上 各社が最新技術 ITS世界会議