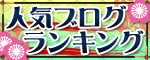
人気ブログランキングへ
秋本俊二の“飛行機と空と旅”の話:
私たちの乗った便は、成田を離陸して順調に飛行を続けている。気流も安定し、フライトの妨げになるような雷雲などもルート上にはしばらくなさそうだ。もちろん、万が一機体にカミナリが落ちたからといって、そう慌てる必要はない。「旅客機と空港のQ&Aシリーズ」第3弾は、まずはこの落雷の問題にスポットを当ててみよう。
【画像:主翼や尾翼に装着されたスタティック・ディスチャージャー、ほか】
●旅客機にもカミナリは落ちる?
旅客機にもカミナリは落ちるのか? よく、そんな質問を受けることがある。「落ちます」というのが、その答えだ。──といっても、心配は要らない。以前取材したある機長も、こう話していた。
「フライトでは気象レーダーで飛行ルート上の雷雲をあらかじめキャッチし、それを回避して飛んでいますが、雲の多い日や悪天候の中ではごくまれに“被雷”することもあります。その場合に大事なのは、到着してから整備士に報告し、機体を十分に点検してもらうこと。機体の外観や通信装置、アンテナなどの入念なチェックを怠らなければ、カミナリは大きな問題ではありません」
機長も「被雷」という言葉を使っていたように、エアラインの世界では「落雷」とは言わない。カミナリは“落ちるもの”とは限らないからだ。平地で見ていると雷光は上から下に走るが、目標物さえあればカミナリは横にでも上に向かっても攻撃してくる。では、飛行中に旅客機が被雷した場合、乗客になぜ危険はないのか?
カミナリで人に被害が及ぶのは、それ受けて電気が身体を通り抜けたときである。その際に重いやけどを負ったり、ショックで心臓が停止して死に至ることがある。しかし機内の乗客は、金属でできた機体自体に保護されているため、安全なのだ。
カミナリが鳴ったときは車の中にいるといい──などとよく言われる。これは電気を金属ボディを通して地面に逃がしてしまうためで、同じことが旅客機にも当てはまる。
また飛行中は、大気との摩擦で旅客機の機体に静電気が生じる。この静電気が計器類や通信機器に影響を及ぼす可能性があるため、防止策として主翼や尾翼など機体の数カ所に静電気を放電させる「スタティック・ディスチャージャー」と呼ばれる装置が装着されている。スタティック・ディスチャージャーは長さ10センチほどの細い棒状のもので、飛行中にカミナリを受けてもこのスタティック・ディスチャージャーが避雷針の役割を果たすのだ。この放電装置が、中型機では20~30本、大型機では計50本も取り付けられている。
●座席のテーブルは傾いているって、ホント?
離陸して1時間が経過し、水平飛行に移ると、キャビンでは食事のサービスが始まった。水平飛行とは、翼に生じる揚力(上へ引っ張る力)と機体にかかる重力(下へ引っ張る力)が釣り合っている状態である。しかし巡航高度に達して水平飛行に移っても、そのときの角度は厳密には「0度」ではない。
最新の旅客機にはFMS(フライトマネジメントシステム)というコンピュータシステムが搭載され、その日のフライトに最適な「経済速度」がコンピュータで算出される。推力レバーもその速度で飛ぶよう自動でコントロールされるが、推進力が絞られると前に進む力が弱くなり、そのままでは必要な揚力を維持できない。そこでFMCは、同じ飛行高度を保つために機首の角度を調整するよう制御コンピュータに指示。すると機体は、水平飛行とはいっても、機首をわずかに上に持ち上げた格好で飛行を続けていくことになる。
このときの進行方向に対する機体の角度を「迎え角」、機首を上げたり下げたりして角度を変える操作を「ピッチ・コントロール」という。では、旅客機はどれくらいの「迎え角」で巡航飛行を続けるのだろうか?
旅客機は経済速度を維持するため、巡航高度でも通常2.5~3度の迎え角で飛行を続ける。これが最も効率よく飛ぶときの旅客機の姿勢と考えていいだろう。ちなみに、離陸して上昇していくときの迎え角は、国際線では15度程度。それに比べると3度というのはごく小さく、その程度の傾きにはまったく気づかない人もいる。
しかし感覚の鋭い人なら、化粧室に立ったときなどに多少の違和感を覚えるかもしれない。水平飛行中に通路を歩いてみると、前方へは上り坂のように、その反対は下り坂のように感じるはずだ。
さて、上空でのミールサービスの話に戻ろう。3度も傾いていると、そのぶん座席のテーブルに置いた飲み物などもこぼれやすいのでは? そんなふうに心配する人もいるだろうが、大丈夫。どのエアラインも新しい旅客機を導入するときには、座席のテーブルもあらかじめ3度ほど前下がりに傾斜をつけて設置している。次のフライトで、ぜひ観察してみてほしい。じゃあ、地上ではどうなのか? それも心配ない。巡航高度での飛行に移らないと、テーブルを引き出すことはまずないのだから。いや、でも一つだけ──地上でのウェルカムドリンクの際には、前にこぼさないよう少しだけ注意が必要かも。
●機長と副操縦士の食事はなぜ別メニュー?
機内食の話をもう一つ。キャビンのギャレー(厨房施設)で乗客への食事サービスの準備が始まると、その何ともいえないいい香りがコクピットにも漂ってくる。そして客室でのサービスがひと通り終わる頃、客室乗務員の一人が機長と副操縦士に食事の注文を聞くため、コクピットに現れる。
「どうする?」と、機長が隣の副操縦士に聞く。「どちらか、好きなほうを」「いえ、機長からお先にどうぞ」「そう。じゃあ、私は和食で」
すると副操縦士は、必然的に洋食メニューを選択することになる。機長と副操縦士は、同じメニューの食事をとることができないからだ。必ずそれぞれ別の種類を選ばなければならない決まりになっている。その理由は──。
夏場になると、よく集団食中毒のニュースがマスコミを賑わす。臨海学校などで子供たちがいっせいに腹痛を起こし、ダウンしてしまうといったニュースだ。全員で同じ食事をとっていれば、ときに集団で食中毒になるという危険は免れない。
しかし、フライト中のコクピットで機長と副操縦士が同時にダウンしてしまっては、操縦をフォローする人がいなくなる。操縦桿を握る二人がともに食中毒で倒れるような事態は絶対に避けなければいけない。もちろん機内食作りでは専門のケータリング会社が安全衛生面にも万全を期しているが、万が一どちらかが体調を崩しても残った一人が支えられるよう、機内では別々の食事をするルールができているのだ。
ちなみに、コクピットでは二人が同時に食事をとることもない。一人が食べ終えるのを待ってから、残った一人が食べ始める。
●窓から見える“虹の輪”の正体は?
食事が終わり、あとはシートでゆっくりくつろぐ。座席に設置された個人モニターで映画を楽しんだり、ときどき窓のシェードを上げて外を眺めたり。窓から見えるのは雲と海ばかりという日が多いが、ごくまれに不思議な光景に遭遇することがある。客室乗務員として国内外の空を飛びつづける知人からも先日、こんなメールが届いた。
「飛行機の窓の外に真ん丸い“虹の輪”が見えて、お客さまに聞かれることも何回かありました。あれは何なんだろう、って。虹が丸いのも驚きなのですが、その輪の中に飛行機の影が小さく映り、私たちといっしょに同じ速度で移動しています。いつも思うのですが、とても神秘的な光景です」
この“虹の輪”──飛行機を利用することの多い人なら、一度か二度はご覧になっているかもしれない。私もメールを読んで、ずっと以前にキャビンの窓から写真に撮ったことを思い出し、古いファイルの中から引っ張り出してみた。薄い“虹の輪”の中に、飛行機の影が映っているのが分かるだろう。さて、この不思議な現象の正体は?
これは、いわゆる「ブロッケン現象」と呼ばれるもの。飛行機に太陽の光が当たると、その光が機体を回り込んで反対側に進んで雲のスクリーンに影を映し出す。山頂などでもよく見られる現象で、太陽を背にして立ったときに、自分の影が前方の雲や霧に浮かび上がることがある。周囲に色のついた光の輪が出現するのは、空気中の水滴によって光が屈折するからだ。
ところで、メールをくれた知人によると、国内線での乗務で“虹の輪”に遭遇するのは瀬戸内海の上空あたりが多かったとのこと。そして客室乗務員の間では「“虹の輪”に出会うと幸せになれる」という噂があるそうだ。
ちなみに“虹の輪”が見えるのは、太陽が出ているのとは反対側の窓側席。また、雲に映し出される飛行機の影を見るわけだから、太陽が真上にあるときにはなかなか遭遇できない。時間帯は、朝や夕方の太陽が傾いている時間がベストだ。次のフライトの際には、みなさんも目を凝らして探してみてはいかがだろうか。
[秋本俊二,Business Media 誠]
- 「秋本俊二の“飛行機と空と旅”の話」
- 飛行機の便名につけられた数字のルール、知ってますか?
- 上昇中の機内で耳がキーンと痛くなるのは、どうして?
- 機長が荷物運びを? シートの背もたれが倒れない? LCCの“格安”のヒミツ
- “激安運賃”で注目のLCC。安全性は本当に大丈夫なのか?