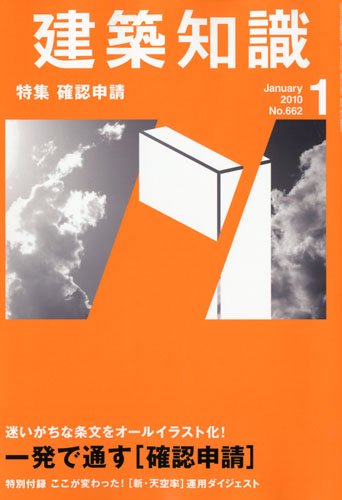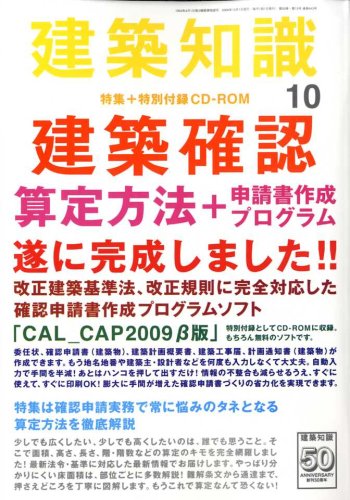ブログをはじめました。
はじめまして、色葉(いろは)一級建築士事務所です。
建築士を目指す方を対象に、ちょっとした豆知識を書いていこうと思います。
宜しくお願いいたします。
では、さっそく始めます。
今日は道路台帳から幅員を計算する方法をお伝えいたします。
ただの数学の内容なので、おさらいとして確認してくださいね。
まず、
↓こんな感じのもの。
道路の状況や埋設物など、道路に関する諸々の情報を図面や調書にまとめたものを道路台帳といいます。
基本的には各行政の路線課や道路課などで1分程度で取得できます。
※ちなみに今まで50以上の行政をまわってきましたが、過去唯一1分以上かかった行政があります。
それは足立区です。あそこは日本ではないのかもしれません。一時間以上かかるので、気を付けましょう。
これを取得して道路幅員を調べます。
基本的には行政で「管理幅員」というものを各路線ごとに決めているので、
「管理幅員はいくつですか?」と聞けば良いのですが、
「道路台帳によります」との返答があった場合は、道路台帳からしらべます。
たいていの道路台帳には幅員は記載されていません。
計るか計算するか台帳の図面をCAD化してCAD上で計ります。
道路が求積図で管理されていれば、素人の方でもその通りにCADに写して計ることが出来ますし、
求積図を基に垂直距離が算出できるでしょう。
実はそれは座標で管理されている場合も同じです。
座標を基に図面を書くことも計算することも出来ます。
ただ、実施設計や高さ制限が厳しい時で無ければ、とりあえず幅員を算出すれば問題ありません。
ですので座標を基に幅員を計算する方法を簡単に説明しますね。
※座標をもとに図面を書く方法はまた後日お伝えします。
まずは、下記のような道路平面図と座標があります。
朱い線で書かれた距離を計算します。
ここからは、もう記憶の片隅に追いやってしまった高校数学を思い出しましょう。
必要なポイントはK5・K10・K4です。
K5・K10のポイントを通る直線に対しK4の垂直距離を測ります。
なんか聞き覚えありませんか。
これ高校の時に勉強しましたよね。
動くP点てなんだよ、とか思いながら勉強しましたね。
今回のP点は動きませんが、それを思い出しましょう。
K5を(x₁、y₁) K10を(x₂、y₂) K4を(x₀、y₀)とします。
これを
y-y₁=(y₂-y₁)/(x₂-x₁)×(x-x₁)
に算入してK5K10の直線の方程式を作ります。
次にこれを
ax+by+c=0
の式にしましょう。
最後に
d=(ax₀+xy₀+c)÷√(a²+b²)
これに入力しましょう。
計算していくと
≒6,529mm
となります。
一度やってみてくださいね。
以上、お読みいただきありがとうございました。
参考までに、私がいつも仕事で参考にしている資料を載せておきます。
↓プランニングの際に、法令集と告示だけで判断できないときは、これを調べましょう。
これでも判断できないときは、この書籍を携えて審査機関と相談になります。
↓消防関係については、まずこちらを読みましょう。
その上で各行政で予防火災条例を取り決めていますので、そちらも読みましょう。
↓天空率についてはこれ!付録でついてくる天空率のダイジェスト版をいまだに使っています。
↓面積表の作り方はいまだにこれを参照にしています。
とてもわかりやすいです。
※最後の2冊については、10年以上前になりますので、現法と照らし合わせながら確認してくださいね。
以上、もしよければ購入してってくださいね。