新課程チャート式基礎からの数学1+A/数研出版
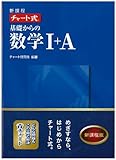
¥1,966
Amazon.co.jp
最低限の教材に関する情報として、中堅以下の一貫校で配られる事が多い青チャートと、上位校で副教材として配られる事が多い1対1について触れておきます。
青チャートはほとんど計算や処理の作法を学ぶことに主眼が置かれている問題集です。定石の暗記も一部含まれますが難しいことはほとんどありません。4stepや体系数学から1対1につなげるために使われるのが通常で、もともと処理が速い、筑駒・灘・開成と言った進学校に通う子にとっては(中学受験時にそのエッセンスとなる訓練を既に終えているので)あまり意味をなす問題集でもありません。
他方で殆どの学生にとってはまずこの作業的な訓練を通じて半ば強制的に処理能力を引き上げていく必要があり、また(中学受験時に手を抜いていたり、もともと向いていない場合は)そのプロセスが追加されるため、これを越えるために多くの時間を割くことになります。一部の中堅から下位に位置する一貫校が予備校化しているのにはこうした原因があります。学校の予備校化は頭を硬くさせると言う意味において褒められた話ではありませんが、プロセスの重さから、自分から率先して学ぶことが出来ないこともまた多いため、学校側が必要悪として予備校化の方針を敷いてしまうというのもまた事実でしょう。
1対1対応の演習/数学1 新訂版 (大学への数学 1対1シリーズ)/東京出版

¥1,188
Amazon.co.jp
1対1は東大・京大および旧帝大と単科医大の医学科を除けば、合格ラインを確保するために超える最低限の山として多くの学生に認識されています。いわゆる縦割り学習の最終地点です。学年のセンター平均が86-8%程度となる学校では、これが通常授業の副教材として渡されているのは、収録されている殆どの問題は定石ばかりであるためです。とはいえ、殆どの学生にとっては分量と答案の長さから(と言っても型は決まっているのですが)、特に、学校のカリキュラムがしっかりしていない女子校等では息切れしてしまうことも多い、あるいはここまでが限界、ということが多い問題集でもあります。
大学以降の数学に触れ、意識すると言う意味合いにおいては、この二つの問題集をこなすことはいわば準備運動に過ぎないのですが、上記の通り多くの学生が労力を割く必要が出てくるため、その先にいく事が出来ずに終わってしまいます。一番の原因は丁寧に受験に備えていこうとすると、定石を網羅的に学ぶ必要があり、記憶しなければいけない情報量が増えることにあります。これで頭が一杯になってしまう学生がまた大半でもあり、それが「数学」を学ぶということなのだと認識が支配されてしまうこともまた問題です。
そして殆どの父兄の皆さんにとっての「数学」の「難しさ」は、この水準を指し示しているのが通常です。また横断的な理解が身についていないため、わが子に対しても「勉強しろ」と言い放つばかりで、元来の数学の奥深さの一端を感じさせるような学習への促しが出来ない大きな理由にもなっています。
cocではこうした難易度の問題は自習を課し、通常授業では問題数を絞って認識の仕方に柔軟性をもたらすことに時間を多く割いていますが、個別指導ではこれを軸に扱うことも多くあります。数学が苦手な子、手を出そうとは思っているのだけれどもなかなか腰が重くて・・・と考えている子は、個別指導をご検討いただければと思います。
またこの先にある学びはもっと楽しいものになりますから、こうした難易度における学びと同時並行して出来る学びを cocではメインで提供しつつ、モチベーションを維持し続けられるような指導を提供しています。これについては別の記事で触れたいと思います。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

HP http://www.classoncloud.jp
facebook https://www.facebook.com/classoncloud.jp
mail customer.classoncloud@gmail.com
体験授業は土曜17:00から随時定期的に実施しています。
どうぞお気軽にお問い合わせください
>>>体験授業のお問い合わせはこちら
説明会・食事会も定期的に実施しています!高校生・大学生が主な対象となります。
>>>食事会へのご参加はこちらから
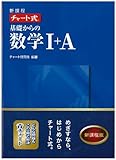
¥1,966
Amazon.co.jp
最低限の教材に関する情報として、中堅以下の一貫校で配られる事が多い青チャートと、上位校で副教材として配られる事が多い1対1について触れておきます。
青チャートはほとんど計算や処理の作法を学ぶことに主眼が置かれている問題集です。定石の暗記も一部含まれますが難しいことはほとんどありません。4stepや体系数学から1対1につなげるために使われるのが通常で、もともと処理が速い、筑駒・灘・開成と言った進学校に通う子にとっては(中学受験時にそのエッセンスとなる訓練を既に終えているので)あまり意味をなす問題集でもありません。
他方で殆どの学生にとってはまずこの作業的な訓練を通じて半ば強制的に処理能力を引き上げていく必要があり、また(中学受験時に手を抜いていたり、もともと向いていない場合は)そのプロセスが追加されるため、これを越えるために多くの時間を割くことになります。一部の中堅から下位に位置する一貫校が予備校化しているのにはこうした原因があります。学校の予備校化は頭を硬くさせると言う意味において褒められた話ではありませんが、プロセスの重さから、自分から率先して学ぶことが出来ないこともまた多いため、学校側が必要悪として予備校化の方針を敷いてしまうというのもまた事実でしょう。
1対1対応の演習/数学1 新訂版 (大学への数学 1対1シリーズ)/東京出版

¥1,188
Amazon.co.jp
1対1は東大・京大および旧帝大と単科医大の医学科を除けば、合格ラインを確保するために超える最低限の山として多くの学生に認識されています。いわゆる縦割り学習の最終地点です。学年のセンター平均が86-8%程度となる学校では、これが通常授業の副教材として渡されているのは、収録されている殆どの問題は定石ばかりであるためです。とはいえ、殆どの学生にとっては分量と答案の長さから(と言っても型は決まっているのですが)、特に、学校のカリキュラムがしっかりしていない女子校等では息切れしてしまうことも多い、あるいはここまでが限界、ということが多い問題集でもあります。
大学以降の数学に触れ、意識すると言う意味合いにおいては、この二つの問題集をこなすことはいわば準備運動に過ぎないのですが、上記の通り多くの学生が労力を割く必要が出てくるため、その先にいく事が出来ずに終わってしまいます。一番の原因は丁寧に受験に備えていこうとすると、定石を網羅的に学ぶ必要があり、記憶しなければいけない情報量が増えることにあります。これで頭が一杯になってしまう学生がまた大半でもあり、それが「数学」を学ぶということなのだと認識が支配されてしまうこともまた問題です。
そして殆どの父兄の皆さんにとっての「数学」の「難しさ」は、この水準を指し示しているのが通常です。また横断的な理解が身についていないため、わが子に対しても「勉強しろ」と言い放つばかりで、元来の数学の奥深さの一端を感じさせるような学習への促しが出来ない大きな理由にもなっています。
cocではこうした難易度の問題は自習を課し、通常授業では問題数を絞って認識の仕方に柔軟性をもたらすことに時間を多く割いていますが、個別指導ではこれを軸に扱うことも多くあります。数学が苦手な子、手を出そうとは思っているのだけれどもなかなか腰が重くて・・・と考えている子は、個別指導をご検討いただければと思います。
またこの先にある学びはもっと楽しいものになりますから、こうした難易度における学びと同時並行して出来る学びを cocではメインで提供しつつ、モチベーションを維持し続けられるような指導を提供しています。これについては別の記事で触れたいと思います。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

HP http://www.classoncloud.jp
facebook https://www.facebook.com/classoncloud.jp
mail customer.classoncloud@gmail.com
体験授業は土曜17:00から随時定期的に実施しています。
どうぞお気軽にお問い合わせください
>>>体験授業のお問い合わせはこちら
説明会・食事会も定期的に実施しています!高校生・大学生が主な対象となります。
>>>食事会へのご参加はこちらから