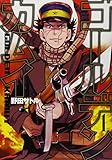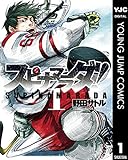今年は映画ちゃんと観よう!という気持ちで感想です。ネタバレがんがんあります。
観たやつ→ロング・ウェイ・ノース/ディリリとパリの時間旅行/パラサイト 半地下の家族/家族を想うとき/マリッジ・ストーリー/ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス/ジョジョ・ラビット
レミ・シャイエ『ロング・ウェイ・ノース 地球のてっぺん』
とにもかくにも画の美しさがものすごかったです。サンクトペテルブルクの街並み、屋敷の調度にかかる柔らかなライティングから、大胆なレイアウトで描かれる北極の海、クレバス、ブリザードの身構えるほどの迫力。可愛すぎる犬。主線を排した絵柄の、貼り絵のような濃淡に吸い込まれるようでした。
尺の短さも若干シンプルすぎるシナリオも、画の美しさに注視させる導線として機能していたように思います。ヘタに冒険活劇にしない勇気。
観た映画館の暖房が不調で、ちょっとした4DXでした。良い体験。
ミッシェル・オスロ『ディリリとパリの時間旅行』
メラネシアの少女ディリリの、ノーブルかつ愛らしい闊達さを軸に、美しい色彩と細やかな演技と若干マジか!?ってレベルのCGで展開される、素朴なフェミニズムと文化礼賛の映画でした。
タイムトラベルものなのかと思わせて別にそういう訳でもないんですが(原題も『Dilili à Paris』で時間要素なし)、「時間旅行」という言葉は大いに示唆的だなと思いました。人種やジェンダーに対する現代的な感性を携えて過去を振り返る(それを素材に物語を作る)事は、懐古話とも歴史劇とも単純には同一視できない、からこそのこの邦題だったのかなと。それはタランティーノが『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』でやろうとした事と通底するし(ワンハリの邦題は『クウェンティンとハリウッドの時間旅行』でも良かったかもしれない(?))、良きにつけ悪しきにつけ「無邪気」とか「素朴」って印象とも接続する。芸術や科学技術の発展が寛容の精神を培うのだという強靭な信念は眩しく納得できるものだけれど、21世紀に生きている私たちは今や、ノブレスオブリージュが絶滅寸前であることを知ってしまっているので……大いに肯きながらどこか小骨が刺さったような気持ちで観てしまったというのが正直なところです。
私はベルエポックの時代にもフランスの文化人にも全く疎いのでパンフレットは必須でしたが、詳しい人が観ればもうアベンジャーズ的に楽しいのではないかな。カミーユ・クローデルの事、恥ずかしながら知らなかったです。知った後に反芻してみると、ちょっとワンハリにおけるシャロン・テートみたいな位置づけだったな、とか。
マジか!?と言いつつCG結構見どころだとも思う……特に犬……。もぎたてみたいな3Dモデル凄いから見てほしい……。
ポン・ジュノ『パラサイト 半地下の家族』
もう、べらぼうに面白くて隙の無い、良き映画でした。水は下に向かって流れる。下水は上へと逆流する。机の下でも繋がるWi-Fi。レトルト麺の中の高級牛肉。見立てと対比に溢れた、感情の動きすらそっくり含めて「構図」そのもののような映画。とりわけ完璧だったのが「予感」のコントロールで、次の瞬間に起こりうる悲喜劇に身構えさせながら、予想の一段先へと踏み外させる手練手管の連続、なすすべなく滑り落ちていく快感がありました。途中の大仕掛けには何となく既視感があってそんなに驚かなかったんですが、『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』のとあるエピソードとか『クリーピー 偽りの隣人』の事が無意識に頭にあったからかもしれない。
「構図」そのものと言いつつ、ステレオタイプを弄している訳では当然無く、だからこそ心の弱い部分に一段深く刺さってしまいました。身に覚えのある感情をこうも逃げ場なく見せつけられると……。物質的な豊かさや文化的資本以上に、洗練された身振りや性根の善を目の当たりにした時「身の丈」を自覚させられるんですよね。「金持ち」の卑しい部分やダサい部分を必死こいて探してる途中、ふと我に返る時、体の内側に向かって生えてくる「身の丈」という棘を。
同じ空間に対峙するその人の目の中の網に、自分の存在がどこにも引っ掛からず滑り落ちていく時の惨めさ。「居心地の良い」底辺に自らを封じ込め、尊厳の無い充足に満足を偽る哀しさ。大きく奪われ続けている事に目をそらし、掠め取る側を気取る愚かさ。殺意すら重力に勝てないどうしようもなさ。呪詛というにはやり場のない、汚水のように溜まる空しさ。身の丈ボコボコスタンプラリー。なんかめちゃめちゃ書いてますね……止まらなくなる……。
ともかく、大好き!というにはちょっと隙が無さ過ぎたけど、思うところが噴出しまくる大変面白い映画でした。ミッドタウン日比谷で観たので、上映後歩きながら苦いつばが出まくりました。
ケン・ローチ『家族を想うとき』
ほんっとうに『パラサイト』の後に観てよかった……。ジャンル映画が当然取りこぼす社会のひだの部分こそが中心に映されていて、同じ格差社会の苦い話なのに、かえって心の安定が保たれるような気持ちになりました。フランチャイズという「発明」で、本来支払うべきコストを当人や社会保障になすりつけて悪びれもしない企業のフリーライド根性に、もう、もう、暴動しかないわね……とお気持ちになりつつ、映されている人々は終始適切な距離と柔らかな光の中で尊厳を保たれていて、とてもつらい展開でも心にすっと染み入ってきました。例えば息子の反抗一つとっても、そこに至るプロセスや環境を丁寧に描き出すことで、家族間の軋轢に対して当人の資質に責任を負わせすぎない優しい視点があったなと思います。しかし問題やストレスを思いやりで乗り越えていったとしても、それすら単なるメンテナンスコストとして利用されてしまう出口の無さ。家族の間を巡る愛情に、システムの側こそが寄生している構図、ぼ、暴動!!!!
(あと、作中の家族の絆が深い分、家族関係の破綻した人や家族の無い人たちの現実はもっともっと苛烈なものだと思うので、「本来このような階層にいるはずじゃない人たち」すら抜け出せない新自由主義社会、というアプローチなのかな、それでこぼれるものはあるかもな、とはほんのちょっぴり思いました)
ノア・バームバック『マリッジ・ストーリー』
普段あまり観ないタイプの映画なのですが、人に薦められたのと『ブラック・クランズマン』での佇まいにアッ……アッアッ……となったアダム・ドライバーが出ていたので。前2本が2本だったので、パワーカップルだな……って感想が真っ先に出ちゃったのですが、面白かった!スカーレット・ヨハンソンのユニセックスな魅力が爆発してたしアダム・ドライバーは上半身が変に分厚くて最高だった。あとスカヨハ姉(メリット・ウェヴァー)のシーン、声出して笑っちゃうくらい良かったんですが、『マーウェン』のおもちゃ屋店員役の彼女だったのね。気付かなかったです。
社会の中で生きている限り身一つなんて幻想で、職や実家や世間体みたいな外側のネットワークに伸ばす脚まで含めた総体を個人と呼ぶのであって、家族をやっていく事ってそういうタコ足同士が奇跡的に、努力の末、見て見ぬふりをしながら、絡み合うことなんだな……やば……ムッズ……無理では……という気持ちになりました。
一番グッと来たアダム・ドライバーはうっかり包丁で腕切ってキッチンの隅にうずくまって転がるも息子からは無視されるアダム・ドライバーでした。唯一無二の情けなさが出てたんだ。
フレデリック・ワイズマン『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』
観よう観ようと思ってたら結局2020年になってしまった。開幕即ドーキンスでちょっと笑いました。映っているものが全てだし、「図書館は民主主義の柱である」という信念にほぼ完全同意なのでそんなに書くこと無いのですが、予算をもぎ取るプロセスが繰り返し登場するところが本当に良かったです。資金繰りについて映すのって誠実。
「寛容」の実践がまさにあるなと思いました。ここまでやるんだ!と驚きの連続。スクリーンで観られてよかった。
タイカ・ワイティティ『ジョジョ・ラビット』
こどもの主観として描くことを徹底している映画だったな。個人的には『崖の上のポニョ』を観た時に感じたいびつさ、おそらく意図的な、に近いものがありました。主人公ジョジョが見聞きした事、知っている事、あるいは薄々気付いている事だけで作品世界は構築されていて、リアリティラインが奇妙な場所で浮遊していました。イマジナリーヒトラーは勿論、ゲシュタポの男の極端な長身やレベル・ウィルソン演じる女性党員の豊満さ、幼児性の強いカリカチュアライズなどは、こどもの主観がゆがめた世界を表すギミックだったのではないかと。だから後半にかけて画面から色彩が急速に失われていくのは、戦争末期という表現以上にジョジョの主観世界の広がりを表しているのだろうし、本質はやっぱり少年の成長譚なのだろうと思います。
だからこそナチズム信奉という罪を少年の形で受肉させユダヤ人の少女と交流させる事と、子どもに罪はなく大人と環境に責任があるという真っ当なステートメントが組み合わさる事で、ある種の免罪符ととられかねない危うさは確かにあるなとニイさんの感想を読んで思い至りました。ジョジョが何を代表しているのかは慎重に検討した方がよさそう。
と、言いたいことは色々ありつつ、キャストの強靭な愛らしさには終始やられてしまいました。
また出たスカヨハはこちらでも卓越した魅力のママを演じていたし、脇カプこと大尉と部下も最高でしたね。戦場で着飾ってドンキホーテ的に見栄を切る男男の図とてつもなく良かった。あの後多分部下の方が先に死んでるのもビンビン来ました。あと私は太った子供が大好きなので……ヨーキー……アーチー・イエイツくん……あれだな……ソフトクリーム食べるか……?
でもやっぱり最後の、ユダヤ人の少女エルサの、ぎこちなくリズムをとる首の動きに全部持って行かれました。トーマシン・マッケンジーさん。おばけのフリの演技も大変素敵だった。
劇中曲の解説は、たまたま聴いてた「ジェーン・スー 生活は踊る」高橋芳朗さんのコーナーがとても参考になりました。
あと、洋画に本当に疎いので、全編英語でドイツの話をやるのってどういう感覚なんだろうかと掴みかねてます。セルフ吹替みたいな感じなのかしら?この疑問からして島国根性なのかな。前情報殆ど入れずに行ったので、最初アメリカのネオナチカルトが子供洗脳してヒトラーユーゲントの真似事する話なのかな?と思っちゃったくらい。
![パワー [ ナオミ・オルダーマン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7551/9784309207551.jpg?_ex=128x128)