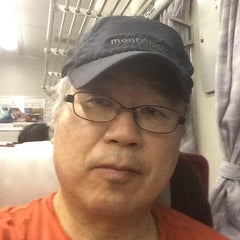日高町の富川は、沙流川の河口に近く昔からの交通の要衝で、日高の海岸線を走る国道235号線と沙流川に沿い旧日高町に行く国道237号線の分岐地である。今でも日高自動車道の富川インタが町の北にある。
日高本線富川駅も、国鉄時代は日高線の主要駅のひとつであって「急行えりも」も停車していた。私の古い記憶では、駅弁も販売されていたと思う(自信はないが)。かつては、沙流川流域から搬出された木材を運ぶ沙流鉄道(軽便)がここから分岐し、十数キロ先の平取とを結んでいた。
私が実際にこの駅から列車に乗ったのは2012年、占冠駅から国道237号線を日高峠を越え、旧日高町からは沙流川に沿って自転車で走った時である。すでに1面1線のなんの変哲もない無人駅となっていて、住宅街に埋もれたその小さな駅舎を見つけるのに苦労した。、線路の北側に広がる草叢がかつては交換可で貨物も扱い機関支区もあった時代が偲ばせる。古い時代に一度この駅に降りてみるべきだったと悔やまれる。
富川の街は、以前国道274号線の夕張市紅葉山・日高町間が未通の時代に道東方面に行くとき、ここから国道237号に入り日勝峠を抜けたので何度も通った。重厚感のあるトラス橋の沙流川鉄橋の手前に古い大きな旅館があった。かつては林業関係者や行商人などが富川駅を降りて利用していたのではないかと思われるが、今も健在だろうか?
沙流川は鵡川は日高山脈北部から並行してから太平洋に注ぐ大河であり、ともに広大な河原を有しているのでよく混同する。富川駅より少し北に行くともう平取町である。しかしさらに北に行くと再び日高町となる。旧門別町と旧日高町が飛び地合併して(新生)日高町となったためである。平取町が合併に応じなかった理由はなんであったのだろう?
この辺りはアイヌ語地名がよく残されている地域だが。沙流川の河口を意味する「佐瑠太」(サルブト;本来のアイヌ語地名はサルプト゚)を「猿}を連想するということで佳名の「富川」と改名してしまったのはちょっと残念である。だから以前の駅名は「佐瑠太」であった。
それにしても、交通の要衝、それなりの市街地を持ち、近くに道立高校もあって乗降客も日高門別より多い富川駅が日高町の代表駅ではないのはどうしてだろう?