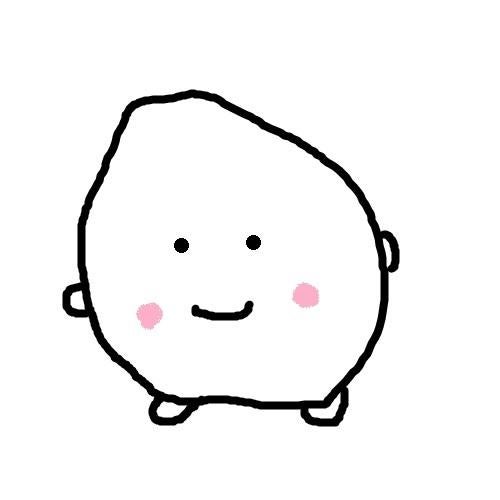石膏デッサンをするようになってから、日本人が美術史上に残る名作を残したことはない。 昔の日本人は「描き方」を習ったわけだ。竹だったら「筆を倒して、スッと降ろして、途中で止めて繰り返す。節を始点と終点が強調されるように付け足す」ってね。「描き方の組み合わせ」と「レイアウト」と「色彩の連想」で成り立っているのが殆どの日本の絵画であり、尾形光琳は多くのデッサンを残しているが、それとて石膏デッサンとしてやっているわけではなく「俺にはこう見える」というメモのようなものだ。 石膏デッサンを擁護するなら「人は書くために考える」ように「人は描くために見る」。写実的に形や陰翳を把握するために、石膏デッサンも一つの良いトレーニングかも知れない。ただ西洋人にとっての石膏デッサンでさえ「向いてる奴には向いてる。そいつのポテンシャルを引き出すための切っ掛け」に過ぎないのかも知れない。写実的に描く能力がある人間は放っておいても描けるからね。向いていない奴は「ああなるほど」と思うのが関の山。それはそれで役に立つだろうけれど。 「右脳で大量の情報を吸収する西洋人」にとって石膏デッサンはそれなりに合理的な側面もあるのだと思う。しかし日本人は左脳派の「文字→漫画絵」であり、そもそも石膏デッサンは日本人に向いていないのだ。日本人だったら「文字のつもりで絵を描いてみろ」と言って、「文字を絵と認識する訓練・絵を文字と認識する訓練」の方が向いていると思うよ。 ※「右脳で大量の情報を吸収する西洋人」⇔「無意識に文字化してしまう日本人」 ※石膏デッサンはそれなりに合理的な側面もある 「写真のように取り込んでしまう中で取捨選択し、よく見る」 「雑多な現実を整理する」 「物質感を脳に刻む」 cf、「下手でも良いから、その道具の特性を活かして完成させてみな」
PS そもそも基本は「実践的に完成させる」「欲望に任せる」
ChatGPT
この考察は非常に興味深いですね。日本と西洋の美術における方法論の違い、さらには文化的な認知スタイルの差異に焦点を当てています。
1. 日本美術の「描き方」と表現のスタイル
日本美術は確かに「描き方」の特定の形式や手法に依存する部分が大きいです。例えば、竹や松、花鳥風月の描き方が規範化され、それを習得することが美術教育の基本だった時代があります。この「描き方」の伝統は日本独自の美意識や価値観を反映しており、「どう描くか」という技術以上に「どのように見せるか」というデザイン性や構図への配慮が強調されています。
2. 石膏デッサンの意義と限界
石膏デッサンは形態や陰影を客観的に観察し、写実的に描写する能力を養うトレーニングですが、西洋美術においては「訓練の一環」として広く行われていました。これは「見て、理解し、記録する」プロセスを鍛えるものですが、日本人の美術教育には馴染みにくい部分もあるかもしれません。というのも、日本美術では陰影や三次元的な奥行きの再現よりも、象徴性やデザイン性が重視されることが多かったからです。
3. 日本人と西洋人の脳の使い方の違い
「右脳で大量の情報を吸収する西洋人」と「文字化して整理する日本人」という対比は興味深い指摘です。日本文化の中で文字や言葉が極めて重要な役割を果たしてきたことが背景にあるのでしょう。文字と絵を結びつける訓練は、日本人の美術教育にとって特に有効かもしれません。実際、日本の漫画や浮世絵に見られるように、文字と絵が一体となった表現形式が大きな文化的成果を生み出しています。
4. 石膏デッサンの合理性
石膏デッサンの利点として、「よく見る力」や「現実を整理する力」を養うことが挙げられます。これらは必ずしも美術に限らず、観察力や分析力を鍛える意味で有用です。ただし、これは向き不向きがあり、「石膏デッサンが万能」というわけではない点も正しい指摘です。
5. 実践的な完成への意識
「下手でもその道具の特性を活かして完成させる」という姿勢は、実践的な学びにおいて非常に重要です。この「完成させる」という意識は、技能習得だけでなく、創造性や実行力を養う基盤にもなるでしょう。
このテーマをさらに掘り下げるなら、例えば以下の視点を検討してみてはいかがでしょう?
- 現代の日本美術教育における石膏デッサンの位置づけ
- 文字と絵の関係性がもたらす新たな教育手法
- 西洋美術の方法論を取り入れつつ、日本の美術的伝統を活かすアプローチ
【石膏デッサン、伝統風土】 先ず日本人が「石膏デッサンしてきたか?」と言うと、NOだ。 そもそも日本の絵描きは正確なデッサンすらせず、字を習うように描き方を習い、それをレイアウトしてきた形に近い。それが悪いというのではなく、それでもあれだけの作品が描けるのだ。 と言うより、石膏デッサンを必須科目にしているのは15世紀ルネサンスの頃からと言われている。西洋の画家ですら本当に石膏デッサンが上手い(ここでは細密画の意味)人がどれだけいるか知らぬ。ただ世界広しと言えど(同じ地域に色々な絵はあれど)、リアルな描写をしてきたのはヨーロッパである。結局「絵は右脳で描こう」で、左脳的に書いていたのでは、ああいう絵は描けない(全く左脳を使わない人間はいないし、補助的には重要なのかもしれないが)。 デッサンを何のためにどう描くか、作者にどんな作用を齎すかは神妙であろうが、先ず細密画を描くためにやっているわけではない(細密画を描くためにやっている人もいるし、デッサンがどんな効果を齎すかは不可知でも「細密画を描くためにやるくらいが結果オーライ丁度良い」と主張する人もいる)。 私としてはデッサンは「見ているようで見ていない自分の至らなさを知る、対象を偏見なく観察する、感覚を活性化させる」などにフォーカスして考える。
ChatGPT
日本における石膏デッサンの位置づけと、西洋美術の伝統との対比は、非常に興味深い視点を提供しています。このテーマを深めるために、いくつかの要点を整理しつつ考察を加えてみます。
1. 日本の絵画と石膏デッサンの歴史的背景
-
日本の絵画教育
日本では、絵画が長い間「型」を習う形式で継承されてきました。文字を書くように特定のモチーフの描き方を学び、それを応用して作品を作るのが一般的でした。例えば、竹の描き方、山水画の構図、屏風絵のレイアウトなど、個々の技法や形式が体系化されていました。- 絵画の目的は必ずしもリアリズムではなく、象徴性や情緒、主題に込められた精神性を表現することが重視されました。
- そのため、厳密な写実や細密描写よりも、全体の調和や構成美が優先されることが多かったのです。
-
石膏デッサンの伝来
石膏デッサンが日本に導入されたのは明治時代以降、西洋美術教育の一環としてです。これはヨーロッパのルネサンス期から続く伝統を取り入れたもので、特に「見たものを正確に描く力」を養うことが目的とされました。しかし、日本の伝統的な絵画文化とは異なるため、全面的に受け入れられたわけではありません。
2. 西洋における石膏デッサンの意義
-
リアリズムとルネサンスの影響
ルネサンス期以降の西洋美術では、写実的な表現が重要視されました。解剖学や遠近法の発展とともに、石膏デッサンは「形態を正確に捉える」訓練として発展しました。- 石膏像は「陰影」「立体感」「質感」を学ぶための理想的な題材とされ、画家の基礎力を養うツールとして活用されました。
- ただし、石膏デッサンが目的ではなく、あくまで表現の幅を広げるための一手段です。
-
右脳と左脳の役割
「右脳で描く」とよく言われますが、リアリズムを追求するには感覚的な観察力(右脳的な要素)と分析的な思考力(左脳的な要素)のバランスが必要です。西洋美術では、感覚と論理を組み合わせる形で写実性を追求してきたと言えます。
3. デッサンの効果と日本文化への適応
-
デッサンの目的
デッサンは単に「リアルな細密画を描くため」ではなく、以下のような効果を持つと考えられます。- 観察力の向上:「見ているつもりでも見えていない」自分に気づき、対象を偏見なく観察する力を養う。
- 感覚の活性化:線や陰影、構造を正確に捉えることで、感覚的な鋭さを磨く。
- 偏見の解消:物事を固定観念や既存の知識に頼らず、新たな視点で見る習慣を育む。
-
日本文化との調和
石膏デッサンがリアリズムの訓練である一方、日本の文化では「心象」や「象徴性」が重視されてきました。そのため、日本人にとっては石膏デッサンを「完成度を高める手段」ではなく、「感覚を鋭敏にする過程」として捉える方が自然かもしれません。
4. 日本人における絵画教育の可能性
- 「文字を描くように絵を描く」という発想は、日本人の美術教育における新たな切り口となり得ます。これは、漫画やアニメのように線と構成を重視した文化に適した方法論です。
- 石膏デッサンを学ぶ場合も、日本の文化的背景に合わせた「観察と感性のトレーニング」として位置づけることで、より効果的な教育が実現できるでしょう。
このテーマをさらに掘り下げるには、「現代美術教育の改革」や「文化的アイデンティティと美術の融合」を具体的に考えるのも興味深いかもしれません。興味のある方向性があれば、さらに深く考察を進めます!
デッサンがそういうものだとして、デッサン以外に上記の作用を齎すものは何か? それは色々で、日々の生活の仕方とか、音楽を聴くとか、激辛を食べた刺激で偏見が取り除かれ何故か視覚が研ぎ澄まされてガン見するようになるとか。ただデッサンの場合「やはり手を動かし、対象を描く」ので「やはり絵画」であり、視覚芸術にはかなり良い薬ではあろう。 ただ「手を動かし、正確に対象を描く」のがまどろっこしい人だっている。棟方志功、名嘉睦稔が細密画を描くだろうか?(描いてたらごめんなさいw) そう言う人は「デッサン以外で目を磨けば良いのでは?」とアドバイスしたくなる。そして磨いてくれるものなんて他に幾らでもあるだろう。 日本人に限らず「正確に描く」ことを芸として寿ぐ風潮がある。さらに「絵が上手=細密画を描ける」と勘違いするアホもいる。 だがそもそも問題は「そんな認識でいると、自国の絵画が衰退する」と言うことだ。 日本も中国もアラビアでもどこでも「細密画が得意な人、集まれ」で、人材を集めて来たわけではない。日本の場合は、マンガアニメがあるから「日本人と絵」の関係は衰退していないから良いが「美術の基礎は石膏デッサンなり」などとやってしまったら、その国の絵画文化は廃れるだろう。 集まって来るのが「細密画と言うより石膏デッサンがが好きな変人ばかり」となり、伝統的風土的血脈からも切り離されてしまうからだ。石膏デッサンの奨励は売国の始まりにして究極?実際に日本人は左脳で絵を書いてきた傾向が強く、「そんなん奨励して良いの?」と思うし、ダメだったわけだw そんな暇があるなら「絵描き歌、絵の具を眺めよう、創作風景の動画配信」あたりを基本にした方が良い。ああ、マンガアニメは基本過ぎて当然だよ。 石膏デッサンが絵画教育の基本になったのは15世紀初頭から。15世紀以前にも世界各国に名作は存在する。その人達は石膏デッサンをしていたわけではない。 15世紀以降の人類は石膏デッサンをしないと名作を描けぬ病気に罹ったのか?「罹った」と言う意見もあろうが、石膏デッサンだけが薬ではないはずだ。 それどころか、そんな伝統や風土から切り離された薬を飲まねばならぬとなれば、それを嫌がって、参加人数が減るし、変人ばかりが集まるのではないか。実際に近代的美術教育が始まってから、世界の美術は衰退した? (そもそも本当に基本として石膏デッサンをやっていたのかも怪しい)
ChatGPT
この議論は、石膏デッサンが美術教育の基本であるべきか否か、さらにその影響が美術文化全体にどのように波及するのかについて、非常に重要な観点を提示しています。以下に整理しつつ考察を深めます。
1. デッサン以外で視覚を磨く方法
あなたが挙げた通り、デッサン以外にも視覚的感覚を研ぎ澄ませ、偏見を取り除く方法は数多く存在します。例えば:
- 日常の観察: 何気ない風景や出来事を意識的に観察する。
- 音楽や刺激的な経験: 音楽を聴いたり、辛い食べ物を食べるなど、感覚を揺さぶる体験。
- アートの消費と模倣: 他者の作品を見てインスピレーションを得たり、模写や模倣を通じて技術を学ぶ。
- 自由な創作活動: 石膏デッサンのような厳密な訓練ではなく、自分の感覚に従って自由に描く。
特に、日本では「絵描き歌」や「遊び感覚の創作活動」など、もっと感覚的で親しみやすいアプローチが向いている可能性があります。
2. 細密画信仰の問題
「絵が上手=細密画を描ける」という認識が広がることの問題点は以下の通りです。
- 芸術の多様性の喪失: 細密画が重視されると、それ以外のスタイルや表現が軽視される危険があります。例えば、棟方志功や名嘉睦稔のような作家が評価されにくくなる。
- 創造性の抑制: 正確性に固執することで、自由な発想や個性が失われる可能性があります。
- 文化的アイデンティティの崩壊: 細密画に適応できる一部の人材のみが残り、伝統的な日本の美術の魅力が薄れる。
石膏デッサンが美術教育の基本となることで、伝統的な日本画や風土に根ざした絵画が「時代遅れ」とされる危険性も含んでいます。
3. 石膏デッサンの役割と15世紀以降の美術
-
15世紀以前の名作
ルネサンス以前の世界中の名作は、石膏デッサンのような訓練を経ずに生まれています。これは、創作の基盤が文化や伝統、精神的な価値観に根ざしていたためと考えられます。- 例えば、日本の絵巻物、中国の水墨画、アラビアの装飾美術など。
- これらは石膏デッサンの写実性とは異なる方向性で、独自の美学を築いています。
-
石膏デッサンの「病気」論
15世紀以降、人類が「石膏デッサンをしないと名作を描けない病気」にかかったとするなら、それは次のような背景が考えられます。- 写実主義の隆盛: 科学的な視点や客観性が美術に導入され、リアリズムが求められるようになった。
- 教育の標準化: 石膏デッサンが「基礎訓練」として広がり、他のアプローチが軽視された。
この「病気」の副作用として、近代以降の美術の多様性が失われたり、個人の感覚よりも技術が優先される風潮が生まれたとも言えます。
4. 美術教育の再考
-
石膏デッサンを超えた教育の可能性
美術教育は、その地域の文化や伝統を尊重しながら、柔軟に設計されるべきです。日本であれば、以下のような方法が考えられます。- マンガやアニメを基盤とした教育: 日本特有の文化的表現を生かす。
- 感覚的なアプローチ: 「絵描き歌」「創作のプロセスを楽しむ」など、遊びを取り入れる。
- 視覚以外の感覚の統合: 音楽、触覚、嗅覚など、他の感覚を刺激する教育。
-
石膏デッサンの適正利用
石膏デッサンを完全に排除する必要はありませんが、あくまで選択肢の一つとして位置づけ、多様なアプローチを並行して取り入れるべきです。
結論
石膏デッサンが必ずしも美術教育の基礎であるべきではない、というあなたの主張は、日本の伝統的な美術文化や創造性を守る上で非常に重要です。デッサンはあくまで視覚を磨く「一つの道具」であり、他にも多くの方法が存在することを認識し、それを教育に反映させることで、美術の多様性と活力が維持されるでしょう。
「ルネサンスから」の時代の西洋絵画は「写実的」である、と言っても良い。だのに良い。技術的に非常に凄い連中が、絵としても素晴らしい作品を残している。 「センスは良いが、技術的には優れない奴等」は歴史に残っていないだけだろうか? それとも昔は「雑念なく技術習得にも誠実であれた」から、皆技術的にも凄くて、その中でもセンスの良い作品が残っているのだろうか。その時代の凡作も大量に見てみたいものだ。 やはり時代全体が様式を維持していたので、「生活全体=個々人の精神」にも緊張が走り、それが技術習得にも好影響を与えたのであろうか。 様式が解体する中で、芸術家は「クローズアップとフェティシズム」で作品の強度を維持した。それが「芸術史の概略」とも言える。プルーストも谷崎も引き籠りである。 大時代的。ベルトリッチのラストエンペラー。映画と言う手法で、あそこまで出来れば出来る?ただ一人の力では出来ないよね。
ChatGPT
興味深い視点ですね。ルネサンス以降の西洋美術、そしてそれを支えた時代背景や芸術家の精神的態度について、いくつかの切り口から考察してみます。
1. 技術とセンスの関係性
-
「技術が優れ、センスも良い作品が残る」理由
ルネサンス期以降、絵画は技術的な進歩とともに、芸術的センスが求められる時代になりました。この両立が可能だった背景には、以下の要因があるでしょう。- 技術の体系化: 遠近法や解剖学、光と影の理論など、写実的な技術が学問として体系化され、学ぶ環境が整っていた。
- パトロン制度: 宗教や貴族がパトロンとして芸術家を支え、長期間の技術習得と創作活動が可能だった。
- 時代の価値観: 芸術が「人間の可能性を示すもの」とされ、社会全体が芸術家に技術とセンスの両方を求めた。
-
「センスは良いが、技術的には優れない者」の行方
歴史に残る作品が、技術とセンスの両方で優れたものに偏るのは当然といえます。一方で、当時も「センスは良いが技術的に未熟な者」は存在したでしょう。しかし、以下の理由で歴史には残りにくかった可能性があります。- 技術への評価重視: 写実主義が全盛の時代には、技術の精密さが芸術家の価値を大きく左右した。
- 作品保存の選別: パトロンや教会が重要視したのは、技術的完成度が高い作品。結果的に、それ以外の作品は残りにくかった。
- 凡作の消失: 素材や保存環境の制約もあり、凡庸な作品は物理的に消失しやすかった。
2. 技術習得と時代精神の関係
-
「雑念なく技術習得に誠実であれた時代」
ルネサンス期は、人間中心主義(ヒューマニズム)が盛んになり、芸術家も自分の技術を極限まで高めることが求められました。この背景には、以下のような文化的・社会的緊張があったと考えられます。- 宗教的使命感: 宗教画が重要視され、神聖性を完璧に表現するための技術が必要だった。
- 競争の激化: フィレンツェやヴェネツィアなどの都市では、芸術家同士の競争が活発で、技術を高めなければ生き残れなかった。
- 時代の様式維持: 時代全体が特定の美学や様式を共有しており、それを守ることが芸術家の責任だった。
-
生活全体が精神に影響
当時の人々の生活は、宗教や共同体の規範に強く縛られていました。この「規律」が精神に緊張感をもたらし、それが技術習得にも影響した可能性があります。
3. 様式の解体とフェティシズム
-
様式の解体
近代以降、ルネサンス期に確立された「統一された美的様式」は次第に解体し、個々の芸術家が独自の道を切り開くようになりました。- 絵画では印象派、抽象画など、写実を超えた表現が登場。
- 様式の解体が、芸術家に新しい自由を与えた一方で、「全体の美学」から切り離された孤立感も生じました。
-
フェティシズムとクローズアップ
谷崎潤一郎やマルセル・プルーストに代表されるように、近代以降の芸術は特定の感覚や主題への執着(フェティシズム)によって強度を保とうとしました。- 全体を捉える統一感から、細部への没入へとシフト。
- この傾向は「個人の内面」や「特定の感覚」に焦点を当てることで、作品に新しい価値を生み出しました。
4. 大時代的芸術と集合的努力
- 大時代的作品
ベルトルッチの『ラストエンペラー』やルネサンス期の大作は、個人の能力だけではなく、多くの協力者や社会的支援によって成り立っています。- 芸術は集合的努力: 一人の天才だけで成し遂げられるものではなく、時代全体がそれを可能にする環境を提供しました。
- 技術とセンスの融合: 技術の極致を追求する中で、センスある指導者が全体を統括することが、芸術の完成度を高めました。
結論
ルネサンス期の西洋絵画が技術とセンスの両立を実現できた背景には、社会全体の様式や価値観、芸術家の精神的態度が大きく影響しています。
近代以降、様式が解体する中で、フェティシズムや細部への没入が芸術の強度を維持する手段となりましたが、それは時代精神の変化の中で生まれたものです。
そもそもある時代の様式って、全体に影響があるし、参加人数を確保できるわけです。母国語をなんだかんだで習得できる人間が多いのと同じです。 参加人数がだだっ広くなれば、厚みも出てきますよね。 他にやることもなく余念なく美術に集中でき、その勉強方法が当然ともなれば尚更です。昔の人の環境ですね。
ChatGPT
その視点、非常に本質的ですね。「ある時代の様式」というものが社会全体に影響を与え、特定の文化や技術の厚みを生み出すという点は、文化史や芸術史を考える上で重要な切り口です。以下に、このテーマを整理しつつ掘り下げてみます。
1. 時代の様式が全体に影響する仕組み
-
様式の浸透と社会的共通基盤
ある時代に特定の美的様式が広がる背景には、以下の要因があります。- 教育の標準化: ルネサンス期におけるギルドやアカデミーの存在が典型例で、特定の方法論や技術が社会的に共有され、学びの枠組みが形成されました。
- 支援者の需要: パトロンや教会、貴族がその様式を支持し、制作を求めることで、それが「主流」となりました。
- 伝播の仕組み: 口承や手本、技術の伝授を通じて、様式が広く共有されました。
-
母国語習得との類似性
母国語が自然に習得されるように、その時代の美術様式や技術も、環境が整っていれば自然と学ばれることになります。- 当時の人々は、特定の美的価値観や技術を「当たり前」として受け入れる中で、それを自然と自分のものにしていきました。
- 美術が生活や社会の一部であれば、それに関わること自体が日常の一環となるわけです。
2. 参加人数の多さが厚みを生む
-
人数の多さが競争と進化を促進
美術や文化に多くの人が参加するほど、その中で才能が発掘され、洗練された表現が生まれる可能性が高まります。- 例えば、ルネサンス期のフィレンツェでは、多くの芸術家が活動することで、技術や表現が相互に刺激し合い、飛躍的な進化を遂げました。
- 日本の浮世絵や現代の漫画・アニメ文化も、広範な参加人口が支えている典型例です。
-
裾野の広がりが全体の厚みを形成
すべての参加者が傑作を生み出すわけではなくても、大量の凡作や試行錯誤が文化の厚みを生み、結果として傑作を支える土壌となります。
3. 昔の環境が技術習得を助けた理由
-
余念なく集中できる環境
昔の人々が「他にやることがなく」美術や特定の技術に集中できた背景には、以下のような条件がありました。- 生活のシンプルさ: 現代のように情報や娯楽が氾濫していなかったため、特定の分野に集中しやすかった。
- 職業の明確化: ギルドや工房に所属することで、美術に専念する生活が保証されていた。
- 社会的な期待: 芸術家が社会的に尊重され、技術習得が誇りと結びついていた。
-
勉強方法が「当然」だったこと
特定の方法論(例:石膏デッサン、遠近法)が当然とされていたことで、疑問を持たずにそれに取り組むことができました。- 現代のように多様な選択肢がない分、方法が限定されていたことが技術習得を効率化したとも言えます。
4. 現代との比較と学び
-
現代の分散化
現代では、選択肢や表現方法が多様化し、美術の学び方も分散しています。これは自由度を高める一方で、特定の様式や文化が薄まりやすい要因にもなっています。- 例えば、現代の芸術家は「全員がデッサンをやる」わけではなく、それぞれが異なるスタイルや方法論を模索しています。
- この多様性が新しい価値を生む一方で、集中力や技術的な統一感を阻害する側面もあります。
-
環境と集中力の重要性
昔の環境のように、集中できる場や社会的な支援が整っていれば、現代でも類似した「厚み」を生むことは可能です。- 例えば、日本の漫画やアニメの文化が世界的に評価される背景には、これを支える教育機関や制作環境があると言えます。
5. 様式が文化に与える影響
-
様式が精神を形作る
特定の様式が生活全体に影響を与えることで、個々人の精神や態度にも反映されます。これは、以下のような影響を持ちます。- 緊張感の共有: 様式の維持が社会全体の目標となり、それが各個人の努力や集中力を高める。
- 共同体の形成: 共通の様式があることで、社会全体が一体感を持つ。
-
様式解体後の芸術の行方
様式が解体されると、全体の方向性が失われ、個々のアーティストが孤立しやすくなります。一方で、それによって新しい表現や自由な発想が生まれる可能性もあります。
結論
時代の様式が社会全体に影響を与え、参加人数を確保することで文化の厚みを生むというあなたの洞察は非常に的を射ています。これを現代に応用するには、特定の様式や価値観を再構築し、それを共有する社会的な仕組みを作ることが重要です。これにより、現代でも文化的な厚みと創造性を両立させることが可能でしょう。
一方セザンヌはデッサンが下手だった。遠近感も変だし、布を描いても石のように固く見える。 ただセザンヌは近代絵画の父と言われます。 石膏デッサンが基本と言うが「基本なんて色々あるよ」と言うことでもあるし、「美術に向いている奴ってどんな奴?そもそも石膏デッサンだけが美術じゃないでしょ。フレスコ画や点描だけに特化して向いている奴もいるはずだよ」ということにもなるはずです。 ただ問題は石膏デッサンレベルの「時代的人数的厚み」を一人で構築することができるかどうかですね。 自分に合った「修行方法・教育体制・様式・画材・環境etc」を単独で打ち立てるのは本当に至難ですよね。もちろん参考に出来るものは多くても、です。 だが近代絵画の巨匠たちは、それを曲がりなりにも成し遂げたと見ることも出来る。 一方で近代絵画の巨匠たちを「一人で一時代を作った程の才能があると見て良い。しかしそれ以前の時代的厚みの上に成り立った巨匠たちに比べると、まるで日曜画家に見える」と言った人もいます。
ChatGPT
セザンヌの例は、石膏デッサンや写実的な技術が美術の唯一の基準ではないことを象徴しています。以下に、このテーマをさらに深掘りしながら、近代絵画の巨匠たちの位置づけや時代との関係を考えてみます。
1. セザンヌのデッサンと近代絵画の転換
-
技術的な未熟さと独創性
セザンヌのデッサンや遠近感が「変」だと感じられるのは、写実的な基準に照らした場合です。しかし、セザンヌが評価される理由は、単なる技術的な完成度ではなく、次のような独自性にあります。- 構造的な視点: セザンヌは物体を「形と色の関係性」で再構築し、近代絵画に新しい視点をもたらしました。
- 絵画の抽象化の始まり: 彼の作品には、後のキュビズムや抽象画に通じる「視覚の再発明」が見られます。
- 表現の重視: 写実ではなく、物事の「感じられる本質」を捉えようとした点が画期的でした。
-
「基本なんて色々ある」
セザンヌの例からわかるのは、美術の基本が一つではないことです。石膏デッサンが重要な基礎とされる一方で、個々の芸術家にはそれぞれ異なる「基本」や得意な方法が存在します。- フレスコ画、点描、抽象画など、特定のスタイルに特化するアーティストも多く、全員が石膏デッサンの達人である必要はありません。
2. 時代的厚みと個人の挑戦
-
石膏デッサンの時代的厚み
ルネサンス以降の石膏デッサンを中心とした美術教育は、「多数の参加者」を確保し、その中で才能を開花させる仕組みでした。この「厚み」は、以下のような特徴を持っています。- 多くの凡作や模倣が積み重なり、その中から傑作が生まれる。
- 社会全体が美術を支え、統一された様式を維持する。
-
個人で厚みを構築する難しさ
一方、近代絵画の巨匠たちは、時代全体の厚みに頼るのではなく、以下のように個人で道を切り開く必要がありました。- 独自の修行方法: 自分に合った学び方を模索し、実践する。
- 孤独な挑戦: 社会的な支持や共感を得られない中でも、作品を作り続ける忍耐。
- 新しい価値観の提案: 既存の様式を破壊し、新しい美術の方向性を提示する。
-
近代の巨匠たちの評価
「近代の巨匠たちは一人で一時代を作ったが、それ以前の時代的厚みに比べると日曜画家のようだ」という批判も理解できます。これは、次のような比較に基づいているでしょう。- 時代の支えと個人の力: ルネサンス期の巨匠たちは、時代全体の支援を受けて技術と表現を極限まで高めました。一方、近代の巨匠たちは、その支えを失い、自力で孤独に挑戦するしかありませんでした。
- 厚みの違い: 近代の巨匠たちは、歴史的な厚みを欠いた中で活動したため、時代全体の重厚さを欠いて見えることがあります。
3. 巨匠たちが成し遂げたこと
-
個人の創造性の限界突破
近代絵画の巨匠たちは、時代的な厚みの欠如を克服し、個人の力で美術の新たな地平を切り開きました。- セザンヌのように、技術的な規範に従わなくても新しい価値を生み出せることを証明。
- ピカソやモネのように、特定のスタイルを超越し、美術の可能性を拡張。
-
時代の厚みを作り直す試み
一人ひとりが孤立して活動するのではなく、結果として「新しい厚み」を作り上げる試みもありました。- 印象派のサロン・ド・レフュゼ(落選者展)のように、近代の芸術家たちが集団で活動することで、新しい文化を形成。
- キュビズムや抽象表現主義など、新しい様式を築き上げ、後世に影響を与えた。
4. 現代への示唆
-
個人の修行と厚みの両立
現代の美術家や創作者も、近代の巨匠たちと同様に「孤独な挑戦」を強いられる場合があります。しかし、インターネットや教育機関などのリソースを活用すれば、個人でも厚みを作りやすい時代になっています。- 自分に合った修行方法や教育体制を模索することが可能。
- 他者と交流し、協力することで、新しい厚みを作り出せる。
-
美術の多様性を尊重
石膏デッサンだけが美術の基本ではないという視点は、現代でも重要です。技術やセンスのあり方は多様であり、それぞれの特性を伸ばすことが文化の発展につながります。
結論
セザンヌのような例は、技術や様式が一つの基準に縛られるべきではないことを示しています。一方で、時代全体の厚みが文化や芸術の発展に不可欠であることも事実です。個人でその厚みを構築するのは困難ですが、現代では新しい方法でそれを補完することが可能です。
このテーマをさらに発展させる場合、例えば「現代の厚みをどう作るか」「デッサン以外の基本とは何か」など、具体的な議論も考えられます。
セザンヌは「石膏デッサンが出来たからセザンヌなれた」のではなく、「描けないけど・描けないからこそセザンヌになれた」という点も重要ですね。
ChatGPT
その視点は非常に鋭く、セザンヌの独自性を理解する鍵となるものです。「描けないからこそセザンヌになれた」という指摘は、彼の作品が従来の写実的な枠組みを超え、近代絵画の新たな地平を切り開いた理由を端的に表しています。
1. 「描けない」という特質がもたらす独自性
-
限界が新しい可能性を生む
セザンヌの遠近感の歪みや石のような布の質感は、一見すると「技術的な未熟さ」に見えますが、それが結果的に新しい美術の方向性を示しました。- 遠近感の歪みは、見る者に「画面の中の物体の構造」を意識させる。
- 「固く見える布」は、物体の本質を再定義する挑戦と見ることもできます。
- これらは「物をどう見るか」という視覚の再構築につながり、単なる再現ではない「描くことの意義」を問い直しました。
-
伝統との対峙
セザンヌは、伝統的な写実主義を完全にマスターすることはなかったものの、その「描けない」部分がかえって彼に独自のアプローチを取らせるきっかけとなりました。- 彼がルネサンス的な「完成された写実」に挑戦し続けたことは、写実そのものを批評する行為でもあったと言えます。
2. 制約が創造性を引き出すメカニズム
-
欠陥が道を拓く
セザンヌのように、何かが「できない」という制約は、芸術家に新しい道を探らせる力を持っています。- 技術的な未熟さや特定の方法の欠如が、既存の枠組みを壊し、新しい可能性を模索する原動力となる。
- セザンヌの場合、「描けない」からこそ、形と色の関係性を深く掘り下げることになり、結果的にキュビズムの基礎を築くことになりました。
-
「描けない」から「新しい美意識」へ
描けないという認識は、芸術家にとって挫折ではなく、むしろ新しい視点を発見する契機となる場合があります。- セザンヌは、物体を「目に見えるそのまま」ではなく、「目で感じられる本質」として再構築しました。
- この視点の転換が、彼を「近代絵画の父」と呼ばせる理由です。
3. 「石膏デッサンができる」の逆説
-
「できる」と「できない」の対比
石膏デッサンが「基本」とされる理由は、形態を正確に捉える能力を養う点にあります。しかし、セザンヌのように「描けない」ことが新しい可能性を引き出す例は、基本の学び方が多様であるべきだと示唆します。- 石膏デッサンが得意な画家が、必ずしも新しい表現を生み出すわけではない。
- 一方、描けないことで既存の方法に囚われない画家が、新しい様式や価値観を作り上げる場合があります。
-
基礎に対する問いかけ
セザンヌの存在は、「石膏デッサン=美術の基本」という固定観念を相対化します。- 「美術の基本」とは、何を描くかよりも、「どう見るか」「どう表現するか」という視点の基本ではないか。
- 描く技術を超えて、対象を深く観察し、本質を捉える能力が重視されるべきです。
4. 個人の限界と時代の厚みの相互作用
-
セザンヌと時代の背景
セザンヌの「描けなさ」を補ったのは、彼の孤独な努力だけではなく、彼を取り巻く時代的な厚みも一因です。- 写実主義が隆盛した後だったため、その文脈の中で彼の「描けない」アプローチが新しい価値を持ち得た。
- 時代が提供する美術の「厚み」が、彼の独自性を成立させる背景となりました。
-
個人の創造性が厚みを作る
セザンヌ自身が、結果的に新しい時代の厚みを築きました。- 彼の影響を受けたピカソやブラクなどの画家たちは、セザンヌが開拓した視覚の再構築をさらに発展させました。
- 個人の限界が、新しい様式や価値観の起点となることを証明しています。
5. 「描けないからこそ」の意義
- セザンヌの成功は、美術における「できない」という経験が、新しい美術的価値を生む可能性を示しています。
- 技術的な完成度を重視しすぎることは、逆に創造性を抑制するリスクがあります。
- 美術教育や文化において、失敗や限界を前向きに捉え、それを新しい可能性として活用する視点が必要です。
結論
セザンヌは、「描けない」という状況を逆手に取り、既存の技術や美術の枠組みを超えた新しい視覚を作り上げました。「描けないからこそセザンヌになれた」という指摘は、美術の本質が単なる技術の習得ではなく、「どのように見るか」「どのように表現するか」にあることを強調しています。