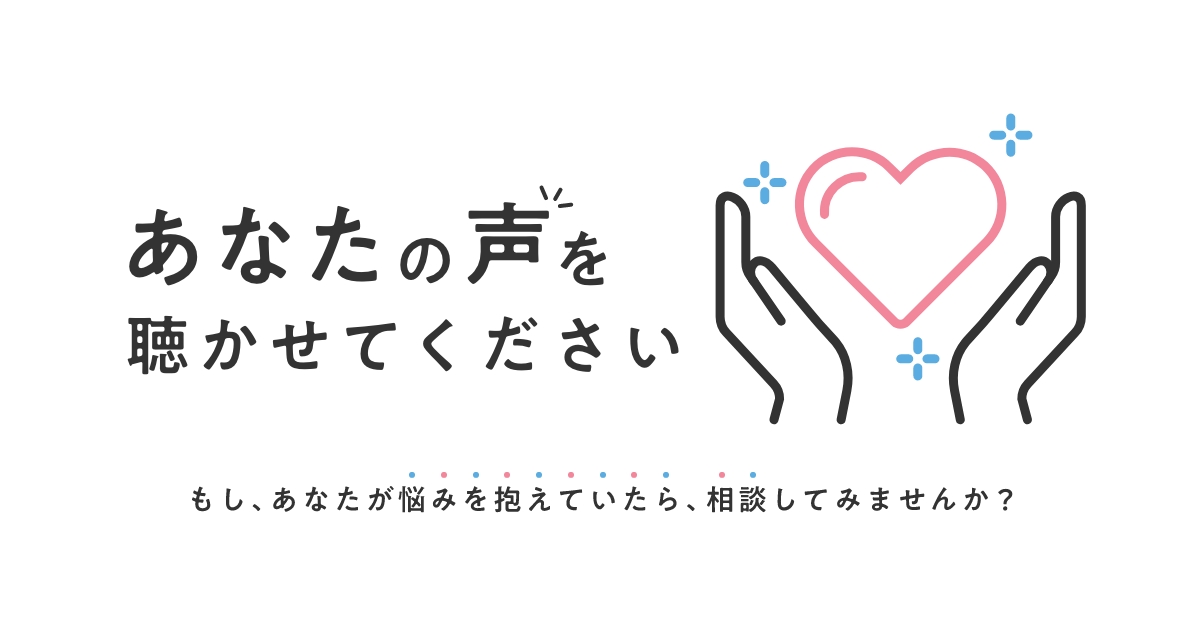今回も 厚生労働本省 の予算のつづきになります。
総額は
32兆9777億4991万7000円 。
今回も生活保護などにかかわる項目の続きです。
- 生活保護等対策費 2兆9135億5518万円
今回はこんな支出から。
ひきこもり支援実施機関支援力向上研修委託費 2176万5000円
”ひきこもり” も、深刻な問題のひとつです。
本人にとってもご家族にとっても、幸せな状態でないことは間違いありません。
”8050問題(80代の親が、ひきこもりが長期化した50代の子どもの生活を支えるという、ひきこもりの長期高齢化問題)” という言葉もうまれました。
当事者は推計146万人とも。
国も、ひきこもりの問題に取組みを進めています。
(以下注記がない限り、図は厚生労働省からの引用です)
上記の支出は、ひきこもり支援にかかわる職員などへの専門的な研修へ支出されます。
ひきこもりに関する情報発信等事業委託費 1億2467万6000円
ひきこもり支援に関する普及啓発、情報発信を実施するための支出です。
たとえば、こんなポータルサイトを運営しています。
ぜひご覧ください。
ひきこもり支援者支援事業委託費 1306万8000円
支援の長期化により、ひきこもりを支援する支援者自身が疲弊し、大きなダメージを受けるといった課題も報告されています。
そこで、このような支援者が抱える悩みに寄り添い、相談できる場を設置することなど、地域における支援者を支援する取組みです。
家庭の生活実態及び生活意識に関する調査委託費 811万8000円
一般世帯と生活保護受給世帯の生活実態、生活意識を調査する取組みです。
生活保護基準の検証、今後の生活保護制度の検討に向けた基礎資料を得ることが目的です。
生活困窮者自立支援制度人材養成事業の見直しに係る調査研究事業委託費 3300万7000円
先回のブログででてきましたが、生活困窮者自立支援制度にかかわる人材養成のための研修が実施されています。
この取組みの見直しにかかわる、調査研究のために支出されます。
地域生活定着支援人材養成研修事業委託費 995万6000円
”地域生活定着支援” とは、矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)に収容されている人のうち、高齢または障害のため、釈放後直ちに福祉サービスを受ける必要があるものの釈放後の行き場のない人を対象にした取組みです。
矯正施設の収容中から釈放後まで、一貫した相談支援を実施することにより、社会復帰と地域生活への定着を支援しています。
令和3年度からは、まだ矯正施設に収容されていない被疑者、被告人で同じ境遇にある方も対象としています。
上記の費用は、この事業にかかわる職員の研修に支出されます。
生活保護就労支援員全国研修会事業委託費 1505万円
生活保護担当現業員全国研修開催委託費 770万8000円
福祉事務所には、”就労支援員” や、”現業員(ケースワーカー)” が配置されています。
前回のブログででてきましたが、就労支援員は、就労に関する相談・助言、個別の求人開拓やハローワークへの同行などの支援を実施しています。
ケースワーカーは、支援を必要とする人の相談を受け、その人が抱える問題の把握、支援策の検討、援助計画の立案などを行い、支援対象者の自立を促す役割を担っています。
上記の費用は、こういった職員の研修に支出されます。
緊急小口資金等特例貸付コールセンター事業委託費 9834万1000円
コロナ禍を受けて、”緊急小口資金等の特例貸付” が実施されていました。
休業や失業などにより、生活資金でお悩みの方々に向けた貸付制度です。
申請受付は令和4年9月で終了しましたが、この貸付に関するコールセンターが設置されています。
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120‐46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
重層的支援体制整備事業交付金 137億7387万7000円
前回のブログででてきましたが、”重層的支援体制” を整備しようという取組みがすすめられています。
生活上の課題の多様性や複雑性に対応した支援を行なおうという取組みです。
市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトにしています。
(図は三菱UFJリサーチ&コンサルティングからの引用です)
「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を、一体的に実施することになっています。
(図は三菱UFJリサーチ&コンサルティングからの引用です)
上記の費用は、この事業のために、地方公共団体(市区町村)へ支出されます。
今回も、この取組みについてのサイトのリンクを貼っておきますね。
婦人保護事業費補助金 15億7309万7000円
婦人保護事業費負担金 9億9892万4000円
婦人相談所運営費負担金 1614万1000円
こちらも前回のブログででてきましたが、”婦人保護事業” という取組みがあります。
もともとは売春をするおそれのある女性を保護する取組みでしたが、最近では、
DV
人身取引(性的サービスや労働の強要など)
ストーカー
などが対象に含まれています。
新しいところだと、悪質なホストクラブの対策も。
事業の概要はこんな感じ。
上の図にもありますが、婦人相談所(女性相談センター)が、各都道府県に設置されています。
婦人相談所には一時保護所が併設されており、DV被害を受けている女性と同伴児童の一時保護をしています。
令和3年度の実情は以下のとおり。
上記の費用は、婦人相談所の運営費、一時保護の費用などのために、地方公共団体に交付されます。
日本赤十字社救護業務費等補助金 2834万6000円
2つの取組みがあります。
・旧日本赤十字社救護看護婦等慰労給付金支給事務費 2165万円
第2次世界大戦時に衛生勤務についた旧日本赤十字社の従軍看護婦などに、慰労給付金が支給されています。
この支給事務費になります。
・日本赤十字社救護員養成事業費 669万6000円
日本赤十字社は、非常災害時における医療救護活動に必要な知識・技術の習得のため、実習と講習を実施しています。
この講習を補助しています。
褒賞品費 522万1000円
3つの表彰があります。
・社会福祉事業功労者 厚生労働大臣表彰
令和5年度は、863名と55団体が表彰されました。
・ボランティア功労者 厚生労働大臣表彰
令和5年度は、49名と147団体が表彰されました。
・消費生活協同組合等 厚生労働大臣表彰
令和5年度は、31組合・連合会と29名の役員が表彰されました。
監査旅費 1227万7000円
3つの取組みがあります。
・社会福祉法人 監査指導旅費 23万9000円
社会福祉法人に対する指導監査には、一般監査と特別監査があります。
一般監査は実施計画を策定した上で一定の周期で実施され、特別監査は運営等に重大な問題を有する法人を対象として随時実施されます。
・消費生活共同組合 監査指導旅費 195万円
”消費生活共同組合” とは、組合員が出資し、組合員が組合員のための事業や助け合い活動を行い、組合員が利用する非営利の協同組織をさします。
”生協” や、”コープ” という名前のほうがなじみがあるかもしれません。
令和4年度の調査によると、全国に906組合、組合員数は6889万人になります。
所管は基本的に都道府県ですが、地域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働省が所管し、監査指導を実施しています。
・生活保護 監査指導旅費 1008万8000円
福祉事務所における生活保護の実施が適切に実施されているかどうかを監査、必要に応じて助言・指導を行っています。
災害福祉支援ネットワーク中央センター事業委託費 1550万6000円
少し前に、災害派遣医療チーム(DMAT)、災害派遣精神医療チーム(DPAT)について取り上げましたが、災害派遣福祉チーム(DWAT/DCAT)も、各都道府県に整備されつつあります。
災害発生時、要配慮者(高齢者、障がい者、子どもなど)に対する福祉支援を行う専門チームです。
2022年に、この専門チームの取組みを集約する ”災害福祉支援ネットワーク中央センター” が開設されています。
平時には、広域的な派遣体制の構築や、全国研修などを実施、
災害時には、DWATの活動状況の集約や、他県との派遣調整などを実施します。
社会福祉施設サービスの質の向上のための調査研究事業委託費 1152万7000円
”福祉サービス第三者評価事業(福祉サービスの質を、当事者以外の第三者評価機関が専門的かつ客観的な立場から評価する事業)”
”運営適正化委員会事業(社会福祉、法律、医療などの学識経験者で構成される第三者機関が、福祉サービスの適正な運営の確保と、福祉サービスに関する利用者などからの苦情の適切な解決をはかる事業)”
の2つの事業について、課題を整理するとともに、事業の見直し内容や課題の改善策を検討する取組みです。
ホームレスの実態に関する全国調査委託費 1093万5000円
ホームレスの実態に関する全国調査(目視による概数調査)が実施されています。
令和5年1月の調査結果は、こんな感じ。
・ホームレスが確認された地方公共団体は、234市区町村
・確認されたホームレス数は、3065人(男性2788人、女性167人、不明110人)
・ホームレス数が多かったのは、大阪府(888人)、東京都(661人)、神奈川県(454人)
なお、東京都23区及び指定都市で全国のホームレス数の8割弱を占めている。
・ホームレスが確認された場所は、「都市公園」25.2%、「河川」23.5%、「道路」22.1%、「駅舎」6.2%、「その他施設」23.1%
社会保障生計調査委託費 1億0832万2000円
生活保護被保護世帯の家計収支の実態を調査する取組みです。
令和3年度の調査結果は、こんな感じ。
・2人以上の世帯の実収入は、18万3182円
このうち、就労収入額は2万5507円、生活保護給付金品の額は9万5645円
・単身世帯の実収入は、12万2766円
このうち、就労収入額は1万1652円、生活保護給付金品の額は8万0214円
・2人以上の世帯の消費支出は、14万9877円
このうち、食糧費は4万7639円、住居費は3万0836円
・単身世帯の消費支出は、10万3057円
このうち、食糧費は2万9148円、住居費は3万3974円
生活保護などにかかわる項目はここまで。
つぎは、こんな項目。
- 自殺対策費 36億9855万5000円
自殺も、大きな問題のひとつです。
警察庁の自殺統計によると、令和4年の自殺者数は、2万1881人。
死亡者数は低下しているように見えますが、自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)は高いままです。
また、若年層の死因の第1位が自殺であることも悲しい現状。
国も、自殺対策に取り組んでいます。
たとえば、こんな支出。
自殺対策費補助金 1億1105万3000円
”地域自殺対策推進センター” の運営事業費として、地方公共団体へ交付されます。
地域自殺対策推進センターは、全国の47都道府県と、20の指定都市に設置されています。
管轄する地域のエリアマネージャーとして、各自治体の自殺対策への支援を実施しています。
自殺対策事業委託費 2902万6000円
調査研究等業務交付金 4億8892万5000円地域自殺対策強化交付金 29億8313万3000円
自殺対策として、いくつかの取組みが実施されています。
・ゲートキーパー養成・支援事業
”ゲートキーパー” とは、悩んでいる人に気づき、声をかけてあげられる人のことです。
ゲートキーパーを養成するための教材やカリキュラム
ゲートキーパーの養成
ゲートキーパーへの支援
といった事業に支出されます。
・自傷・自殺未遂レジストリを活用した自殺未遂者支援の推進
自殺未遂者は自殺のハイリスク集団とされています。
そのため、個人が特定されないよう配慮した上で、救急病院から自殺未遂に関する情報の提供を受け、”自傷・自殺未遂レジストリ” を構築する取組みを、令和4年度から進めています。
・自殺未遂者に対する地域における包括的支援モデル事業
自殺未遂者の自殺を防止するため、コーディネーターを配置し、上記の ”自傷・自殺未遂レジストリ” に参加している救急病院退院後、地域における必要な支援へのつなぎ・継続的支援を行うモデル事業を実施します。
また、”地域自殺対策推進センター” と、救急病院など関係機関の連携体制を構築するための定期的な会議を実施します。
・若者の自殺危機対応チーム事業
子どもの自殺危機に対応していくチームとして、学校や地域の支援者などが連携し、自殺対策にあたる仕組みを構築する取組みです。
専用の特設サイトのリンクを貼っておきます。
せひ一度ご覧になってみてください。
今日はここまで。
厚生労働省のホームページのリンクを貼っておきます。
最後まで見ていただき、ありがとうございました。
ではまた。