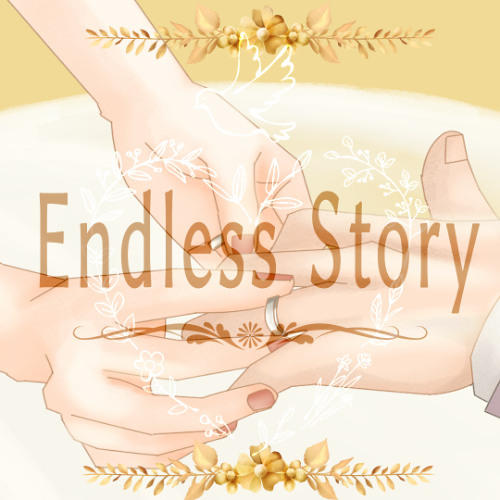こんにちは
解説方法を大幅に変えた関係で2部体制で収まりきらなくなってしまったため、急遽「後編」を設けて間奏2以降の解説をして閉幕したいと思います
間奏2の解説の前に、最近のブログで実施していた1コーラス(1番)の各セクションの冒頭のコードの配置を図で確認しておきましょう
予備知識として、ほとんどの楽曲がどのように作られているのかという大枠を再確認しておきましょう
こんな感じで野球のベースランニングのようにホームベースであるイントロから始まり、間奏1に還るようなイメージで1コーラス(1番)というのが一般的な作り方です
これに従いつつ、冒頭サビを設けたり、イントロカット、Bメロスキップなどといった様々なアレンジを施して数多くのパターンの楽曲が世に誕生しているわけですが、この大前提を理解した上で今作の1番はどんな風に構成されていたのかを確認してみましょう
良い機会なので今回からは各セクションの冒頭に加え、結尾のコード進行についても確認出来るようにコード数を増やしました
また、冒頭サビはボーカルのメロディのみのN.C.区間なので省略させていただきました
こんな感じで、AメロだけⅠM7冒頭、あとはみなⅣM7冒頭となっています
結尾については間奏1だけⅠM7、あとはみなⅤ7の半終止を使っています
漫画とかで例えるのであれば、間奏1のⅠM7結尾が1話目の完結を示す重要なポイントになっていますね
先に伝えますと、間奏2は間奏1のコード進行を引用しているため、結尾はAMaj(ⅠMaj)となっています
つまり、1番の物語が本当の意味で一区切りつくのは間奏2まで聴いてからという事になります笑
冒頭が物語に大きな影響を与えるのは事実で、実際にⅠM7冒頭とばかりしてしまうとトニックの性質故か、変わらない展開からマンネリ化しかねません
それを避けるためにどこか別のセクションでⅣM7冒頭にするといった凹凸を作らないといけません
なぜそのコードを冒頭にしたのかを示す重要な意味を持っているのが実は前セクションの結尾のコード
最近のブログで導入し始めた時はそこまで結尾に対して重要視していなかったのですが、この各セクション内のケーデンス(チャプター)解説を開始してから結尾のコードの存在も非常に重要な意味を示しているという事を痛感しましたので、この新しい解説方法に導入させていただきました
今後もこのやり方で1番の解説終了後に1番の全体像を図で確認するという事を行っていこうと思います
そもそもこの解説を最近のオリジナル楽曲のブログから加えた始めたのは、楽曲というのは基本的に1番で基本骨格が出来上がっているようなものなので、1番さえその楽曲の全容がほぼほぼ理解する事が可能だからです
特殊なセクションを設けない限りは大抵の場合、2番以降は1番の骨格を準えてアレンジする事がほとんどなので、1番だけ分かっていれば誰でも曲は作れるという事も同時に意味しています
もちろん、これを聴いたからといって既存曲を1番だけ聴いて知った気になられるのは困りますので、あくまでそうした構造をしているという事を参考程度に知った上で2番以降も楽しむという深い次元で音楽に触れるための豆知識として持ち帰って下さい
ここからは間奏2の解説に移りたいのですが、これ以降は一部を除いて1番までのコード進行をベースにして制作しているので、これ以降解説すべきコード進行はほぼほぼありません
ですので、ここから先は★をつけたセクションを除き、箇条書きでコード進行の引用元を羅列していきます
間奏2…間奏1-2を引用(AMaj(ⅠMaj)を1小節短縮)
Aメロ2…Aメロ1を引用
Bメロ2…Bメロ1を引用(EMaj(ⅤMaj)を2小節延長)
間奏3…間奏2を引用(1~4小節を3ループ)
★ラスサビ前…サビを引用、13~16小節目だけこの後解説
ラスサビ…サビを引用(EMaj(ⅤMaj)を3小節延長)
アウトロ…間奏1-2を引用
以上です
★をつけたラスサビ前の13~16小節目のコード進行だけ最後に解説して終了します
DMaj(ⅣMaj) - F#m(Ⅵm) - C#7(Ⅲ7) - F#m(Ⅵm) - EMaj(ⅤMaj) - Asus4(Ⅰsus4) - A7(Ⅰ7)
これがそのコード進行です
サビと異なるポイントはEMaj(ⅤMaj)の半終止で終わるはずのものを「Ⅰsus4 - Ⅰ7」を加えて延長しているところです
本当なら「Ⅰsus4 - ⅠMaj」と進行すべきところなのですが、それを嫌っているのは、このセクションがまだラスサビ"前"だからです
この二次ドミナント「Ⅰ7」はⅠMaj(ⅠM7)のドミナントⅤ7なので、当然Key=Aにそのコードはダイアトニックコードとして存在していません
ではどこのⅤ7なのかと言いますと、Key=DのA7(Ⅴ7)です
実はこの後に続くラスサビの冒頭DMaj(ⅣMaj)とでKey=Dの「Ⅴ7 - ⅠMaj」のドミナント・モーションを組んでいたものになります
他Keyからの一時的な拝借なので転調という言い方はしないものの、ピボットコード転調をかすっていると言えばかすっています
DMaj(DM7)…Key=AのⅣMaj(ⅣM7)
DMaj(DM7)…Key=DのⅠMaj(ⅠM7)
ディグリーネームは違えど、両者共にMaj(M7)のコードで共通しています
この場合、コードの機能に関係なく同じコード同士を架け橋役として利用して転調させる事が出来るというのがピボットコード転調なので、実質それが成立していると言えば成立しています
ただ、実際にはDMaj(ⅣMaj)を解決先としている事から、実際にKey=Dに転調しているわけではなく、そういう流れだけを利用してA7(Ⅰ7)を半終止役としてKey=Dから拝借したにすぎません
単にAMaj(ⅠMaj)として完結させないための延命措置です
中編の時にAadd9(Ⅰadd9)を引き合いに出して違いについて解説しましたが、Aadd9(Ⅰadd9)はAMaj(ⅠMaj)を母体にしている側面があるので、単体で用いる事も出来るし、AMaj(ⅠMaj)に帰結するようにして拡張型変終止要員で用いると綺麗に収まります
これでA7(Ⅰ7)を持ってくるという展開はやった事がないので何とも言えませんが、パンチがありすぎて逆に相性が良くないようなイメージがあります
一方で、Asus4(Ⅰsus4)のように調性感が曖昧なコードと組み合わせる事でセオリー通りにAMaj(ⅠMaj)に解決する以外にA7(Ⅰ7)への解決をしても違和感がないという選択肢が増えるので、Ⅰ7の可能性をより引き出すのにうってつけな相棒とも言えるわけです
何より、躊躇なくノンダイアトニックコードを組み込めるという余白をⅠsus4が設けてくれているので、有効利用しないわけにはいきません
二次ドミナントはこうした異文化交流的な意味合いを込めたドミナント・モーションを組んで原曲キーだけでは再現出来ない一風変わった雰囲気を作り出す事が出来ますが、その中でもⅠ7は代表格であり、Ⅰsus4とのコンビネーションは抜群なので、今後も度々登場します(これも好きなコードの1つ笑)
使ってみたいと思った方は是非各自の楽曲の中に導入してみて下さい
ダイレクトで挿入するのとⅠsus4を介すのとで違った景色が見れる事でしょう
せっかくなので最後にラスサビ前の全容を図にしてみました
二次ドミナントなので本当はドミナントとしようと思ったのですが、枠が変に伸びてしまうし、そもそもAMaj(ⅠMaj)に進行するフリしてA7(Ⅰ7)としたという背景もあるので、あえてトニック枠として扱いました
これでまらラスサビ前が続くのであればChapter 4を更にリエントリーする事になったのですが、ここでラスサビ前が終了するので、AMaj(ⅠMaj)による完全終止と見せかけたノンダイアトニックコードによる半終止がこのセクションの答えです
こういった事もあるからこそ、結尾のコードが何で終わっているのかという事にも着目しないといけませんね
自身の解説方法がまだまだ不十分であった事を痛感した次第です
こんな感じで第1回目となるEndless Storyの歌詞とコード進行について解説しました
今作はⅠsus4絡みでⅠ7の運用方法やⅠadd9の使い方など様々な応用方法が詰め込まれていますので、少しずつ理解しながら各自の音源に還元していって下さい
図面展開で各セクションの実態を把握するというのも面白いですし、各終止がもたらす効果や意味を知るのにも有効だと判断されましたので、次回以降もその方法を用いて解説をしていこうと思います
また、更新形式によるコード進行のブログについてですが、こちらも最新の解説方法に基づいてもう一度書き直そうと思います
現在公開しているもの達は一旦下書き編集中という形にして一度非公開にさせていただき、最新の状態にして順次更新していきたいと思いますので、ご理解・ご協力をお願い板いますm(_ _)m
それではまた、次回のブログでまたお会いしましょう
(^ ^)ノシBye Bye♪
Endless Storyの音源はこちら↓↓
ボーナストラック的に制作したMale Ver.も公開中↓↓
「不器用な想いを音で描く」を信条に、SoundCloudにオリジナル楽曲と東方自作アレンジを公開中です
興味があれば聴きに来て下さい♪
※ジャケット画像:太郎様
※Endless Storyの音源動画用のサムネイル画像をジャケット画像用に編集したもの