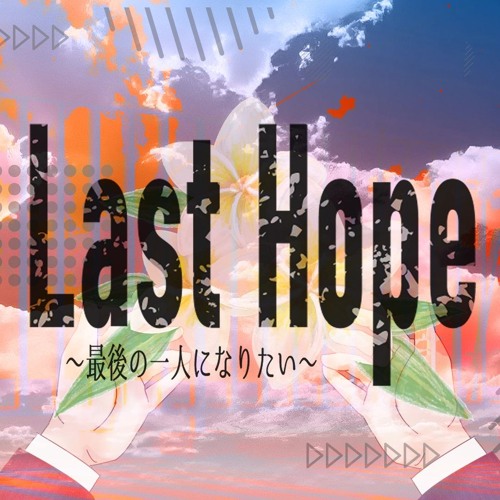こんにちは
文字数制限が怪しいところまできたので一度区切らせていただきましたが、今回は前回の続きで、Last Hopeのサビ1のコード進行の解説から再開していきます
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - Am(Ⅲm) - Dm(Ⅵm)
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - Fsus4(Ⅰsus4) - FMaj(ⅠMaj) - Gm(Ⅱm) - Am(Ⅲm)
これがサビ1前半8小節のコード進行です
1~4小節目は純粋な王道進行、5~8小節目は「451」のスリーコード進行にFsus4(Ⅰsus4)を経過和音的に挿入したものに9小節目のB♭Maj(ⅣMaj)に繋げるために「Ⅱm - Ⅲm」を経過和音的に挿入した複合アレンジとなっています
5~8小節目については、
①451進行+123進行
②4512進行+123進行
という見方が出来ます
こう捉えたらキリがないですが、4小節目のDm(Ⅵm)と9小節目のB♭Maj(ⅣMaj)も含めると、
③6451進行+1234進行
こうすればFMaj(ⅠMaj)を軸にした4コード進行の合体技と見る事が出来ます
8小節全体で見るならば、
④4536進行+6451進行+1234進行
Dm(Ⅵm)も含めてこういう事になります
割と綺麗に収まっている事に驚きです笑
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - D♭dim(♭Ⅵdim) - Dm(Ⅵm)
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - FMaj(ⅠMaj) - Csus4(Ⅴsus4) - C7(Ⅴ7)
FMaj(ⅠMaj) - B♭Maj(ⅣMaj) - Am(Ⅲm) - B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj)
次はサビ1後半12小節分のコード進行の解説に移ります
17~20小節目はAメロ2に繋げるためのきっかけとして設けた延長分になるので、見方によっては「間奏1」と言われても不思議ない4小節ではありますが、ここでは「サビ1」のものとして包含しました
さて、4小節単位で見ていきましょう
9~12小節目は1~4小節目の王道進行がベースとなり、Am(Ⅲm)をD♭dim(♭Ⅵdim)に置き換えたアレンジとなります
このD♭dim(♭Ⅵdim)はDハーモニック・マイナースケールのD♭dim(Ⅶdim)をメジャー#5・スケール視点に変換したものになります
本来ならノンダイアトニックコードとして扱う事になるはずのものですが、この解釈法を独自考案した事でD♭dim(♭Ⅵdim)をダイアトニックコードの範疇として使用可能としました
まぁ、元を辿ればD♭dim7(♭Ⅵdim7)はA7(♭9, omit 1)(Ⅲ7(♭9, omit 1))ですからね
表の通り、A7(♭9, omit 1)(Ⅲ7(♭9, omit 1))のルート音を除けばD♭dim7(♭Ⅵdim7)になります
故にA7(Ⅲ7)の、Am7(Ⅲm7)の代わりに使う事が出来るわけです
ところで、A7(♭9, omit 1)(Ⅲ7(♭9, omit 1))の♭9を半音上げて9thとしてあげると、D♭m7(♭5)(♭Ⅵm7(♭5))になります
表の通り、A7(9, omit 1)(Ⅲ7(9, omit 1))のルート音を除けばD♭m7(♭5)(♭Ⅵm7(♭5))になります
Dジャズ・マイナースケールのD♭m7(♭5)(Ⅶm7(♭5))がこれに当たるのですが、メジャー#5・スケールに変換すると♭Ⅵm7(♭5)になるので、これもダイアトニックコードとして使用する事が可能です
何が面白いかと言えば、D♭dim7(♭Ⅵdim7)もD♭m7(♭5)(♭Ⅵm7(♭5))も、A7(Ⅲ7)がルーツとなっているという事です
故にドミナントとして機能するのも頷けます
ただ、D♭m7(♭5)(♭Ⅵm7(♭5))に関しては中途半端な存在であるためか、運用方法についてネットでもあまり紹介されていません
では全く使えないのか?と思っていたのですが、これまでに学んできたm7(♭5)の特徴についての知識を総動員し、このような結果を得る事が出来ました
左はルート音だけを半音下げたCM7(ⅤM7)、右はルート音を転回したEm6(Ⅶm6)です
ⅤをM7化するというのはドミナントの存在を否定する事になるので理屈上成立しないでしょう
一方で、Em6(Ⅶm6)はEm7(Ⅶm7)の代わりに使えるという点で再現性は高いでしょう
そういった楽曲を今後作るかどうかは別として、D♭m7(♭5)(♭Ⅵm7(♭5))を運用出来る可能性が見えただけ良い収穫でしたね
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - FMaj(ⅠMaj) - Csus4(Ⅴsus4) - C7(Ⅴ7)
FMaj(ⅠMaj) - B♭Maj(ⅣMaj) - Am(Ⅲm) - B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj)
さて、9~12小節目で大分語ってしまいましたが、次は13~16小節目の解説に移りましょう
こちらは451進行で一度ケーデンスを完結させている中で17小節目のFMaj(ⅠMaj)に続くための延長で「Ⅴsus4 - Ⅴ7」を挿入したものになります
Ⅴsus4も僕はよく使うので使用方法の参考にしていただけたらと思います
最後の17~20小節目ですが、こちらはFMaj(ⅠMaj)で3小節消費後に1拍単位で4345進行を使った半終止にてサビ1を完結します
サビ1の全容を図に示すとこんな感じですね
前半8小節までを細分化すると、
①453進行+645進行+123進行
②453進行+6451進行+123進行
③453進行+645進行+451進行+123進行
④453進行+645進行+4512進行+123進行
⑤4536進行+645進行+123進行
⑥4536進行+6451進行+123進行
⑦4536進行+645進行+451進行+123進行
⑧4536進行+645進行+4512進行+123進行
などですね
他にもやろうと思えば出来ますが、①ほど重複のないきれいな細分化は出来なさそうですし、キリがないのでここまでにしておきます
後半8小節までを細分化すると、
①453進行+645進行+151進行+4345進行
②453進行+6451進行+151進行+4345進行
③4536進行+645進行+151進行+4345進行
④4536進行+6451進行+151進行+4345進行
などでしょうかね
さて、今作の1番までのコード進行をここまで解説してきました
大分細かく見るやり方をしてきましたが、ちょっと大変ですね、これは笑
別で用意したコード進行に関する更新型ブログには実践的なアレンジ例だけを掲載するような感じにしていこうと思います
この後はAメロ2以降の各セクションのコード進行の引用元をまとめていくのですが、その前に今作の1番のコード進行の冒頭と結尾を表を用いて確認していきましょう
こんな感じですね
マイナーキーに見せかけたイントロのⅥm7冒頭の後にAメロ1ではⅠM7を冒頭としてきちんとKey=Fである事を示しています
本当に最初だけインパクト要員でⅥm7冒頭を使っただけですね
結尾はバラバラですが、ⅣM7に繋げるという条件が揃えばAメロ1で使ったⅢm7結尾はⅤ7結尾よりも下手したら活躍する場面が多いかもしれません
運用方法の参考になれば幸いです
ここからはAメロ2以降のコード進行について各セクションのコード進行の引用元を箇条書きでまとめていきます
その中で、★をつけたセクションだけは個別で解説していきます
Aメロ2…Aメロ1を引用
Bメロ2…Bメロ1を引用、最後のN.C.をCMaj(ⅤMaj)完結に変更
サビ2…サビ1を引用、17~20小節目はカット
間奏1…Bメロ2後半8小節を引用
間奏2…Bメロ1の1~4・13~16小節を合体して引用
ラスサビ前…サビ1を引用、13~16小節目を最後の4小節をBメロ2最後の4小節に変更
ラスサビ1…サビ1を引用、17~20小節目を最後の4小節をBメロ2最後の4小節に変更
★ラスサビ2…この後解説
★アウトロ…この後解説
こんな感じですね
間奏1・2は若干複雑なのですが、Bメロ1・2をベースにして必要な部分だけをピックアップして組み込んだ感じになります
★のついたセクションだけ補足的に話をして終了したいと思います
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - D♭dim(♭Ⅵdim) - Dm(Ⅵm)
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - FMaj(ⅠMaj) - Csus4(Ⅴsus4) - C7(Ⅴ7)
FMaj(ⅠMaj) - Gm(Ⅱm) - Am(Ⅲm)
まずはラスサビ2の12小節のコード進行から見ていきましょう
ラスサビ2と名づけてはいますが、ラスサビ1の延長分を切り分けての事なので、ラスサビ1と合わせて実質「ラスサビ」となります
1~8小節目はサビ1の9~16小節目と同じ作りになっているので解説済みとして省略します
ここで補足的に解説したいポイントは9~12小節目のFMaj(ⅠMaj)3.5小節消費後の「Ⅱm - Ⅲm」を連結した123進行
FMaj(ⅠMaj)単一で進行した後にアウトロのB♭Maj(ⅣMaj)にするというパキっとした進行を滑らかにするために「Ⅱm - Ⅲm」を連結してセクション跨ぎで「1234進行」としています
1234進行は非常に便利なコード進行で、「ⅠMaj - ⅣMaj」の流れを滑らかにするのに最適です
僕の作り方からすると大抵この後は「Ⅳ(M7) - Ⅴ(7)」になる事が多いので、Ⅲm(7)とした拡張型偽終止解決という風にする事がほとんどです
Ⅲm(7)とするならば、「Ⅳ(M7) - Ⅰ(M7)」という変終止として用いるのが好ましいので、そうしない限りはⅢm(7)で解決した方が色々と誤解を招かずに済みますしね
まぁ、ⅢMajを使ったらもう何の言い訳のしようもないですがね笑
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - Am(Ⅲm) - Dm(Ⅵm)
最後に解説するアウトロのコード進行ですが、1~8小節はサビ1の前半8小節をそのまま引用しています
1~4小節目は王道進行をそのまま使っています
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - Fsus4(Ⅰsus4) - FMaj(ⅠMaj) - Gm(Ⅱm) - Am(Ⅲm)
こちらの5~8小節目のコード進行をよく覚えておいて下さい
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - D♭dim(♭Ⅵdim) - Dm(Ⅵm)
アウトロの9~16小節目のコード進行がこちらです
こちらもサビ1の後半8小節を基にしているので、9~12小節目はサビ1の9~12小節目と同じものを扱っています
重要なのが次の13~16小節目なのですが、
B♭Maj(ⅣMaj) - CMaj(ⅤMaj) - Fsus4(Ⅰsus4) - FMaj(ⅠMaj) - Gm(Ⅱm) - Am(Ⅲm)
先程の5~8小節目を再度ここで用いています
ここがサビ1と異なる大きなポイントとなっているのですが、これは曲が閉幕に向かうという事もあってサビ1の展開とは違うものにするために同じフレーズを繰り返しています
今作のコード進行の全体を先にご覧いただいてもお分かりの通り、今作は前作のOdyssey同様、フェードアウト方式で曲が終わる作り方をしています
音量を徐々に下げて静かに終わらせていくという点ではフェードアウト方式で終わる楽曲においては聴き覚えのあるフレーズを繰り返して終わらせる方がセオリーです(フェードアウトするのにきちんと完結する作り方って逆に違和感ありますからね)
そうした戦略の下でこのアウトロはサビ1のフレーズを使って永続ループするような作りにしているのですが、それを象徴しているのが5~8・13~16小節目の4小節になります(後者は前者のコピー)
これらの小節のコード進行の最後は共通してAm(Ⅲm)となっていますので、完全終止になっていないから再度ケーデンスを繰り返さないといけません
「Ⅰsus4 - ⅠMaj」によって前のチャプターが一度完結し、新たなチャプターが1234進行として開始している点から、このAm(Ⅲm)はそうした役割を担うためにGm(Ⅱm)とセットになって永続ループの意味を示している事になります
このサビ1っぽい作りをしている16小節1セットを再度繰り返しながらフェードアウトしていく方向に持っていっているのがアウトロの存在意義になります
大抵はイントロ(冒頭サビなどがある場合は間奏1とか?)かサビが使われるケースが多い印象にあります
そんな中で今作はサビ1を繰り返すという風にしましたが、どこのセクションのフレーズを繰り返した方がいいかは制作者の中にしか答えはありませんので一概には言えません
あとは制作される皆様の中で各自納得のいく作りをしていっていただければと思います
といった感じで前編から続くLast Hopeのコード進行の解説をこれにて終了します
解説の仕方はまだまだ試作段階ではありますが、今回も皆様にとって学びのある何かを得るものがあれば幸いです
それではまた、次回のブログでまたお会いしましょう
(^ ^)ノシBye Bye♪
Last Hopeの音源はこちら↓↓
「不器用な想いを音で描く」を信条に、SoundCloudにオリジナル楽曲と東方自作アレンジを公開中です
興味があれば聴きに来て下さい♪
※ジャケット画像:太郎様
※Last Hopeの音源動画用のサムネイル画像をジャケット画像用に編集したもの