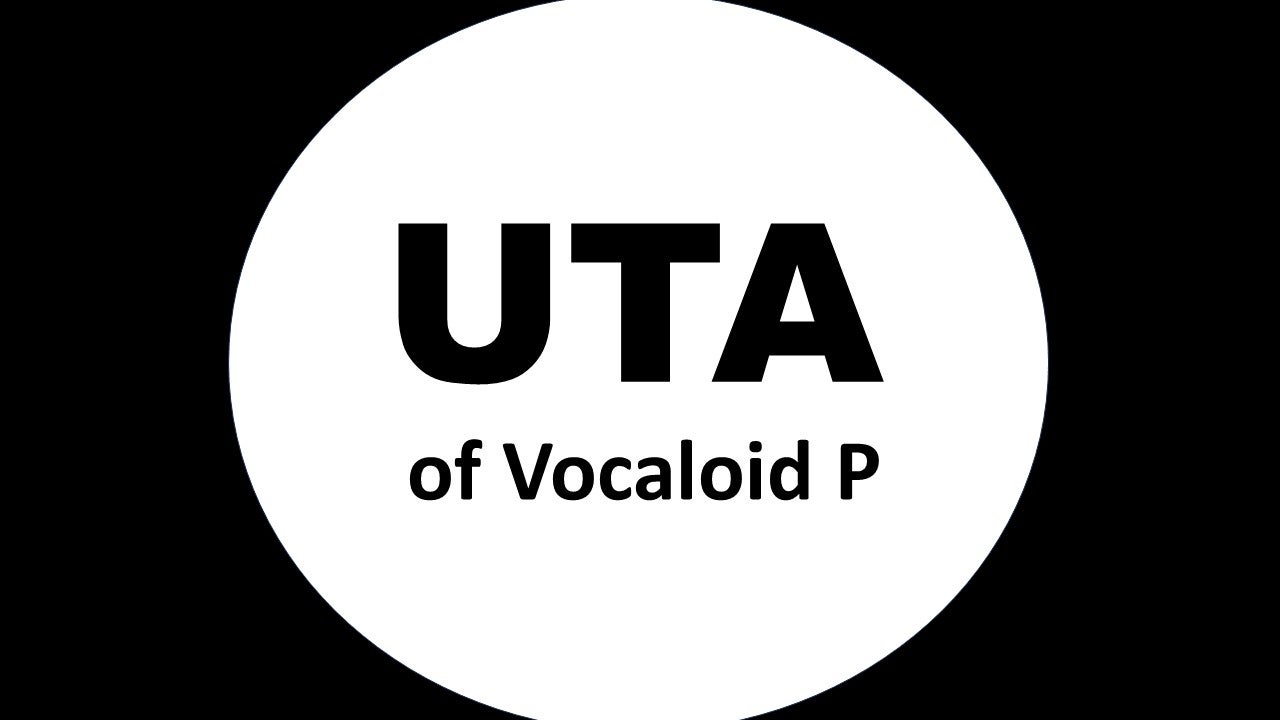こんにちは
前回、Blkの正規のフォーメーション「0・2・6・10」の状態で当てはまる既存のコードスケールの検索と、分数augなるものがどういった考えの下で生まれ、それの何に問題があったのかといった事について既存の音楽理論を駆使し、独自視点で語りました
今回はそうした発想によって閃いたこのフォーメーションのパズルパターンを様々検討し、前回のブログで行った既存のコードスケールの一致不一致の検証を様々やってみたいと思います
これまでにない新しい景色が見られるかもしれません(多分笑)
例の如く、↓↓の表を例にして様々なパターンを検証していきます
0(C)…完全1度
2(D)…長2度(9th)・減3度
6(F#)…増4度(#11)・減5度
10(B♭)…増6度(#13)・短7度
従来のフォーメーション「0・2・6・10」はこんな感じでしたね
まずはこの4つの数字の組み合わせの中で理屈上フォーメーションチェンジ可能なパターンがどれくらいあるのかを確認していくのですが、どういったパターンが可能かというのは大凡見当がついています
今回実験するパターンをコードで示すと、以下の3パターンです
・Daug/C
・F#aug/C
・B♭aug/C
…あれ?
Daug/Cって本家フォーメーションでやってませんでしたっけ?
察しの良い方々からそんな声が聴こえてきそうな気がしますが、確かにその通りです
で・す・がっ!
本家フォーメーションの時はあくまでベース音であるCを0番目としてやっていただけで、Dを0番目としていたわけではないんですよね
つまり、今回検証するパターンというのは、
分数augなる転回パターン3つのそれぞれのルート音を0番目として並び替えて出来るサブタイプ的フォーメーション上でBlk成立を試みる
こういう実験をするというわけです
本家フォーメーションを「プランA」とするならば、今回検証するのはプランB・C・Dみたいな感じの事をすると思ってもらえればと思います
これが面白そうだな!と思っていただけた方はぜひ続きを読んでいただき、どんな結末を迎えるのかを共に見届けて下さい♪
さて、どれから始めようかなと悩ましい所なのですが、ここは僕の話の展の都合に合わせる感じでまずはプランD的な感じの「B♭aug/C」から始めます笑
実はこのB♭aug/C Ver.に関しては、
↑↑の時に一度問題提起していたのですが、ここでようやくその検証を正式に行えます笑
さて、このB♭aug/Cを例に今回検証するサブタイプなるものの見つけ方について話そうと思いますが、まず本家フォーメーションに倣い、Cを0番目として
10(B♭)・0(C)・2(D)・6(F#)
という風に並び替えます
今行っているのは本家フォーメーションのまま単にパズルゲームの如く組み替えただけで、元々の本家フォーメーションのような0から始まる数字の配置にはなっていません
もしこれを、
・Cを0番目のままにし、それに合わせて他の音程の数字を変更
・B♭を10番目のままにし、それに合わせて他の音程の数字を変更
という基準を設けた場合、
・-2(B♭)・0(C)・2(D)・6(F#)
・10(B♭)・12(C)・14(D)・18(F#)
となるはずなのです
さすがにマイナスはないにしても、B♭を10番目のままにしてしまうと1オクターブ上の話みたいになってしまってより訳が分からなくなるので、これを本家フォーメーションに倣い、B♭を0番目として数字の配置をこのように変更すると、
0(B♭)…完全1度
2(C)…長2度(9th)・減3度
4(D)…長3度・減4度
8(F#)…増5度(#12)・短6度(♭13)
はい、また違う顔を見せてくれましたね笑
テンション・ノートに該当しそうなものとして、
ナチュラル・テンション…9thC
オルタード・テンション…♭13G♭
準オルタード・テンション…#12F#
が含まれています
これがB♭aug/Cで作ったフォーメーションのサブタイプ
0(B♭)・2(C)・4(D)・8(F#)
です
名前は何でもいいのですが、本家フォーメーションの時にCを0番としてやっていたので、その名残でここでは
サブタイプ Ver. B♭
という事にしておきましょうか
このサブタイプ Ver.B♭の面白いのは、0(B♭)・2(C)までは本家の同じ度数なのですが、後半の4(D)・8(F#)が大きく変わったというところですね
本家の時は増6度(#13)・短7度を含んでいたために短7度の存在を必須条件にするみたいにしていましたが、今回は増5度(#12)・短6度(♭13)に変わっているため、7度の選択が自由になった事で使える既存のコードスケールの選択肢が増える可能性が期待出来ます
一方で、本家の増4度(#11)・減5度が長3度・減4度に変わったというのもかなり重要で、長3度という条件提示がなされた事で既存のコードスケールで再現するダイアトニックコードがメジャー系であるという縛りが加わりました
要約すると、サブタイプ Ver.B♭で出来るコードはⅤ7系に加えて「M7系」の選択肢も可能としたフォーメーションと言えます
この仮説を基に、前回のブログで行った異名同音の変更も1カウントとして、
◎→完全一致
〇→部分一致(1ヶ所のみの変更で成立)
△→部分一致(2ヶ所の変更で成立)
の条件提示をした上で既存のコードスケールで再現可能かどうか検証してみましょう
なお、アメブロの文字数制限(画像などの暗号みたいなのもカウント)の事もあるので、今回は結果のみを提示し、細かい解説は省略させていただきます(画像を用いて簡潔に述べる程度の事はします)
気になる方は各自コードスケールを調べて各々の手元で再現して確かめて下さい(人に教わっただけでは本当の意味では理解出来ないし、自分の言葉で話せないからね)
それではいきましょう
サブタイプ Ver.B♭を実現可能な既存のコードスケールは以下の通りです
①完全1度・長2度(9th)・長3度・増5度(#12)
◎アイオニアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(ハーモニック・マイナースケール)
◎リディアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(メロディック・マイナースケール)
◎ホールトーンスケール:拡張Ⅴ7
〇ミクソリディアン♭6・スケール:Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
→増5度(#12)を短6度(♭13)とすれば◎
〇ハーモニック・メジャースケール:ⅠM7
→増5度(#12)を短6度(♭13)とすれば◎
〇シンメトリック・オーギュメントスケール:拡張Ⅰ(♭Ⅲ)・Ⅳ(♭Ⅵ)M7
→長2度(9th)を持つⅠ(♭Ⅲ)M7・Ⅳ(♭Ⅵ)M7であれば◎
△オルタードスケール:拡張Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
→増5度(#12)を短6度(♭13)に変更、長2度(9th)を持つⅤ7であれば◎
△ウルトラ・フリジアンスケール:拡張Ⅴ7(ダブルハーモニックメジャースケール)
→増5度(#12)を短6度(♭13)に変更、長2度(9th)を持つⅤ7であれば◎
△ロクリアン♭♭3♭♭7・スケール:拡張Ⅴ7(ダブルハーモニックメジャースケール)
→増5度(#12)を短6度(♭13)に変更、長3度を持つⅤ7であれば◎
②完全1度・長2度(9th)・長3度・短6度(♭13)
◎ミクソリディアン♭6・スケール:Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
◎ハーモニック・メジャースケール:ⅠM7
〇アイオニアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(ハーモニック・マイナースケール)
→短6度(♭13)を増5度(#12)とすれば◎
〇リディアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(メロディック・マイナースケール)
→短6度(♭13)を増5度(#12)とすれば◎
〇オルタードスケール:拡張Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
→長2度(9th)を持つⅤ7であれば◎
〇ウルトラ・フリジアンスケール:拡張Ⅴ7(ダブルハーモニックメジャースケール)
→長2度(9th)を持つⅤ7であれば◎
〇ロクリアン♭♭3♭♭7・スケール:拡張Ⅴ7(ダブルハーモニックメジャースケール)
→長3度を持つⅤ7であれば◎
〇ホールトーンスケール:拡張Ⅴ7
→短6度(♭13)を増5度(#12)とすれば◎
△シンメトリック・オーギュメントスケール:拡張Ⅰ(♭Ⅲ)・Ⅳ(♭Ⅵ)M7
→増5度(#12)を短6度(♭13)に変更、長2度(9th)を持つⅠ(♭Ⅲ)M7・Ⅳ(♭Ⅵ)M7であれば◎
③完全1度・減3度・長3度・増5度(#12)
〇アイオニアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(ハーモニック・マイナースケール)
→減3度を長2度(9th)とすれば◎
〇リディアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(メロディック・マイナースケール)
→減3度を長2度(9th)とすれば◎
〇ホールトーンスケール:拡張Ⅴ7
→減3度を長2度(9th)とすれば◎
△ミクソリディアン♭6・スケール:Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
→減3度を長2度(9th)に変更、増5度(#12)を短6度(♭13)とすれば◎
△ハーモニック・メジャースケール:ⅠM7
→減3度を長2度(9th)に変更、増5度(#12)を短6度(♭13)とすれば◎
△シンメトリック・オーギュメントスケール:拡張Ⅰ(♭Ⅲ)・Ⅳ(♭Ⅵ)M7
→減3度を長2度(9th)に変更、長2度(9th)を持つⅠ(♭Ⅲ)M7・Ⅳ(♭Ⅵ)M7であれば◎
④完全1度・減3度・長3度・短6度(♭13)
〇ミクソリディアン♭6・スケール:Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
→減3度を長2度(9th)とすれば◎
〇ハーモニック・メジャースケール:ⅠM7
→減3度を長2度(9th)とすれば◎
△アイオニアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(ハーモニック・マイナースケール)
→減3度を長2度(9th)に変更、短6度(♭13)を増5度(#12)とすれば◎
△リディアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(メロディック・マイナースケール)
→減3度を長2度(9th)に変更、短6度(♭13)を増5度(#12)とすれば◎
△オルタードスケール:拡張Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
→減3度を長2度(9th)に変更、長2度(9th)を持つⅤ7であれば◎
△ウルトラ・フリジアンスケール:拡張Ⅴ7(ダブルハーモニックメジャースケール)
→減3度を長2度(9th)に変更、長2度(9th)を持つⅤ7であれば◎
△ロクリアン♭♭3♭♭7・スケール:拡張Ⅴ7(ダブルハーモニックメジャースケール)
→減3度を長2度(9th)に変更、長3度を持つⅤ7であれば◎
△ホールトーンスケール:拡張Ⅴ7
→減3度を長2度(9th)に変更、短6度(♭13)を増5度(#12)とすれば◎
⑤完全1度・長2度(9th)・減4度・増5度(#12)
〇アイオニアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(ハーモニック・マイナースケール)
→減4度を長3度とすれば◎
〇リディアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(メロディック・マイナースケール)
→減4度を長3度とすれば◎
〇ホールトーンスケール:拡張Ⅴ7
→減4度を長3度とすれば◎
△ミクソリディアン♭6・スケール:Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
→減4度を長3度に変更、増5度(#12)を短6度(♭13)とすれば◎
△ハーモニック・メジャースケール:ⅠM7
→減4度を長3度に変更、増5度(#12)を短6度(♭13)とすれば◎
△シンメトリック・オーギュメントスケール:拡張Ⅰ(♭Ⅲ)・Ⅳ(♭Ⅵ)M7
→減4度を長3度に変更、長2度(9th)を持つⅠ(♭Ⅲ)M7・Ⅳ(♭Ⅵ)M7であれば◎
⑥完全1度・長2度(9th)・減4度・短6度(♭13)
〇ミクソリディアン♭6・スケール:Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
→減4度を長3度とすれば◎
〇ハーモニック・メジャースケール:ⅠM7
→減4度を長3度とすれば◎
△アイオニアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(ハーモニック・マイナースケール)
→減4度を長3度に変更、短6度(♭13)を増5度(#12)とすれば◎
△リディアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(メロディック・マイナースケール)
→減4度を長3度に変更、短6度(♭13)を増5度(#12)とすれば◎
△オルタードスケール:拡張Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
→減4度を長3度に変更、長2度(9th)を持つⅤ7であれば◎
△ウルトラ・フリジアンスケール:拡張Ⅴ7(ダブルハーモニックメジャースケール)
→減4度を長3度に変更、長2度(9th)を持つⅤ7であれば◎
△ロクリアン♭♭3♭♭7・スケール:拡張Ⅴ7(ダブルハーモニックメジャースケール)
→減4度を長3度に変更、長3度を持つⅤ7であれば◎
△ホールトーンスケール:拡張Ⅴ7
→減4度を長3度に変更、短6度(♭13)を増5度(#12)とすれば◎
⑦完全1度・減3度・減4度・増5度(#12)
△アイオニアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(ハーモニック・マイナースケール)
→減3度を長2度(9th)に変更、減4度を長3度とすれば◎
△リディアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7(メロディック・マイナースケール)
→減3度を長2度(9th)に変更、減4度を長3度とすれば◎
△ホールトーンスケール:拡張Ⅴ7
→減3度を長2度(9th)に変更、減4度を長3度とすれば◎
⑧完全1度・減3度・減4度・短6度(♭13)
△ミクソリディアン♭6・スケール:Ⅴ7(メロディック・マイナースケール)
→減3度を長2度(9th)に変更、減4度を長3度とすれば◎
△ハーモニック・メジャースケール:ⅠM7
→減3度を長2度(9th)に変更、減4度を長3度とすれば◎
以上8パターンの総合結果です
なお、この8パターンは以下の通りに3つの音程の異名同音を固定し、グループ分けをして増5度(#12)と短6度(♭13)の違いを見るという方法で行ったものです
①・②…完全1度・長2度(9th)・長3度固定
③・④…完全1度・減3度・長3度固定
⑤・⑥…完全1度・長2度(9th)・減4度固定
⑦・⑧…完全1度・減3度・減4度固定
①~④の4グループのみで決着がついた感じですね
⑤以降は①~④の異名同音の複数パターンみたいな感じで新しいコードの発見に繋がるようなものは残念ながらありませんでした
いやぁM7系もいけるでしょうとか予想の段階でホラってましたが、まさかハーモニック・メジャースケール:ⅠM7がピンポイントで完全一致するパターンが存在するとは思いませんでした笑
Blkが単一のコードで縛られていない事でこうも表現の多様性を秘めているとは…
Taipaleさん、あなたは音楽において本当に大切な事を教えてくれるマジックコードを提供して下さっていると思います
ありがとうございますm(_ _)m
おかげさまで毎日脳が活性化してフィーバーモードに突入しています笑
その他にも既存のコードスケール上で再現可能なものとして見つかったのが、
アイオニアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7
リディアン・オーグメンテッドスケール:♭ⅢaugM7
ミクソリディアン♭6・スケール:Ⅴ7
ですね
マイナーキーの♭ⅢaugM7はジャズで使われる事が多いって言われているのですが、これだとジャズの人達は既にBlkを使いこなしていたって事になりますね笑
「あぁ、Blkってそういう事なの? それならいつもやってるやつだよ_:(´ཀ」 ∠):プップスー」案件確定ですやんヤダーってやつですね、これは笑
あとは本家フォーメーションの時には該当しなかったウルトラ・フリジアンスケールの亜型オルタードスケールが初参戦しましたね
せっかくなので表にして見てみましょう
E7(Ⅴ7)を例にするとこんな感じですね
サブタイプ Ver.B♭として成立したコードスケールを黄で示しました(□はサブタイプ Ver.B♭のフォーメーションに該当する音程)
それぞれのオルタードスケール毎で評価は以下の通りになりました
まずはオルタードスケール(スーパーロクリアンVer.)ですね
サブタイプ Ver.B♭に内包されている長3度と短6度(♭13)を収容していますので、あとは長2度(9th)が含まれている既存のⅤ7のコードスケールとの合体技によってBlkを成立させる事が可能となります
それが実現出来たのが本家フォーメーション同様、ミクソリディアンスケールとミクソリディアン♭6・スケールでした
次はウルトラ・フリジアンVer.ですね
こちらはダブルハーモニックメジャースケールのⅢ番目のコードスケールを亜型オルタードスケール(ダイアトニックコードが組めないため)として取り扱っているのですが、♭9・#9・♭13のオルタード・テンションに加え、ナチュラル・テンション13thが加わったものになります
こちらも先程のオルタードスケールと同様、サブタイプ Ver.B♭に内包されている長3度と短6度(♭13)を収容していますので、あとは長2度(9th)が含まれている既存のⅤ7のコードスケールとの合体技によってBlkを成立させる事が可能となります
それが実現出来たのがミクソリディアン♭6・スケールのみでした
最後はロクリアン♭♭3♭♭7 Ver.ですね
サブタイプ Ver.B♭に内包されている長2度(9th)・長3度・短6度(♭13)を全て収容していますので、全てのⅤ7のコードスケール上で成立しました
いや本当に「ロクリアン♭♭3♭♭7・スケール=Blk」って方程式を作ってもいいってくらい条件揃いすぎててびっくりですね笑
また、これらのオルタード拡張コードスケールのうち、黄で示した8種類のコードスケール上でaug7の実現が可能です
異名同音に関する事については定義づけられていないので、短6度を増5度とみなして対応しました
なお、Blkが再現出来ないⅤaug7のコードスケールについては灰で区別しています
もう大丈夫だとは思いますが、Ⅴaug7として運用する場合は完全5度の封印をお忘れなくw
次はホールトーンスケールの確認もしておきましょう
前回のブログで使用したものをそのまま転用しました
長2度(9th)も内包しているため、長2度(9th)を持っていないフリジアン・ドミナントスケールやミクソリディアン♭6・スケールでもサブタイプ Ver.B♭のBlkサウンドの再現が可能です
最後は今回初登場のシンメトリック・オーギュメントスケールです
本家フォーメーションでは短7度の指定があったためにaug7限定の再現となってしまっていましたが、サブタイプ Ver.B♭では7度の指定がないため、こうしたM7系のコードスケール上でもBlkサウンドが再現可能となっています
ただし、長2度(9th)をM7系限定です
シンメトリック・オーギュメントスケールには長2度(9th)が含まれていないため、黄で表記したアイオニアンスケールやリディアンスケールのように長2度(9th)を持つM7系のコードスケール上で実現可能です
…結局文字数多くなってしまったので、続きは次のブログに持ち越します笑
ここでは最後にBlkにまつわる話で個人的に引っ掛かっている「omit3」に対する個人的見解について話して終了したいと思います
Blkに初めて触れた当時は今ほどaugの何たるかも含めてBlkの実体が全くといっていいほど掴めていなかったので、omit3なる理屈がなぜ成立するのかも全く分かっていませんでした
参考情報元によると、このomit3の話をしているのは、
・ドミナントナインス型
・ハーフディミニッシュ型
の2点上で理論展開がなされているのです
なぜそういう解釈が出来るのかが分からなすぎるので詳しい解説はここでは控えますが、おそらくBlkのフォーメーションに当てはまる4つの数字の音程の組み合わせの中でこれらの亜種みたいなのが作れるという話からそういう説が浮上したものと思われます
これに対する今の僕の見解として皆さんにお伝えしたいのは、
条件付きでアリ
です
その条件とは、
メロディライン上のみ
つまり、コードをomit3するなという事を言いたいのです
↑↑の時にパワーコードの上にのせる3和音の3つ目である3度はエレキギターなどにおいては省略可能という話をしましたが、あれはエレキギターのような力強いサウンドを奏でる楽器において完全1度と完全5度だけ(パワーコード)で音楽として成立と言われているが故に3度省略可能と言われているだけで、3度不要論みたいな感じの意味ではありません
エレキギターで省略した分を別の楽器(ボーカルなども含めて)のメロディライン上で3度を混ぜる事をしないと調性がなくなり、楽曲の統一感もなくなってしまいます
そんなパワーコードですら楽譜上では「〇5」という書き方をします
「〇Maj(omit3)」「〇m(omit3)」みたいな書き方で「パワーコードです!」なんて言い方は基本的にはしません(見た事ない)
こう書いてしまうと3度がなくても音楽として成立するんだという大いなる誤解をする人が増えてしまいます
例えが合ってるか分かりませんが、1階と2階の間に壁という隔たりがある間取りの一軒家に「広々空間が欲しい!」みたいな感じでその壁をぶち抜いて吹き抜け空間を作るみたいな事をしてるようなものです
一見するとオシャンティ~♪と思うかもしれませんが、それがもし耐震性を維持するために重要な壁だったとしたら地震が着た瞬間ガラガラガッシャンっ!からのチーンorz川 って事になるわけですよ
ましてやⅤ7のような長3度と短7度によるトライトーンが重要視されるコードにおいてomit3などと楽譜上に書き起こすものなら、先の耐震性といった構造や文脈を重要視するジャズの人達に「何してくれてるの?お前(゚Д゚#)」って怒られると思いますorz
そのコードがメジャー・マイナーどちらの性質を持ったコードなのかをハッキリさせるための重要な役割を担っているからこそ、3度は7度以上に重要視される存在(ジャズでは7度も必須)なので、このブログを読んで下さった皆さんはomit3したコードの譜面再現は用いないように気をつけましょう
ただし、先程もお伝えした通り、メロディライン上でomit3をするのは問題ないと見ています(コードに直接影響ないので)
という事で、少しでも腑に落ちたところがあったらいいなと思いながら一旦サブタイプ Ver.B♭の解説(勝手に作り出したものだけど笑)と、おまけで用意したomit3との向き合い方についての話を終了します
次回は別のサブタイプの掘り下げをしていきますのでお楽しみに♪
ここまで読んでいただきありがとうございました!!!
いつもの感じで締めさせていただきます
それではまた、次回のブログでまたお会いしましょう
(^ ^)ノシBye Bye
参考情報元の数々↓↓
Blackadder Chordを、コード進行に手軽に取り入れよう!
マイナーキーのダイアトニックコード【エレキギター博士】←♭ⅢaugM7について
「不器用な想いを音で描く」を信条に、SoundCloudにオリジナル楽曲と東方自作アレンジを公開中です
興味があれば聴きに来て下さい♪