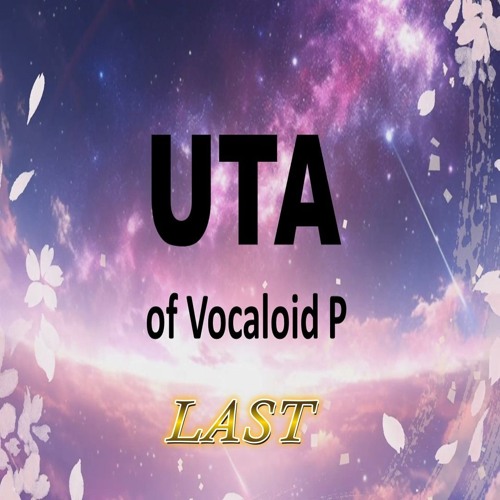おはようございます
前回のsuicide note同様、こちらも2024.11.15に公開していたものですが、歌詞の内容よりもコード進行の組み立て方を中心とした解説を増やす形に改良し、より実践的な曲作りの参考資料としてご活用いただけるよう「改」の字を付記して2025.7.8に更新しましたが、いくつかブログを更新していく中でコード進行の解説を再度見直したいと考え、コード進行の解説のみ改訂した「改2」を最新版とする形で再度更新しました
改めまして、オリジナル楽曲「LAST」の歌詞とコード進行(最新表記)を公開します
後悔のない人生を生き抜く事をテーマにしたアップテンポなハードロックソングです
音源はこちら↓↓
UTA's No.9(Chaso's No.14)
LAST
歌:KYO(V6)
作詞・作曲・編曲:UTA
終わりの見えない長い旅
答えは未だ見つからぬまま
教えて どこまで歩いていけば
知りたかった答えに出会える?
何のために生きているのだろう?
冷徹なこの社会の中で
何を求めて生きているのだろう?
死ぬまで続く悩みの連鎖
君が歩いてきた道は未来の君へと続く
どんなに外れた道を歩いたとしても
自分の過去を消すことだけはしないで
生きる証となっていつか役立つ日が来るから
現実から逃げ出したその分だけ
臆病になり 立ち上がれなくなる
現実に立ち向かったその分だけ
逆境に負けない人間(ひと)へ成長する
何を望んで生きているのだろう?
自分の幸せ? 社会の平和?
何をしたくて生きているのだろう?
答えはきっと 光の向こう側に
一人一人が人生の主人公で
自分だけの物語の主役なんだよ
他人に流されるだけの生き方はしないで
自分だけにしかない輝きを解き放て
一人で生きるのが辛いなら
君の側に寄り添っていいかな?
歌うことしか出来ないけれど
君が立ち上がるまで歌い続けるよ
届け… 想いよ… 愛しい… あなたへ…
擦り剥いた傷が教えてくれるのは
傷の痛みと傷は治るということ
一度の失敗で全てを投げ出さないで
何度だって人生はやり直せるから
人生という名の旅の本当の終わりは
自分にしかない使命を果たした時
思い残す事や悔やむ事のないように
死を迎えるその日まで全力で生きよう
恥ずかしながら、歌詞の内容は僕自身を鼓舞するための目的で書いたものになります
曲名に込めた意味ですが、一般的にLASTと聞くと「最後」の印象が強いかと思います
しかし、その他に「続く」という意味も持っているそうで、このLASTは、
死という目的地が決まっている中、どう生き続けていくのか
人生を語るように過去の自分を激励する指針のような内容として描いたものになります
人に流されず、自分意志と責任と覚悟をもって現世を生き抜くという強い決心を込めています
これまでに制作してきた楽曲の殆どは何かしらの手解きをする事が多いのですが、今作はシンセとストリングスを新たに加えてリアレンジした以外で大きな変更点はない完成度の高い楽曲の1つとなっています(珍しい)
それだけ当時原案を作っていた僕はブレない想いを形にする事が出来たのでしょう
正直驚いています笑
ここからはコード進行の解説に移ります
通常コード表記
Key=C
BPM:176
イントロ1
|N.C.、 |
|N.C.、 | | | |
|N.C.、 | | | |
イントロ2
|Am、 | | | N.C.、 |
イントロ3
|Am、 | |F、 |G、 |
|Am、 | |F、 |G、 |
Aメロ1
|F、 |G、 |E、 |Am、 |
|F、 |F/G、 |Am、 |E、 |
|F、 |G、 |E、 |Am、 |
|F、 |G、 |Am、、Bm7(♭5) E7/G#、|Am、 G/B、|
Bメロ1
|C、 |G/B、 |Am、 | G、 |
|F、 |G、 |Am、 |G、 G/B、 |
|C、 |G/B、 |Am、 | G、 |
|F、 |G、 |Em、 、Am| N.C.、 |
サビ1
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |Am、 、G| Dm、E、|
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |G#dim、 、Am| |
間奏
|Am、 | |F、 |G、 |
|Am、 | |F、 |G、 |
Aメロ2
|F、 |G、 |E、 |Am、 |
|F、 |F/G、 |Am、 |E、 |
|F、 |G、 |E、 |Am、 |
|F、 |G、 |Am、、Bm7(♭5) E7/G#、|Am、 G/B、|
Bメロ2
|C、 |G/B、 |Am、 | G、 |
|F、 |G、 |Am、 |G、 G/B、 |
|C、 |G/B、 |Am、 | G、 |
|F、 |G、 |Em、 、Am| N.C.、 |
サビ2
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |Am、 、G| Dm、E、|
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |G#dim、 、Am| |
Cメロ1
|C、 |G/B、 |F/A、 |Em/G、 |
|F、 |Am、 |Dm、 |E、 |
Cメロ2
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
Dメロ
|Am、 | | | |
|Am、 |CΔ、、Dm D#dim、|Em、 | N.C.、 |
ラスサビ前
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |Am、 、G| Dm、E、|
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |G/B、 、C| Dm、E、|
ラスサビ
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |Am、 、G| Dm、E、|
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |G#dim、 、Am| |
アウトロ1
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |Am、 、G| Dm、E、|
|F、 |、G |G#dim、 、Am| Dm、E、|
|F、 |、G |G#dim、 、Am| |
アウトロ2
|Am、 | | | |Fin.
白:4分音符間隔
、:8分音符間隔
:2/4拍子
赤:トニック主和音関連
赤:トニック代理和音
緑:サブドミナント主和音
緑:サブドミナント代理和音
青:ドミナント主和音
青:ドミナント代理和音
水:パッシング・ディミニッシュ「♭Ⅲdim7(Key=G)」
白:和声の禁則「Ⅵ→Ⅰ」
ケーデンスや終止についてはEndless Storyを引き継いで対応していきますので、詳しい情報は当該ブログで一度ご確認下さい
前作のsuicide note同様、マイナーキーの作り方で作ったものにはなるのですが、途中でCMaj(ⅠMaj)冒頭が登場するなど前作よりもメジャーキー寄りな作りになっているのが特徴的です
「どっちつかず」って言葉が当てはまるくらいメジャーとマイナーが混在している今作を現行のメジャーキー視点のみで解説しきれるのか
1つずつ順に紐解いていきましょう
イントロ1はサビのボーカルのメロディをリードギター(右)に弾いてもらうためのソロ演出の場面のため、N.C.としています
Am(Ⅵm) - N.C.
イントロ2の4小節のコード進行ですが、ただひたすらAm(Ⅵm)を弾くってだけのセクションで、特に言う事はありません
が、前作のsuicide noteの時もギターソロのセクションでⅥm単一のコード進行を作っていたのに違和感がなかった理由はなぜでしょうか?
その時と感覚と今回のとは共通している部分がⅥmを使っているという所にあります
前作の時にも少しだけ議論(一人で笑)したのですが、
代理和音故の自由度の高さ
これかなと思います
そもそもⅥm7というのはⅠ6の転回形でもあるので、ⅠM7をルーツにしている感じがしますね
故にⅠM7のように振る舞う事が出来なくはないのですが、あくまでトニックの代理和音として機能するところまでで線を引かれているのは事実
クラシック音楽においてはマイナーキーとしてⅥm7が主導権を握る事がありますが、現代音楽のようにメジャーキーとマイナーキーが1楽曲内で混在する事も容認しているような音楽においてはⅠM7を中心とした作り方とした方が無難なように感じます
そんな名脇役的存在であるためか、ⅠM7色を残しながら単独で演奏し続けても違和感がないというブランディング力に長けているのはⅠM7にはない特徴でしょう
もちろん、ⅠM7でも単一進行が成立しないなんて事はありませんが、アドリブが効きにくいというか下手なアレンジを加えにくいというのはあるかもしれません
という独自見解の下、単一進行でも違和感なく融通を利かせて成立させる事が出来るⅥm7の柔軟性は非常に大きな武器になります
ビジネス的な視点で言うならば、
ⅠM7…会社が掲げる理念や理想などが詰まったマニュアルに沿って作るオーソドックスな世界
Ⅵm7…現場というリアルで臨機応変にアドリブ(即興)での対応を求められる世界
という風に考えれば両者の間に優劣があるわけではなく、状況に応じて役割を替えながら難局を乗り越えていくというチームマネジメント力が問われているようなものと思ってもらえればと思います
両者の立場が入れ替わりながら様変わりする今作のコード進行の続きを見ていきましょう
Am(Ⅵm) - FMaj(ⅣMaj) - GMaj(ⅤMaj)
Am(Ⅵm) - FMaj(ⅣMaj) - GMaj(ⅤMaj)
こちらはイントロ3の8小節のコード進行です
5~8小節目は1~4小節目をただ繰り返すだけなので、1~4小節目の解説をもって解説済みとさせていただきます
さて、中身に着いてですが、Ⅰ(M7)をⅥmに置き換えた「Ⅵm - ⅣMaj - ⅤMaj」の3コード進行です
と言いたいところなのですが、厳密に言うとⅠ(M7)を省略してⅥm開始とした3コード進行とするのが解釈としては正しいです
という事になります
ちなみに、5~8小節目はこの「645進行」を偽終止でループさせているという事になりますので、解説の省略をさせていただいたのはそのためです
さて、一見すると何の変哲もない「645進行」ですが、今作のイントロ3のようにマイナーキー系の楽曲において手軽にマイナーキー感を出すのに非常に便利かつ単独で循環進行としても成立する汎用性の高いコード進行です
マイナー系の曲を作りたいという時に最小単位で出来るコード進行なので、困った時にイントロなどで使ってみるとそれっぽく表現出来るかもしれません
イントロ1はリードギター(右)の単音弾きのN.C.セクションなので、イントロ2・3でまとめました
Chapter 1に関してはN.C.完結としているのでChapter 2の省略されたⅠ(M7)との関連性はありません
よって、Chapter 1とChapter 2は同じイントロの名を冠してはいるものの、完全に独立して存在している事になります
ただ、イントロという大きな枠組みの中で見た時にチャプターが複数存在する事にはなるため、このような表記としています
Chapter 2(イントロ3)に関しては見事な偽終止循環進行を形成しているのがよく分かるくらいシンプルな作りとなっています
これでGMaj(ⅤMaj)による半終止完結でAメロ1に移るわけですが、645以外のコード進行が思い浮かびようがないのでコード進行の細分化はしません(645を繰り返しているだけだから要らないよね?笑)
FMaj(ⅣMaj) - GMaj(ⅤMaj) - EMaj(ⅢMaj) - Am(Ⅵm)
FMaj(ⅣMaj) - FMaj/G(ⅣMaj/Ⅴ) - Am(Ⅵm) - EMaj(ⅢMaj)
次はAメロ1の前半8小節のコード進行です
1~4小節目はEMaj(ⅢMaj)にアレンジした王道進行がベースとなっていますが、正直これはEm(Ⅲm)でいいなと個人的には思っています
当時は今ほどコード進行についてそこまで深く追究しておらず、既存の音楽理論で示されていたマイナーキーの作り方を参考にしてEMaj(ⅢMaj)にしていただけなので、正直そうまでしてEMaj(ⅢMaj)にしなきゃいけない理由はあんまりありません
これは追々見直していきたいと思います
次の5~8小節目はある意味今作の注目ポイントでもあるのですが、FMaj/G(ⅣMaj/Ⅴ)という珍しいコードを使っています
FMaj(ⅣMaj)なのになぜドミナント?と不思議に思った方もいらっしゃるかと思いますが、このコードはとあるコードを分数コード化してドミナントとして機能させているものになります
先に言いますが、Fadd9(Ⅳadd9)ではありません
確かにFadd9(Ⅳadd9)の9thが「G」なのでそう思いたい気持ちも分かりますが、もしそれだとするならば、Endless Storyの時のように「Ⅰadd9 - ⅠM7」という感じで拡張型変終止の一環として用いる事が多いので、今回の雰囲気を見る限りではFadd9(Ⅳadd9)説が成立するような条件は揃っていないので除外されます
では今回のFMaj/G(ⅣMaj/Ⅴ)はそういった意味を持ったコードなのか?
これ分かった方はすごいのですが、実はこれ、
G7sus4(9, omit5)
というsus4系分数コードを再現したものになります
こんな感じでG7sus4(9)の完全5度Dを除くと、音の順番は違えど、FMaj/G(ⅣMaj/Ⅴ)の音程が揃います
FMaj(ⅣMaj) - G7sus4(9, omit5)(Ⅴ7sus4(9, omit5)) - Am(Ⅵm) - EMaj(ⅢMaj)
というコード進行をベースにした「4563進行」の「5」の部分をFMaj(ⅣMaj)で継続しながら「Ⅴ」の音もほしいという中々に無茶な願いを叶えたのがFMaj/G(ⅣMaj/Ⅴ)という事になります
しかも、FMaj/G(ⅣMaj/Ⅴ)とした事でG7sus4(9)(Ⅴ7sus4(9))によるCM7(ⅠM7)への準強制的な解決感も和らぐため、Am(Ⅵm)への進行すらも許される点も非常に有能です
スマートな形でまとめられたsus4系分数コードを使った応用例としてかなり優秀な部類に入りますので、運用方法の参考にしていただけたらと思います
ちなみに、ドミナントと言えど、元々がFMaj(ⅣMaj)なので、コード進行の骨組みは「463」の3コード進行というのが答えです
また、最後のEMaj(ⅢMaj)はE7(Ⅲ7)とする事でトライトーンによるAm7(Ⅵm7)への進行を強める効果を軽減出来るため、次のFMaj(ⅣMaj)への進行の可能性も示唆出来るように仕向けているものになります
FMaj(ⅣMaj) - GMaj(ⅤMaj) - EMaj(ⅢMaj) - Am(Ⅵm)
FMaj(ⅣMaj) - GMaj(ⅤMaj) - Am(Ⅵm) - Bm7(♭5)(Ⅶm7(♭5)) - E7/G#(Ⅲ7/♭Ⅵ) - Am(Ⅵm) - GMaj/B(ⅤMaj/Ⅶ)
次はAメロ1の後半の8小節のコード進行ですね
9~12小節目は1~4小節目と同じですので省略します
次の13~16小節目は大分詰め込んだ感じになってますが、
FMaj(ⅣMaj) - GMaj(ⅤMaj) - Am(Ⅵm)
Bm7(♭5)(Ⅶm7(♭5)) - E7/G#(Ⅲ7/♭Ⅵ) - Am(Ⅵm) - GMaj/B(ⅤMaj/Ⅶ)
という細分化が出来ます
前者は偽終止を使った3コード進行「456進行」、後者はⅦ-Ⅲ-Ⅵ型Ⅱ-Ⅴ-ⅠにBメロ1の冒頭CMaj(ⅠMaj)に繋ぐための経過和音的役割でGMaj/B(ⅤMaj/Ⅶ)を挿入して半終止完結としたものです
特に後者はE7/G#(Ⅲ7/♭Ⅵ)からのベースライン・クリシェを引き継いでいるかのような動きを示し、Bメロ1の冒頭CMaj(ⅠMaj)への繋がりを意識したものになります
少々歪なベースライン・クリシェではありますが、こうした形で先のコードが何なのかというのを想定しながら制作しています
なお、Bメロ1の冒頭CMaj(ⅠMaj)を細字表記としていないのは、GMaj/B(ⅤMaj/Ⅶ)からの流れがあるとは言えど、GMaj/B(ⅤMaj/Ⅶ)でAメロ1が完結している関係から正式に繋がっているわけではないため、不完全終止ではなく、単なるⅠMaj冒頭としているだけにすぎません
この辺も解釈する人によって意味合いが変わる部分ではありますが、僕の自作曲、かつ僕の中での解釈としてこうしていますので、参考にして下さい
Aメロ1の全体像がこちらです
大画面で見る際に見づらくなりそうだったので、前半と後半とで分断して横に伸ばして再編集しました
完全終止保留を挟みつつも偽終止を使って同じチャプターを永続的に繰り返すという僕が思うマイナーキーというのがおそらくこれだろうと思われる模範の形をしていますが、和声学の完全終止と偽終止の大きな違いがここで如実に現れました
ⅠM7による完全終止はチャプター(及びセクション)の終幕と新章開幕を意味するような完結感があると言われていますが、偽終止はⅠ6が基になったⅥm7(転回するだけで成立する関係性)という所でトニックとして振る舞えるがⅠM7ではない
故に「偽」の字を冠しているわけですから、未完結のまま同チャプターを繰り返す事になるのは性質上当然っちゃ当然です
それを利用して未完結感に味を示したのがマイナーキーというのであれば、「Ⅵ→Ⅰ」の禁則を使っていたsuicide noteやカナシミノサキニよりもそれらしい形で君臨する今作のAメロ1は意味理想的な形、あるべき姿とも言えるかもしれません
メジャーキーのディグリーネームでマイナーキーらしい楽曲を作った場合にこうなり得るというのを一つの参考にしてみて下さい
コード進行の細分化ですが、
4536+463+4536+456+7365
という感じで下手な重複もなく3・4コード単位で綺麗に細分化出来ました
文字数が怪しくなってきたので「改」に倣い、今回はここらで一旦区切ります
次回はBメロ1から解説を再開します
それではまた、次回のブログでまたお会いしましょう
(^ ^)ノシBye Bye♪
「不器用な想いを音で描く」を信条に、SoundCloudにオリジナル楽曲と東方自作アレンジを公開中です
興味があれば聴きに来て下さい♪
※ジャケット画像:太郎様
※Endless Storyの音源動画用のワンシーンを活用し、ジャケット画像用に編集したもの