【カルーゾ】
※喉頭癌に倒れた伝説のオペラ歌手、カルーソーの晩年をテーマをにしたカンツォーネ!恋人(娘)へ別れと、諦観を歌い上げるルチオ・ダッラの名曲!
----------------------------------------------------------
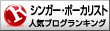
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
おかげさまで、現在、第1位です!クリックすると順位が見られますよ!!
みなさま、おはようございます。村上リサです。連日、「村上リサの発声の秘密」と題して、発声の技術の習得に関して、特集をしています。
昨日、一昨日に引き続きまして、本日は3日目です。
今までは、「1.歌うときの姿勢」、「2.歌うときの呼吸法」の習得法について書いてきました。
はじめてお読みになる方のために、簡単におさらいします。
詳しくは、昨日一昨日の記事をご覧ください。
壁に背を着けて、「かかと」、「お尻」、「後頭部」が一直線になるように立ちます。
(足の前後は、100m走のスタートの前後を参考に)
マリオネットが吊られているように、肩を持ち上げてストンと落として、首の余分な力を抜き、胸郭を柔らかく開きます。手首、足首、膝の裏側も硬くせずに!
そして呼吸ですが、習得法としては、「ラジオ体操第一」の前屈のように、上半身を折り曲げて両手でウエストを持ち、そこを膨らます感じで、注射器のピストンのように、空気を取り込みます。
そして、体を起こして、おへそのした3cmの点に力を入れて、ウエストラインの緊張感を失わないように、おへそのしたの点を、注射器のピストンの様に、息を送っていきます。
その感覚を、体を曲げなくても、できるようにして、息を細く、強く、長く「スー(フー)」と吐く息にのせて、歌を歌っていくわけです。
それでは、今日は実際に声を出してみる段階になります。
n
叫んだり、怒鳴ったりする声ではなく、楽器のようにしっかりと音程がつけられる、響きのある声です。
皆さんは、「ハミング」って御存知ですか?
1/3ではありませんよ!・・・。洗濯の時入れる時の。
口を閉じて鼻の奥で、「N~~」と鳴らすやつです。
それを、先ほどの姿勢と呼吸にのせて、細く、長く、力強くとも喉に力を入れず、出していきます。(高さは、出しやすいところがいいのですが、大体真ん中のソからドぐらいがやりやすいのではないでしょうか)
望遠鏡や顕微鏡のフォーカスがピタリと決まるように、声の響きがクッキリと、鮮明に聴こえるポジションがあります。
そこを探していきます。
いいポジションが見つかったら、「N~~」から、「N~Naa」とハミングの響きを失わないようして、「A」の母音のソングトーンを出してみます。
ここで、間違えやすいには、息を全部鼻の方にもって行こうとすると、
鼻声になってしまいます。
あくまで少しハミングの響きを残しつつ、硬くしない喉のを通過した声が、鼻の奥の一点でに集まっている感じです。
お腹を使って、送られた息が喉を通過して、すべて声に変わり、鼻の奥の「アジシオのキャップより2回りぐらいの小さい箱」を感じて、その中の一点が響きの像を結ぶ」 感じです。
最近LEDの電球が有名ですが、ほとんど電気は熱に変わらず、光に変わっています。
でも旧来の電球は光以外に、かなりの熱に変化している。
声も息漏れをおこさす、全部声に変わる感じで!
誤解を恐れずに言うと、息が漏れない声とは、前に向かって息を吐きながら発声しているのですが、後ろに引っ張っているような感じです。
ここの取り方を間違えると、鼻声になったり、喉声になったり、体から声が遠くに飛ばない声になったりします。
はじめの頃によく誤解されやすいのが、
喉先に押し付けて一見きれいなテノールの声に聴こえる、クネーデル(お団子声)は初級クラスの?学習者には区別がつかないかも知れません。
そこで大切なのが、自分でも歌えて、このわずかな違いを聴きわける耳を持っている、ボイストレーナーの存在です。
マイクを使わないことを前提にした発声では、マイクを使った人で言ったら、マイクのスイッチを入れるか、切るかぐらいの違いになってきます。
その部分が、まず最初の難関です。
声が頭や鼻の奥や、口の奥に(胸にも)共鳴して、洞窟の中のよに日々いえいる感じ。
そこから、同じ高さの二分音符で「A →E→I→O→U 」と、一つの息で、鼻の奥の響がなるべく変わらない様な場所を探していきます。
それから、様々な、ヴォカリツィ(ボーカルトレーニング)のパターンを学び、テクニックを磨いていきます。
大まかな流れはこんな感じです。
いかがですか?これは発声のフォームを作る、基礎の基礎です。
そこから、楽器としての音にできる「声」を作るために、ピアノで言うと「バイエル」や「ツェルニー」の練習曲を学ぶように、「コンコーネ」や「ヴァッカイ」の練習曲を学び、曲をマスターするマスターするために「ソナチネ」や「ソナタ」に取り組むように、「イタリア古典歌曲」や「ドイツリート」に取り組みはじめて、オペラやオラトリオ等の自分の取り組みたい分野を中心に極めていくわけです。
そして、それらに取り組む過程で、きちんと体系付けられたテクニックを計画的に身に付けていきます。
テクニックにも、アクート(高音域で使う技術)の問題や「コロラトゥーラ」や「メッサ ディ ヴォーチェ」、「アポジャトゥーラ」、「アチャカトゥーラ」、「トリル」、「メッザ ヴォーチェ」など名前の付いた技術があり、メソッドとして確立しています。
「こうすればこうなる」と言うことが、科学的に実証されているテクニックをしっかり学んでいくわけです。
メソッドが確立していないと、結局、経験則からのアドバイスになってしまいがちで、それもいい場合もあるのですが、結果オーライに陥り易くなる点は注意が必要です。
メソッドがあると言うことが大切なのは、ダンスで例えるとジャズダンサーやコンテンポラリー系のダンサーが、「バレエのレッスンを受けて自分の動きや技術に磨きをかけているのと同じで、「アラベスクターン」や「アチチュードターン」、「ピルエット」精度を上げているのですが、これは、ワガノワメソッドを学んでも、彼ら彼女らは、バレエダンサーになろうとしているのではないのです。
自分の専門分野のダンスに、メソッドの技術を取り入れて、洗練した踊りにしようとしているのです。
メソッドは、こうすればこうなるという、科学的に技術を集約して体系化したもの。
それさえ手に入れれば、それでいいのではなく、それを身に付けるところが、自分の個性を生かした歌を創造するためのスタート地点なのです。
<
安定した呼吸法を習得できれば、発声の7割以上はできたようなもの。特に、この呼吸は大切なことです。
腹式呼吸はあくまでも、おおかたのジャンルの発声法の共通の基本であると思います。(すべてとは言いきれませんが)
それは、表現上、喉の過度な圧迫と声の押しつけを避けて、柔らかくて、芯があり、浸透生のある、そして、喜怒哀楽の感情に対して、声のコントロールによって無理なくメリハリが付けられるメリットがあるからです。
声が柔らかく浸透するということは、聴き手の心を優しく包み込むのに非常に大切な要素です。
また、時には力強く声を張れるということも、威厳を増したり、ダイナミックの幅を拡げ、多彩な表現を可能にします。
具体的に、習得方法を書いてみます。
昨日、説明したように、力みのないよい姿勢で立ちます。
そして、足を平行に開いて、「ラジオ体操第一」の前屈の時のように、ウエストラインから上の上半身をダラリと下に折り曲げます。
このとき、途中で力で上半身をキープしようとせず、上半身の力をしっかり抜くこと。
その状態で、おへその下3cmぐらいの1点に、力を入れながら、ウエストの一番細くなっているところを膨らませるようにして、空気を体に取り込みます。
空気を取り込むとき、両手をウエストの一番細くなっているところに、添えてみて下さい。
表現は抵抗がありますが、「ウエストが太くなるように吸って下さい」。
そして、吸えたら、そのまま体を起こして、息を前歯の一番真ん中のすき間から、細く、力強く「スー~~」と長く吐いてみましょう。
そう、そう。糸を引くように、喉、首は楽にして、ウエストラインの緊張感を失わずに、体を大きな注射器のように、おへその下3cmの点を押し上げていく感じです。
そして、その吐いている細い息は、ネックレスの真ん中を通っている糸のようなもの。
そして、それにビーズの球がつくように、言葉を紡いでいきます。
同じ上半身の中でも、胸や首や喉は楽にしていながら、ウエストラインの緊張を失わず、おへその下の点を押し上げていく。
う~ん!ここがどの程度の力かというのはとても伝えづらいのですが…。
自分にとって一番バランスがよくて、力を入れやすい場所ですが、。どこか一カ所を、石のように硬くするわけではなく、上半身を中心にした、全身の連携運動です。
この、「スー」という吐き方を、「フー」とやってもいいです。(喉に力が入りやすい人の場合)
最低30秒は続けたいものです。
慣れてくると、1分間くらいは軽くできるようになります。
目に見えない息を、しっかり吸えてしっかりと、「細く」、「長く」、「力強く」。
慣れた来れば、上半身を折り曲げなくても、ウエストを膨らませることで息が吸えるようになります。
いかがですか・・・・・。
このように基本的なことを、繰り返し繰り返し練習して、癖にしてしまいます。
この呼吸のイメージを大切にして、深い深い呼吸ができるようにしていきましょう。
深く心を揺さぶる声は、深い呼吸から。
時には、コンサートなどでも、1曲でもいいから、技術を盗む目で鑑賞していてみてはいかがでしょうか?
曲の内容から一歩引いて、発声の仕方を分析的に見てみる。
だた、「上手いな~」とか、「曲の内容に没頭して聴くのではなくて」、そういうテクニックや、力のバランスなどを体感するように聴いてみるのです。
毎日やっている内に、自分なりのバランス「これだ」というのが、段々鮮明になってきます。
まるで、カメラのフォーカスがピッタリ定まるように。
感性を鋭くして、具体的には、「今やっていることに集中して」練習してる人だけが見えてくるものがあります。
明日は、「響きについて」の予定ですが、夜にナポレターナ(カンツォーネ)界の重鎮、マリオ・マリョーネさんのコンサートがあります。
場合によっては、そのことが先になるかも知れません。
共に頑張っていきましょう!
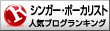
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
【今日の一曲】 「Voce ’e notte」 クルティス 作曲
貧しさ故に、恋人と別れ年老いた富豪との結婚を余儀なくされた娘に、嫉妬に苛まれた元恋人が、窓の下で歌うマドリガーレ。
マリオ・マリョーネが歌う正調ナポレターナ、「夜の声」。日本のギターの伴奏で、その内の一本を引きながら歌う、ロベルト・ムーロロの伝統的なスタイルを受け継ぐ歌手です。
今日の夜、18:00から「渋谷 伝承ホール」です。
今日のピアノ伴奏は、いつもリサがお世話になっている、中上香代子さんです。
追伸
昨日の「徹子の部屋」でリサが、一番に印象的だった写真です。
いつも颯爽とカッコイイNEROさんの、こんな幼い頃の写真です。
お二人の表情を見る度に感慨深く・・・・・、・・・・・、言葉にできません・・・・。
本日も最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。
【リサのライブ予定です】
(お問い合わせは「メッセージ」からお願い致します)
6/17(月)
「月曜シャンソンコンサート」
開場 pm6:00 場所 渋谷 SARAVAH東京
7月27日(土)
「昼下がりのシャンソン」
開場 pm2:00 開演 pm2:30 場所 新宿 シャンパーシュ
【村上リサライブ動画】
【村上リサ ライブスケジュール】
【フェイスブックページ】
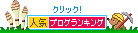
人気ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!




※喉頭癌に倒れた伝説のオペラ歌手、カルーソーの晩年をテーマをにしたカンツォーネ!恋人(娘)へ別れと、諦観を歌い上げるルチオ・ダッラの名曲!
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
おかげさまで、現在、第1位です!クリックすると順位が見られますよ!!
みなさま、おはようございます。村上リサです。連日、「村上リサの発声の秘密」と題して、発声の技術の習得に関して、特集をしています。
昨日、一昨日に引き続きまして、本日は3日目です。
今までは、「1.歌うときの姿勢」、「2.歌うときの呼吸法」の習得法について書いてきました。
はじめてお読みになる方のために、簡単におさらいします。
詳しくは、昨日一昨日の記事をご覧ください。
壁に背を着けて、「かかと」、「お尻」、「後頭部」が一直線になるように立ちます。
(足の前後は、100m走のスタートの前後を参考に)
マリオネットが吊られているように、肩を持ち上げてストンと落として、首の余分な力を抜き、胸郭を柔らかく開きます。手首、足首、膝の裏側も硬くせずに!
そして呼吸ですが、習得法としては、「ラジオ体操第一」の前屈のように、上半身を折り曲げて両手でウエストを持ち、そこを膨らます感じで、注射器のピストンのように、空気を取り込みます。
そして、体を起こして、おへそのした3cmの点に力を入れて、ウエストラインの緊張感を失わないように、おへそのしたの点を、注射器のピストンの様に、息を送っていきます。
その感覚を、体を曲げなくても、できるようにして、息を細く、強く、長く「スー(フー)」と吐く息にのせて、歌を歌っていくわけです。
それでは、今日は実際に声を出してみる段階になります。
n
叫んだり、怒鳴ったりする声ではなく、楽器のようにしっかりと音程がつけられる、響きのある声です。
皆さんは、「ハミング」って御存知ですか?
1/3ではありませんよ!・・・。洗濯の時入れる時の。
口を閉じて鼻の奥で、「N~~」と鳴らすやつです。
それを、先ほどの姿勢と呼吸にのせて、細く、長く、力強くとも喉に力を入れず、出していきます。(高さは、出しやすいところがいいのですが、大体真ん中のソからドぐらいがやりやすいのではないでしょうか)
望遠鏡や顕微鏡のフォーカスがピタリと決まるように、声の響きがクッキリと、鮮明に聴こえるポジションがあります。
そこを探していきます。
いいポジションが見つかったら、「N~~」から、「N~Naa」とハミングの響きを失わないようして、「A」の母音のソングトーンを出してみます。
ここで、間違えやすいには、息を全部鼻の方にもって行こうとすると、
鼻声になってしまいます。
あくまで少しハミングの響きを残しつつ、硬くしない喉のを通過した声が、鼻の奥の一点でに集まっている感じです。
お腹を使って、送られた息が喉を通過して、すべて声に変わり、鼻の奥の「アジシオのキャップより2回りぐらいの小さい箱」を感じて、その中の一点が響きの像を結ぶ」 感じです。
最近LEDの電球が有名ですが、ほとんど電気は熱に変わらず、光に変わっています。
でも旧来の電球は光以外に、かなりの熱に変化している。
声も息漏れをおこさす、全部声に変わる感じで!
誤解を恐れずに言うと、息が漏れない声とは、前に向かって息を吐きながら発声しているのですが、後ろに引っ張っているような感じです。
ここの取り方を間違えると、鼻声になったり、喉声になったり、体から声が遠くに飛ばない声になったりします。
はじめの頃によく誤解されやすいのが、
喉先に押し付けて一見きれいなテノールの声に聴こえる、クネーデル(お団子声)は初級クラスの?学習者には区別がつかないかも知れません。
そこで大切なのが、自分でも歌えて、このわずかな違いを聴きわける耳を持っている、ボイストレーナーの存在です。
マイクを使わないことを前提にした発声では、マイクを使った人で言ったら、マイクのスイッチを入れるか、切るかぐらいの違いになってきます。
その部分が、まず最初の難関です。
声が頭や鼻の奥や、口の奥に(胸にも)共鳴して、洞窟の中のよに日々いえいる感じ。
そこから、同じ高さの二分音符で「A →E→I→O→U 」と、一つの息で、鼻の奥の響がなるべく変わらない様な場所を探していきます。
それから、様々な、ヴォカリツィ(ボーカルトレーニング)のパターンを学び、テクニックを磨いていきます。
大まかな流れはこんな感じです。
いかがですか?これは発声のフォームを作る、基礎の基礎です。
そこから、楽器としての音にできる「声」を作るために、ピアノで言うと「バイエル」や「ツェルニー」の練習曲を学ぶように、「コンコーネ」や「ヴァッカイ」の練習曲を学び、曲をマスターするマスターするために「ソナチネ」や「ソナタ」に取り組むように、「イタリア古典歌曲」や「ドイツリート」に取り組みはじめて、オペラやオラトリオ等の自分の取り組みたい分野を中心に極めていくわけです。
そして、それらに取り組む過程で、きちんと体系付けられたテクニックを計画的に身に付けていきます。
テクニックにも、アクート(高音域で使う技術)の問題や「コロラトゥーラ」や「メッサ ディ ヴォーチェ」、「アポジャトゥーラ」、「アチャカトゥーラ」、「トリル」、「メッザ ヴォーチェ」など名前の付いた技術があり、メソッドとして確立しています。
「こうすればこうなる」と言うことが、科学的に実証されているテクニックをしっかり学んでいくわけです。
メソッドが確立していないと、結局、経験則からのアドバイスになってしまいがちで、それもいい場合もあるのですが、結果オーライに陥り易くなる点は注意が必要です。
メソッドがあると言うことが大切なのは、ダンスで例えるとジャズダンサーやコンテンポラリー系のダンサーが、「バレエのレッスンを受けて自分の動きや技術に磨きをかけているのと同じで、「アラベスクターン」や「アチチュードターン」、「ピルエット」精度を上げているのですが、これは、ワガノワメソッドを学んでも、彼ら彼女らは、バレエダンサーになろうとしているのではないのです。
自分の専門分野のダンスに、メソッドの技術を取り入れて、洗練した踊りにしようとしているのです。
メソッドは、こうすればこうなるという、科学的に技術を集約して体系化したもの。
それさえ手に入れれば、それでいいのではなく、それを身に付けるところが、自分の個性を生かした歌を創造するためのスタート地点なのです。
<
安定した呼吸法を習得できれば、発声の7割以上はできたようなもの。特に、この呼吸は大切なことです。
腹式呼吸はあくまでも、おおかたのジャンルの発声法の共通の基本であると思います。(すべてとは言いきれませんが)
それは、表現上、喉の過度な圧迫と声の押しつけを避けて、柔らかくて、芯があり、浸透生のある、そして、喜怒哀楽の感情に対して、声のコントロールによって無理なくメリハリが付けられるメリットがあるからです。
声が柔らかく浸透するということは、聴き手の心を優しく包み込むのに非常に大切な要素です。
また、時には力強く声を張れるということも、威厳を増したり、ダイナミックの幅を拡げ、多彩な表現を可能にします。
具体的に、習得方法を書いてみます。
昨日、説明したように、力みのないよい姿勢で立ちます。
そして、足を平行に開いて、「ラジオ体操第一」の前屈の時のように、ウエストラインから上の上半身をダラリと下に折り曲げます。
このとき、途中で力で上半身をキープしようとせず、上半身の力をしっかり抜くこと。
その状態で、おへその下3cmぐらいの1点に、力を入れながら、ウエストの一番細くなっているところを膨らませるようにして、空気を体に取り込みます。
空気を取り込むとき、両手をウエストの一番細くなっているところに、添えてみて下さい。
表現は抵抗がありますが、「ウエストが太くなるように吸って下さい」。
そして、吸えたら、そのまま体を起こして、息を前歯の一番真ん中のすき間から、細く、力強く「スー~~」と長く吐いてみましょう。
そう、そう。糸を引くように、喉、首は楽にして、ウエストラインの緊張感を失わずに、体を大きな注射器のように、おへその下3cmの点を押し上げていく感じです。
そして、その吐いている細い息は、ネックレスの真ん中を通っている糸のようなもの。
そして、それにビーズの球がつくように、言葉を紡いでいきます。
同じ上半身の中でも、胸や首や喉は楽にしていながら、ウエストラインの緊張を失わず、おへその下の点を押し上げていく。
う~ん!ここがどの程度の力かというのはとても伝えづらいのですが…。
自分にとって一番バランスがよくて、力を入れやすい場所ですが、。どこか一カ所を、石のように硬くするわけではなく、上半身を中心にした、全身の連携運動です。
この、「スー」という吐き方を、「フー」とやってもいいです。(喉に力が入りやすい人の場合)
最低30秒は続けたいものです。
慣れてくると、1分間くらいは軽くできるようになります。
目に見えない息を、しっかり吸えてしっかりと、「細く」、「長く」、「力強く」。
慣れた来れば、上半身を折り曲げなくても、ウエストを膨らませることで息が吸えるようになります。
いかがですか・・・・・。
このように基本的なことを、繰り返し繰り返し練習して、癖にしてしまいます。
この呼吸のイメージを大切にして、深い深い呼吸ができるようにしていきましょう。
深く心を揺さぶる声は、深い呼吸から。
時には、コンサートなどでも、1曲でもいいから、技術を盗む目で鑑賞していてみてはいかがでしょうか?
曲の内容から一歩引いて、発声の仕方を分析的に見てみる。
だた、「上手いな~」とか、「曲の内容に没頭して聴くのではなくて」、そういうテクニックや、力のバランスなどを体感するように聴いてみるのです。
毎日やっている内に、自分なりのバランス「これだ」というのが、段々鮮明になってきます。
まるで、カメラのフォーカスがピッタリ定まるように。
感性を鋭くして、具体的には、「今やっていることに集中して」練習してる人だけが見えてくるものがあります。
明日は、「響きについて」の予定ですが、夜にナポレターナ(カンツォーネ)界の重鎮、マリオ・マリョーネさんのコンサートがあります。
場合によっては、そのことが先になるかも知れません。
共に頑張っていきましょう!
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
【今日の一曲】 「Voce ’e notte」 クルティス 作曲
貧しさ故に、恋人と別れ年老いた富豪との結婚を余儀なくされた娘に、嫉妬に苛まれた元恋人が、窓の下で歌うマドリガーレ。
マリオ・マリョーネが歌う正調ナポレターナ、「夜の声」。日本のギターの伴奏で、その内の一本を引きながら歌う、ロベルト・ムーロロの伝統的なスタイルを受け継ぐ歌手です。
今日の夜、18:00から「渋谷 伝承ホール」です。
今日のピアノ伴奏は、いつもリサがお世話になっている、中上香代子さんです。
追伸
昨日の「徹子の部屋」でリサが、一番に印象的だった写真です。
いつも颯爽とカッコイイNEROさんの、こんな幼い頃の写真です。
お二人の表情を見る度に感慨深く・・・・・、・・・・・、言葉にできません・・・・。
本日も最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。
【リサのライブ予定です】
(お問い合わせは「メッセージ」からお願い致します)
6/17(月)
「月曜シャンソンコンサート」
開場 pm6:00 場所 渋谷 SARAVAH東京
7月27日(土)
「昼下がりのシャンソン」
開場 pm2:00 開演 pm2:30 場所 新宿 シャンパーシュ
【村上リサライブ動画】
【村上リサ ライブスケジュール】
【フェイスブックページ】
人気ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!




