【カルーゾ】
※喉頭癌に倒れた伝説のオペラ歌手、カルーソーの晩年をテーマをにしたカンツォーネ!恋人(娘)へ別れと、諦観を歌い上げるルチオ・ダッラの名曲!
-----------------------------------------------------------------
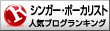
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
おかげさまで、現在、第1位です!クリックすると順位が見られますよ!!
みなさま、おはようございます。村上リサです。
昨日は、カンツォーネ歌手、クラウディオ・ビルラをご紹介いたしました。
その朗々たる歌唱に脱帽。オペラ歌手並みの声量や音域に驚愕し、ファンになってしまったのでした。
そして、彼の歌う「帰れソレントヘ」と3大テノールの一人、ホセ・カレーラスの歌い方を比較し、この違いを明確にすることが、「ポピュラーとクラシックの歌い方の違い」を理解することにつながることも申しあげました。
いかがでしたか?考えてみましたか?
昨日、分かりやすく説明しようと思案中に、別の分かりやすい例を見つけました。
安定した歌唱力で定評のある、オペラ歌手(テノール)、カルロ・ベルゴンツィの歌う「忘れな草」です。
昨日、クラウディオ・ビルラの歌う同じ曲をご紹介しましたが、1番だけでいいので、聴き比べてみてください。(何回もご面倒をおかけいたします!)
【忘れな草】
〔クラウディオ・ビルラ〕
〔カルロ・ベッルゴンツィ〕
いろいろあるとは思いますが、リサが思う、ポピュラーのカンツォーネとクラシックのカンツォーネをの分かれ目とは。
それは、許容される「メロディーの崩し方のスタイル」にある。
伴奏がバンドと、ピアノだけということは別にして、ビルラの方は、終始打楽器や電子楽器のような音が「123」.「123」…とマーチングバンドの打楽器のように、均等な速さで3拍子を刻み続けています。
それに対して、ベルゴンツィの方のテンポの取り方は、「123」と均等割ではなく、「1」「2」「3」.「1」「2」「3」。
要するに、それぞれ「1」と「2」、「2」と「3」、「3」と「1」の間に微妙に伸び縮みを付け、作曲家の書いたリズムは原則として崩しません。特別な部分は別ですが。
ですから、メロディーの歌い出しを、記譜されたぴったりのタイミングで入ってきます。
そして、メロデイーを、テンポの伸び縮みで表情をつけます。「少しゆったりしたら、その遅れを取り戻すように速くしたり」、「速目にしたら、その後、少しゆっくりにして」、つじつまを合わせるがごとく、テンポの揺れを作っています。
それに対して、ビルラの方は、均等割の「123」.「123」の中で、生き生きと表情をつけなければなりません。
その状態で、メロディーを全く崩さなければ、譜読みの練習みたいに、無機質な演奏になってしまします。
そこで、ビルラや、ポピュラーの歌手達は、メロディーの原形を留める範囲で、「リズムそのものを変えている」のです。
「123」.「123」と刻み続けるドラムは、ここはゆっくり目に歌おうとしても、原則として待っていてはくれません。だから、そういう時は、遅れて出て、その後どこかを短めにして追いつかなくてはなりません。その過程で、作曲者の指定したリズムを正確に歌いながら追いかけよとすると、せっかちで落ち着きのない歌になってしまいます。
だから、リズムは変えざるを得ない。
そして、その部分の処理の仕方は、すべて歌い手のセンスと力量にゆだねられるのです。
極端に言うと、楽譜を正確に歌ってはいけないのです。確かに難しい世界ですよね。
楽譜に書いてある通りに歌い、(記譜上の)リズムを壊さず、正しく守って、テンポの変化で表情を出すクラシック。(アコースティックなので、ダイナミックの幅も大きいという要素もありますが)
楽譜に書いてないように歌い、テンポは崩さず、リズムや出だしのタイミングを変えて表情を出すポピュラー。
発声法は似ていても、この違いは決定的です。
それは、ピアノやオーケストラを伴奏として発達してきた、クラシックの世界と、、バンドをバックに発展してきたポピュラー世界の歴史的な成立の過程に起因する要素もあることでしょう。
「帰れソレントへ」ビルラの歌も、部分部分を区切って、テンポの速いところと、遅いところはありますが、「123」という、かたまりの中の均等割は一貫していて、「1」と「2」の間、あるいは、「2」と「3」間に大きな伸縮の変化は、クラシックのように極端ではありません。
ただ、あの曲の特徴として、「フェルマータ」はあります。「123」の流れとストップさせて、特定の音を長く伸ばすことはやっています。
それにしても、このような、フェルマータや小刻みなテンポの切り替えに対応するドラムの人は、もの凄い力量だと思われます。
ちなみに、リサの場合は、この2つの歌い方を、曲によって使い分けています。
この見方は、どこかの本やネットで調べてものではなく、クラシックの世界から、ポピュラーの世界に来て、戸惑いながら、歌唱スタイルを模索する中で、リサが直接感じ取ったことです。
【今日の1曲】
「Burava(ブラーヴァ)」
素晴らしい演奏が終わった瞬間、BURAVO(ブラーボ)と声がかかることがあります。
演奏者が女性の場合は、本当は「ブラーバ」といわなければならないのです。
今日はカンツォーネの女王、ミーナの歌で聴きましょうか。
MINA BRAVA!!
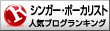
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
追伸
ビルラは、若い頃はオペラ歌手を目指したらしいのですが、先輩格にあの、黄金のトランペット、マリオ・デル・モナコがいたので、彼のいないポピュラー界を目刺したのだとか。
真相はいかに?モナコ1915年生まれ。ビルラ1925年生まれですから、10歳違うんですね。むしろ、ベルゴンツィの方が近く、ひとつ年上の1924年生まれです。
そして、昨日の写真の2ショット、パヴァロッティは10歳下の1935年生まれです。
いかがですか?ビルラの若い頃の写真です。かっこいいですね!
こうしてみると、容姿って誰でも、年齢と共に変わっていくものなんですね。男性から女性へと変身した私が言うのも何ですが・・・・(笑)
本日も最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。
【リサのライブ予定です】
(お問い合わせは「メッセージ」からお願い致します)
6/17(月)
「月曜シャンソンコンサート」
開場 pm6:00 場所 渋谷 SARAVAH東京
5/8(水)
Chambre Des Chansons
「~受け継がれるシャンソンスピリッツ~ 」<font size="2">Vol 1
開場17:00 開演18:00 大井町きゅリあん 小ホール
戸川昌子さん、うつみ宮土理さん他、豪華キャストと共演です!
【村上リサライブ動画】
【村上リサ ライブスケジュール】
【フェイスブックページ】
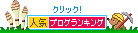
人気ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!




※喉頭癌に倒れた伝説のオペラ歌手、カルーソーの晩年をテーマをにしたカンツォーネ!恋人(娘)へ別れと、諦観を歌い上げるルチオ・ダッラの名曲!
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
おかげさまで、現在、第1位です!クリックすると順位が見られますよ!!
みなさま、おはようございます。村上リサです。
昨日は、カンツォーネ歌手、クラウディオ・ビルラをご紹介いたしました。
その朗々たる歌唱に脱帽。オペラ歌手並みの声量や音域に驚愕し、ファンになってしまったのでした。
そして、彼の歌う「帰れソレントヘ」と3大テノールの一人、ホセ・カレーラスの歌い方を比較し、この違いを明確にすることが、「ポピュラーとクラシックの歌い方の違い」を理解することにつながることも申しあげました。
いかがでしたか?考えてみましたか?
昨日、分かりやすく説明しようと思案中に、別の分かりやすい例を見つけました。
安定した歌唱力で定評のある、オペラ歌手(テノール)、カルロ・ベルゴンツィの歌う「忘れな草」です。
昨日、クラウディオ・ビルラの歌う同じ曲をご紹介しましたが、1番だけでいいので、聴き比べてみてください。(何回もご面倒をおかけいたします!)
【忘れな草】
〔クラウディオ・ビルラ〕
〔カルロ・ベッルゴンツィ〕
いろいろあるとは思いますが、リサが思う、ポピュラーのカンツォーネとクラシックのカンツォーネをの分かれ目とは。
それは、許容される「メロディーの崩し方のスタイル」にある。
伴奏がバンドと、ピアノだけということは別にして、ビルラの方は、終始打楽器や電子楽器のような音が「123」.「123」…とマーチングバンドの打楽器のように、均等な速さで3拍子を刻み続けています。
それに対して、ベルゴンツィの方のテンポの取り方は、「123」と均等割ではなく、「1」「2」「3」.「1」「2」「3」。
要するに、それぞれ「1」と「2」、「2」と「3」、「3」と「1」の間に微妙に伸び縮みを付け、作曲家の書いたリズムは原則として崩しません。特別な部分は別ですが。
ですから、メロディーの歌い出しを、記譜されたぴったりのタイミングで入ってきます。
そして、メロデイーを、テンポの伸び縮みで表情をつけます。「少しゆったりしたら、その遅れを取り戻すように速くしたり」、「速目にしたら、その後、少しゆっくりにして」、つじつまを合わせるがごとく、テンポの揺れを作っています。
それに対して、ビルラの方は、均等割の「123」.「123」の中で、生き生きと表情をつけなければなりません。
その状態で、メロディーを全く崩さなければ、譜読みの練習みたいに、無機質な演奏になってしまします。
そこで、ビルラや、ポピュラーの歌手達は、メロディーの原形を留める範囲で、「リズムそのものを変えている」のです。
「123」.「123」と刻み続けるドラムは、ここはゆっくり目に歌おうとしても、原則として待っていてはくれません。だから、そういう時は、遅れて出て、その後どこかを短めにして追いつかなくてはなりません。その過程で、作曲者の指定したリズムを正確に歌いながら追いかけよとすると、せっかちで落ち着きのない歌になってしまいます。
だから、リズムは変えざるを得ない。
そして、その部分の処理の仕方は、すべて歌い手のセンスと力量にゆだねられるのです。
極端に言うと、楽譜を正確に歌ってはいけないのです。確かに難しい世界ですよね。
楽譜に書いてある通りに歌い、(記譜上の)リズムを壊さず、正しく守って、テンポの変化で表情を出すクラシック。(アコースティックなので、ダイナミックの幅も大きいという要素もありますが)
楽譜に書いてないように歌い、テンポは崩さず、リズムや出だしのタイミングを変えて表情を出すポピュラー。
発声法は似ていても、この違いは決定的です。
それは、ピアノやオーケストラを伴奏として発達してきた、クラシックの世界と、、バンドをバックに発展してきたポピュラー世界の歴史的な成立の過程に起因する要素もあることでしょう。
「帰れソレントへ」ビルラの歌も、部分部分を区切って、テンポの速いところと、遅いところはありますが、「123」という、かたまりの中の均等割は一貫していて、「1」と「2」の間、あるいは、「2」と「3」間に大きな伸縮の変化は、クラシックのように極端ではありません。
ただ、あの曲の特徴として、「フェルマータ」はあります。「123」の流れとストップさせて、特定の音を長く伸ばすことはやっています。
それにしても、このような、フェルマータや小刻みなテンポの切り替えに対応するドラムの人は、もの凄い力量だと思われます。
ちなみに、リサの場合は、この2つの歌い方を、曲によって使い分けています。
この見方は、どこかの本やネットで調べてものではなく、クラシックの世界から、ポピュラーの世界に来て、戸惑いながら、歌唱スタイルを模索する中で、リサが直接感じ取ったことです。
【今日の1曲】
「Burava(ブラーヴァ)」
素晴らしい演奏が終わった瞬間、BURAVO(ブラーボ)と声がかかることがあります。
演奏者が女性の場合は、本当は「ブラーバ」といわなければならないのです。
今日はカンツォーネの女王、ミーナの歌で聴きましょうか。
MINA BRAVA!!
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
追伸
ビルラは、若い頃はオペラ歌手を目指したらしいのですが、先輩格にあの、黄金のトランペット、マリオ・デル・モナコがいたので、彼のいないポピュラー界を目刺したのだとか。
真相はいかに?モナコ1915年生まれ。ビルラ1925年生まれですから、10歳違うんですね。むしろ、ベルゴンツィの方が近く、ひとつ年上の1924年生まれです。
そして、昨日の写真の2ショット、パヴァロッティは10歳下の1935年生まれです。
いかがですか?ビルラの若い頃の写真です。かっこいいですね!
こうしてみると、容姿って誰でも、年齢と共に変わっていくものなんですね。男性から女性へと変身した私が言うのも何ですが・・・・(笑)
本日も最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。
【リサのライブ予定です】
(お問い合わせは「メッセージ」からお願い致します)
6/17(月)
「月曜シャンソンコンサート」
開場 pm6:00 場所 渋谷 SARAVAH東京
5/8(水)
Chambre Des Chansons
「~受け継がれるシャンソンスピリッツ~ 」<font size="2">Vol 1
開場17:00 開演18:00 大井町きゅリあん 小ホール
戸川昌子さん、うつみ宮土理さん他、豪華キャストと共演です!
【村上リサライブ動画】
【村上リサ ライブスケジュール】
【フェイスブックページ】
人気ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!






