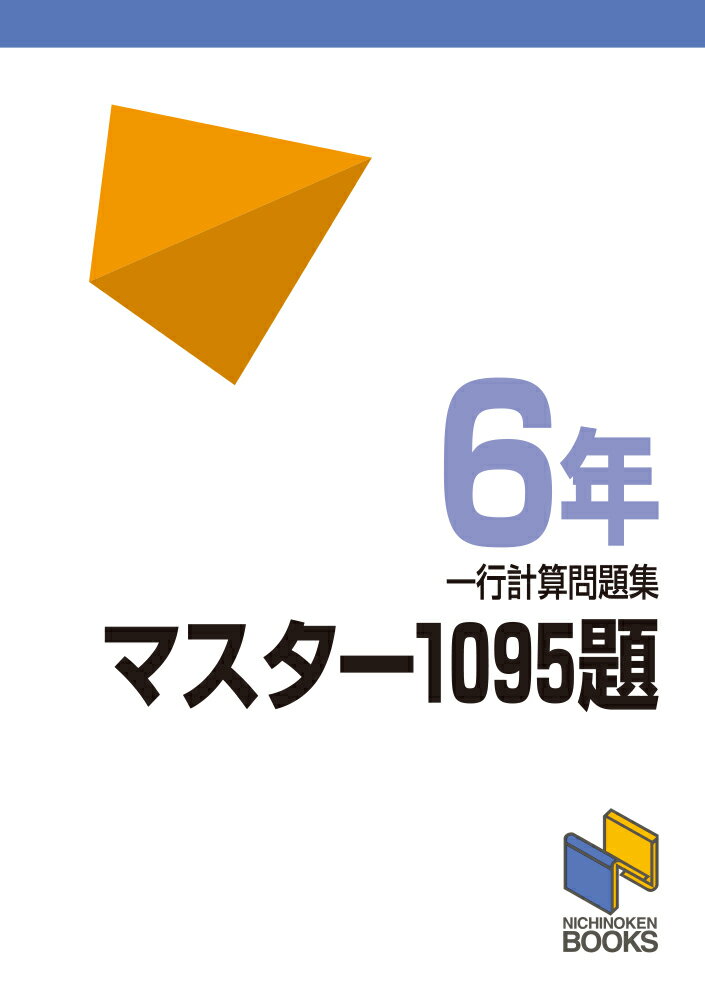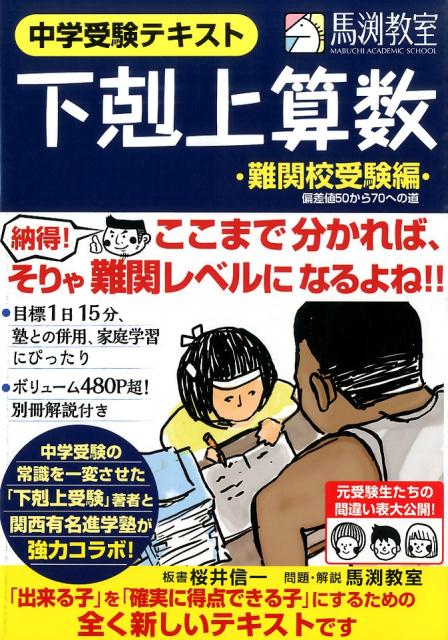小6カリキュラムが始まり3週間が経ちますね。
塾の教場からは
「夏休みまではひたすら算数!算数!算数で良い」
「算数で受験校が決まる」
「理科も計算分野以外はうまく手を抜け」
などと言われており、
理社は塾での演習解説に任せるところは任せてしまい、家では算数7,社会1.5,理科1,漢字と言葉0.5くらいの比率で家庭学習を回しています。
6年上の予習シリーズ算数は
4,5年の復習+必修例題+発展例題
という構成になっていますが、
発展例題にはかなり難しめの問題があったりします。
なので、解説を読んでパパにも理解不能な問題があれば、「塾で解説があったらよーく聞いておいで」とだけ伝えて、家庭学習では深追いしないようにしました。
これまでであれば、コベツバを使ってなんとしても解法を叩き込まねば、と躍起になっていたところでしたが
それよりもまずは4,5年の復習や、必修例題のところで取りこぼしが無いよう完璧にしていく、何度も解いて標準的な解法を定着させていく方を優先しています。
毎朝のルーティーン(マスター1095,下剋上算数)も、三日坊主にならず、ちゃんも続けられています。👏
マスター1095に毎日コツコツ3問取り組んでいるおかげで、技術が上がり、徐々にスピードも増してきたように感じます。
毎日横について計算の跡を辿っていると、どういうところに弱点があるか(我が子は小数の取り扱いがすこぶる下手なことが判明)がわかって良いですね。
そりゃあ理科の計算問題を苦手にするわけだな、というレベルで小数計算のセンスがない。💦
これはもっと早くから手当てしておくべきだったと後悔していますが、小6頭に気づけて良かったと前向きに捉えることにします。
下剋上算数(青)も毎日一回分を継続できています
全問正解する日もあれば、半分くらい間違う日もありますね
1ヶ月近く続けていると、苦手な単元や、苦手な聞かれ方の傾向が明確に見えてきます。
「またコレ間違っとるやんけ」と言いたくなるのをグッと堪えて、間違った問題をコピーしてノートに切り貼りしてストックしてから会社に行くまでが私のルーティーンです。
今日のような祭日のタイミングで一気にストックのやり直しをやりたいですね。
我が子にとって難しすぎる問題までは深追いせず
基本に忠実に、基礎を丁寧にコツコツと。