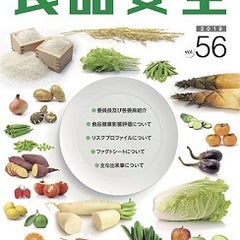食品安全委員会は、食品中の様々な「ハザード」が人の健康に与える影響について、「リスク」評価(食品健康影響評価)を行っています。
ハザード(危害要因)とは、健康に悪影響を与える可能性のある食品中の物質や、そのような食品の状態のことです。ハザードには、自然毒(ふぐ毒等)、意図的に使用される物質に由来するもの(残留農薬等)などがあります(図参照)。
リスクとは、食品中にハザードが存在することにより健康への悪影響が生じる確率と、その程度のことです。実際には、ハザードの毒性と、ハザードの体内への吸収量によって、どのくらいのリスクなのかが決まります。
食品安全委員会が行ったリスク評価に基づき、リスク管理機関(厚生労働省、農林水産省、消費者庁等)が使用基準などを決めていきます。
どんな食品にも、必ずリスクがあります。リスクがゼロの食品はありません。食品の安全を考えるときには、ハザードの毒性の強さだけでなく、その性質や量を意識することが重要です。
もっと詳しく知りたい方は→
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20180309ik1
(みんなのための食品安全勉強会(2018年3月9日)講義資料「食べ物と食品安全の基本について」)
※食品安全委員会では、【食品安全の基本用語】として、食品安全を考えるうえで重要な用語を解説しています。