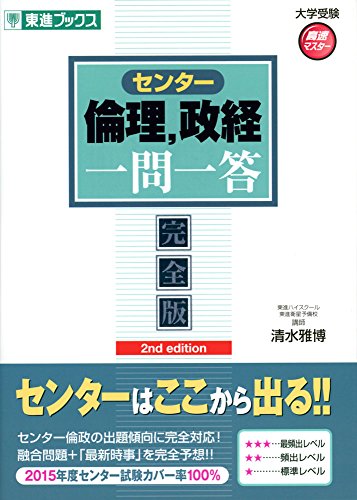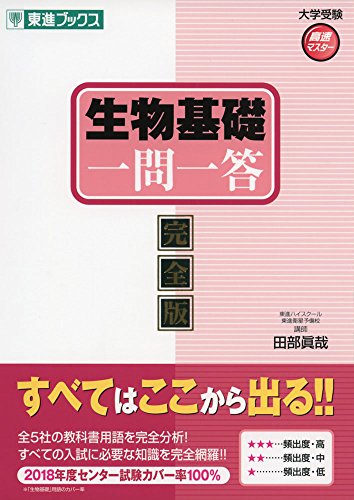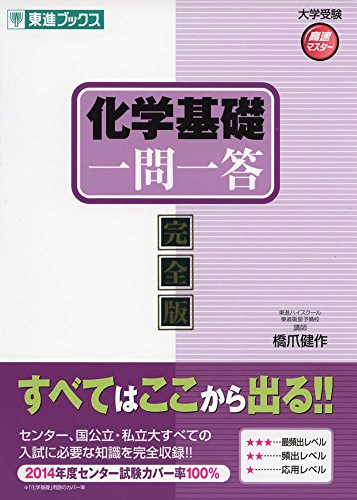受験科目で社会の選択、日本史か世界史かに迷われている子羊が多いので、聞かれるとざっくりとこう答えています。
「漢字が好きか、カタカナが好きか?」
ざっくりしすぎて、答えになってないと思われてスルーされることが多いのですが、結構これ重要なんです。
日本史は答えを漢字で書かせることが多いし、誤字だとバツになります。当たり前ですね。
世界史は人名や地名が長いカタカナだったりすることが多く、カタカナというかシンプルな文字だと印象に残らないという脳の人にはなかなか覚えられないみたいですね。
娘は完全に漢字脳でした。漢字テストは得意だったし。
反対にカタカナ用語は全く頭に入って来ないみたいです。
完全に私と一緒です。DNAゴメン!
なので、やっとこさで読み終えた話題の本
登場人物がそんなに多いわけではないのに、カタカナ名前だから覚えられなくて、あれ?この人とこの人の関係は?っていちいち確認しながら読み進めていたので、えらく時間がかかりました。
娘も読みはじめるや否や、登場人物が覚えられない〜と苦戦してるようです。DNAゴメン!
この本は半世紀以上前に書かれたものなのに、最後の一文は、今現在に繋がっていて、感染病の恐ろしさを改めて考えさせられました。
そして、私的印象的な一文は、「立派な人間、つまり殆ど誰にも病毒を感染させない人間とは、出来るだけ気を緩めない人間のことだ」←図星過ぎる。
今日から、また規制が緩和されますが(無理矢理感否めないが、経済のためオリンピックのためという国の事情)、気を引き締めて生活したいと思います。
って話逸れてしまいすみません。
日本史か世界史かでどっちが受験に有利不利かは無いと思いますので、自分が覚え易い方が良いと思います。
試験問題は、日本史は深くマニアック、世界史は広く浅く出題される傾向にあると言われています。平均点は世界史の方が高くなることが多いので、問題のバリエーションが世界史の方が少ないのかも知れませんね。娘は日本史だったから世界史のことは詳しくないですが。
ある大学では、選択問題の平均点が数学は30点、世界史は70点ってこともあったようで、文系で数学得意だと有利ですね。あまりにも差があると得点調整入るみたいですが。娘は数学が武器にはならなかったので残念〜
日本史はマーチレベル以上だとマニアックな問題が出ることが多かったみたいです。日頃から教科書以外の日本史に関心を持つようにすると良いと思います。歴史小説読むとか、大河ドラマ見るとか。マンガでも。
マンガなら角川がおススメです。
何が良いって、ソフトカバーなところ!軽くて持ち運びに便利です。←そこ?
漫画侮るなかれ、教科書に載ってないようなマニアックなところまで記載、今年の慶應の問題にも出たようで、あの漫画に書いてあった!と思い出して回答出来たようです。
センターでしか使わない科目は、一問一答系しかやりませんでした。しかも本番1ケ月前に買いました(笑)早く買ってもどーせやらないし。
倫理は、キリスト系学校では馴染み深い内容なので割と頭に入りやすかったみたいですが、政治経済には全く興味持てない新聞読まない系女子なので苦戦しましたが、8割取れたので良しとします。
理科基礎も同じく本番1ケ月前から詰め込んで8割。
センターのみの科目を最後の1ケ月で詰め込んだため、主要3科目の勉強が疎かになってしまい、私大3科目組に負けてしまったのは、無念でした。もうちょっと前からやれば良かったけど、追い込まれないと本気出さない省エネ体質系女子なのでこれが限界でした。←○○系女子多用すな。
次回は、研修受けたので、2021年入試変更点をまとめたいと思います。