今日から、このテーマの最終分野、物理分野に入りたいと思います。
物理分野は、娘のような文系DNAを持って生まれた女子にとってはかなり難関で、模試の出題範囲がこの分野になるとがっくりと点数が凹みました(涙)
逆に算数が得意なリケジョさんにとっては、得点源の分野になると思います。
特に娘の進学先は、理系に強い子が多くて、数学や理科の中間テストの平均点の高いこと高いこと!
「え?それって平均点なの?最高点じゃなくて?」と何度も聞き返してしまいました。
案の定、娘は平均点を大きく下回り、補講確定か???
難関校は、入学してからも回りの子が良くでき、授業も難しいということを踏まえて、楽しい中学生活が送れるようにしっかりと受験勉強頑張りましょう~娘のように後悔しないように?
女子校は、理数科目の出来で合否が決まると言っても良いと思います。国社はみんなができるから差がつかないのです。
入学後、在籍数に比べてずば抜けて神奈川最難関女子校の合格者が多い塾の出身者のお母さんに聞いてみたら、「塾では算数ばかりやっていた」そうで、「算数を制する物は、最難関校を制す」ということのようです。
あれ、理科の振り返りなのに、算数になってしまった。まぁ理科も算数も理系科目という括りでご了承願います。
では、電流の働きについて振り返ってみたいと思います。
この分野は比較的早い段階で習う分野だと思います。塾でも4年生~5年生の初めくらい?
小学校でも豆電球とか電池とか、教材を一括購入して実験しますよね。小学校では豆電球がついたね~で終了ですが、受験理科は回路図を用いて、電球が明るいかくらいか、電池を増やすとどうなるかとかいろいろなパターンが出題されます。
電池や電球の記号を用いて回路図を書けるようにし、いわゆる基本9回路を覚えるのが必須です。
娘は長いのが+で、短いのが-という基本中の基本、電池の+-の記号さえも怪しかったです。
電池の直列つなぎは、電池が増えるほど電球は明るくなる。なので電池は早くなくなる。一本道なので電流の大きさはどこも同じ。→志望校に一直線なぶれない奴、がむしゃらに頑張るので体力消耗も激しい。
電池の並列つなぎは、電池をふやしても電球の明るさは変わらない。なので電池は長持ち。たとえば2個並列につなぐと半分ずつの負担で済むので、電流の大きさは半分になる。→2人いれば、半分の労力で済むよね~って感じ?
電球の直列つなぎは、電球を増やすと、一個あたり暗くなる。直列だとどこでも同じ大きさの電流が流れているので、電球が増えれば一個当たりの持ち分が減るため。→一家族の兄弟が多いとおやつの分け前が減るよね~って感じ?
電球の並列つなぎは、電球を増やしても、一個当たりの明るさは変わらない。並列だと、それぞれの分岐に同じ電流が流れるので明るさも同じ。→各家庭に平等におやつが配布されるという感じ?
なんか、変なたとえで余計混乱させてしまったらすみません。
追記*
素人考えで単純に考えて↑のような理屈をこじつけてみたのですが、これが、複数の電池や電球の組み合わせになるとややこしい数字になってきますので、あくまでも基本的な考えとご理解ください。
追記終わり
↑の電池の数とつなぎ方、電球の数とつなぎ方を色々に組み合わせて聞いてくるのでかなり混乱(笑)
更に、スイッチが入ってきたり、ショート回路はどれかとか聞いてきたり、本当にもう、頭がショートしました・・・
あと、電流計の読み方もよく出ましたね。
いわゆる「実験器具の使い方問題」です。
娘は、ことさらこういう「読み取り問題」が苦手で、必ずと言っていいほどミスしてましたね~
私の文系脳的ジャドーな素人解釈で混乱してしまった方のために朗報!え?読み飛ばしてた?
どちらでも構いませんが、上記のことはなかったことにして以下の本を参考にしましょう。
この単元、塾のテキストがとっても分かりにくかったので、(まぁ、先生の説明を前提でテキストを作っているのでテキストだけでは理解しがたいのは当然ですね。)参考にした本。
力と電気、音、光がわかる―ドラえもんの理科おもしろ攻略 (ドラえもんの学習シリーズ)/小学館
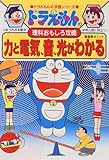
- ¥821
- Amazon.co.jp
電気だけでなく、ばねとかテコとか滑車・輪軸、浮力、音と光という、難解物理分野てんこ盛りなのでとっても役に立ちました。(それでも苦手でしたが・・・)
いつも読んで下さりありがとうございます。