今日は、朝から雨。入学してはじめての雨かも知れないです。
雨のせいなのか、目ざまし時計が鳴らなかったせいなのか、私、30分も寝坊してしまい、お弁当を超特急で作りました。
急いで作ったアスパラの牛肉まきはぐちゃぐちゃになってしまいましたが、なんとか間に合ってセーフ。
お弁当作りは塾弁で鍛えて?いたので、そんな所でも思いがけず塾時代の経験が役立ちました。
では、今日は「月」について、行ってみましよう。
月は、女子校頻出分野と言われています。
なんだかロマンチックな響きもあって、女子はなじみやすい分野かもしれません。
でも、ちょっとした計算問題なんかもあってなかなか侮れないです。
まず、月は太陽のまわりを約27.3日で反時計周りに一周する(月の公転)衛星であることを踏まえ、月の見た目の形が変わる満ち欠けについて理解します。
地球を真ん中にしてその周りを取り巻く月の形(上弦の月とか、満月とか新月とか)の位置を覚えましょう。その際、太陽の向きに注意してください。結構引っ掛け問題?として出たりしますから。
そしてそれぞれ、月の出、南中、月の入りの時刻を覚え、月と太陽の位置関係も大切です。
たとえば、満月は18時に東の空から上り、真夜中0時に南中(一番てっぺん)し、明け方6時に西の空に沈む。その時、太陽は月の反対側にある。
満月にお月見するのは、夕方6時から一晩中見えるので明るく、月を見て楽しむのに適していたからなのでしょう、昔の人は自然の理にかなった生活をしていたことが分かります。まぁ、昔の人は早寝なので一晩中起きていることはなかったと思いますが。
夕方良く見るいわゆる絵に描いたような三日月は西の空に見え、上弦の月は、夕方南中するので南の空に見えます。月の形と時間によって、方角がわかるという、月の動きが分かればこれからの生活に役立つかもと思って楽しんで学習することをお勧めします。
模試では、色々な切り口から、何時にどの方角にどんな形の月が見えるかと問われたりするので、ちょっとした計算問題になりますので、地球を真ん中にしたあの図を良く頭に入れておく必要があると思います。
あと、日食と月食の太陽、月、地球の位置関係は基本ですので、覚えてください。
最後に、月とか星とかの理解の手助けとなるお勧めカレンダー,や絵本を紹介しますね。
一度買うと毎年買いたくなるカレンダー。
- 2014年 太陽・月・星のこよみ/公益財団法人 国際文化交友会
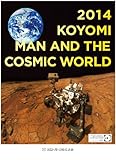
- ¥2,000
- Amazon.co.jp
今年のはもう始まっていますが、天体分野の勉強に本当に役立ちます。天気記号を毎日書くポスターもあって天気記号もばっちり覚えられます(こういう継続するものは苦手な三日坊主娘は数カ月で挫折しましたが)まだお持ちでない方は即買いをお勧めします。
それから、絵本。
- 月の満ちかけ絵本/あすなろ書房

- ¥1,296
- Amazon.co.jp
絵本ですが、参考書並みにレベル高いです。低学年では理解しがたいかもしれませんが、小さいうちに刷り込むには良いかも?
娘が6年生位の時に買ったのですが、読む時間がなくてあまり活用できませんでした。もうちょっと余裕のあるときに一緒に読んだりしたら良かったかなと思いました。