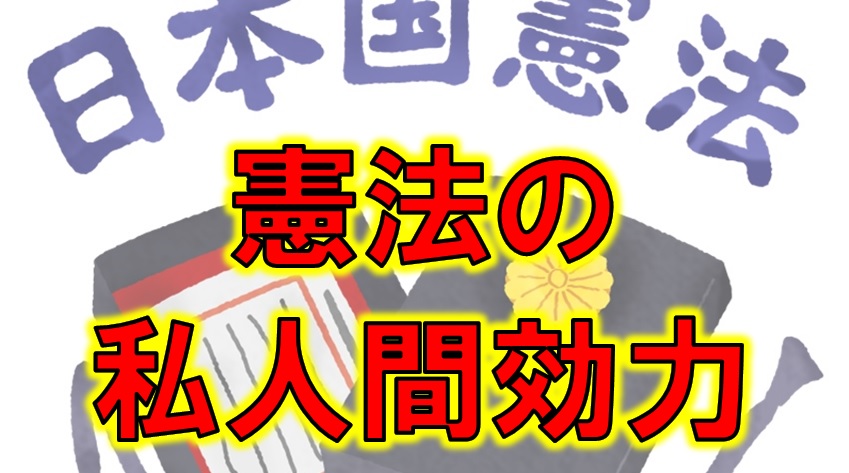憲法は人権を保障しています。
それは今更いうまでもないのですが、
では憲法は、誰に対して「人権を保障せよ」といっているのでしょうか?
基本は国に対してです。
なので、国に対して「人権を保障しろ」というのは至極当然なんですね。
ですが、人権の敵は国だけではありません。
民間同士だって、人権を侵害し合ったりはします。
ではその場合、憲法はどう出るのでしょうか?
今回はそんな、憲法の私人間効力について見ていきます。
私人間効力
「私人」というのは民間人と思って頂ければいいです。
先程も書いた通り、憲法は国民が国家に突きつけた命令書です。
故に憲法が国民に適用されるのは、本来おかしいんですね。
なので「無効力説」、
詰り憲法は私人には一切適用されない、という考え方もあります。
然しそれでは、現代の人権保障には十分ではないです。
なぜなら企業による労働者いじめ、
労働組合による組合いじめ等があるからです。
「私人」といっても、全てが全て、保護されるべき弱い存在かというと、そうでもなく、
大企業や労働組合の様に、強力な力をもった私人もいます。
強い私人が弱い私人の人権を侵害するのに、憲法は何もしません、となると、
実際問題、人権が守られません。
そこで、私人であっても憲法を直接適用しようとする「直接適用説」がでてきます。
但し、直接適用説も問題があります。
私的自治を害するのです。
私的自治とは、ざっくりいえば自由です。
契約自由とか。
あれも憲法がでてくる、これも憲法がでてくる、となると、
民間の自由が著しく制限されます。
憲法は国家を縛る為のものであり、民間を縛る為のものではないのです。
なので直接適用にも無理があります。
無効力もダメ、
直接適用もダメ。
ではどうするか?
通説は間接適用です。
これは「私法の一般条項を通じて間接的に適用する」というもの。
これだけだと何いってるか分りませんね。
例えば民法90条には「公の秩序、又は善良な風俗に反する法律行為は無効」と書いてあります。
これだけだと、
何が公の秩序に反するのか?
何が善良な風俗に反するのか?
よく分らないですよね。
この様に、抽象度の高い条文を「一般条項」といいます。
この一般条項に於て、
何が公の秩序に反するのか?
何が善良な風俗に反するのか?
を判断する際に、憲法を参照します。
「人権を守ってないから公の秩序に違反する」
とかね!
これが間接適用です。
私人間ですから、あくまで適用されてるのは民法等ですが、
裏では憲法原理がしっかり生きているのです。
日産自動車女子若年定年制事件
日産自動車は昔、女性は男性より5年早く定年退職になる、という就業規則がありました。
憲法で考えれば、性別での差別に当るので、14条に抵触する事になります。
但し、日産自動車は国家ではありませんので、憲法を直接適用はできません。
そこで、直接的には民法90条が適用されます。
即ち、「性別で差別するのは公序良俗に違反する」と。
こういう風にして、優秀な女性が救われました。
三菱樹脂事件
大学在学中に学生運動してた人が、それを隠して就職活動しました。
続きはこちらで公開しています!!!
その他の記事はこちらから!!!