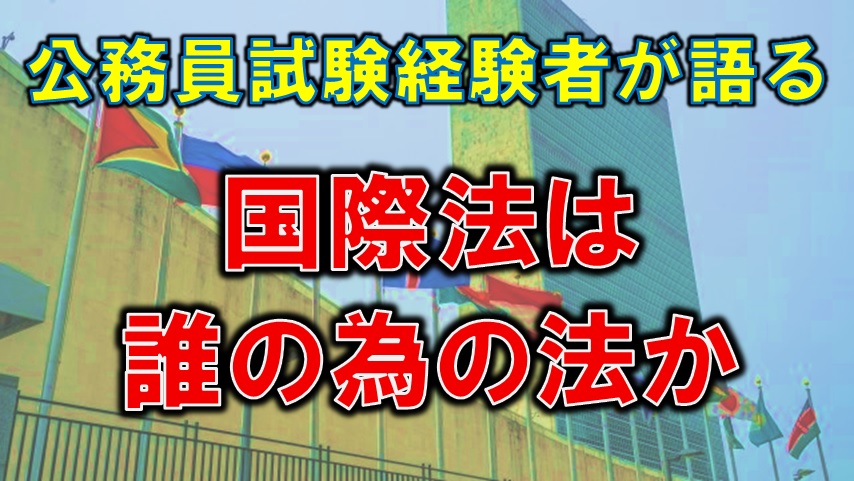さて、国際法解説の第3段!!
今回は、「国際法」という ‘物語’ の登場人物、
言い換えれば国際法は誰の為の法かを考えたいです。
「法」という ‘物語’ に出演できる資格
物語への出演という例えで返って分り難かったら申し訳ないのですが、
法によって権利を得たり縛られたりする対象は、各法毎に決っています。
法的に権利を得たり義務を負ったりするのを、
「権利能力を有する」といいます。
堅苦しいですね。
そして国際法上、’権利能力を有する’ 対象を「国際法主体」といいます。
これからみていくのは、詰る所、国際法上権利能力を有する国際法主体は何か、であります。
国
国際法は国と国との関係を規律する法です。
よって、国際法の主要な登場人物は国、
要するに各国の為の法です。
当然ですね!
そこで今更ですが、
‘国’ とは何ぞや!?
何をもって ‘国’ といえるのでしょうか?
一般的に、国たる要件は以下です。
- 住民
- 領土
- 政府
- 外交能力
まず「住民」ですが、
これも何をもって ‘住民’ とするかで、「主観説」と「客観説」の2つの考え方があります。
主観説は、その人達の意思(何国籍を持ってるか)
客観説は、人種,言語,宗教等で決めましょう
という考え方。
通説は主観説です。
客観説だと、他民族国家、即ち1つの国に沢山の民族がある国をばらばらにしなきゃいけないし、
自分達の民族がよその国にいる場合、それを口実に「あそこの国も俺達の国」と侵略を正当化しかねません。
実際、歴史的にはナチス•ドイツがその理屈でオーストリアを併合してますし。
領土については、これ当然ですよね!
場所がないんだったら、どやって地図ひくんだ、って話ですし。
領土が国の要件になってるので、国の事を「領土団体」とよんだりもします。
こんなの国際法でも滅多に使わない表現ですが、
一応あるにはある表現なので、ご参考までに。
「政府」っていうのは、ここでは領土と住民を支配できる体制をいいます。
続きはこちらで公開しています!!!
その他の記事はこちらから!!!