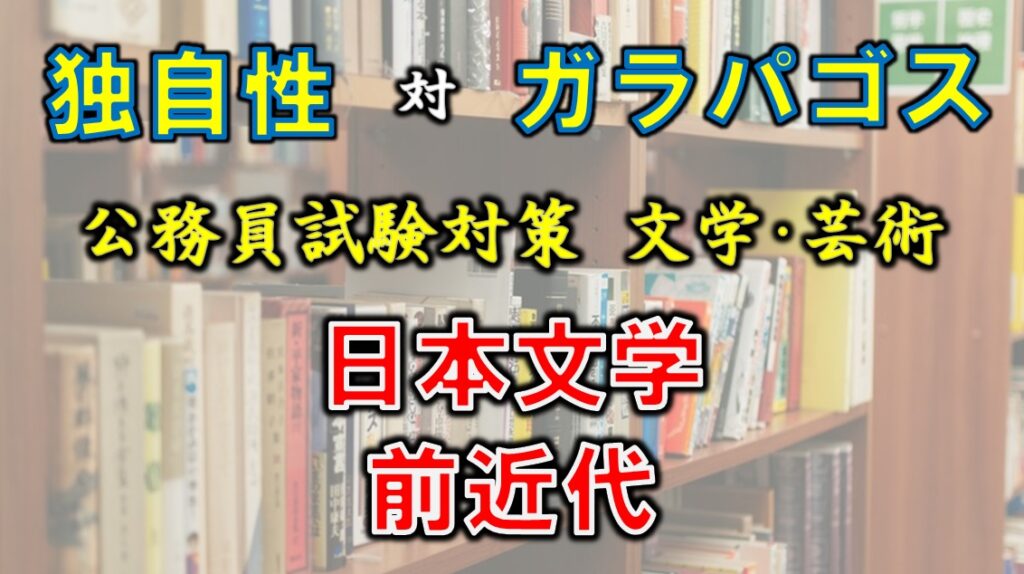前回は西欧文学について述べてきました。
今回は日本文学について述べます。
うぷ主は日本文学をどう習ったか
日本文学も文学史で見るなら古代から現代まで通しで学習すべきでしょう。
ですが当時のうぷ主の講師がいうには「明治維新より前か後かで日本文学の性が全く異なる」と。
それが本当かどうか分かりませんが、
明治維新より前の文学は日本史の文化史でパパッと習い、
明治維新以後の文学は文学•芸術で習いました。
うぷ主的には通しで学習した方がいいと考えますので、古代から通しで叙述しますが、
前近代は何分、適当にしか習わなかったので、雑になるのをご容赦下さい。
上代
これで「じょうだい」とよみます。
飛鳥時代から奈良時代、主として奈良時代をさします。
この時代の特徴として、
まずは歴史書の編纂が行われました。
代表例が「古事記」と「日本書紀」。
後は和歌ですね。
特に「万葉集」は現存する最古の和歌集で、
名もなき庶民から王侯貴族まで、万人の和歌を収録した和歌集としても有名です。
この時代の文字は「万葉仮名」といいます。
結局の所は漢字です。
漢字をその当時の日本語に読み直した、
まあ言っちゃえば '当て字' の元祖みたいな。
漢字それ自体はもっと昔から日本に入ってきてたみたいです。
ほら、有名な「漢委奴国王」って刻まれた金印、あるじゃないですか。
1説にはあれは弥生時代の1世紀頃には入ってきてたをだとか。
この説が正しいとすると、西暦1世紀頃には既に日本人は漢字を知っていた事になります。
古事記や日本書紀が書かれたのが8世紀初頭ですから、
日本人が最初に読み書きを学習してから7百年位は大した文学活動をしてなかったと。
昔の人達は7百年もの間、何してたんでしょうね!?
平安時代
Wikipediaでは「中古文学」として記載されていますが、
「中古」なんて書かれたら
「新品じゃない物!?」
ってなる人が一定数いるでしょうから、ここではあえて平安時代と致します。
文学史でいう「中古」っていうのは、要するに平安時代ですから。
平安時代も相変わらず和歌は盛んで、
初の勅選和歌集である「古今和歌集」が編纂されました。
勅選和歌集とは、天皇(たまに上皇)の命令で編纂された和歌集です。
中古文学の更なる特徴として、
物語文学や随筆が発展しました。
物語文学で超有名なのが紫式部の源氏物語でしょうが、
他にも
在原業平であろう人があっちこっちで女遊びしまくる「伊勢物語」や
かぐや姫で有名な「竹取物語」も平安時代です。
随筆では、
紀貫之が女装して、じゃなかった… 女のふりして書いた「土佐日記」がありますし、
恐らく1番有名なのが清少納言の「枕草子」ですかね。
諸説ありますがこの時代に平仮名や片仮名といった「仮名」が発明されたとする説もありますし、
少なくとも仮名が発展したのは平安時代です。
どうもそれまでは
漢字=男性の字
っていう風潮があったみたいですが、
かなの発明発展によって女性、特に朝廷とかの女官達にとって文学活動がし易くなりました。
確かに宮仕えの女官というのは当時的には 'エリート層' ですが、
文字を書き表す事への門戸を広げたのは間違いないでしょうし、それは日本文学の発展に多大な貢献をしたのでしょう。
続きはこちらで公開しています!!!
その他の記事はこちらから!!!