なぜ売れすぎ?セブン限定“ゴンチャ”ドリンク、「タピオカなしでも」歴代トップ級ヒットの理由
セブン限定「ゴンチャのペットボトル」はなぜこんなにも売れているのか?
セブン-イレブンでは2年連続で日常的に本格ティーが楽しめるグローバルティーカフェチェーン「ゴンチャ」とのコラボペットボトル飲料を販売しています。実は昨年、セブンの歴代限定飲料の中でもトップラスに売れたという「ゴンチャのペットボトル」。ゴンチャ=パール(タピオカ)と思っている方の中には「パール入っていないよ?」と不思議に思う方もいるかもしれません。
⇒【写真】なぜコラボ?なぜタピオカは入っていない?セブン歴代の限定飲料の中でトップクラスに売れた「ゴンチャのペットボトル」の詳しい画像をもっと見る(全5枚
なぜ売れすぎ?セブン限定“ゴンチャ”ドリンク、「タピオカなしでも」歴代トップ級ヒットの理由(MonoMax Web)
なぜタピオカは入っていないのか?そしてなぜこんなにも売れているのか?セブン-イレブン・ジャパン 商品本部 マーチャンダイザー大口裕也さんにお聞きしました。
「セブン歴代の限定飲料の中でトップクラスに売れた」理由は?
セブン-イレブンは2024年、初めてゴンチャとキリンビバレッジとのコラボ飲料を発売。大きな話題を呼び、発売後1週間で累計約570万本(約2か月分の計画数)の販売を記録しました。これは“セブン歴代の限定飲料の中でトップクラス”とのことです。 セブン-イレブンとのコラボにあたり、ゴンチャ ジャパン社長の角田氏は「顧客との接点を増やし、販売機会を増加させたい」と話していましたが、実際にゴンチャの店舗がない地域の方にも楽しんでいただけたそうで、そこは全国約21,000の店舗を持つセブン-イレブンならでは。 「販売実績を分析すると、特にゴンチャ様の店舗がない地域においても顕著な販売増が見られました。一方で、ゴンチャ様店舗の多い都心部においても堅調な売れ行きとなりました。ゴンチャ様からは、『これまでゴンチャをご利用いただいたことのないお客様が、セブン-イレブンのペットボトル商品をきっかけに実店舗へ足を運んでくださるケースが多数報告されている』とお聞きしております」(大口さん) セブン-イレブンとしても、新たな客層を広げるきっかけにもなりました。これまでペットボトル飲料を購入するのは40~50代が多かったのに対し、「ゴンチャのペットボトル」は30代以下に多く売れています。 これだけたくさん売れた理由について大口さんはこう分析します。 「当初私たちはクッキーとのペアリング提案をしていたのですが、SNS上では『セブン-イレブンのプライベートブランド商品の黒糖わらびを入れるとお店の味に近づく!』との投稿が大きな反響を呼びました。その結果、多様なアレンジレシピが次々と発信され、これが商品の認知拡大および売上促進に寄与したと考えています」(大口さん) まるで正解のない多様性の時代を象徴するかのように、100人いれば100通りのアレンジがしやすい商品であったことも理由の一つかもしれません。単体で飲んでももちろん美味しいけれど、何かを加える余力もある。今年も発売から1か月以上たちますが、売れ行きは好調だといいます
そもそもなぜ、セブン-イレブンがゴンチャとコラボ??
2024年にセブン-イレブンとゴンチャがコラボすることになったのは、大口さんの前任者がコラボ打診を行ったことがきっかけだったのだそう。ゴンチャ側としては他コンビニチェーンでも良かったかもしれないのに、なぜセブン-イレブンとのコラボを決意したのでしょうか? 「セブン-イレブンは多様なコラボレーション機会を頂いておりますが、多くのパートナー様から『セブン-イレブンは品質に対する理念を深く理解している』とご評価いただいております。有名ラーメン店とのカップ麺コラボレーションも多数手掛けていますが、どのブランドも、自らの看板を安易に掲げることを良しとはしません。そのなかで、『コラボを実施するなら間違いなくセブン-イレブンだ』とご信頼を寄せていただいていることを、大変光栄に思っています」(大口さん) 前任者の方がゴンチャとのコラボをしたいと思ったきっかけは、「コロナ禍でもなぜかゴンチャにはいつも行列が絶えない」ことに興味をもったからだそうですが、当時はタピオカブームの真っただ中。素人の発想だと、チルド飲料としてタピオカを入れたものを販売したくなってしまいますが、タピオカを入れなかったのはなぜでしょうか? 「セブン-イレブンとしては日々変化するお客様のライフスタイルや嗜好に寄り添いながら、いま本当に求められてる価値をスピード感持ってお届けすることを大切に商品開発をしています。ゴンチャ様は、かつてのタピオカ飲料店のイメージから、『グローバルティーカフェチェーン』へと成長を遂げる過程にありました。そのため、本商品はお茶の可能性に着目し、その魅力を最大限に引き出すことを意図して開発いたしました」(大口さん) また、タピオカ入りの飲料にする場合、ゴンチャの店舗で提供しているクオリティに合わせることが難しかったことも理由のひとつ。ゴンチャの店舗で提供しているものは、お店で毎日丁寧に仕込み、すぐに飲むことが想定されているのに対し、ペットボトル飲料は数か月間品質を維持する必要があるためです。 そして近年の若年層にお茶派が広がっており、ゴンチャ様の調査結果によると「お茶しよう!」と言われて、30~40代よりも10~20代の方がコーヒーではなくお茶を飲むことを想起する傾向があるようです。コーヒーチェーン各社もティー専門店を展開するなど、ティーカフェ市場は拡大しています。そこで中味開発及び製造はキリンビバレッジに担当いただくことに決定しました。 「ティーといえばキリンビバレッジ様、という確固たるイメージがあります。『午後の紅茶』は1986年の発売以来、約40年にわたり継続的に支持され続けており、この長期にわたる安定した実績こそが、信頼の証であると考えました」(大口さん
ゴンチャの店舗とペットボトル飲料は「目的」が異なる
試行錯誤の結果、2025年版はさらにゴンチャらしさをアップすべく、ゴンチャらしい黒糖の風味とミルクの味わい、そして口に含んだ瞬間から飲み終わった後までの風味や香りの設計の調整を続けたといいます。 たしかに、2025年バージョンはよりゴンチャらしい味に近い風味豊かな味わいになったと筆者も感じました。実際、飲んだ方からも
『ゴンチャらしい味に近づいた』
『ほぼゴンチャの味じゃん』
というコメントも多く寄せられているといいます。ただし、「そんまんまお店の味」にすることが正解とは限りません。
「ペットボトル版のゴンチャ飲料は、あえて店舗で提供される味と完全に同一にはしておりません。
これは、両者の目的が異なるためです。店舗の商品は、その場で会話を楽しみながら味わうものです。一方でペットボトル飲料は“喉の渇きを潤す”ことを主な目的としており、400mlの容量設定にしております。
喉の渇きを癒しつつ、ゴンチャらしい味わいをしっかり感じていただき、最後まで美味しく飲み切れる甘さのバランスを追求しています」(大口さん) 甘さや氷の量、トッピングなど、そのときの気分でカスタマイズができるゴンチャ店舗で飲む飲料と異なり、ペットボトル飲料は均一な味わい。全体でより甘さを全体に感じられる味にしているという違いもあるそうです。 今後について大口さんは、「まだまだお茶の可能性はあると思っていますので、よりティーカルチャーを楽しんでもらうためのアレンジ方法や販促も考えています。今後もぜひゴンチャのペットボトルを様々な場所で楽しんでくださいね」と話します。これからもセブン-イレブンで手軽にゴンチャのペットボトルコラボが楽しめることに期待しましょう!
文・撮影/松本果歩
MonoMaxWeb編集部
========================================================================================================================================
株式会社ゴンチャ ジャパン 代表取締役社長 角田 淳氏【飲食の戦士たち:株式会社キイストン特別コラム】
株式会社ゴンチャ ジャパン 代表取締役社長 角田 淳氏
update 24/09/10
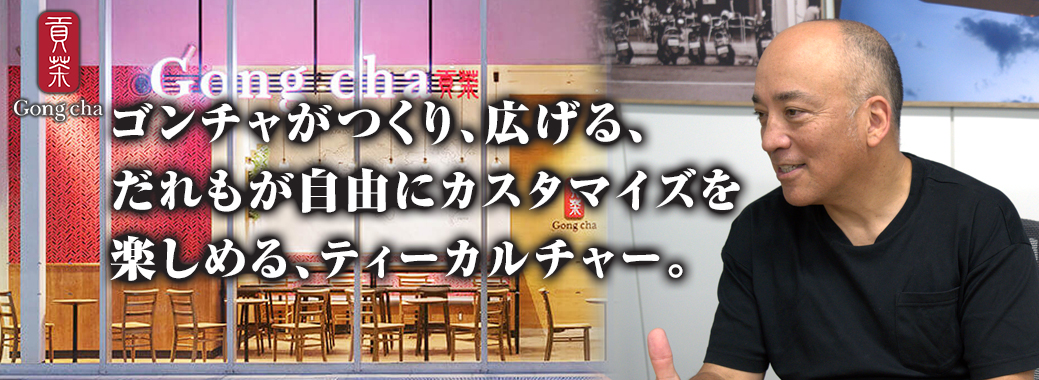

| 株式会社ゴンチャ ジャパン 代表取締役社長 角田 淳氏 | |
| 生年月日 | 1971年3月25日 |
| プロフィール | アメリカの大学を卒業したのち、大手自動車メーカーに勤務するかたわらで、スポーツイベントや音楽イベントの企画やマネジメントを行い、それが、のちに本業になる。10年間スポーツマネジメントに携わり、39歳の時に日本サブウェイに入社。マーケティング・経営企画などを経て、社長に就任。2021年10月、サブウェイを退社し、ゴンチャ ジャパンに入社、社長に就任する。 |
| 主な業態 | 「ゴンチャ(Gong cha、貢茶)」 |
| 企業HP | https://www.gongcha.co.jp/ |
タピオカブームと、ゴンチャ ジャパンと。
いろいろあった、と言えば怒られるだろうか。
ゴンチャが日本に初めてオープンしたのは、2015年。2018年あたりから空前のタピオカブームが始まり、ゴンチャの前には連日、長蛇の列ができた。
SNSなどを通じたコミュニケーションが盛り上がるタイミングだったことも、ゴンチャにとっては追い風だったにちがいない。スマホで撮影されたタピオカドリンクは、デジタルの世界をかけめぐった。
ただし、第三次と言われたタピオカブームも、やがて終わり、タピオカドリンクのショップも次々、姿を消す。
ゴンチャ ジャパンでも経営者がかわるなど、そういう意味でもいろいろあった。
粥(かゆ)を導入したり、コーヒーを始めたり。ティーカルチャーを標榜するゴンチャ ジャパンが、迷走を始めたと言っていい。その時、現れたのが、今回、ご登場いただくことになった角田淳さん。
じつは、角田さんには2019年の10月に、この「飲食の戦士たち」にご登場いただいている。その時は、サブウェイの代表として。
あの時も低迷し、立ち直り始めた業績を立て直すのが角田さんのミッションだった気がする。もちろん、角田さんの実績は今のサブウェイをみれば明らか。「いまや絶好調だ」と角田さんも笑顔で語っている。
ちなみに、現在は別の事業に携わっていらっしゃるが、当時の日本サブウェイ合同会社の共同代表、鈴木孝尚さんにも「飲食の戦士たち」にご登場いただいているので、興味のある方はコチラをご覧いただきたい。
では、ゴンチャ ジャパンのお話に入る前に、角田さんの生い立ちを、今回はさらりと追いかけてみよう。
ブラジル育ちの、グローバルな小学生。
角田さんが、生まれたのは1971年。生まれてすぐに父親の仕事の関係でブラジルへ渡り、小学校入学直前まで生活していたそうだ。つまり、南米育ち。
「ポルトガル語、スペイン語、そして、小学校になって初めて日本語をつかうようになります」。
小学生で3ヵ国語を話すことができたんだろうか。まさに、グローバルな小学生である。
校長先生の薦めもあり、中学から静岡の学校に進み、寮生活を開始。ラグビーも始めている。高校を卒業するとアメリカの大学に進学。
もともとグローバルな小学生である。角田さんにすれば、アメリカの大学の進学は日本の地方の大学に進学するのと、そうかわらないのかもしれない。ちなみに、お姉さまは、高校から渡米されている。
アメリカの大学を卒業した角田氏は帰国し、大手自動車メーカーで勤務。その一方で、様々なイベントの企画やマネジメントを行い、スポーツイベントや音楽イベントをプロモートもする仕事を行っていく。
39歳、知人の紹介で、サブウェイに入社。その時、角田さんは「スポンサー側の仕事をしたことがなかったので、一度、経験してみたいと思い、新しい世界に飛び込んだ」と言っている。
そのサブウェイ時代の実績が評価され、ゴンチャ ジャパンの株主たちから、オファーがとどく。
サブウェイと、ゴンチャと。
サブウェイとゴンチャ。フードとドリンク。文化ももちろん異なるが、似ているところもなくはない。
消費者がカスタマイズして、つくる。楽しみと同時に、初オーダーだと、とまどいがなくはない。
実際、角田さんも「ポイントカードをお持ちのコアなファンは慣れていらっしゃるので、オーダーのスピードもやはり早いですが、SNSでも時折『オーダーの仕方がわからない』という投稿があり、そういうユーザーは少し時間がかかるようですね」と、おっしゃっている。
もちろん、この「むずかしさ」が「たのしさ」にかわる。これも、おなじ。
もう一つ、サンドイッチとティーと、アイテムは異なるが、新たなカルチャーを日本に広げるというミッションも似ている。
もっともサブウェイに比べ、ゴンチャ ジャパンのあゆみは、まだ10年にもならない。
空前のタピオカブームで業績が加速し、店舗数が拡大。ティーカルチャーがファンの心をつかんだのはまちがいないが、ブームが去った今、業績は、どうなっているのだろう。
つぎに、そんなお話もうかがった。
「現在(2024年5月)の店舗数は約160店舗。私がこちらに来たのは2021年10月ですが、その時は約100店舗でした。2015年の1号店オープンから現在まで、ブームなどもあり業績が上下したのは事実ですが、ゴンチャ ジャパンがオススメする、ティーベースドリンクは、この9年間で、ある一定の定着をみたように思います」。
ゴンチャのファンの多くは、流行に敏感な10代、20代の若い世代。
「この世代は、ゴンチャの文化と一定の親和性がある世代です。カスタマイズした、ティーを楽しむ。若いからこそ、楽しみ方を知っているように思います」。
たしかに、ゴンチャの文化は、「自由に、ティーを楽しむ」こと。それを体現しているのが、この世代。たしかにドリンクをもった若者は絵になる。
じつはタピオカブームの時と比べても、店舗の数は増えているそうだ。ゴンチャが一過性のものでなかった証でもある。
「当面の目標は200店舗です。将来的には、年間の来店数を、4000万人にもっていきたいですね。その時には400店舗が視野に入ってくると思います」。
ただし、数字に縛られない。急ぐこともしない。
「まず、ブランドを360度、確立することだ」と角田さんはいう。対ユーザーだけではなく、クルーのトレーニングや、サプライチェーンの確立など、インフラ整備も行っていかないといけない。
やることは、いろいろありそうだ。だが、就任後の3年間で角田流の改革は大きく前進している。その点についても、うかがっている。
ゴンチャのレシピは、自由に、楽しめること。
「外部に向け最初に行ったのは、ソーシャルメディアの活用です。ゴンチャが推し進めるティーカルチャーを広く浸透させていくための、方法の一つです。Xやインスタグラムなど、Z世代やα世代を中心に情報を拡散しています」。
角田さんも、日々、SNSのチェックはかかさないという。さすが、もとプロモーター。
その一方、内部に向けては、「我々が大事にしていることってなんだっけ?」と、問いかける。マネージャークラスといっしょに合宿し、話はつづく。
「ゴンチャのハピネスってなんだっけ? それってどういうこと? 新たなものをクリエイトするというより、理念などの再確認ですね。お客様が、その日の、その時の気分で自由にチョイスできる、そういう楽しみをゴンチャは大事にするんじゃなかったっけ? そんな話です」。
「じつは、そのあたりが、ボヤっとしていたんですね。タピオカがブームになったものだから、効率化だけを追い求めて時間がかかるフローズンをやめたり、味のチョイスも、カスタマイズの種類も減らしたりして。なんのために『ハピネス』をうたっているんだっけ? 自由に楽しめる、それがゴンチャの価値だとすると、なんでそれやめちゃったんだろうかって。そういうことを一つひとつ整理していきました」。
原点にもどり、ブレを修正する?
「そうですね。品質にこだわったお茶と、だれもが自分の好みに合ったカスタマイズを楽しめる。ゴンチャの創業者が追いかけ、形にしたのが、このレシピだったんです。それを見失っていたかもしれません」。
「店舗のクルーに対してもおなじことが起こっていました」と角田さん。
「店舗のクルーたちには、髪色のカラーチャートが渡され、ある一定の範囲でしかカラーが許されていなかったんです。それって、おかしくないかって。だって、自由じゃないでしょ。ゴンチャで働く人が、自由じゃなきゃ、ブランドの理念はどこにいっちゃうのって話です。だから、今、カラーチャートはありません」。
ティーカルチャーと、自由。千利休が知れば、どう思うだろう。案外、ゴンチャの空気を気にいるんじゃないだろうか。わびさびを開放した、もう一つの文化。
茶道の対局にある、大衆の文化。もうひとつの茶道が花開くと言ったら、おおげさすぎるだろうか。ともあれ、角田さんとスタッフたちの対話はつづく。
「全体への共有はもちろんですが、定期的にワークショップを行い、キックオフミーティングなども行っています」。
店舗のクルーからハピネスになる。
角田さんらしく、アーティストなどとのコラボの件数も増やしていく方針。ファンの心を動かすマーケティング、広告、ソーシャルメディアもまだまだ活用する。
現在のゴンチャ公式X(旧Twitter)アカウントのフォロワーは約50万人、年内に100万人をめざしている。ニュースの発信にも注力する。期間限定商品を年6回から11回にアップし、ファンとコミュニケーションを取りつづける。
「今のゴンチャが大事にすべきは、スピードです。走りながら、微修正を繰り返す。最初から完璧をもとめすぎてはかえって大きな問題を生むと思っています」。
スピードを重視する角田さんによって、社内の体制もいっぺんした。全社員が年俸制に移行。賞与も設定された。ただし、業績に連動するタイプの賞与である。
「コロナ禍があけ、業績が上がったので」と笑う。
3年前とはクルーたちの表情もいっぺんしているのではないだろうか。
これが、経営者のちから。
「ブランドは外からだけではなく、中からもつくりあげていかなければなりません。だから、クルーもハピネスじゃないといけないのです」。
そういった角田さん。
今回も、「ゴンチャ」というブランドを再設定し、みごとに再構築している。言葉にすれば簡単だが、これはまちがいなく偉業だ
