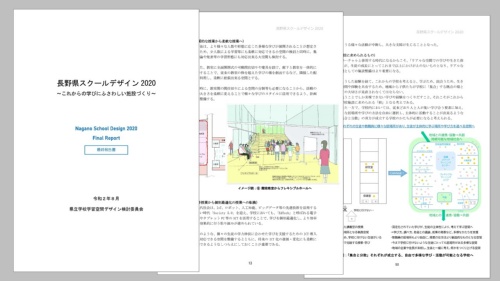建築設計者が基本計画から完成まで関わり続ける、長野県の学校改革
森山 敦子
日経クロステック
学校を建てる際、建築設計者を基本計画段階から完成まで携わる「パートナー」として、プロポーザルで選定する――。
長野県や長野県教育委員会は、
これまでにない学校改革に取り組んでいる。
「長野県スクールデザインプロジェクト(以下、NSDプロジェクト)」だ。
その第1弾として、
県教育委員会は2022年度に4つの学校の基本計画策定支援を行う
建築設計者を選定するプロポーザルを実施した。
どのようなプロセスで、どのような建築設計者を選んだのかをリポートする。
22年度プロポーザルの経緯を説明する前に、そのベースとなるNSDプロジェクトについて説明しておく。
県教育委員会は学校改革を進めるに当たり、県立学校の新しい学習環境整備を具体化するため、建築や財政、環境など多様な分野の専門家による「県立学校学習空間デザイン検討委員会(委員長:赤松佳珠子法政大学教授・シーラカンスアンドアソシエイツ代表)」を18年8月に設立した。
検討委員会は20年8月、
新しい学びに対応し、
効率的な整備・維持管理の指標とするための報告書「⻑野県スクールデザイン 2020」(以下、NSD)をまとめた。
この中で、
基本計画段階から
基本設計、
実施設計、
工事監理まで、
一貫して同じ建築設計者が関わり続けるという手法を定めた。
また、計画時に運用や維持管理まで検討し、
建築設計者の意図が施設運用に反映されるような工夫が必要だと記している。
赤松委員長は
「基本計画段階で建築設計者を選定することで、地域との関係づくりや丁寧なプログラムづくりができるようにしたいと考えた」と話す。
報告書の完成を踏まえて県教育委員会が22年6月に開催した
「長野県スクールデザインプロジェクトキックオフシンポジウム」で、
赤松委員長は県民など参加者らに向けて、新しい学校建築の在り方などを説明した。
「⻑野県スクールデザイン 2020」の一部(出所:長野県教育委員会)
[画像のクリックで拡大表示]
県教育委員会がNSDプロジェクトで建築設計者に求めているのは次のような項目だ。
NSDの理念に対する考え方や学びに対する理解と技術力、
未来の子どもたちが持つ可能性や地域に存在するポテンシャルに丁寧に向き合える力、
地域住民を含めた多様な関係者と調整しつつ解決に導く柔軟性などだ。
県立の学校として、NSDプロジェクトの対象となるのは高校や特別支援学校だ。
22年度に実施した4つのプロポーザルの審査委員は
建築関係者の他、
特別支援や教育、地域の専門家など、
各校の特色に合わせた構成とした。
4校共通の審査委員は
赤松委員長(建築)、
垣野義典・東京理科大学教授(建築・教育)、
高橋純・東京学芸大学教授(教育)、
寺内美紀子・信州大学教授(建築)、
西沢大良・芝浦工業大学教授・西沢大良建築設計事務所代表取締役(建築)の5人だ。
特別支援学校2校では
下山真衣・信州大学准教授(特別支援教育)、
高校再編2校では武者忠彦・信州大学教授(地域)が委員を務めた
建築設計者が基本計画から完成まで関わり続ける、長野県の学校改革 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)