英語で、
「イリタボー・ボーエル」(ま、超・神経質な過敏な腸の症状)
といって、
超・有名な、病名で、
アメリカの、いたるところの、”多くの街のクリニックの待合室”などに、
ブローシャ―(パンフレット、チラシ、小冊子などなど)が、
おいてあるほどの、病気/症状なのです。
2022年、いまだに、世界の誰も、解決しておりません。
そんな、厄介な病気で、、、
治療法も、原因もわからず、
世界、全ての医者も、試行錯誤で、
「これをトライ(飲んでみて)してみてください!」
ていう感じです。
Irritable Bowel Syndrome Treatment - IBS
過敏性腸症候群
アメリカでは、たいていは、
(今、ググってみましたが、
日本では、日本名/薬名も、ないし、薬も、販売していない感じで?????
わかりませんでした、ごめんなさい)
「ベラ・ドンナ」
や、
「ダナタル」
という、
プリスクリプション、を、処方します。
(こともあります、もちろん、医者や、患者により、全然、相違します)
(自分のお医者さんや、、専門医と相談してください)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
下は、単なる、Googleからの引用ですし、十二分に、
自分の専門医と相談してください。
抗コリン作用とは?抗コリン薬・コリン作動薬のすべて | 医者と学ぶ「心と体のサプリ」
1.抗コリン作用とは?
身体への抗コリン作用は、リラックスできない時の状態をイメージすると理解しやすいです。脳への抗コリン作用は、覚醒状態を邪魔してしまいます。
抗コリン作用とは、アセチルコリンの働きを抑えることによる作用です。アセチルコリンは、身体だけでなく脳でも働いています。しかもその働きは、身体と脳で異なります。身体と脳に分けてみていきましょう。
身体では、アセチルコリンは副交感神経を刺激する作用があります。アセチルコリンは神経と神経の橋渡しの働きをし、ムスカリン受容体に結合することで副交感神経が刺激されるのです。この結果、副交感神経に関わる様々な器官に影響を及ぼします。
抗コリン作用は、このムスカリン性アセチルコリン受容体を遮断し、副交感神経系の作用をブロックするのです。これにより、さまざまな全身への影響がでてくるのです。
副交感神経はリラックスさせる方向に働く自律神経ですので、抗コリン作用は「リラックスできない時はどういう状態なのか?」をイメージすると理解しやすいです。
リラックしている時に食べ物の消化はすすみます。このため、唾液が分泌され、胃腸は動き、尿や便は排泄されやすくなります。ですから抗コリン作用では、この反対のことがおこります。口がかわいたり、便秘になったり、尿が出にくくなるのです。
交感神経と副交感神経でバランスをとっている「目」も影響をうけます。抗コリン作用が働くと、瞳孔が開いて付け根にある毛様体の筋肉が緩みます。この部分は目の中をめぐっている房水という液体の出口なのですが、筋肉に押されて狭くなってしまいます。このため、うまく水が抜けなくなるので眼圧が高くなります。ですから抗コリン作用は、緑内障の方は注意が必要です。また、涙も出にくくなるのでかすみ目などになります。
脳では、アセチルコリンは記憶や注意、集中に関係していると考えられています。まだまだわかっていないことも多いのですが、脳の細胞活動を高める作用があります。このため抗コリン作用が働くと、脳の活動が落ちて眠気が認められます。注意力や集中力が落ちてしまいます。
また、長期的に抗コリン作用が続くと、認知機能に影響を及ぼすと考えられています。認知症の患者さんの脳では、アセチルコリン量が低下していることがわかっています。認知症の治療薬としても、脳のアセチルコリンを増やすお薬が使われているのです。
2.「抗コリン作用」による副作用
便秘・口渇・尿閉・眼圧上昇・目のかすみ・眠気・認知機能低下などが認められます。
本来は意図していないものの、薬が働いてしまって抗コリン作用をもたらすことがあります。これがデメリットとなると、副作用になります。抗コリン作用としては、便秘・口渇・尿閉・眼圧上昇・目のかすみ・眠気・認知機能低下(せん妄)などがあげられます。
抗うつ剤では、トリプタノールといった三環系抗うつ薬、新しい抗うつ薬の中ではパキシルでよくみられます。抗精神病薬では、第一世代抗精神病薬(定型抗精神病薬)のコントミンなどのフェノチアジン系と呼ばれる力価が低いもの(=mgが大きいもの)に多いです。第二世代抗精神病薬(非定型抗精神病薬)では、ジプレキサに認められます。
3.抗コリン薬
止痢薬・気管支吸入薬・頻尿改善薬・抗パーキンソン薬・多汗症治療薬として使われています。
抗コリン作用を利用した薬もたくさん開発されています。それぞれのターゲットに選択的に働くように工夫がされています。
- 止痢薬:胃腸の動きを抑える働きを意識して、下痢止めに用います。(ブスコパン)
- 気管支吸入薬:気管を拡張させる働きから、喘息やCOPDなどで用います。(アトロベント・スピリーバ)
- 頻尿改善薬:膀胱の平滑筋を緩めて尿をためることで、頻尿を改善します。(ベシケア・デトルシトール・バップフォー・ポラキス)
- 抗パーキンソン薬:アセチルコリンの過剰を改善し、ドパミン作用を強めます。(アキネトン・アーテン)
- 多汗症治療薬:汗の分泌を抑えます。(プロ-バンサイン)
4.コリン作動薬
排尿障害改善薬・緑内障治療薬・シェーグレン症候群治療薬・認知症治療薬として使われています。
コリン作用を利用した薬もたくさん開発されています。ターゲットに選択的に働くように工夫がされています。
アセチルコリンを増やすには2つの方法があります。
1つ目は、アセチルコリンの刺激自体を増やす方法です。アセチルコリンが作用するムスカリン受容体を刺激することで、コリン作用を強めることができます。
2つ目は、アセチルコリンの分解を邪魔する方法です。不要となったアセチルコリンを分解しているコリンエステラーゼの働きを邪魔します。これによってアセチルコリンが分解されずに残り、コリン作用が強まります。
後者のメリットは、アセチルコリンが分泌されているときにだけ働くという点があります。アセチルコリンが分泌されていなければ、分解を邪魔するも何もアセチルコリン自体がありません。
- 排尿障害改善薬:膀胱の収縮を促して、排尿を改善します。(①ベサコリン②ウブレチド)
- 緑内障治療薬:縮瞳させて隅角を広げ、房水の排出を促し眼圧を下げます。(①サンピロ②ウブレチド)
- シェーグレン症候群治療薬:唾液の分泌を促して口渇を改善します。(①サラジェン・サリグレン)
- 認知症治療薬:脳において不足しているアセチルコリンの分解を抑えます。(②アリセプト・レミニール・リバスタッチ・イクセロン)
※①:ムスカリン受容体刺激薬②:コリンエステラーゼ阻害薬
コリンを刺激するような副作用は、基本的にはありません。まれにコリン作動性クリーゼという状態がみられます。コリン作動薬を使用した時に、アセチルコリンが急激に増加してしまってバランスが崩れた状態です。
アセチルコリンが過剰な症状として、嘔吐、腹痛、下痢、発汗、徐脈、唾液分泌過多などがみられます。発展すると、呼吸困難から死に至ることもあります。
5.抗コリン作用による副作用への対応
原則的に、可能であれば薬の減薬や変更を検討します。薬によるメリットが大きくて減量や変更が難しい場合、副作用を抑えるための薬を用いることがあります。
5-1.便秘への対処
生活習慣を改善して上手くいかない場合、便秘の状況に応じて薬を使っていきます。
まずは生活習慣です。排便習慣・食事・運動の3つが重要です。朝にトイレに座る習慣を作っていただきます。そして朝食をちゃんととるようにしていただき、水分や食物繊維を摂取していただきます。また、少しずつ運動償還をつくっていきます。
それでも改善が見られない場合、薬を用います。薬には軟下剤と緩下剤の2種類があります。お通じが固い場合、水分を多くするような軟下剤からはじめます。
軟下剤としては、マグラックス・カマなどのマグネシウム製剤が中心です。緩下剤とは、腸を直接動かすような薬です。センノサイド・アローゼンなどを用います。また、便秘には漢方も有効です。大黄甘草湯などを用います。
5-2.口渇への対処
生活習慣から改善を図ることが中心です。糖尿病には注意が必要です。
薬の副作用としての抗コリン作用が、口の渇きの原因になることはよくあります。ですが糖尿病が隠れていて、その症状としての口の渇きであることもあり、注意が必要です。
口がかわくことに対する薬は、シェーグレン症候群という自己免疫疾患か、放射線治療後などでの後遺症など、何らかの原因で唾液腺が破壊されているときにしか用いることができません。漢方として白虎加人参湯などを用いることもありますが、効果は人によってまちまちです。
このため、生活習慣に頼ることになります。うがいや水分を多く摂取したり、唾液腺のマッサージをしたりすることなどが有効です。また、歯磨きも唾液分泌を促します。
5-3.排尿困難への対処
生活習慣では難しく、薬の調整で改善を図ることが多いです。
特に男性では前立腺がありますので、排尿困難が見られます。排尿困難に関しては、なかなか生活習慣などで改善できる余地が少なく、薬による対処を検討することが多いです。
原因となっている薬の変更が可能である場合、症状を起こしにくいような薬に切り替えをします。改善が難しい場合、コリン作用を強くして膀胱の収縮を促します。コリン作動薬としてベサコリン、コリンエステラーゼ阻害薬としてウブレチドが用いられます。
まとめ
身体への抗コリン作用は、リラックスできない時の状態をイメージすると理解しやすいです。脳への抗コリン作用は、覚醒状態を邪魔してしまいます。
抗コリン作用による副作用としては、便秘・口渇・尿閉・眼圧上昇・目のかすみ・眠気・認知機能低下などがあります。
- 抗コリン薬としては、止痢薬・気管支吸入薬・頻尿改善薬・抗パーキンソン薬・多汗症治療薬として使われています。
- コリン作動薬としては、排尿障害改善薬・緑内障治療薬・シェーグレン症候群治療薬・認知症治療薬として使われています。
抗コリン作用による副作用の症状ごとの対策をみてみましょう。
- 便秘への対処は、生活習慣を改善して上手くいかない場合、便秘の状況に応じて薬を使っていきます。
- 口渇への対処は、生活習慣から改善を図ることが中心です。糖尿病には注意が必要です。
- 排尿困難への対処は、生活習慣では難しく、薬の調整で改善を図ることが多いです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
やはり、”腸”に関係ということは、
「敵は、グルテンのようです!」(????)
下は、あるサイトからで、
この症状に、おすすめの、食べ物です。
Less FODMAP diet
Doctors recommend trying a special diet—the low FODMAP diet—to reduce or avoid certain foods that contain carbohydrates that are hard to digest. These carbohydrates are called FODMAPs which include:
Fruits
- Apples
- Apricots
- Blackberries
- Cherries
- Mango
- Nectarines
- Pears
- Plums
- Watermelon
- Juice containing any of these fruits
Vegetables
- Artichokes
- Asparagus
- Beans
- Cabbage
- Cauliflower
- Garlic And Garlic Salts
- Lentils
- Mushrooms
- Onions
Dairy Products
- Milk
- Milk Products
- Soft Cheeses
- Yogurt
- Custard
- Ice Cream
Others
- Rye and wheat products
- Honey
- Foods with high-fructose corn syrup products, like candy and gum, with sweeteners ending in "–ol," such as mannitol, sorbitol, xylitol, and maltitol
-----------------------------------------------------------------------------
過敏性腸症候群(IBS)ガイドQ&A過敏性腸症候群(IBS)についてお話しします。
過敏性腸症候群(IBS)ガイド|患者さんとご家族のためのガイド|日本消化器病学会ガイドライン
IBSはどうして起こるのですか?
腸(小腸や大腸)は食べ物を消化・吸収するだけでなく、不要なものを便として体の外に排泄してくれます。そのためには、食べ物を肛門方向に移動させるための腸の収縮運動と腸の変化を感じとる知覚機能が必要です。運動や知覚は脳と腸の間の情報交換により制御されています。ストレスによって不安状態になると、腸の収縮運動が激しくなり、また、痛みを感じやすい知覚過敏状態になります。この状態が強いことがIBSの特徴です。実際に、大腸に風船を入れて膨らませて刺激すると、健康な人は強く刺激しないと腹痛を感じないのに対し、IBSの患者さんでは弱い刺激で腹痛が起こってしまいます。
IBSになる原因はわかっていません。しかし、細菌やウイルスによる感染性腸炎にかかった場合、回復後にIBSになりやすいことが知られています。
感染によって腸に炎症が起き、腸の粘膜が弱くなるだけではなく、私たちの腸にいる腸内細菌の変化も加わり、運動と知覚機能が敏感になるためです。
近年はIBSでみられる腸や脳の機能異常を起こす物質を見つける研究、遺伝子の研究や機能的MRI検査などを用いた脳機能画像の研究が盛んです。原因が明らかにされる日が楽しみです。
=============================
10年以上苦しんだ過敏性腸症候群 完治のきっかけは「自分は不幸」をやめたこと
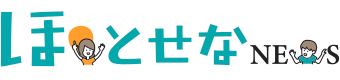
通常の検査では異常が見当たらないのに、慢性的な腹痛や下痢、便秘などの症状に悩まされる
過敏性腸症候群は誰にも相談できず、悩んでしまうことも多い病気。YouTuberのあんずさんも、この病気に10年以上悩まされたが、生き方を見つめ直し、病気を克服した。
過敏性腸症候群に苦しめられた子ども時代
過敏性腸症候群は、トイレへ行きづらい状況下で腹痛と便意を感じる「下痢型」、便意を伴うもなかなか排便できない「便秘型」、この2つの特徴を併せ持った「混合型」の3タイプに分けられ、中には腹部が張り、おならが出る「ガス型」の症状が現れる人もいる。 あんずさんは、下痢型。小学2年生の頃から学校で自由にできない、制限されているというストレスから腹痛を感じるようになり、小学4年生の時、病院へ。その時は菌の影響だと診断され、治療薬を貰ったが症状は改善せず、腹痛の頻度が増加した。 中学入学後、症状は悪化し、校内では席に座っていないといけない状況や集会の時間が苦痛に。そうしたストレスが引き金となり、パニック障害を発症。明るい性格であったからこそ、友達に病気を相談できなかった。 教室や体育館に集まる時は席を後ろにしてもらい、腹痛や動悸を感じたら、すぐ抜けられるようにしていたが、人からどう見られているかが気になった。 そうしたストレスもあってか、症状はさらに悪化。学校に行く前や通学中の電車内、休日の外出時や移動時にも腹痛に悩まされるようになった。 耐えきれず、中学3年生の終わりから不登校に。その後は高校に進学したが、あまり登校できず。この頃には、うつ病も発症していたという。 状況を変えようと投薬治療を開始し、ネットで効果があったと言われているサプリや健康法も試したが、腹痛を感じる頻度は週2~3日から、週4~7日へとさらに増加。 「遊びに行く時も、緊張したらどうしよう……と考えると腹痛。薬を飲んでも変わらず、症状が出たら、その場から一旦逃げる、耐える、休むなどしかできませんでした」 その後、とにかく手に職を……と考え、専門学校へ行くも体調は悪化し、休学。留年し、同じ学校で再スタートしたが、めまいや気持ち悪さに悩まされ、ベッドから立てない日を送ることとなった
「自分満たし」をするようになって病気が完治
もう、打つ手がない。生きていたくない。そう心が折れた時、YouTubeでたまたま目にしたのが、神社参拝の動画。もともと神社が好きだったあんずさんは動画を見て、今までなかった考え方や視点に触れられたと感じた。精神面からも、自分を見つめ直してみたい。そう思い、とあるYouTuberに電話相談。それが、生き方を変えるきっかけとなった。 「それまで私は自分を責め、制限をかけ、信じなかったり貶したりしていました。自分自身との信頼関係が全然なかったんです。でも、自分を幸せにしてあげたいと思った時、ストレスを与えていたのは私自身で、解放してあげられるのも自分だけだということに気づいた。だから、固定概念やポリシー、窮屈に思うことを捨てることにしました」 そして行ったのは、目標や信念を持たずに通っていた専門学校をやめること。顔に自信がない、周りの目が気になるなどの理由で諦めていた「YouTuberになる」という夢を叶えることだった。 「YouTubeは辛い時に自由な世界を見せてくれ、楽しい時間をもたらしてくれました。動画を見ることで幸せになる人がいると自分で証明されていたので、YouTuberに憧れていましたが、その選択肢はないものと考え、やりたいことが分からないと自分に嘘をつき続けていた。だから、SOSが病気という形で出たんだと思います」 そう気づいたあんずさんは、自分を責めることや不幸だと決めつけて生きること、持っていないものやできないことばかりに目を向けることもやめた。 「それまでの私は拗ね散らかし、不幸だと思っていました。だけど、自分を不幸だと決めつけたのは私自身でした。自分自身にしてあげられていないことを誰かに求めたり、周りが変わったりするのを待つのではなく、“自分で選ぶこと”を常に意識し、生きるようになりました」 あんずさんは自己肯定感を高めるため、自分優先の生活を心がけ、「今日できたことリスト」を毎日書き、声に出して読んで自分を褒めるなどの「自分満たし」をスタート。すると、体調はどんどん回復し、長い間悩まれ続けていた過敏性腸症候群も、なんと完治したのだ。 現在はパニック障害も回復に向かっており、電車や新幹線に乗れ、車の運転もできるようになった。 視野が広くなったあんずさんは、かつての自分と同じ悩みを抱える人に届くよう、YouTubeで過敏性腸症候群であったことを告白した。 「病気というサインが出てくれなかったら、ずっと自分を信頼できなかっただろうし、言い訳をして、やりたいことや夢も見えなくなっていたはず。だから、病気を経験したことは不幸ではない。もし、あの時の自分に会えるなら、違和感を覚えた時に自分を見張る方向や努力の方向性を、色んな角度・視点から再確認しようと伝えたいです」 あんずさんのように、生き方を変えるのは勇気も時間も必要となるため、決してたやすいことではない。だが、病気という形でSOSを訴える自分の心の声に耳を傾けることは、新しい治療のヒントを見つけるきっかけになるだろう。 「自分の人生は不幸前提の視点で見ると不幸に見えていたけれど、幸せ前提の視点で見ると幸せであった」 そう語るあんずさんは新たに見つけた、声優になるという夢に向かって邁進している。
古川諭香
10年以上苦しんだ過敏性腸症候群 完治のきっかけは「自分は不幸」をやめたこと(ほ・とせなNEWS) - Yahoo!ニュース
