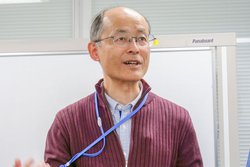日本が誇る「世界一のヴィデオ・プレイヤー」
パナソニックス―ー――「あっぱれ!!!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「すべてやり切った」。パナソニック渾身の最上位プレーヤー「UB9000(Japan Limited)」はこうして生まれた
インタビュー・構成:秋山 真『君の名は。』やスタジオジブリ作品など、高画質で名高い名作UHD BD/BDのエンコードを数多く手がけ、現在もパッケージソフトや配信の高画質化を手がける秋山 真氏。今回秋山氏は、12月7日に発売されるパナソニックのフラグシップUHD BDプレーヤー「DP-UB9000(Japan Limited)」(関連ニュース)の開発陣に、大阪・門真の開発拠点でインタビューを行った。

「DP-UB9000(Japan Limited)」¥OPEN(予想実売価格21万円前後)
筆者は画質評価の仕事にパナソニック以外のプレーヤー、レコーダーは使わない。これは5年半の間、パナソニックハリウッド研究所で日々、マスターデータとエンコードデータの比較をしてきた経験に基づく。BDプレーヤーは正しいデコードができることが大前提であり、それを抜きにした物量投入型の高級プレーヤーなどナンセンスだと考えているからだ。
しかし2K BD時代、その頼みの綱であるパナソニックからフラッグシッププレーヤーが登場することはついに無かった。もちろん、その代わりをBZT9000以降のプレミアムDIGAは立派に担ってきたわけだが、その間もフラグシッププレーヤーを待望するAVファンの声は大きかった。
そして2018年末、最後の映像パッケージメディアとも言われるUHD BD市場の成熟を受けて、いよいよ我々の悲願が成就する時が来た!
居ても立ってもいられなくなった筆者は、最終追い込みの真っ最中である大阪府門真市の開発拠点に突撃取材を敢行した。出迎えてくれたのは総勢9人のスタッフ。想定外の大人数に圧倒されたが、これでもUB9000開発チームの一部だという。早速その時のインタビューの模様をお届けしよう。彼らも長年、心に秘めてきた熱い思いを語りたくてうずうずしているのだから!
■欧州仕様と日本仕様ははじめから違う商品として企画・開発
村上氏(以下すべて敬称略) UB9000の話が持ち上がったのは、今から1年半ぐらい前です。日本での販売も予定していましたが、プレーヤーは台数的にも欧州市場が重要になってくるので、まずは1,000ユーロクラスのプレーヤーとして企画が始まりました。
岡崎 欧州でも本格的なプレーヤーが欲しいという声はありました。レコーダーの延長線上だったUB900はセンターメカでもありませんし、シャーシ周りも一般的なものです。その一方で、欧州市場ではあまりに高額なプレーヤーでは受け入れられにくいという事情もあります。
村上 しかし日本には既に「DMR-UBZ1」というハイエンドレコーダーがあるなかで、果たして「フラグシッププレーヤーが1,000ユーロクラスの製品で良いものか」という議論になりました。やるからにはUBZ1の価値を認めて頂いている方々にも、心から満足してもらえるようなプレーヤーを作るべきなのではないかと。その結果、欧州仕様と日本仕様は最初からグレードの違う製品として開発をスタートすることになったのです。
-- つまり、日本仕様が途中から枝分かれしたわけではないのですね?
村上 はい。共有できる部分があるとはいえ、開発チームには実質的に2機種のプレーヤーを設計してもらうことになり、大変な思いをさせてしまいました。
■アルミの無垢材で剛性を高めた筐体
-- センターメカの採用は、DVD時代の名機DVD-H2000以来ですよね?
濱野 そうですね。本格的なプレーヤーというからにはセンターメカの採用は譲れないと考えました。私はH1000やH2000のシャーシ設計も担当していたので、UB9000の内部写真を見ると、ところどころに共通点があるのがお分かり頂けると思います。高級プレーヤーとして、イチからシャーシを開発したのは約20年ぶりですね。だから20年間温めていたアイデアも今回投入しています。当時は回路規模が大きく、技術的に実現不可能だったのです。
-- この分厚いフロントパネルは、叩いても全く鳴かないですね。
濱野 フロントパネルは樹脂パネルとの組み合わせではなく、7mm厚のアルミの無垢材です。
神園 この価格帯だとサイドパネルは樹脂製になることが多いのですが、UB9000はサイドにも3mm厚のアルミ無垢材を使って、筐体の剛性を高めています。
宮本 このあたりはテクニクスの構造設計思想が入っています。開発当初から外装だけでなく回路設計についてもテクニクス部門との共同開発を進めており、「Tuned by Technics」はここから始まりました。
神園 ちょっとJapan Limitedの底板を持ってみて下さい。重いので気を付けて下さいね

「DP-UB9000(Japan Limited)」¥OPEN(予想実売価格21万円前後)
筆者は画質評価の仕事にパナソニック以外のプレーヤー、レコーダーは使わない。これは5年半の間、パナソニックハリウッド研究所で日々、マスターデータとエンコードデータの比較をしてきた経験に基づく。BDプレーヤーは正しいデコードができることが大前提であり、それを抜きにした物量投入型の高級プレーヤーなどナンセンスだと考えているからだ。
しかし2K BD時代、その頼みの綱であるパナソニックからフラッグシッププレーヤーが登場することはついに無かった。もちろん、その代わりをBZT9000以降のプレミアムDIGAは立派に担ってきたわけだが、その間もフラグシッププレーヤーを待望するAVファンの声は大きかった。
そして2018年末、最後の映像パッケージメディアとも言われるUHD BD市場の成熟を受けて、いよいよ我々の悲願が成就する時が来た!
居ても立ってもいられなくなった筆者は、最終追い込みの真っ最中である大阪府門真市の開発拠点に突撃取材を敢行した。出迎えてくれたのは総勢9人のスタッフ。想定外の大人数に圧倒されたが、これでもUB9000開発チームの一部だという。早速その時のインタビューの模様をお届けしよう。彼らも長年、心に秘めてきた熱い思いを語りたくてうずうずしているのだから!
■欧州仕様と日本仕様ははじめから違う商品として企画・開発
村上氏(以下すべて敬称略) UB9000の話が持ち上がったのは、今から1年半ぐらい前です。日本での販売も予定していましたが、プレーヤーは台数的にも欧州市場が重要になってくるので、まずは1,000ユーロクラスのプレーヤーとして企画が始まりました。
岡崎 欧州でも本格的なプレーヤーが欲しいという声はありました。レコーダーの延長線上だったUB900はセンターメカでもありませんし、シャーシ周りも一般的なものです。その一方で、欧州市場ではあまりに高額なプレーヤーでは受け入れられにくいという事情もあります。
村上 しかし日本には既に「DMR-UBZ1」というハイエンドレコーダーがあるなかで、果たして「フラグシッププレーヤーが1,000ユーロクラスの製品で良いものか」という議論になりました。やるからにはUBZ1の価値を認めて頂いている方々にも、心から満足してもらえるようなプレーヤーを作るべきなのではないかと。その結果、欧州仕様と日本仕様は最初からグレードの違う製品として開発をスタートすることになったのです。
-- つまり、日本仕様が途中から枝分かれしたわけではないのですね?
村上 はい。共有できる部分があるとはいえ、開発チームには実質的に2機種のプレーヤーを設計してもらうことになり、大変な思いをさせてしまいました。
■アルミの無垢材で剛性を高めた筐体
-- センターメカの採用は、DVD時代の名機DVD-H2000以来ですよね?
濱野 そうですね。本格的なプレーヤーというからにはセンターメカの採用は譲れないと考えました。私はH1000やH2000のシャーシ設計も担当していたので、UB9000の内部写真を見ると、ところどころに共通点があるのがお分かり頂けると思います。高級プレーヤーとして、イチからシャーシを開発したのは約20年ぶりですね。だから20年間温めていたアイデアも今回投入しています。当時は回路規模が大きく、技術的に実現不可能だったのです。
-- この分厚いフロントパネルは、叩いても全く鳴かないですね。
濱野 フロントパネルは樹脂パネルとの組み合わせではなく、7mm厚のアルミの無垢材です。
神園 この価格帯だとサイドパネルは樹脂製になることが多いのですが、UB9000はサイドにも3mm厚のアルミ無垢材を使って、筐体の剛性を高めています。
宮本 このあたりはテクニクスの構造設計思想が入っています。開発当初から外装だけでなく回路設計についてもテクニクス部門との共同開発を進めており、「Tuned by Technics」はここから始まりました。
神園 ちょっとJapan Limitedの底板を持ってみて下さい。重いので気を付けて下さいね
-- が、ガチで持ち上げるのがシンドイです……。
神園 欧州仕様はシャーシ部分と1.6mm厚の鋼板プレート1枚で構成されていますが、日本仕様はシャーシとプレート×3の4層構造です。底板だけで総重量5.6kgもあります(笑)。黒い塗装も家電製品では珍しい、カチオン電着という方法でやっています。
-- 高級なオーディオボードを下に敷いているようなものですね。
神園 インシュレーターはハイカーボン鋳鉄のTAOC製ですが、中央に貼ってある滑り止めのゴム素材も特殊です。これはUB9000に合わせて音質的に吟味したものになります。
神園 欧州仕様はシャーシ部分と1.6mm厚の鋼板プレート1枚で構成されていますが、日本仕様はシャーシとプレート×3の4層構造です。底板だけで総重量5.6kgもあります(笑)。黒い塗装も家電製品では珍しい、カチオン電着という方法でやっています。
-- 高級なオーディオボードを下に敷いているようなものですね。
神園 インシュレーターはハイカーボン鋳鉄のTAOC製ですが、中央に貼ってある滑り止めのゴム素材も特殊です。これはUB9000に合わせて音質的に吟味したものになります。
濱野 トップパネルも特徴的です。薄い1枚板では叩いた時にバンバン鳴いてしまって音質に悪影響を及ぼします。ところが天板を厚くし過ぎると、今度は詰まったような音になってしまうのです。そこでUB9000では強度と薄さを併せ持った2層構造を採用しました。このあたりの設計思想はDVD-H2000の頃と変わっていますね。
-- 見た目からは分かりづらいのですが、ドライブを支えるシャーシ部分だけでもメチャクチャ重いですよね。
神園 Japan Limitedでは3層仕様になっているのですが、欧州向けには上下の板金がありません。
濱野 梁の部分も、ただ単にフロントとリアに締結しているだけではダメなんです。下に横方向のベース部分がないと、ねじれに対する剛性が上がりません。
岡崎 こうした細かな積み重ねが最終的にはコストに大きく影響してきます。実は当初、日本仕様と欧州仕様の発売は同時で考えていました。しかしUBZ1の画質・音質を超えるべく各部門が試行錯誤を重ねた結果、発売が年末までずれ込んでしまったというわけです。というか、今も発売に向けて最終追い込みの真っ最中です(汗)。
-- BZT9000以降、プレミアムDIGAの画質が良すぎたが故に、製品ラインナップの上下関係においてもレコーダーとプレーヤーの間でねじれが発生していましたよね。それが今回のUB9000 Japan Limitedでようやく解消したと思います。個人的にも長年パナソニックのフラグシッププレーヤーの登場を待ちわびていたので、今はただただ胸熱です。
濱野&宮本 技術チームとしてもやりたいという思いがずっとありました!!
村上 レコーダーとして設計すると、特に音質面で、どうしても構造上の制約が出てしまいます。しかし当社の音響設計チームが最初から専用プレーヤーを作れば、他社製品には絶対負けないというプライドもありました。今回それがようやく証明できたと思います。
-- 小さなUSBパワーコンディショナーひとつとっても、驚くべき効果だったので、あの技術力がフルサイズ機で発揮されるとなると、なおさら凄いですよね。
■各種パーツの選定から電源回路の設計まで徹底的に追い込んだ音質
村上 今日はこれまでの試作機を全部お持ちしました。(台車には山積みの試作機が)
岡崎 これが最初の欧州向けの試作機です。アルマイト処理はしていませんが、この時点でもフロントとサイドパネルはアルミです。自分たちのやろうとしていることが、このサイズに全て収まるのか検証するのに使いました。ちゃんと画も音も出るんですよ。
ウデーニ そして、これが音質評価用の実験システムです。(巨大な建造物がドーン!)
-- うわッ、これは大規模ですね!
宮本 Japan Limitedの開発規模がどんどん大きくなってしまったので、途中から電源周りのスペシャリストであるウデーニにもチームに参加してもらいました。実は社内にはUB9000開発以前から、半ば趣味でやっているオーディオクラブというのがありまして、彼はそこのメンバーだったのです。UBZ1を改造してみたり、いわば “ハイエンドBDプレーヤーを作りたい会” といった感じのクラブ活動ですね(笑)。
ウデーニ これまではサウンドバーなどの開発に携わってきましたが、Japan Limitedの企画を聞いて燃えましたよ! そこで、この巨大な三階建ての評価用基板を使って、各種パーツの選定から電源回路の設計まで徹底的に追い込んでいったのです。
宮本 (ガサゴソと袋の中から何やら取り出して)これも掲載NGで申し訳ないんですけど、DACチップに関しても、このように各社のものを検討しました。最終的に採用したのは旭化成エレクトロニクス製のチップですが、最初からこれを使うことが決まっていたわけではありません。各社ともにそれぞれ良い部分がありましたが、旭化成の滑らかな階調表現力と細かいニュアンスの再現性が、我々の目指すサウンドに一番合っていると判断しました。
2ch用DACチップに現時点で最上位のAK4497を採用したことだったかもしれません。
甲野 私も開発中にこの実験システムを使って音を聴かせてもらったのですが、その時点でもかなり本格的な音が出ていて驚きました。でもこれ、最終的にちゃんと筐体の中に入るの? と(笑)
濱野 構造上は、できるだけコンパクトにまとめた方がシグナルパスの距離が短くなって、理論的に有利というのがあります。
ウデーニ 実は、最初に筐体内に詰め込んだ際には、躍動感やスケール感のある音になりませんでした。
濱野 構造上は、できるだけコンパクトにまとめた方がシグナルパスの距離が短くなって、理論的に有利というのがあります。
ウデーニ 実は、最初に筐体内に詰め込んだ際には、躍動感やスケール感のある音になりませんでした。
映像回路やドライブ周りからのノイズの影響を受けていたんですね。
これではせっかくのAK4497がポテンシャルを発揮できません。
そこでまずは躍動感を得るため、2ch DACチップ用のDC電源系統を細分化しました。しかもただ増やすだけではなく、より重要な箇所には産業用や車載用で使われている
そこでまずは躍動感を得るため、2ch DACチップ用のDC電源系統を細分化しました。しかもただ増やすだけではなく、より重要な箇所には産業用や車載用で使われている
アナログ・デバイセズ社(旧リニアテクノロジー社)製のレギュレーターを5つも採用しています。低ノイズ設計のもので、民生機ではほとんど採用例がない
と思います。
宮本 また電源基板に関してもUBZ1から大幅に強化されていて、基板上の面積だけ見ても規模がまるで違うのがお分かり頂けると思います。
例えば電源トランスにしても、従来は1つのスイッチングトランスで全ての電源を賄っていましたが、ドライブ回路などは変動が大きく、それがD/A変換後のアナログ段に悪影響を及ぼしていました。そこでUB9000では、アナログオーディオ専用にもう1つトランスを搭載しています。そのトランス自体も日本仕様はOFC巻線の特注品になっています。
ウデーニ 実はこのOFC巻線トランスも、当初はクラブ活動の中で実験的に作ってもらったものです。しかし一度聴いてしまったら元には戻れませんでした。通常より電圧も巻線径も上がっており、音のパワー感、情報量、レンジ感が素晴らしかったのです。そこで一次電源の担当者に頼み込んで実現してもらいました。
-- 基板の表面が黒いというのも、単純に見ているだけでカッコイイですよね。
宮本 見た目だけでなく、音質にも効いています。黒くした方が音に落ち着きが出ます。本当に、何を変えても音は変わるんですよね。
ウデーニ 日本仕様は電源基板の裏側も特徴的です。太く曲線状にハンダが盛られているのが分かると思いますが、これも基板の強度を上げ、インピーダンスを下げるため、敢えてこうしています。
-- 壮観です。
ウデーニ またノイズをいかに効果的にグラウンドに逃がすか、というのも非常に重要になってきます。DACチップ周りに関しては旭化成エレクトロニクスさんとも協力しながら、切ったり貼ったり、何度もパターンも引き直しました。さらにHDMI端子周りのグラウンド処理も従来とはだいぶ変わっています。これらの効果は、音質だけではなく画質にも現れていると思います。
■UBZ1から見較べると、驚くほどの画質
-- 今回、クロマアップサンプリングなどの画質の基礎となる部分は、UBZ1からアップデートされていないですよね? にも関わらず、ストレートデコードの画で両者を見較べてみると、驚くほどの差があります。
甲野 そうですね。MPEGデコードに関する信号処理は変わっていません。クロマアップサンプリング技術に関しては既に完成の域にあると考えています。しかし、これだけ画質に違いが出たのは、やはり高音質化のために数々の対策を施した結果だと思っています。
もちろん、以前からこうした電源や筐体の違いが画質に影響を与えるのは認識していましたが、私の担当はあくまで映像信号処理であり、それ以外の分野に関しては、敢えてあまり発言してきませんでした。しかし今回のUB9000 Japan Limitedでは、商品コンセプトやユーザー層も考慮して、私からもこの違いを積極的に訴求していきたいと考えています。
-- いっぽうで、今年2月にUB9000が発表された際、映像面での一番のサプライズはドルビービジョン対応だったかもしれません。
甲野 ユーザーからの要望があるのならば、どんなフォーマットでも対応しようというのが我々の基本姿勢です。実はドルビービジョンに関しては、ディスクがドルビービジョンタイトルと認識され、接続されたテレビがドルビービジョンに対応していれば、チップ内の信号処理経路はドルビーさんから提供された回路へ切り替わります。そこでのデコード結果がHDMIからそのまま出力されます。
つまり我々としては、クロマアップサンプリングも含めて一切信号には手を加えていません。これはドルビービジョンの仕様として決まっていることなのです。
-- しかしUB9000にはドルビービジョンを「切」にできるという、マニア注目の機能がありますね。
甲野 はい。「切」にすることで、ドルビービジョンディスクのベースレイヤー部分に収録されているHDR10ストリームを、通常のHDR10タイトルと同じように、我々の信号処理を使って再生することができます。
-- つまりUB9000をドルビービジョン対応テレビに接続した場合、「入」の状態ではドルビーの独自回路による映像信号が出力され、「切」にするとクロマアップサンプリングも含めた、UB9000ならではの高品位なMPEGデコードが可能になるということですね?
甲野 そういうことです。
-- ドルビービジョン対応のテレビで実際に比較させてもらいましたが、ドルビービジョン再生と「切」によるHDR10再生では、両者はまるで別物に見えます。ドルビービジョンは色乗りがかなり派手ですね。少なくとも私の眼には、HDR10の方が明らかにフラットな画質です。これを12bitと10bitの差、そしてダイナミックメタデータの有無だけで説明するのは難しいですね…。
甲野 ドルビービジョン再生に関しては、テレビ側も含めてドルビーさんが画作りをされていると思います。
-- もちろん意図したものなのでしょうけど、個人的には以前からドルビービジョンの画作りは派手だなという印象があったので、いろいろと合点がいく結果でした。とはいえ、対応しているのと非対応なのとでは、プレーヤーとしての価値は雲泥の差になると思います。ドルビービジョンとHDR10+に両対応という英断に感謝したいです。
甲野 我々としては、ディスクとテレビがドルビービジョンに対応していれば、ドルビービジョン「入」で見て頂くのが基本と考えています。もちろんHDR10+の場合も同様です。ただ、どのように見るかは最終的にはユーザーが決めるべきですし、特にUB9000はリファレンスとなるモデルとして、どのような見方もできるようにしておきたかったので「切」の機能も入れています。
-- そしてドルビービジョンとHDR10+の両対応よりもさらに凄いのが、ここまでやるかというくらいに練りに練られたトーンマップ処理の数々ですね。
甲野 UBZ1発売以来3年間で、UHD BDのHDR再生における問題点がいろいろと浮かび上がってきました。1つはタイトル毎にピーク輝度にかなりバラツキがあることです。なかには実際に計測してみるとHDR10のメタデータと実際の輝度が合っていないタイトルもありました。
そこで信野と二人で、巷のUHD BDを片っ端から検証してみることにしたんです。信野がメタデータの解析、私が実際の輝度の計測を担当しました。
信野 “朝活” と呼んでいましたね(笑)。毎朝出社すると1本調べるみたいな。
甲野 信野は元々デジタル周りのハードウェア設計者です。ところが以前から映像のことについて、ちょくちょく私のところに訊きに来ていたんですよ。私も長年、画質担当の仕事をしていますが、そろそろ後継者を育てなくてはいけない年齢になりました。
でも秋山さんもよく仰ってますけど、こういう仕事ってキリが無い世界じゃないですか。本人に「やりたい」という意思がないと絶対に無理なんですよね。だから、彼ならやれるのではないかと思ったんです。「そんなに画質に興味があるならやってみないか?」と声をかけたのが一昨年くらいでした。
-- 実際にやってみてどうですか?
信野 沼でしたね(笑)。
甲野 でも彼は趣味でカメラもやっていて、いくつもレンズを買ったりして沼には慣れっこなんですよ(笑)。
-- ここには電源沼の人もいるし、素晴らしいですね(笑)。
ウデーニ (笑)。
甲野 そんなわけで、これも掲載NGで申し訳ないのですが、国内で発売されているほとんどのUHD BDを検証した結果を相関図にしてみました。
-- これは大変貴重なデータですよ!
甲野 でも、信野が作っているデータベースはもっと凄いんですよ。タイトルに関するありとあらゆる情報が記載されていて、メタデータはその一部に過ぎません。
信野 AV雑誌での採点表やコメントまで全部記載しています。
-- いやはや、素晴らしい後継者ができましたね、甲野さん!
甲野 その相関図を元に、今度は各社のHDR対応テレビが、メタデータに対してどのような振る舞いをしているのかを検証していきました。するとこちらも、随分とバラツキがあることが分かったのです。
-- プロジェクターも同様の問題を抱えていますよね。
甲野 UB9000では、自動トーンマップ処理に徹底的にこだわっています。組み合わせるテレビやプロジェクターの最高輝度に最も近い数値(目標輝度)を指定することで、SDR領域の中低輝度部分には影響の出ない、滑らかなカーブを描くように設計しています。その際に高輝度部分の色味が変わらないようにR/G/Bで連携処理しているのも特徴です。
これらの処理をきちんと行うためには、計算上27bitの精度が必要になるのですが、ユーザーがダイナミックレンジ調整やシステムガンマ調整をすることまで考慮して、結果的にUB9000の新画質エンジンではR/G/B各最大32bit処理という高精度演算を行っています。ところが、ここで1つ問題になることがあります。
甲野 ドルビービジョン再生に関しては、テレビ側も含めてドルビーさんが画作りをされていると思います。
-- もちろん意図したものなのでしょうけど、個人的には以前からドルビービジョンの画作りは派手だなという印象があったので、いろいろと合点がいく結果でした。とはいえ、対応しているのと非対応なのとでは、プレーヤーとしての価値は雲泥の差になると思います。ドルビービジョンとHDR10+に両対応という英断に感謝したいです。
甲野 我々としては、ディスクとテレビがドルビービジョンに対応していれば、ドルビービジョン「入」で見て頂くのが基本と考えています。もちろんHDR10+の場合も同様です。ただ、どのように見るかは最終的にはユーザーが決めるべきですし、特にUB9000はリファレンスとなるモデルとして、どのような見方もできるようにしておきたかったので「切」の機能も入れています。
-- そしてドルビービジョンとHDR10+の両対応よりもさらに凄いのが、ここまでやるかというくらいに練りに練られたトーンマップ処理の数々ですね。
甲野 UBZ1発売以来3年間で、UHD BDのHDR再生における問題点がいろいろと浮かび上がってきました。1つはタイトル毎にピーク輝度にかなりバラツキがあることです。なかには実際に計測してみるとHDR10のメタデータと実際の輝度が合っていないタイトルもありました。
そこで信野と二人で、巷のUHD BDを片っ端から検証してみることにしたんです。信野がメタデータの解析、私が実際の輝度の計測を担当しました。
信野 “朝活” と呼んでいましたね(笑)。毎朝出社すると1本調べるみたいな。
甲野 信野は元々デジタル周りのハードウェア設計者です。ところが以前から映像のことについて、ちょくちょく私のところに訊きに来ていたんですよ。私も長年、画質担当の仕事をしていますが、そろそろ後継者を育てなくてはいけない年齢になりました。
でも秋山さんもよく仰ってますけど、こういう仕事ってキリが無い世界じゃないですか。本人に「やりたい」という意思がないと絶対に無理なんですよね。だから、彼ならやれるのではないかと思ったんです。「そんなに画質に興味があるならやってみないか?」と声をかけたのが一昨年くらいでした。
-- 実際にやってみてどうですか?
信野 沼でしたね(笑)。
甲野 でも彼は趣味でカメラもやっていて、いくつもレンズを買ったりして沼には慣れっこなんですよ(笑)。
-- ここには電源沼の人もいるし、素晴らしいですね(笑)。
ウデーニ (笑)。
甲野 そんなわけで、これも掲載NGで申し訳ないのですが、国内で発売されているほとんどのUHD BDを検証した結果を相関図にしてみました。
-- これは大変貴重なデータですよ!
甲野 でも、信野が作っているデータベースはもっと凄いんですよ。タイトルに関するありとあらゆる情報が記載されていて、メタデータはその一部に過ぎません。
信野 AV雑誌での採点表やコメントまで全部記載しています。
-- いやはや、素晴らしい後継者ができましたね、甲野さん!
甲野 その相関図を元に、今度は各社のHDR対応テレビが、メタデータに対してどのような振る舞いをしているのかを検証していきました。するとこちらも、随分とバラツキがあることが分かったのです。
-- プロジェクターも同様の問題を抱えていますよね。
甲野 UB9000では、自動トーンマップ処理に徹底的にこだわっています。組み合わせるテレビやプロジェクターの最高輝度に最も近い数値(目標輝度)を指定することで、SDR領域の中低輝度部分には影響の出ない、滑らかなカーブを描くように設計しています。その際に高輝度部分の色味が変わらないようにR/G/Bで連携処理しているのも特徴です。
これらの処理をきちんと行うためには、計算上27bitの精度が必要になるのですが、ユーザーがダイナミックレンジ調整やシステムガンマ調整をすることまで考慮して、結果的にUB9000の新画質エンジンではR/G/B各最大32bit処理という高精度演算を行っています。ところが、ここで1つ問題になることがあります。
-- トーンマップの二重掛けですね?
甲野 そうです。テレビやプロジェクター側でもHDR10のメタデータに基づき、大なり小なり何かしらのトーンマップ処理をしていることが多いので、二重掛けによっておかしな画になってしまう可能性があるのです。しかも先ほどお話ししたように、受像機側のトーンマップ処理の方法は各社バラバラです。そこで考え出したのが、目標輝度に合わせてメタデータを書き換えてしまおうというアイデアでした。
-- なるほど、その手がありましたか!
甲野 例えばピーク輝度が1,000nitの有機ELテレビの場合、メタデータが示す輝度ピークが1,000nitであれば、基本的には1,000nitまでの範囲をリニアな明るさで表示しようとするはずです。なので、仮にUHD BDに収録されたメタデータのピーク輝度が4,000nitであっても、UB9000側の高精度演算で1,000nit上限にトーンマップして、さらにメタデータも同じく1,000nitと書き換えてあげれば、トーンマップの二重掛けが防げると考えたのです。
信野 しかし理論上は問題なくても、これまでに前例の無い方法ですので、各社のテレビを集めて慎重に動作検証を行いました。数が多すぎて、研究室の中にテレビをドミノ状に並べて作業していましたね(笑)。
甲野 ちなみにドルビービジョンとHDR10+では、トーンマップ処理は働きません。規格の主旨からしても対応テレビ側で行うことになります。とにかくトーンマップ処理に関しては、現時点で考えつくことは全てやった感じです。その分、ソフトウェア部門にはエライ苦労をかけました。
松井 いろいろな新機能を実装するのも大変ですが、それが商品になった際、ユーザーがどのような使い方をしても、正しく動作させることが何より大切です。
信野 しかし理論上は問題なくても、これまでに前例の無い方法ですので、各社のテレビを集めて慎重に動作検証を行いました。数が多すぎて、研究室の中にテレビをドミノ状に並べて作業していましたね(笑)。
甲野 ちなみにドルビービジョンとHDR10+では、トーンマップ処理は働きません。規格の主旨からしても対応テレビ側で行うことになります。とにかくトーンマップ処理に関しては、現時点で考えつくことは全てやった感じです。その分、ソフトウェア部門にはエライ苦労をかけました。
松井 いろいろな新機能を実装するのも大変ですが、それが商品になった際、ユーザーがどのような使い方をしても、正しく動作させることが何より大切です。
-- ダイナミックレンジ調整やシステムガンマ調整も、裏では非常に高度な演算処理をしているのに、メニューUI上では直感的でユーザーライクに実装されているのが素晴らしいと思いました。
甲野 ハードウェア部門は今日みたいに “夏休みの自由研究” 的なものをお見せしながら苦労話が出来ますが、ソフトウェア部門はその努力や成果をこういう場でお伝えしにくいんですよ。
松井 甲野からの膨大なリクエストに応えるために、膨大な時間をかけてプログラミングしました。でも、ハードと違って見せられるものが何もないんです(笑)。
一同 (笑)
甲野 我々が目指している次元の “高画質” というものは、ハードウェアを組み合わせただけでは到底実現できません。ハードウェアをどううまく使いこなすか、どういうアルゴリズムで動かすか、そこに重要なノウハウがあります。我々の画質はハードウェアとソフトウェアの両輪で成り立っており、それらがうまく噛み合うことによって初めて、これほどまでの映像表現が可能となるのです。
■4K時代の決定版ともいえる製品がUB9000 Japan Limitedという形で結実
-- 画質、音質が素晴らしいのはもちろんですが、私はUB9000の無駄を廃したデザインにも非常に惹かれています。これ見よがしな重厚長大さではなく、澄ました顔して凄いことをやっている感じがたまりません。なんというか “プロ機っぽさ” を感じるんですよね。
甲野 なるほど、プロ機っぽさですか。機能面でもそういった部分がありますし、確かにそうかもしれません。
-- 内部が電源、アナログ、デジタル、ドライブの4ブロック独立構成で、それぞれが隙間なく理路整然とレイアウトされているので、余計にそう感じます。
神園 そのあたりはかなり意識して綿密に設計していますね。
宮本 ケーブルによるワイヤリングがほとんど無いのも、量産品として品質管理をする上では非常に重要でした。ケーブルを使うと製造時の微妙な這わせ方の違いで、音にバラツキが生じてしまうのです。
神園 ネジも100本以上使っていますが、宮本と相談しながらトルク管理まで徹底しています。
ウデーニ 各ブロックをパズルのようにジョイントするためのパーツも、金メッキ処理された高品位なものです。特にドライブのシャーシ部分を貫通して、アナログオーディオボードと繋がるブリッジの部分は、丁度良い高さのパーツをあちこち探し回ってようやく見つけました。これがなければ今の姿にはならなかったかもしれません。おかげで外装担当の濱野とは何度も喧嘩しましたけど(笑)。
濱野 (笑)。組み立て時にコネクタ部分にストレスがかかると、結局それが音にも影響してしまいますからね。
宮本 DIGAでの経験もあって、狭いところにモノを詰め込む技術には、我々は非常に長けていると自負しています。
甲野 これまでも定期的にDIGAでプレミアムモデル的なものは作ってきましたが、システムの基本部分はレギュラーモデルと共通設計の部分も多かったので、プレミアムとしてこだわる部分の開発はもっと少人数でやっていたと思います。ところが今回はたくさんの人が寄ってたかって「良いものを作るぞ!」と突っ走り、そのまま走り抜いた感じがありますね。
こんなことは初めてです。やはり、この先の8Kの時代を前に、UHD BDを使った4K時代の決定版ともいえる製品を作っておかねばという意識が、社内で共有されていたのだと思います。それがUB9000 Japan Limitedという形で結実しました。
濱野 次にやるのは、また20年後くらいになるかも(笑)、というのは冗談ですが、全員がそれくらいの強い思いで取り組み、最後までやり遂げることができました。その分、開発リーダーの岡崎には迷惑もかけましたが(苦笑)。
岡崎 ホント、皆がこだわればこだわるほど、何度も何度もスケジュールを組み直しましたよ(遠い目)。でもこれでようやくパナソニックのフラグシップUHD BDプレーヤーを皆様にお届けできます。
-- 我が家も頑丈なラックを用意しました。受け入れ準備は万端です!
一同 (笑)
甲野 日進月歩のAV機器の世界で、長く使ってもらえる趣味性の高いプレーヤーに仕上がったと思います。皆様、本当にお待たせ致しました!
口々に「やり切った」と話す開発メンバーたち。UB9000 Japan Limitedの高S/Nな画質や音質にも負けない、晴れやかな笑顔が印象的だった。詳細な画質・音質レビューは近日中にお届けする予定なので、乞うご期待!
秋山 真
20世紀最後の年にCDマスタリングのエンジニアとしてキャリアをスタートしたはずが、21世紀最初の年にはDVDエンコードのエンジニアになっていた、運命の荒波に揉まれ続ける画質と音質の求道者。2007年、世界一のBDを作りたいと渡米を決意しPHLに参加。ハリウッド大作からジブリ作品に至るまで、名だたるハイクオリティ盤を数多く手がけた。帰国後はアドバイザーとしてパッケージメディア、配信メディアの製作に関わる一方、オーディオビジュアルに関する豊富な知識と経験を生かし、2013年より「AV REVIEW」誌でコラムを連載中。リスとファットバーガーをこよなく愛する41歳。