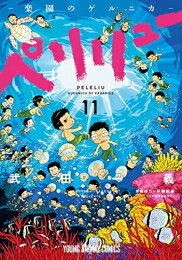こんばんは。図書室の先生です。
約2年前に漫画で読み、感銘を受けた『ペリリュー 楽園のゲルニカ』が映画化されたので、早速見に行ってきました。
↓これは原作の漫画です。
田丸と吉敷のストーリーを中心に、美しい南の島を舞台に描かれる戦争は、3等身の可愛らしいキャラクターからは想像できないほど、シビアで残酷なものでした。
特に辛かったのは、終戦を知らずにジャングルに潜伏する日本兵が仲間割れし、味方同士で殺し合いになってしまったシーンです。
実は、『ペリリュー 楽園のゲルニカ』が映画化されるときいてから、自分の祖父の兵隊さん時代のことを調べ始めました。
まず手始めに、祖父が生まれ育った土地の人が多くいた師団や連隊について調べ始めました。
自治体単位の『◯◯市史』みたいな資料を当たったところ、大きな括りでしか記録がなかったりして、南方に行った師団は「玉砕した」と書かれているものもあったりしました。
それは、私が幼い頃祖父からきいた話の様子とはかなりかけ離れていて、にわかに信じがたいものでした。
そんなこんなで大きな図書館でレファレンスサービスを使ってみたところ、自治体の記録以外にも、戦争についての手記のようなものに、意外と詳細なことが書いてあることがあると教えていただきました。
その頃、図書館で軍歴証明書の取り方についての本も見つけていました。
↓この本です。
軍歴証明書を取得したことで、祖父が現役兵を任期満了したあと田舎に戻り、再び赤紙で召集されたことが分かりました。
そこには、祖父がいた島の名前や、病気をしたことや怪我をしたこと、終戦後、その島から移動させられて、翌年の3月に復員したことなどが書かれていました。
軍歴証明書をもとに、祖父のいた島の名前でインターネット検索をしたり、都道府県で作成した戦争についての手記などをあたるうち、そこそこ詳しいことを知ることができました。
ペリリュー島とは違い、
祖父がいた島では、終戦時、司令部が残っていたことが幸いしたようでした。「今日は、飛行機が少ないな」と不思議に思っていたら上官に呼び出され、終戦を知った、そう書いてある手記を見つけたのです。
映画に描かれていた満天の星空、サンゴ礁の美しい海、椰子の葉陰、そして頭上を飛び回る敵の飛行機、空腹、喉の渇き。
これと同じような景色を、きっと祖父も見ていたに違いありません。
敵の飛行機のエンジン音や爆撃の音など、私は映画であることがわかっていても、とても恐ろしく感じました。
そして、「生きて虜囚の辱めを受けず」のような教育が、さらなる悲劇を招いたことは、決して許されることではないと感じます。
今年は戦後80年にあたる年です。
たくさん人が死に、暴力的なシーンも出て来るのでPG−12指定になっている映画ですが、
この映画をお子さんと一緒にみてほしい、そう思います。
田丸も吉敷も、戦争がなかったら、漫画家を目指す食堂の息子と、農家の跡取り息子でいられたのですから。