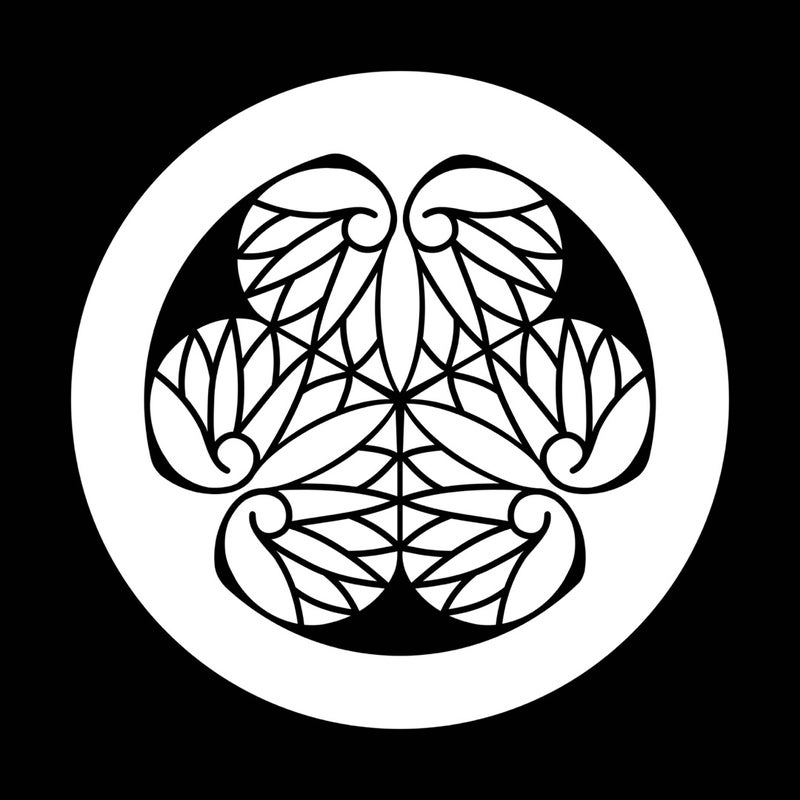清水家はご案内のように八代将軍徳川吉宗が嫡流の9代将軍徳川家重以降、世継ぎが無い場合の養子を迎える家柄として建てた家。一橋、田安、清水家を御三卿とした。彼らは9代将軍徳川家重の兄弟ですから重い位置にあったんですねー。
家格は10万石程度なので立派な大名格です。
但し所領はあったようですが御三家のように城持ち大名ではありません。つまり所詮は将軍家の “部屋住み” に過ぎません。
将軍の世継ぎのない場合のスーパーサブです。
とはいえ所詮控えは控え。出番がなければそれまでですね。
では、御三家はというと、時代が遡って徳川黎明期の時代。神君家康公の九男義直、十男頼宣、十一男頼房がそれぞれ尾張、紀州、水戸家の藩祖となる。
(画像は尾州徳川家の葵紋。各家微妙に異なる)
有名な水戸光圀公は第二代水戸藩主。十一男頼房の子であるから家康様の孫になる。つまり三代将軍家光とは従兄弟になり「光」の字は元服時に家光が将軍であったために頂いたもの(ちなみに同じく二代目尾張藩主の名は光友、紀伊は光貞)。
家康様の孫であるから、そりゃあ、幕閣たちも気い使うわ。当然、大事な事の決定は御三家に相談という流れになる。
さて、落語『紀州』では、七代将軍家継が早世し直系が絶えると親戚筋から選ぶことになった。この時、御三家で最も年齢が高かったのが三代水戸藩主綱條。高齢を理由に綱條は将軍継承を辞退。しかし長幼の列を重んじた当時は綱條の意見力は大きい。
それが一部の噺家さんが『紀州』で水戸家を御三家筆頭と誤って言ってしまっている原因だと私は思っている。しかし事実は尾張家が筆頭である。だからこそ次期将軍第一候補だったのだ。
蛇足だが、綱條公が紀州を推したとすればお互いの藩祖の御母堂が同じお万の方であったことが理由であろうか。実際、紀州家と水戸家は仲は良かったらしい。
このように徳川黎明期から18世紀前半頃までは意見力が強かった。但し、時代が下るにしたがって宗家とは血の繋がりが薄れていくわけです。その時その時の将軍に近い縁戚が立場は強い。
ですから紀州家から入った吉宗以降は紀州家の系統が将軍職を継ぐことになった。ちなみに最後の将軍慶喜が水戸から一橋家に入ったのも将軍になるための正統性を得るためと言えます。
では、御三家と、御三卿どっちが偉い?
そんな疑問に答えるならば、仮に将軍抜きにして一対一で戦えばもちろん国持ち大名である御三家の方がが圧倒的に強いでしょう(最も紀伊家は御三卿の元であるから事を構えるようなことはないでしょうが 笑)。尾張62万石は大納言ですし、石高が一番低い中納言水戸家でさえ35万石です。
御三卿は将軍家の部屋住みですから将軍家あって初めて存在理由がある。単独では何も出来ない。繰り返しになりますが、あくまでも将軍家のスーパーサブだったのです。