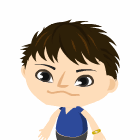先日投稿しましたが、税金を正しく計算出来るシートを作成しました。
このシートでは、ふるさと納税の上限額も計算出来るようになりました。
総務省ホームページでの上限目安
| ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
| 325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
| 425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
| 450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
| 475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
| 500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
| 525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
| 550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
| 575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
| 625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
| 650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
| 675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
| 725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
| 750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
| 775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
| 800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
...
となっています。例として、600万円で独身または共働きの例を見ると77000円となっています。
上の表の上限額計算
そもそも、ふるさと納税の控除は3つの部分に分けられます。
- 所得からの控除:ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
- 住民税からの控除(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×10%
- 住民税からの控除(特例分):(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
上限に当たる条件は3つあります。
- 所得からの控除: 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
- 住民税からの控除(基本分):控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
- 住民税からの控除(特例分):住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。
この中で一番キーになるのが、「住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。」です。
年収600万の場合の課税総所得金額を計算してみましょう。
課税総所得金額=給与収入 - 給与所得控除 - 社会保険料控除 - 基礎控除 - (その他控除もろもろ)
となるので、
6,000,000 - 1,640,000 - 861,000 - 430,000 - (今回はその他の控除を考えない)
住民税を計算する際の課税総所得金額は、 3,069,000円となります。
そして、住民税所得割額を計算します。
住民税所得割額=課税所得金額 x 税率 - 税額控除額 3,069,000円 x 10% - 2500(いろいろ控除がある人はここを変更しないといけない) = 304,300円となります。
そして遂に、「住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。」
を考えることができます。
「特例分が60,860円(304,300円の2割)を超えないようにする」
特例分は、「住民税の80%」だったので、「(ふるさと納税額 - 2,000円)x80%が60,860円(304,300円の2割)を超えないようにする」と読み替えることができて、
(ふるさと納税額 - 2,000円)x80% ≦ 60,860円
これを解くとふるさと納税の上限額は78,075円となります。
表の77000円とことなるのは、社会保険料の額は異なるためともう一つは、やや少なめに表には記載されてあるはずです。
実は、この上限計算をするために、寄付金控除を0として計算しているので、実際にふるさと納税をするとふるさと納税分の控除額寄付金控除として控除されることとなるため、所得税、住民税が少し少なくなります。
そうすると、この上限の計算で使っていた住民税所得割額も若干減ります。つまり、ふるさと納税上限額も実際は78,075円よりも下がるということです。
計算が複雑になっている点には、両辺に「ふるさと納税額」入っている不等式を解く必要があるためです。
義務教育で習った算数や数学はこういうものを正しく理解するためにあるんですね。
単純化すれば一次不等式の解を求めるだけなので、小学生か中学生でも出来るはずではありますが、正しい解を出せる大人は少なそうですね。