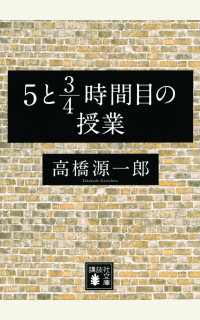明治学院大学で「言語表現学」の教授を務める小説家の高橋源一郎先生が、
自身お子さま、末っ子ふたりの通う「学校法人 きのくに子どもの村学園」のひとつである「きのくに国際高等専修学校」で、二日間にわたっておこなわれた特別授業の内容を書籍化しています。
Audible版もあり、私は活字で読む方が早く読了しました。Audible版であれば会場の雰囲気や話の「間」も感じられ、お好みでどちらを利用してもよさげ。
一日目の講義、「たぶん、読んじゃいなよ!」
教材は自前のプリントを配って行われます。読み方に正しさはないはずが、実際の公立授業では「正解」を問われます。では、その「正解」とは何か?を問うておられます。
二日目の講義は、「なんとなく、書いちゃいなよ!」
私のお勧めはこちらの内容。大学でも実践する方式で、子供たちに前日から宿題を出していました。この方法で4月から授業を受けた大学生たちは、翌年3月の授業までに必ず全員の文章力があがるそうです。
その話の中では、小説家としての経験談もあり、
私が高校時代に、初めて書いた小説を友達が読んでくれたときに感じた気持ちも、書いてありました。
こうしたネット経由のブログでは実感が難しいことも、身近な人が目の前で読めば、「臨場感」をひしひしと感じます。また、思わぬ言葉が交わされたり、意図を図りかねる言葉がかけられたりもします。
初めて友達が、最初に読んでくれた友達の第一声を、私は今でも覚えています。
「これ、“続き”書くんやろ?」、このひとことは私が知りたかったこととはまったく関係がなく、正直なところでは戸惑いを覚えましたが同時に安堵したこともあり、
今の私がコメントを望まれたときに、相手がネガティブな状態であったり、意図が歪曲を招きそうな際には、盗んで使っています(笑)(笑)
余談ながら、先日の京アニ放火事件公判で被告が述べた、京アニ主催の小説コンテストにおいて「落選は裏切られた気分になった」など、このような経験のある私には考えられません。
高橋先生はこうした書き手の心情を掬い上げ、巧みに授業へ転用されていました。
その実践の様子が、二日目の後半部分に記されています。ここでは前日に出された宿題のテーマ「私について」の作文が披露されており、
きのくに国際高等専修学校に通う子供たちの発想の素晴らしさ、また一晩で書き上げた文章力を、ぜひご覧ください。
幼稚園~中学生の子供を持つ保護者の方や、
教育に携わる業務の方には、
ぜひとも知っていただきたい内容ばかりが詰め込まれた一冊。
文庫版も、出版されました。
こちらの書籍には書かれていませんが、高橋源一郎作品の中には
ー「ことば」というものは、下から上へ積み上がってゆく構造をしています。それは、そもそも、脳のはたらきが、脳幹→大脳辺縁系→大脳皮質、というしくみになっているのに、対応しているのですー
このように、脳のはたらきに伴い「生きる」→「たくましく生きる」→「うまく生きる」の過程を、可視化しやすい文章に変換する技術を披露なさっています。それはすなわち、コミュニケーション能力と密接に関連すると私は感じました。
同じ内容の脳構造を、ライトノベル女性作家の麻城ゆう先生は「特捜司法官S・A」シリーズで丁寧にストーリーに沿わせて書かれてあり、人が普遍に養える能力ではないかしらん。
それらを知った上で、子どもたちと会話される様子は、日常でも役立てることができるはず。