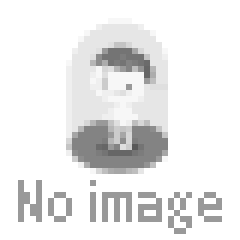Q207) 読者の方から、far fromの問題について書かれた研究を紹介されました。同時にコメントもありましたので、ここに紹介して、また私の意見も書いておきたいと思います。なお、読者の方のメールを修正しております。
いつもためになるブログありがとうございます。(ちょっとコメントさせていただきますが、)メールの目的は添付のサイトをお送りすることです。
(中略)
far from 句の語法をめぐって - 成城大学(Adobe PDF)
https://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/journal/english/pdf/seng-42-16.pdf#search=%27%E2%84%8De+is+far+from+happiness.%27
上記のサイトをざっと見たのですが、satisfactionが文法的に間違っていると思いません。
p.316にこう書かれています。
(36) a. He is far from being a critic. b. He is far from a critic.
(36a)は「彼は批評家というにはほど遠い」という意味になり、(36b) は無標の解釈では、「ある批評家から遠く離れた所にいる」の意味に解釈される可能性が高いとしている。ただし、八木も指摘しているように、 criticに定冠詞をつけなければ容認されない。
私には、satisfactionに定冠詞がないから不適だとは考えづらいのですが。
A) まず資料を教えていただきありがとうございました。同資料は「far from句」について戦前からの探求の歴史が詳しく述べてあり、勉強になりました。
ただ、質問者の方が勘違いなさっていますので、説明したいと思います。
質問者の方が引用している原文を紹介します。「ネイティブの直観にせまる語法研究」(八木克正著)(研究社)の187ページにこうあります。
6.far from (being) happy
形容詞をとる場合、far from being happyよりfar from happyの方が普通であると考えられているようだが、実際はどうだろうか。
まず、実際の例を調べて頻度から検証してみると、far fromの後に形容詞が来た場合は、beingをとらないのがやはり多い。
(中略)
これに比べて、名詞句、前置詞句、あるいは過去分詞の場合は、beingをとるのが普通である。
far fromが成句化して副詞として使われるとはいえ、fromはもともと前置詞である。名詞を従えれば成句としての解釈がしにくくなり、距離が隔たっているという普通のfar+前置詞の解釈になるから、「…という状態からはほど遠い」の意味にしたければbeingが必要になることは容易に想像できる。
(5) a. He is far from being a critic.
b. He is far from a critic.
(5b)は、普通の解釈では、「ある批評家から遠く離れたところにいる」の意味に解釈される可能性が高い。(実際にはHe is far from the critic.のようにしなければ容認されない)
上記の(実際にはHe is far from the critic.のようにしなければ容認されない)の意味を説明します。
(5b)が「遠く離れたところにいる」の意味になるためには(5c)にしなければなりません。
(5c) He is far from the critic.「彼はその批評家から遠く離れたところにいる」
それは、a criticのままだと、「彼はある任意の批評家から遠く離れたところにいる」の意味になり、文意が成立しないからです。特定のthe critic「その批評家」にしなければなりません。
よって、質問者の方は「私には、satisfactionに定冠詞がないから不適だとは考えづらいのですが。」と言われていますが、satisfactionは抽象名詞であり、theはつきません。
なお、「far from 句の語法をめぐって」を読んだのですが、「far fromの後に来る名詞は何が可能か」の問題には答えてくれません。「5.結び」には残された課題が4つあると書かれていました。その一つがこの問題です。こう書いてあります。
4つ目はfar from NPに関しての問題である。He is far from (being) happy/ intelligent.と対照的に、* He is far from happiness/ intelligence.は文法的であっても容認されない。これに対して、far fromの補部が同じ抽象名詞であってもThis work is far from completion.のような場合は問題なく容認される。far from NPにはある種の慣用語法的な側面があるように思われるので、今後は以上の4つの問題点を明らかにしつつ、精緻な語法記述を目指していきたい。
どうやらこの問題は、柏野先生もおっしゃっていた「慣用的」な側面が濃いようです。
以上です。