昨日の朝礼で、校長先生は、ご自身が佐藤学さんという教育学者の講演を聞きに行かれた話を少しだけ紹介してくださいました。
校長先生は、佐藤学さんの教育哲学に非常に共感されたとおっしゃっていました。
佐藤学さんは、私が以前から尊敬する教育学者です。
私が佐藤さんの教育哲学に共感したきっかけは、以下の本との出会いでした。
- 習熟度別指導の何が問題か (岩波ブックレット)/佐藤 学
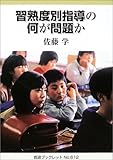
- ¥588
- Amazon.co.jp
今から7年前に、私は、日本の教育現場が、日毎に生徒たちを学力で差別化する制度にどんどん移行していくことに、大きな疑問を感じていました。
教育こそ、すべての子どもに対して平等に行わなければならない
これは、私の教育信念ですが、年月が経つにつれて、子どもたちを「上位」、「中位」、「下位」に分けて授業を行っていくスタイルが当たり前のようになりました。
そして、わたしの勤務校でも、この傾向が顕著になってきました。
実際、「中位」や「下位」のクラスの授業を担当していると、子どもたちから、「自分はできないから」という言葉を頻繁に聞くようになり、非常に心苦しく思っています。
一方、「上位」の生徒たちだけを集めたクラスの授業を担当していると、これまである集団においてトップの成績を収めていた生徒が、現在のクラスでは最下位になることで、どんどん自信をなくしていく様子が見られます。
この本は、以上のような習熟度別指導について警鐘を鳴らしています。
佐藤さんは、「習熟度別指導(トラッキング)」は「時代遅れ」だとして、この導入の有効性に異議を唱えておられます。
アメリカでは、1970年代にトラッキングの効果の無さに気づき、それ以降この指導は行っていません。
トラッキングは、一部の英才教育においては有効かもしれませんが、「下位」の生徒にとっては危険だと筆者は述べています。
佐藤さんは、現在のような日本の画一的な教育から脱却し、「共同的な学び」を行うことを推進されています。
「能力や個性の差異にいかに対応するかではなく、能力や個性の差異を生かした学び合いをどう創造するかを問うべき」
と佐藤さんは強調されています。
PISA調査でフィンランドをはじめトラッキングを行わない国が上位であり、トラッキングを行っているドイツやスイスが下位に位置したことは、決して見逃せない事例だと思います。
私は、昨日、校長先生が、教育の本質について、少しではありましたが、私たちに語りかけてくださったことに、心から感謝しました。
