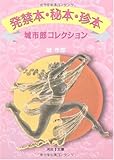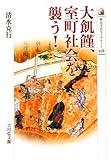1.序
初めまして皆様、
この度こちらのスペースで稚拙な論評を発表するに至った橘と申します。
今回こちらのスペースを利用するということで
僕の簡単な自己紹介をしたいとおもいます。
と云いましても、誕生日とかパーソナルデータを教えるわけではありませんよw
僕が今、取り組んでいる研究と大体僕がこのスペースで語る内容についての
概説のようなものを皆様に紹介したいと思います。
2.研究課題
この章では、僕が現在取り組んでいる研究についての紹介をしたいと思います。
今現在取り組んでいる研究は
『 艶 笑 文 学 と は 何 か 』
についてです。はい、そこ変な目で見ない←
『艶笑文学』、初めて聞く人もいると思いますのでまずは「艶笑」とは何か、
こちらは字義的な意味で教えますと、
「あでやかに笑うこと。」
「いろけのあるおかしみ。」(『広辞苑第五版』より引用)
の二つがあります。大漢和辞典、日本国語大辞典を引用したいところですが、
大変に長くなりますし、まずは親しみを持ってもらいたいということで、
誰でもすぐ確認できるような形で行きたいと思います。
これで大体の「艶笑」というものがどういう概念かのイメージが出来たかと思います。
念のため、艶笑小咄なるものを紹介したいと思います。
「あっちこっち」
えー、こちらはお妾さんを持つ男で、初めはこっそりと囲っておりましたが、
そのうちに本妻にバレてしまった。
ツノが生えるかと思ったら、なかなかものわかりのいいかみさんで、
「いいんですよ、男はそのくらいの甲斐性がなければ、大きな仕事なんぞできやしませんよ。
そのかわりね、向うに熱をあげすぎたら、承知しませんからねッ」
てんで、半分公認になり、男ァ両方をうまく牛耳っております。
本宅で本妻を抱いております、その床の中で
「ねえ、あなた……」
「なんだい?」
「あなたの体はこっちにあっても、心はきっと向こうにあるんでしょうねえ……」
「バカなことを言っちゃァいけない。心も体も、今はこっちだ。」
「あしたは、どうなの?」
「うん、心だけこっちへ置いといて、体は向こうへ行こう」
【定本艶笑落語1・艶笑小咄傑作選/小島貞二編】
こちらが艶笑ものとして落語家が話される作品です。
字義的な意味と今回の話で大分、「艶笑」と云うものに興味を持たれたんではないでしょうか。
ここで一つお互いの共有点としてあげるならば、
「性的なものを孕んだおかしみのある物語。」があると思います。
これを一つのスタンダードとして覚えておいて下さい。
3.結びにかえて
私の研究についての紹介は前章で出来る限りわかりやすくお伝えしました。
次に、それ以外の私が提供するものについてお伝えします。
私がこちらの管理者に任されたのは大まかに
「ある本を読んでその批評をすること」
です。まぁ管理者とやっていることはおおむね同じなんですがね。
ただ、僕が管理者と違うのは物事に対して、かなりWetな立場をとることが多いです。
研究することにおいて客観的な立場でものを見なければいけないのに、
視野が狭くなったり、感情を織り交ぜてしまう危険性を孕んでいます。
ですので、出来る限り皆様に見てもらえるような批評を描くよう努力いたします。
これから不定期になるかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。
初めまして皆様、
この度こちらのスペースで稚拙な論評を発表するに至った橘と申します。
今回こちらのスペースを利用するということで
僕の簡単な自己紹介をしたいとおもいます。
と云いましても、誕生日とかパーソナルデータを教えるわけではありませんよw
僕が今、取り組んでいる研究と大体僕がこのスペースで語る内容についての
概説のようなものを皆様に紹介したいと思います。
2.研究課題
この章では、僕が現在取り組んでいる研究についての紹介をしたいと思います。
今現在取り組んでいる研究は
『 艶 笑 文 学 と は 何 か 』
についてです。はい、そこ変な目で見ない←
『艶笑文学』、初めて聞く人もいると思いますのでまずは「艶笑」とは何か、
こちらは字義的な意味で教えますと、
「あでやかに笑うこと。」
「いろけのあるおかしみ。」(『広辞苑第五版』より引用)
の二つがあります。大漢和辞典、日本国語大辞典を引用したいところですが、
大変に長くなりますし、まずは親しみを持ってもらいたいということで、
誰でもすぐ確認できるような形で行きたいと思います。
これで大体の「艶笑」というものがどういう概念かのイメージが出来たかと思います。
念のため、艶笑小咄なるものを紹介したいと思います。
「あっちこっち」
えー、こちらはお妾さんを持つ男で、初めはこっそりと囲っておりましたが、
そのうちに本妻にバレてしまった。
ツノが生えるかと思ったら、なかなかものわかりのいいかみさんで、
「いいんですよ、男はそのくらいの甲斐性がなければ、大きな仕事なんぞできやしませんよ。
そのかわりね、向うに熱をあげすぎたら、承知しませんからねッ」
てんで、半分公認になり、男ァ両方をうまく牛耳っております。
本宅で本妻を抱いております、その床の中で
「ねえ、あなた……」
「なんだい?」
「あなたの体はこっちにあっても、心はきっと向こうにあるんでしょうねえ……」
「バカなことを言っちゃァいけない。心も体も、今はこっちだ。」
「あしたは、どうなの?」
「うん、心だけこっちへ置いといて、体は向こうへ行こう」
【定本艶笑落語1・艶笑小咄傑作選/小島貞二編】
こちらが艶笑ものとして落語家が話される作品です。
字義的な意味と今回の話で大分、「艶笑」と云うものに興味を持たれたんではないでしょうか。
ここで一つお互いの共有点としてあげるならば、
「性的なものを孕んだおかしみのある物語。」があると思います。
これを一つのスタンダードとして覚えておいて下さい。
3.結びにかえて
私の研究についての紹介は前章で出来る限りわかりやすくお伝えしました。
次に、それ以外の私が提供するものについてお伝えします。
私がこちらの管理者に任されたのは大まかに
「ある本を読んでその批評をすること」
です。まぁ管理者とやっていることはおおむね同じなんですがね。
ただ、僕が管理者と違うのは物事に対して、かなりWetな立場をとることが多いです。
研究することにおいて客観的な立場でものを見なければいけないのに、
視野が狭くなったり、感情を織り交ぜてしまう危険性を孕んでいます。
ですので、出来る限り皆様に見てもらえるような批評を描くよう努力いたします。
これから不定期になるかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。
発禁本・秘本・珍本--城市郎コレクション (河出i文庫)
posted with amazlet at 10.06.06
城 市郎
河出書房新社
売り上げランキング: 229541
河出書房新社
売り上げランキング: 229541