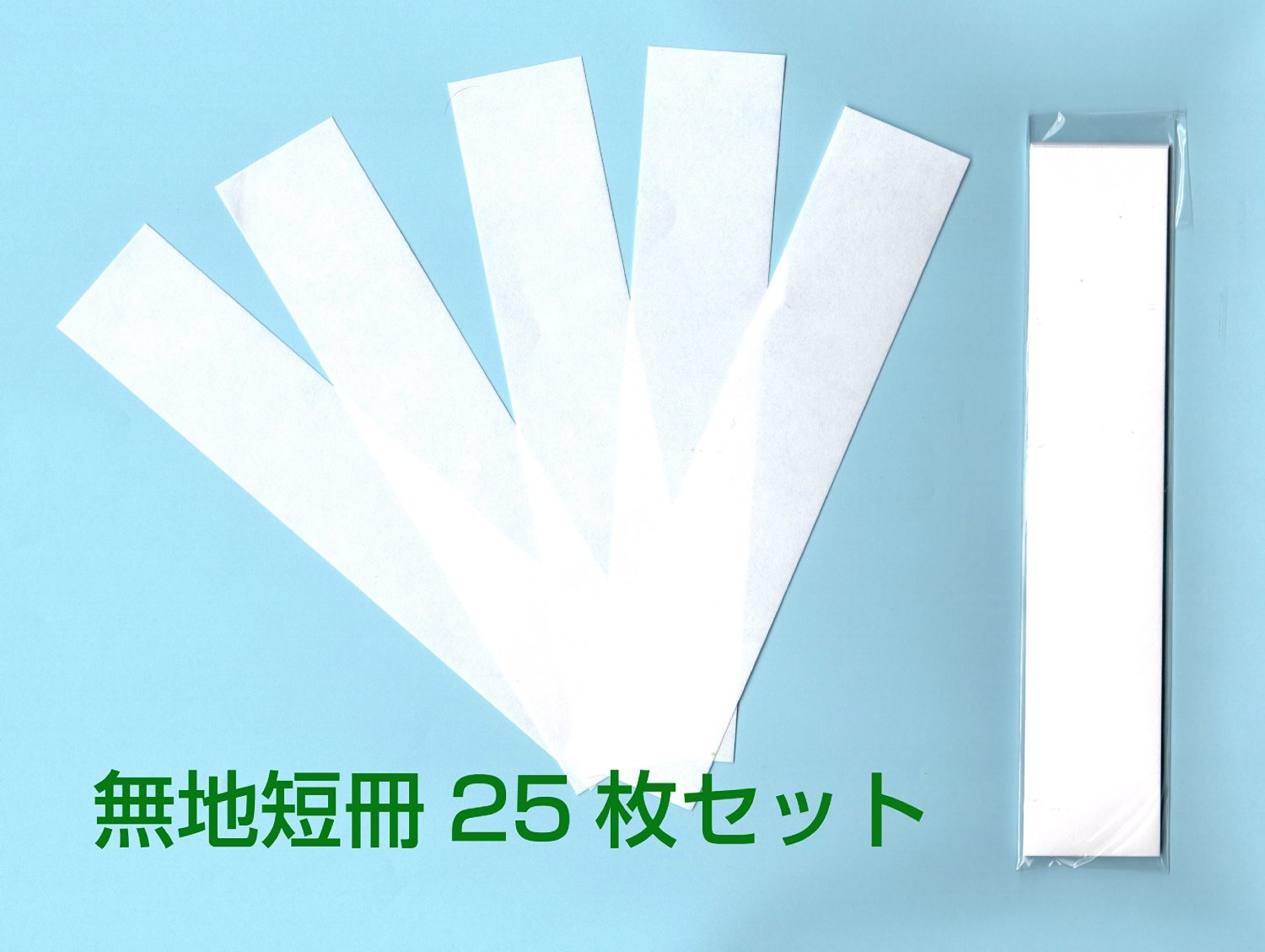お礼の額で右往左往してる間にお稽古日がやってきました。
結論から言いますと、「今回はお礼なし」でした。
(先生からキッパリ断られた)
あくまで「今回は」であって、次回は上級の許状になりますから、
引継(許状の授与)、先生が亭主を務めてくださるお茶会等
費用とお礼は覚悟して用意しておかないとな訳です。
※この辺の事情は先生によって異なるようです。
許状申請とお礼については、社中の先輩方や、「無粋な事を聞いてすみません」と先生に思い切って聞いてみるのが1番かと。
初級・中級合わせて7通。
「〇〇のお稽古を許可します」と書いてあります。
裏千家についての冊子付き。
やっと入口に立った感じ。
これまでは「通常のお茶会の作法」だけのお稽古でしたが、
ここからは「百万石の大名をもてなすお茶会の作法」に入るそうです。
百万石の大名は存在しない=今は開かれる事はないのですが
(登場するお道具が悉く美術館に収蔵されるクラスのため)
お作法を途絶えさせないように、との事かなと思います。
100万円を超えるお茶碗が出ることもあるらしい。
なので「日頃のお稽古で、お道具を大切に扱う習慣を身につけるのよ」(先生談)
それにプラスして気になってるのが
裏の仕事を覚える
裏の仕事というのは、
・水屋(調理場・洗い場)の仕事
・お炭、灰の仕込み
その他諸々。
水屋には出会った事のないお道具がぎっしり
お稽古が進むにつれ分かって来たんですが、
お茶室の中のお作法だけでなく
周辺の知識や技術が必要になってきます。
・書の知識(掛け物)、技術(お礼状やのしの表書き)
・花の名前
・季節のご挨拶の作法(独身者には欠けがちなアレ)
・窯元の知識(お茶碗、お茶入れ)
・料理の技術(水屋)
・お炭の知識(炉に入れるお炭は形、大きさ、入れる順番が決まってる)
その他諸々
一朝一夕で身につくものでもないですし、時間をかけ少しずつ引き出しを作って行く所存です。
色々決まり事があって面倒くさそうと思われそうですが、
その面倒くさいのを習いに行ってると、覚悟はできてるつもり。
お稽古場の水屋にあったんで買ってみました。
水屋のあれこれがイラストでわかりやすく書かれてます。
のし袋の表書きを失敗しても大丈夫
「御年賀」「御挨拶料」って印刷ないからねえ