タケダが潰れる日は近いな (no.3114)
今がチャンスです、藤沢鎌倉が潰れるか?タケダ薬品が生き残るか?どっち?
藤沢江ノ島のサーファー怒れ!第2の成田空港だ、騒音とか、汚染水流すな!サーファーや漁業関係者と抗議しようそして和解できないなら武田薬品の歴史に終止符だ、オリンパス=似てるなあ=第一三共がアステラスがあれば日本は明るいんだな
タケダ=吉富=大正製薬=ミドリ十字=三菱田辺=チバガイギー=ノバルティス=薬害の系譜、公害=薬害
いまこそ魚をブチマケヨウ!さかなくんも怒る、海を汚すな運動を始めよう、水俣病なんじゃないか?NHKさんよ!是は公害=水質汚染じゃないのか?おこりますよ=株主総会で質問する出来るよな!青野信は厚生省に通じているよん。
議会委員会でのタケダ報告発言の問題部分は? (no.3106)
武田問題対策連絡会会員 平倉 (122.135.223.184) 2011/12/7 14:55:8
藤沢市議会事務局を訪れ、12月2日の厚生環境常任委員会の録音をUSBメモリーに音声書き込みして頂いた。改めて武田薬品側の報告を聞き直して、以下のような疑問点があることがわかった。
1.病原菌が実験室から研究棟内を(1階方向に)移送される?
今回の事故で、P1の場合に実験室では滅菌処理なりオートクレーブ処理なりをしなかったという問題点がでた。これはいままでの市民への説明と違うではないか?
P3実験室はもちろんP2実験室も遺伝子組換え生物は(P1といえども)実験室の中で不活化処理(いわゆる滅菌処理のこと)を行うものと理解していたし、タケダが09年に市民に配布したカラー刷り小冊子で、研究材料の遺伝子組換え微生物はP1レベルのものであっても、(国内カルタヘナ法で)全て不活化処理をすると記載している。そのように、遺伝子組換え生物は実験室内で不活化処理し、研究棟の中を廃液の中に活性のまま移送されることはないものと推測していた。廃液タンクが研究棟の棟毎に置かれること自体は、万一実験作業の手順ミスで遺伝子組換え生物が実験室の外に誤って放出したときの漏出対応を可能にする策として「あるべき」もので、万一研究室から滅菌処理をしないで漏れたような際チェックできる中継タンクとしてを設けておくことは大事なことであろうと考える。
本来の実験作業での滅菌手順をスキップしたミスか、または実験の本作業に付随した補助作業で「滅菌流し台」を使用し、その後で蛇口をキチンと閉めなかったケアレスミスなのか、しろうとは12月2日のタケダ説明を聞いても混乱するだけである。
先ず遺伝子組換えなど研究材料がP1レベルのときは、どうするのか? 廃液のどの段階で不活化の処理を行うか? この際明確にすることを求めたい。そしてこれまでタケダとして「拡散防止措置」をどう組み立てていたか説明されたい。
できれば報告書面を付し、必要な図表(地図など)を用いて分かりやすくするべきだと思う。
たとえば、4階(の流し台)と言うのは、実際には10階建てのどの階をさしているのか? アセス評価書などで、3,5,7,9の階に実験室があると理解している。それに対して報告の「4階」というのはどのフロアか? もし、10階建ての4階だとすれば、その階は実験室ではなくいわゆる「バックヤード」ではなかろうか? 疑問である。
2.「漏れ出した液に危険はない」あるいは「病原性はない」の根拠は?
三井部長の発言の「危険」というのは何をさしているか? 一口に「遺伝子組換えの大腸菌、サルモネラ菌、バキュロウィルス」というが、市民としては「遺伝子組換えの大腸菌、遺伝子組換えのサルモネラ菌、そして遺伝子組換えのバキュロウィルス」が漏れたと解釈するのか、しろうとなので迷っている。
説明の中で「病原性はない」との話も有ったが、橋口リーダーは何をさして「病原性はない」と言えるのか? 文科省の報道発表で「生物多様性への影響の可能性は低いと考える」とあるので、一応それを信用せざるを得ないのが市民の平均的な気持ちだと思う。加えて、市環境部は情報を総合して整理した判断を市民に示し十分説明できるようにして頂きたい。
いつ、どこの実験室が扱った病原体が廃液タンクに存在したのか? それ以前の病原体は不活化されて全て放出されていたと言えるのか? 材料とした病原体の名前を全て挙げ危険度を記載した表などで説明すべき。「環境安全情報データ」は示せないのか? また、サルモネラ菌の「環境安全情報データ」はどういう内容か?
3.文科省の発表には「廃液タンク」しか出てこない。対して橋口は「廃水槽」と言ったり「廃水タンク」と言ったり・・さらに「滅菌廃液タンク」とも。そして 何故オーバーフローしたのか?
一つの実験棟に有る実験室の総床面積は1ha近くあるのに、それら実験室の全部から廃液が合流してくるのであれば,何時間位で溢れると計算したのか? 又はタンクからどこへ移動するのか? さらに、「夜半」だか「未明」だとかに、警報音と警報ランプを確認しているということも橋口マネージャーは深くは報告していない。
30日午前1時頃から垂れ流しとなった「滅菌流し台」およびオーバーフローした「廃液タンク」のそれぞれの機能、構造、処理能力についてタケダは明らかにすべき。
水道水が蛇口から午前1時より垂れ流しされた。垂れ流しの水量を1時間あたり1Whとすると、7時までに6Whの量になる。夜半の警報が4時だったとすれば、3Whが「タンク」に入り、その後7時までに3Whが「タンクからオーバーフロー」したことになるし、「未明」が5時ないし6時であったとしたら、5時までに4Whが「タンク」に、外に2Whが溢れたし、6時であったとしたら6時までに5Whが「タンク」に、外に1Whが溢れたことになる。すなわち、4時警報なら3Whが1リューべで、5時なら2Whが、6時なら1Whが1リューべだということになる。蛇口の水量は大幅に変わる。もっとも重要な情報のひとつである、警報が発せられた時刻とタンクの容量は報告すべきであった。
かつてタケダが藤沢市へ届出したものの、マスキングだらけのフローに出ているのは、終末(東側出入り門守衛所裏手の、半地下間口20m×奥行き18mで、高さ3mくらいのグレー色の建造物か?)を指す「中和処理装置」が記載されているだけである。
他方、アセス評価書では「中継槽」が有って、水質管理が目的になっている。いずれも今回の説明とは全部は符合しない。(中継槽として明示し目的がはっきりしているのはRI排水の場合くらいである)。
1階の「廃液タンク」と「終末貯留槽」の中間に何があるのか? すなわち「廃液タンク」のそばに「滅菌装置」があるのかどうか? (又は、「廃液タンク」が「滅菌装置」である?)これらの疑問について、性能を含め明らかにすべき。
***(つづく)***
つづき (122.135.223.184) 2011/12/7 15:18:36 (no.3107)
***********(つづき)
4.藤沢市への報告の前に、なぜ「文科省と電話相談」があり、どうして電話の結果が市への報告遅れの理由にすると考えたのか?
文科省の発表に法の第12条、第15条が例示されたように、現場の責任者は法令の趣旨に照らし今回の事故について重大性の度合い(事故の程度)を認識したであろうと思う。しかるに文科省の職員から「現場を見なくては分からない」といわれて、行政への事故報告を日延べしている。
両市行政とタケダ社長が9ヶ月前に締結した協定に基づく通報が、何故できなかったのか?
16時頃に報告し、初期対策が実行されていることを伝えれば、タイミング的に文科省職員の現場確認が翌日になるのはほぼ当然のこと。「(文科省が来るのが)翌日になったので、・・そのような(両市行政への報告を翌日にする)段取りになった」などは、報告が後れた言い訳にもならない。
日延べのウラになにがあったのか? 謎だ。三井部長はいつ「起きてはならない『事故』」と事故の重要性を判断したのか? また、橋口リーダーはどういう認識なのか?
行政に対する申し訳は改めてきちんと行って頂きたい。
続いて、最後に年内当面のことがらについて・・
5.「対策には時間がかかる。できるだけ早くとしか言えない」 これでは不誠実も甚だしい
委員会で、市議の委員は「文科省・藤沢市への、原因究明、対策の報告時期」を問うているのである。タケダの方としては、とうに、そのくらいの日程上の目標くらいは、研究所の責任者が実務者らに出させているはずである。はたしてタケダは、現場確認に来た文科省職員にもそのような返答をしているのであろうか?
それにしても、40万市民の藤沢市に向かって言うことか?
三井部長「戸別訪問してお詫びを」は、自ら先頭に立ってぜひ行うべし。「遅くとも再来週から」と言うことは12月15日の辺りからのことである。
6.原因究明・緊急施設点検・再発防止対策と報告・対策の実行」への要望
市民の立場として、当会会員としては先ず以下のことがらを求めたい
1)直ちにマスコミと市民に、事故経過を説明し現場確認をさせること。
2)行政ならびに市民に、諸対策項目「素案」を説明し、引き続き遅滞無く実施する工程表を提出し説明すること。
3)再発防止対策は該当施設に限定せず、類似ないし関連する施設についても十分点検・検討し、「操業」より対策を優先して実行すること。
研究施設が余りに巨大であり、かつ研究員があまりに集約していることからして、今回の災害防止策は、操業当初期にありがちな大小さまざまな事故の行方を占うものになる。対策には県(衛生研やアセス審査委員会含む)や両市行政の知恵も借りるべきであると思う。
(「時間がかかる、できるだけ早くとしか言えない」で押し通さないことを願う)
以上
藤沢市役所でタケダ研究所が事故報告 (no.3092)
タケダ問題対策連絡会 平倉(会員) (122.135.223.184) 2011/12/2 21:15:51
文部科学省はHPのお知らせに、「武田薬品工業株式会社湘南研究所において、遺伝子組換え生物等の不適切な使用等がありましたのでお知らせします。」ではじまる報道発表を12月1日に掲載しました。(発表内容は下記のHPアドレスに)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/12/1313694.htm
武田湘南研究所の廃液タンクのオーバーフローについて12月2日(金)藤沢市議会厚生環境常任委員会(9:30より開催)において、小野環境部長からの報告が有り、続いて武田湘南研究所から事故の経過報告が研究業務部の三井(部長)および橋口(安全性グループリーダー)の両名から説明があったので、主な内容速報したい。(内容への疑問点は追って記載の予定。)
・・・・・
(小野藤沢市部長) 大腸菌、サルモネラ菌、バキュロウィルスを含む廃液タンクから液をあふれさせ、次亜塩素酸にて滅菌処理をした。市への報告は12月1日にあり、報告の遅れに抗議した。
12月1日の内に連絡会議を開催し、タンク、しみ、滅菌作業された現場を確認した。
武田に対策書の提出を要求した。
(三井部長)漏れ出した液に危険は無い。けして有ってはならない事故である。
(橋口リーダー) 上の階で流し台の上水蛇口の栓をかんぜんには閉めなかった。施設管理者のパトロールも蛇口を見逃した。廃液を集め(次に)滅菌する。廃水タンクの上部は(空気穴が)空いていてヘパフィルターが付いている。液が流入するとき槽から空気が外へ出る為である。
廃水槽からオーバーフローして防水パットにあふれ、パットの亀裂から下の地下階に漏れて、コンクリの床に1m2の水溜りになった。それらの廃液を回収し、床を滅菌した。
廃液は上でそれなりの処理をしたもの。
今からやる確認作業あり、液面が接していないところへ飛まつが飛散したかも知れず、そこを滅菌する。
現場写真をプロジェクターにて示す。①滅菌流し台、②1階、タンク、下に通る複数のパイプと耐水塗装された床面、③地下階。
(つづく)














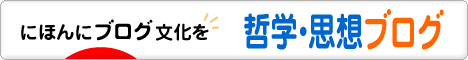

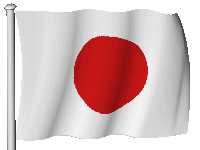





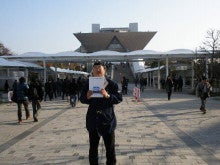































2011年11月25日 at 04:55
昨日熊谷市役所に行ってきた、生活保護者の急増に頭を抱えている、貧困をビジネスにする人も居る、311の今非常にシビアに給付を行わなくてはイケナイが?若者が働かなくなり気力を無くし、希望を無くし生活保護を受けている現状がある、若者というか未だ働ける人たちであるけれど精神を病んでいる、可哀想だけど16万円とか高額の給付がある、原子力発電所を追われた人は働く場が無いのだ、救済を、これは差別問題含め福島で働いていた人の転職は果たして可能だろうか?否なのであるけれど、除染除染言い過ぎると人間そのものが汚染されれば人間はどうやって除染するのか?甚だ疑問だ、共生しかないのだけれども果たして喜んで福島のお嫁さんを貰えるか?果たして喜んで福島の米を僕達は食べるか?胸に手を当てよう・・・そして脱原発も=権力側に付いて来る、脱原発利権?放射能を商売にする人が居るのだ、やらせ集会は東電だけでない九電でもない、脱原発やらせ集会はダメだ、もっと自由に発言しもっと涙しもっと真剣に会議で議論して欲しい、熊谷市民のくらしを良くする会???やらせ集会を行っていた・・・猛烈に抗議した、60000人の先頭に居ても発言させないのだよ・・・右派左派利権はあるけれども貧困や放射能を利権化したら救いようが無い、警察が犯罪者になったら消防署が犯罪者ではイケナイ、電力会社が嘘つきでもイケナイ、利権は人を堕落させる、原発利権=原子力村+脱原発利権?(放射能を商売に利用する人々)もイケナイのだ、右派左派もなく利権も無い世界を望む!市民とはひとり立つのであり、何か?変な団体名は不要だ!個人で立て!其処に真理は宿る