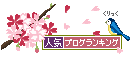心に花を咲かせましょう *葵桜*きもの着付教室 まつさき まゆみ です。
ご訪問いただきありがとうございます。
先日、着物屋さんに、感謝される場面に遭遇しました。
着物に興味のある人の前で素晴らしい商品を見せて、その価値を力説したところで、ただの美術品になってしまうような話の流れの中に、
着付け講師がいたことで、話の展開が大きく変わりました。
そのことを、着物屋さんも着物に興味を持っている人にも感謝されました。
着物は洋服と違って着れる人が増えないことには、ユーザーの底上げができない。
だから、「着物を着れる人を増やしてくれてありがとう」と感謝されました。
私にとっては、当たり前のことですが、自分が当たり前だと思ってることに対して感謝されると嬉しさ倍増ですね。
で、ふと、「着物っていつから習ってまで着るものになったんだろう??」と気になりまして、ここ数日間色々本とか資料を漁っておりました。
もちろん、中には習わなくても着れる人あります。
そして、「昔の人はみんな自分で着れた」という認識の人も多いと思います。
だけど、それはちょっと違うんですよね。
着物の歴史を振り返ると、今の着物の形になったのは、結構最近のことです。
大昔からさかのぼって書き出すと話が大きくそれるので、詳しくはまた別のエントリーで書きたいと思うのですが・・・
着物のの「おはしょり」が生まれたのは<江戸時代中期~後期のこと>。
美しいおはしょりなどは求められておらず、外出時などに動きやすいように、しごきでからげたのが始まり。
「着物に帯を結ぶ」というスタイルは<江戸時代後期のこと>
その前は、細い帯をぐるぐる体に巻いて、後ろで結んでました<安土桃山時代>。
それが、<江戸時代>に入り、帯幅が広くなりました。
最初は、帯は前後左右どこで結んでもよかったのが、しだいにミセスは前で、ミスは後ろで結ぶようになり、
自分では結べなくなったため、「着付け師」という仕事が生まれたそうです。
![]() 昔の人も自分で結べなかったんですよ。
昔の人も自分で結べなかったんですよ。
今の主流のスタイルになっている「着物+名古屋帯でお太鼓結び」が登場したのも、<江戸時代後期>
その時から「枕と帯締め帯揚げ」が登場しています。
そして、今の着物のスタイルが一般の女性に広まったのは、<明治45年(1907年)頃>。
今からたったの100年ちょっとですよ!!
ちなみに、それまでは、上流階級と庶民が着る着物の形は違うもので、
わかりやすいところで言うと、平安時代の十二単は上流階級が着ていたもので、それは人に着せてもらってました。
帯が登場する前までは、庶民は自分で簡単に着られるような着物の形のものを着てました。
それが、明治のころから、上流階級も庶民も同じ形の着物を着るようになります。
で、その結果、帯が結べなくて、(庶民も)人に着せてもらうのが主流になってしまったと推測されます。
その後、<大正時代>に入り、第二次世界大戦の始まりとともに、国防色の上下服、筒袖の着物にモンペスタイルとなります。
そして、<昭和20年(1945年)>に終戦を迎え、アメリカ軍に負けたこともあり、洋服がかっこよくて、和服はダサいといわれるようにもなり、どんどん洋服が主流へと移行されます。
![]() ということは、庶民が着付けをしてもらうようになったのは、お太鼓結びをするようになってから。
ということは、庶民が着付けをしてもらうようになったのは、お太鼓結びをするようになってから。
「昔の人はみんな自分で着てた」と言われますが、「昔」はいつの時代のことを言っているのか??で随分話が変わってきますね。
いずれにせよ、今の着物の形をみんなが自分で着ていたというわけではないのですね。
もとは、人を着せているところを見ていた第三者が「自分でも着れそう」と思い立って着るようになったのがきっかけで「自装」が生まれたそうです。
そして、「着付け教室」のようなものができたのは、<東京オリンピック(昭和39年(1964年)の少し前>に、「外国人にぐちゃぐちゃな着姿を見せるのはみっともない」ということで、国が指導したとのこと・・・(これが自装なのか他装なのかどうかは不明ですが)
![]() 着付け教室できたのって、たかだか50年ほど前なのですね!!
着付け教室できたのって、たかだか50年ほど前なのですね!!
ホンマかいな!?
箪笥の肥やしになっているのが一番多い年代が50代後半から60代というのを聞いたことがありますが、
まさか・・・それまでは自由に着てたらよかったのが、いきなり「きれいに着ること」を強要されて着物離れが始まったってことは・・・ないよね!?
計算が合ってるような合わないような気もしますが・・・
調べた限りでは、そんな感じのようです。
![]() だから、逆に言うと、着物を着れることは当たり前ではないのです。
だから、逆に言うと、着物を着れることは当たり前ではないのです。
昔は簡単に着ていたのが、だんだん「どうやったら美しい着姿になれるのか?」を着物オタクが考え出して、衿芯が登場したり、少しずつマイナーチェンジをしながら、今の形になったのですね。
だから、着物の着方なんて、千差万別なのですよ。
着たい人が、着やすい方法でそれぞれ発明したことだから。
今日も経験者コースの生徒さんが頭こんがらがってはりましたけども、
「着方に全国共通の決まりはない」です。
洋服の時もボタンは第1ボタンから締める・・・
といったルールがないように、着物にもルールはないのです。
生徒さんには「ユーチューブとか見て着付けのおさらいしんといてね・・・」とお願いしています。
違う着方の動画を見ると、混乱されるだけなので。
着付け教室によって「こういう着方が着やすい」「ここに紐がある方が楽ちん」というのを提案して、
それぞれのこだわりを持って、ネットや本にもされているだけのこと。
逆に言うと、それらの動画や本を見て着られるようになる人はそれで十分だと思います。
それでも、「独学で着てたけど、時間がかかりすぎて」とか「綺麗に着られている人とは、○○が違う気がして」、着付け教室に通うことにしました!という生徒さんもたくさん駆け込んでくださいます。
着物を着ると人の目を集めるだけに、どうせ着るなら、「快適に美しく」着たいですものね。
ネットや本ではそういった細かな点は伝わりにくいというのは確かにあります。
茶道などの手順書などは、一番知りたい細かいところは、あえてグレーにしているとも聞きます。
それは、(決して「わからない人に茶道に習いに来てほしい」というのが狙いではなく)その本を見た人が「私が教わったことと違う」と混乱されないため。
着物本もそういう思いがあるのかもしれませんね。
着付け講師の存在に感謝していただいたことをきっかけに、着付け教室はいつからできたのか?を知るために、大きく脱線しましたが、
ここで言いたかったことは、
 着付け講師の存在を認めてもらえてうれしかった。
着付け講師の存在を認めてもらえてうれしかった。
 庶民と上流階級では着ているものが違った。
庶民と上流階級では着ているものが違った。
 庶民の着る着物は自分で簡単に着られる形をしていた。
庶民の着る着物は自分で簡単に着られる形をしていた。
 昔の人が誰でも着れたかというとそうでもない。
昔の人が誰でも着れたかというとそうでもない。
 今の着物の形ができたのも結構最近。
今の着物の形ができたのも結構最近。
 着付け師という仕事ができたのはその後のこと。
着付け師という仕事ができたのはその後のこと。
 着付け教室が生まれたのはもっと最近。
着付け教室が生まれたのはもっと最近。
ちょっとしたことで、着物の歴史や、着付けの歴史、着物の着方などについて改めて整理をするきっかけとなりました。
何日か分けて書いた上にあちこち脱線してかなり長くなりすぎましたが・・・
何とか締めんと終われませんので(笑)
着物が着れる人を一人でも多く増やせるように、明日からもまた頑張ります。

着物の楽しさお伝えします。あなたも一緒に着物ライフを楽しみませんか!?
 お問合せ/お申込みはこちらからお願いします。
お問合せ/お申込みはこちらからお願いします。
※48時間以内にメールにてお返事いたします。
お問合せ/お申し込みの際は、「@gmail.com 」からのメールが受信可能なメールアドレスをお知らせください。
送信後すぐに自動返信メールをお送りしております。
10分以内に自動返信メールの返信がない場合は、メールアドレスに不備があることが考えられますので、(入力ミス・フィルタの設定など)再度ご確認の上、送信をお願いします。
※日中はレッスンを行っております関係上、返信が真夜中になる可能性があります。
真夜中の受信に不都合がある場合は、備考欄に受信可能な時間帯をご記入いただけましたら考慮させていただきますので、よろしくお願いします。
 レッスンメニュー
レッスンメニュー
├ おすすめレッスンメニュー  「初級」コース
「初級」コース

 (次回募集時期は未定です)
(次回募集時期は未定です)
├ その他レッスンメニュー  レッスンメニュー一覧
レッスンメニュー一覧
 ご予約状況
ご予約状況
├ 2016年2月

├ 2016年3月

├ 2016年4月ご予約状況 
 その他
その他
├ 着付(他装)サービス  「着付(他装)サービス」一覧表
「着付(他装)サービス」一覧表
└ ホームページ  *葵桜*きもの着付教室
*葵桜*きもの着付教室