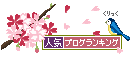心に花を咲かせましょう *葵桜*きもの着付教室 まつさき まゆみ です。
ご訪問いただきありがとうございます。
十二単について、昔習った時の記憶と、昨日の解説と、サイトなどで調べてまとめました。
<十二単とは>
平安時代の中期に完成した女房装束の儀服。成人女性の正装。
宮中などの公の場所で、晴れの装いとして着用されていた。
着用する時も限られていて、宮中の儀式など、公家女房の晴れの装いとして用いられていた。
現在では御即位の大礼の儀、皇族妃の御成婚の儀に用いられる。
<全体の構成>
「唐衣(からぎぬ)・表着(うはぎ) ・打衣(うちぎぬ)・五衣(いつつぎぬ)・単衣(ひとえ)・長袴(ながばかま)・裳(も)」からなり、
髪型は大垂髪(おすべらかし)」で構成されている。
※十二単は十二枚着ているから十二単というと思っている方も多いと思いますが、それは間違い。
十分を通り越して、「十二分に着ている」という意味からそのように呼ばれているそうです。
<普通の着付けと違う点>
着せるときは必ず「前方」と「後ろ方」との二人ペアで着せます。
前方は立ち上がることは許されておらず立膝まで、着物を運ぶときは後ろ方が立ち上がって運びます。
(十二単は宮中の身分の高い方が着るものなので、そのような方の前で立つことが許されなかった)
また、たくさん羽織りますが、紐は2本しか使いません。
1枚目を着せる⇒1本目の紐を結ぶ⇒2枚目を着せる⇒2本目の紐を結ぶ⇒1本目のひもを抜く⇒3枚目を着せるといった形になります。
<服装>
・襪(しとうず)
・小袖(こそで)
・単衣(単)
・檜扇(ひおうぎ)または大翳(おおかざし)
・帖紙(たとうがみ)
<髪型>
・大垂髪(おすべらかし)
垂髪(すべらかし)は古代から現代までの基本の髪型であるが、
大垂髪は、平安時代に始まり、室町時代、江戸時代へと三段階、三様の変化を遂げながら、現代に至っている。
⇒平安時代
垂髪は裾を引くほどに長いのが理想とされ、黒く艶があり、豊かなことが要求された。
成人すると「鬢批ぎ(びんそぎ)」の儀式があり、頬にかかる一部の髪を目より30センチほど下で
短く切る習慣があった。
⇒室町時代
額を四角く出し、髢(かもじ)を繁いで、背中でいくつも結び目を作って垂らした。
⇒江戸時代
結髪式に鬢を張らせるので、後から見た形が杓子に似ている。
この杓子の最も大きいのを「お大(おだい)」と称し、仙花紙を幾枚も張り重ねて堅くし、黒く塗って作った「つとうら」を用いて形を作る。
次に二メートルに近い丸髢を髪上げの道具につないで、前髪の位置から後に垂らす。前髪は上げずに、垂らした髪は元結で四か所結ぶ。
上から首の後の辺りで絵元結を結び切りに、二番目は少し下がった所に紅の水引きを片鉤(かぎ)に結び、
三番目、四番目は共に「こびんさき」と言って、縦四つ織りにした白い紙を、いずれも片鉤に結ぶ。
おまけ。
22歳の頃の私と十二単。
通っていた着付け教室の時代衣装科で着せ合いっこして写真屋さんに撮ってもらいました。
この写真大嫌いやったけど、こうやってみると、平安顔で似合ってる・・・かもね(笑)
引用元
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%8D%98
http://www.wagokoro.com/contents/12hitoe.html
http://www.studio-quon.net/jyuunihitoe/
着物の楽しさお伝えします。あなたも一緒に着物ライフを楽しみませんか!?
 レッスンメニュー
レッスンメニュー├ おすすめレッスンメニュー 「初級」コース
├ その他レッスンメニュー レッスンメニュー一覧
 ご予約状況
ご予約状況├ 2016年2月


├ 2016年3月


├ 2016年4月ご予約状況 レッスンの空き状況
 その他
その他├ 着付(他装)サービス 「着付(他装)サービス」一覧表
├ お問い合わせお申込み お問合せ/お申込みフォーム
└ ホームページ *葵桜*きもの着付教室