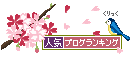前回、意外にも反響が多かった「袋帯の畳み方で気を付けていること 」
お太鼓の柄合わせをしたときに、外側に折ジワがくることで悩まれている方が意外に多かったようですね。
前回、柄合わをして結ぶ場合、「どこの柄を出すかを見極めて、そこに折ジワが入らないように畳むようにしましょう。」
と書きましたが、実際背中に結んでいただくと確実ですが、床置きでも確認できます。
参考までに袋帯(二重太鼓)のチェックの仕方を書きますね。
まずタレ30㎝程のところに帯枕を置きます。
その上から二重太鼓になる部分をかぶせて、
出したい(そろえたい)部分の柄を決めて柄合わせをします。
タレを折り上げてお太鼓を作り、お太鼓の上線とした線にクリップ留めて印をつけます。(白いクリップ)
この帯でいうと、赤のクリップの位置が、消したい折ジワ。
※すでに折り目が入ってしまった帯については、プレスに出します。
ちなみに私は、まずアイロン充てて(当て布忘れずに)、
重しで取れないか試してみて、それでもだめだったらプレスに出します。
プレスに出しても同じところで畳んで返却されることがあるので、要注意![]()
白と白のクリップの間がお太鼓の外側に響く部分。
この間に折ジワが入らないように畳めばOKです。
※「和裁士さんが考えて畳んでくれているので、購入時のその通りにしておいたらしわが入らない」とか「ラインが外に響かないようにお太鼓作ればよい」というご意見もありましたが、体形に左右される部分や出したい柄によっても変わってきますので、意外にそうでもないようですので、ご自身の体形も考慮してチェックしてみてくださいね。
特に、名古屋帯はリサイクルショップで購入したものは小さく畳んであったりして、残念なところに折ジワがついているものが多いです。
同じようにしてお太鼓を作ってみてチェックしてみてくださいね。
着物の楽しさ伝えます。
一緒に『簡単×快適』きものLifeをはじめませんか?
 レッスンメニュー
レッスンメニュー├
 おすすめレッスンメニュー 「帯だけ」コース
(4月生受付中)
おすすめレッスンメニュー 「帯だけ」コース
(4月生受付中) ├ おすすめレッスンメニュー 初級コース (4月生受付中)
├ その他レッスンメニュー レッスンメニュー一覧
 ご予約状況
ご予約状況├ 2015年2月までのご予約状況

├ 2015年3月以降のご予約状況

├ 2015年4月以降のご予約状況 レッスンの空き状況
 その他
その他├ 着付(他装)サービス 着付(他装)サービス 価格一覧表
└ お問い合わせお申込み お問合せ/お申込みフォーム