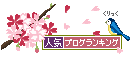生徒さんからのご質問。
袋帯の畳み方で気を付けていること。
袋帯は名古屋帯に比べると、畳みやすいですよね。
だけど、買った時のママ大事に保管していたはずが、
(折り目で八等分にして畳んで保管していると)
お太鼓とタレ先の柄を合わせて結んだ時に、
柄合わせをして結んだ結果、このクリップのラインに、折ジワが。
試しに、このクリップを留めたまま、八等分に畳んでみると、
こうなります。

意味わかります??
ん??良くわからない…と言う方、逆から考えてみてください。
普通に八等分にしていると、このクリップのラインに折り目ができます。
そして、お太鼓結びをすると、このクリップのラインがお太鼓の外側に出てくるというわけです。
折り目がお太鼓の外側に響かないようにする畳み方その①
八等分にする前に、タレ先をを20~30㎝折ってから、畳みます。
※このクリップの位置には折ジワがつかないということです。
折れ山がずれることで、お太鼓の見せたい部分に折ジワが出なくなります。
ただしここで注意点!!
実際、どの部分の柄を出したいか考えて、
その位置に折り目が入らないように畳んでおくようにしましょう。
というのも、上記の方法で畳んでいると、余計にお太鼓の外側に折ジワができる帯もあります、実は。
すると、お太鼓とタレ先の柄を合わせようとすると、ばっちりお太鼓の上に折ジワがでてきました。
というわけで、
折り目がお太鼓の外側に響かないようにする畳み方 その②
下の写真の、赤いクリップの位置がその折ジワのライン。
一方、水色のクリップは柄に合わせてタレを折あげたときにくるライン(線が入っていてOKな位置)。

意外にも、手先とタレ先をそろえて普通に八等分したら、水色のクリップのところが折り目になります。
こういうこともあるんですね!!
ポイントはこの切り替え部分(オランダ線)での柄の細工があるかどうかです。
帯によったら、柄合わせがしやすいように、このラインの部分で柄が切り替わっているものがあります。
その分、前回のような畳んでいると、柄合わせをしてお太鼓を作ろうとした際に外に出る柄の位置が変わります。
ということで、あらかじめ、柄合わせをして結ぶ場合、どこの柄を出すかを見極めて、そこに折ジワが入らないように畳むようにしましょう。
そして、もう一つの対処法!!
折り目がお太鼓の外側に響かないようにする畳み方 その③
8等分ではなく6等分に畳みなおせばかなりの確率で折り目がお太鼓に響かないことが判明。
注意点としては、収納力がやや落ちる事。
桐ダンスの場合、8等分にしておくと横に二本並べて収納できますが、
6等分となるとその分袋帯を収納するスペースが減ってしまいますが、
その問題がクリアできればぜひお試しください。
(私は、空いたスペースで半巾帯などの収納をしています。)
8等分にすると、下の写真の赤と水色のクリップのところに折ジワができているという状況。
その①とその②で述べている通り、柄合わせによったらどちらも悪さします。
それが、6等分にすることで解決するという朗報。
狐につままれたような気分になっている方のために、
この折ジワ問題について検証するための方法を別記事で書きますね。
※すでに折り目が入ってしまった帯については、プレスに出します。
ちなみに私は、まずアイロン充てて(当て布忘れずに)、
重しで取れないか試してみて、それでもだめだったらプレスに出します。
プレスに出しても同じところで畳んで返却されることがあるので、要注意![]()
※「和裁士さんが考えて畳んでくれているので、購入時のその通りにしておいたらしわが入らない」とか「ラインが外に響かないようにお太鼓作ればよい」というご意見もありましたが、体形に左右される部分や出したい柄によっても変わってきますので、意外にそうでもないようです。
ご自身の体形も考慮してチェックしてみてくださいね。
着物の楽しさ伝えます。
一緒に『簡単×快適』きものLifeをはじめませんか?
 レッスンメニュー
レッスンメニュー├ おすすめレッスンメニュー 初級コース (4月生受付開始!!)
├ その他レッスンメニュー レッスンメニュー一覧
 ご予約状況
ご予約状況├ 2015年1月までのご予約状況

├ 2015年2月以降のご予約状況

├ 2015年3月以降のご予約状況

 その他
その他├ 着付(他装)サービス 着付(他装)サービス 価格一覧表
└ お問い合わせお申込み お問合せ/お申込みフォーム