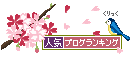本日の午前の生徒さんは、グループレッスン3回目。
着物のおさらいから始めました。
写真は後でもらえるので、それから書きますね。
午後のレッスンは、オーダーメイドレッスンでした。
「着物は着られるけど、お太鼓は結んだことがない」という生徒さんでした(前回までは)。
お太鼓⇒着物⇒二重太鼓⇒カラテア結びの順でマスターしていただく予定です。
前回は名古屋帯で、初めてお太鼓結びをされました。
そして、今日のレッスンも着物にお太鼓姿でお越しいただきました。
今回は、まずお太鼓結びのおさらいから・・・
なのですが、その間に、なんと着物で接客する仕事が受かったらしく、
週3回くらい着物を着てお仕事されていたそう。
面接で着付けを見てもらっての合格です。素晴らしい!!
ただ、お仕事着は帯の結び方が違うとのこと(帯留金具を使う結び方)。
多分、めちゃくちゃ混乱されたと思います。
そうなんです、お太鼓の結び方色々あります。
こういう時に、長年着付習ってて良かったって思います。
私自身が今覚えているやり方だけでも9通りあります。
巻き始めだけでも、色々あります。
肩に掛ける・反転させて肩に掛ける・脇から始める
結び方も、
結ぶ・ねじる、留める①、留める②
後は、関東手と関西手の違いもあります。
他には改良枕を使うのもありますね。
どれも一長一短あると思います。
だから、「絶対この結び方が正しい!」とは言いません。
その結び方のメリット・デメリット、うちの教室で教えている結び方のメリット・デメリットをお伝えさせていただきました。
その結果「どちらでやりますか?」とお尋ねしたら、
「前回教わった結び方をマスターしたい」とのことでしたので、
引き続き、ポイント柄の帯を使って(柄の配置などを含めて)再度レッスンしました。
そしてここで、あえての結びづらいポイント柄の帯の登場。
応用力のある生徒さんとお見受けしましたので、ちょっと深いところもお伝えしました。
その後は、盛りだくさん。
長襦袢までやりましょか・・・と言っていたのですが、結局着物までやりました。
通常レッスンの3倍くらいのエネルギー使ったわ(^^;
まずは、補整。
今お持ちの補整道具を生かしながら、足りないところを足していただきました。
たいてい、厚みが出るから…と補整を省かれる方が多いですが、
補整は大事。
適正な補整を入れることで細く美しく見えます。
そして、次に着姿を大きく左右する長襦袢の練習。
着崩れを防ぐには、紐の位置が大事!!
指一本の高さの違いで衿のくずれがなくなります。
長襦袢では規定回数をすることなく「長襦袢着れますので着物でお願いします」とのことで、
お仕事で週3回着られているということを考慮して、次に進みました。
というか、今日の生徒さん最初から長襦袢も着物も普通に着れはります。
前回に「なぜ習おうと思ったか?」とお尋ねしたときは、
「一度も習ったことがなくて我流でしてきたので」とのことでしたが、全然問題なさそうで。
途中、「あれ?なんかお悩みありましたっけ?」と聞いたくらい。
でも、その時には一つ目のお悩みポイントが解決していて、その後も、いくつか解決していただけたようで、良かったです。
特に、着物のおはしよりのもたつきが、前も後ろもなくなったことを喜んでくださいました。
わーい。私も嬉しい♡
うん、我ながらいい仕事したわ。
3倍の仕事しただけある、ある(笑)
ただ、今日は何度も繰り返して練習していないので、次回までに身体に馴染ませていただきたいなーと思ってます。
(週3回着られてたらめちゃくちゃ上達しはるとは思いますが![]() )
)
レッスン後にお友達と京都散策を楽しまれ、片道2時間かけてご帰宅後の生徒さんからメールいただきました。
「今日の着心地、最高でした。復習して身につけたいです」とのこと。
素晴らしい。
そういえば、前回も、
「長年引っかかっていたお悩みが1回のレッスンで解決するなんてー。」と喜んでいただきました(帯締めの締め方)。
着物着れるけど、着姿に納得できてない方は、一度レッスン受けてみてくださいね。
お悩み解決のために習いに行った教室で、
「そんな着方してたらそら着崩れますわー」とか言われたりするなら相当勇気がいるとは思いますが、それはないのでご安心を。
(長い長いレッスンレポになりました)
お悩み解決メニューはこちらから。
http://ameblo.jp/aoisakura-blog/entry-11923008732.html