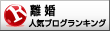悠真も無事進学をし、婚姻費用も決着が着いた。
慎ましいながらも、しばらくは穏やかに暮らせると思っていた矢先の叔父の訪問。
私は心が痛かった。
この1年9ヶ月、夫に散々な目に遭わされ、夫がどんな人間になってしまったのか、十分に思い知ったはずなのに。
それでもまだ、私の心は夫の心無い言動を目にし、耳にする度に傷付くのだ。
それは今でも夫を愛しているからではない。
もう、愛してなどいない。
かつて一度は家族として、愛し合う者として暮らした人間に捨てられたことを再確認して傷付くのだ。
この期に及んでも、傷つけられる度、その傷口からドクドクと血が流れ落ち、私は顔を歪める。
強くなりたい。
傷つくたびに、私はそう願う。
夫など、笑い飛ばせる自分になりたい。
それは叔父が訪ねて来た翌日の午後だった。
また玄関チャイムが鳴った。
まさか、また叔父ということはないよね……
カメラのモニターを見ると、今度は叔母、昨日の叔父の妻だった。
叔母とはスパーなどで会う度に、よく長話をした。
小さな家庭菜園で採れた野菜をもらったこともあった。
私たちの共通点は、浅見家の嫁という立場。
そして叔母は義父が大嫌いということ。
それだけで、盛り上がる共通の話題が私たち二人にはあった。
玄関ドアを開ける。
「麗子さん、久しぶり。昨日は旦那が突然来ちゃってごめんね」
「昨日はちょっとびっくりしました。どうぞ上がってください」
リビングに入ると、叔母はきょろきょろとあたりを見回した。
「ほらね、私が言ったとおりだわ」
「なんのことですか?」
お茶をテーブルに置きながら私は聞いた。
「実は、白寿会の後、私と旦那で健太郎を呼んで話をしたの。麗子さんとのこと」
「そうですか」
「そしたら健太郎が、一生懸命言うわけ。
麗子さんは家事を全くしないって。洗濯なんか一週間もしないって。それ聞いて私ピンと来たのよね。学生って部活あるから毎日体操着洗わなくちゃならないでしょ。それなのに、一週間も洗濯しないんて嘘だなって思ったの」
「そんなこと言ったんですか?」
「それから麗子はごみを捨てないから、リビングなんかに生ゴミの袋が積んであるだって。家中ゴミ屋敷だって」
「…ひどい。それはどこもかしこもピカピカなんて言いませんけど、普通に掃除もしています」
「いや、これくらいきれいにしてたら十分よ。うちなんかよりきれいだわ。やっぱり健太郎君のいうことが嘘だったね。旦那が突然来たのは、それを確かもに来たというのもあるの、本当にゴミ屋敷かどうか」
「どこでも家中見ていってもらって結構です」
「そんな嘘、言いふらされたら頭にくるわよね。
要は、麗子さんがそんなだらしない人だから、俺は違う人を選ばざる負えなかったって言いたいんだろうね。不倫を正当化するために。健太郎君、親戚に認めてもらいたくて必死よ」
「昨日、うちの旦那から聞いたと思うんだけど。おばぁちゃんの白寿会に健太郎君が不倫相手を連れて来たのよ」
「はい…聞きました」
「私ね、健太郎君が女を連れて座敷に入ってくるのを見てたんだけど、女の顔を一目見るなりぞっとしたよ。うわあこりゃダメだって」
「そんなに人相が悪い人なんですか?その女って」
「美人とか美人でないとか、そういうんじゃないのよ。なんていうか、性格がもろに顔に現れてるって言うか。この女を浅見家に入れたら全部取られるな、めちゃくちゃにされるなって思った」
「そんな人なんですか」
「でもね、なにも私だけがそう言ってるんじゃないのよ。親戚みんな同じ意見よ」
もちろん、私もダメ人間で、何一つ自慢できるところなどない。
しかし、一目見ただけで、ここまで他人に悪く言われる人を私は見たことがない。
「うちの旦那、プライド高いのは麗子さんも知ってるよね。うちの旦那が年下の親戚の嫁に土下座するなんてあり得ないと思わない?」
「はい。本当に昨日は驚きました……」
「そんなプライドなんていってられないほど、うちの旦那は危機感を感じたということ。その女を見ただけでね」
叔母はソファから下りると、床に土下座して言った。
「俺だけじゃ足りないと悪いから、お前も土下座して頼んで来いって旦那に言われたの。麗子さんお願い。なんとか耐えて、健太郎君とは離婚しないで!」
「…止めてください」
「麗子さん、本当のこと言うね。皆はね、麗子さんを助けるためにだけにそう言ってるんじゃないの。皆自分の保身のためにお願いしてるの」
「……」
「こんなこと言ってごめんね。
でも、ほんとのこと言った方が麗子さんも納得がいくと思うから。浅見家は代々親戚ぐるみで浅見家を守って来たの。先祖代々の土地もある。それを今管理してるのが健太郎の父親だから。今はよくても父親が死んだら、健太郎が管理することになる。そしたらあの女に全部やられる。みんなそれが怖いのよ」
「…わかります。私も浅見家の嫁でしたから」
「だからあの女を浅見家の嫁にするわけにはどうしてもいかないのよ。麗子さんが良いの。お願い助けると思って」
助ける?
夫に、女に、義父母にここまでのことをされて、なぜ私がその浅見家を助けなくてはならないのだろう。
そんな義理が私にあるのか。
ない。
私はもう浅見家の人間ではないのだから。
「…考えます」
今回もそう言ってごまかした。
それにしても…
自分を正当化するためとはいえ、ゴミ屋敷…
言葉がない。