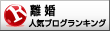約束の日の夕方
夫が9ヶ月ぶりに我が家に
帰って来た。
今日は一日
真夏の日差しを浴びてきましたと
言わんばかりの真っ赤な顔と
右手だけ白く手袋の跡をつけて。
ゴルフ…。
お父さんは
休みがないほど仕事が忙しい。
義母の具合が悪くて大変。
夫が家に帰らない理由を
私が子供達に
そう話していることなど
夫はとうの昔に忘れているのだろう。
そんな日に焼けた夫を見た
子供達はどう思っただろう。
あれほど子供たちに会うことを
拒んでいた夫。
私が夫に放った
「悪意の遺棄になるのでは」
という言葉は
思った以上の効果があったようだ。
夫は長い間
家に帰らないことを
悪びれる様子もなく
堂々と家に入ってくると
ソファーの真ん中に座り
ふんぞり返って足を組んだ。
9か月の間
家にも帰らず電話もせず
少しは子供たちに悪いという
気持ちはないのだろうか。
あったらきっと
こんな態度はとれないだろう。
夫の向かい側には悠真と美織。
ちょっと離れて
ダインイングテーブルに健斗と私。
もう健斗は夫の側には行かない。
夫が
「約束通りお前は席をはずせよ」
と言わんばかりに私を見た。
「ごめん
お母さんちょっと頭痛いから
薬飲んでくるね。
先にみんなで話してて」
私はそんな嘘をついた。
どうか
悠真がちゃんと自分の意見を
言えますように
と祈りながらリビングを出た。
同席したいのは山々だが
それが
夫が我が家に来る条件なのだから
しょうがない。
私は
寝室のベッドに腰を下ろした待った。
話し合いが終わるのを。
「親が子供にすべきことは
心配することじゃなく信じること」
いつか読んだ誰かの本の
そんな言葉が頭に浮かぶ。
一時間もした頃
玄関ドアが開く音がした。
慌てて出て行くと
夫が出て行った後だった。
「お父さん帰ったの?
どうだった?
お父さんとちゃんと話せた?」
リビングの
子供たちに尋ねた。
「お父さんさ
お母さんの言うとおり
俺の大学進学にかなり渋ってた」
と悠真。
やっぱりか…。
「それで?どうなったの?」
「でも最後には
結局昔決めたとおりでいいって
ことになったよ」
と悠真。
「え?じゃあ予定通り
東京の大学に行ってもいいって?」
「うん。
結局、最後にはそう言ってたよ」
「そうか、良かった。
ほんとに良かった。良かった」
「うん…」
「じゃあ、
後は受験勉強頑張るだけだね」
と安堵の笑顔の私。
良かった。
本当に良かった。
なんだかんだ言っても
夫はやっぱり父親なんだな。
離れてはいても
いざというときは
子供のためには
ちゃんとするんだな。
それはそうだ。
夫にとっても
悠真は17年間共に暮らし育てた
実の息子なのだから。
夫は
不倫してても
家に帰らなくても
子供の前でちゃんと父親として
ふるまってくれた。
そう思った私は
どれだけほっとしたことか。
いつも通り
子供達はダイニングテーブルで
夕食を食べ始めた。
私は
ソファーの前の
テーブルの裏から
子供達に気付かれないように
ICレコーダーをそっと取り外す。
夫が来る前
私は夫がソファーに
座るであろうことを想定し
テーブルの裏にICレコーダーを
貼り付けておいたのだ。
ここならもれなく
みんなの声が録音できるはずだから。
私はICレコーダーを
そっとエプロンのポケットにしまった。
夜
私は一人の寝室で
夫と子供達の会話を聞いた。
案の定
横柄で見下したような夫の物言い。
初めはおどおどと
話していた悠真の声。
「お前、本当に大学行って
勉強する気あんのか?」
「あるよ…」
「ほんとうか?
遊びたくて大学行くヤツに
出す金なんかうちには
一円もないからな」
「俺、そんなんじゃないから…」
「お前大学行ったってどうせ
勉強なんか真面目に
やんないだろ?
勉強なんか好きじゃないだろ?
な?
大学なんて行かなくてもいいだろ?」
「……」
レコーダーの中の
夫の言葉に私は凍りつく。
なにこれ…
まるで恫喝。
夫はこんな言葉を
子供達の前で吐いたのか。
しばらくして
そんな夫の言葉に反撃したのは
意外にも普段はおとなしい
美織だった。
「お父さんもおじいちゃんも
お兄ちゃんが小学生の時から
絶対に大学に行けって
ずっと言ってきたじゃん。
それを今更そんなこと言うなんて
ちょっと、ひどいんじゃない?」
「そうだよ。
それにお兄ちゃんは一生懸命
毎日受験勉強してるよ。
お父さん家にいないから
お兄ちゃんが勉強してるとこ
見てないだけだよ」
と健斗。
「お父さん
ここに行くなら大学行っても良いって
前に何度も俺に言ったよね?」
と悠真。
「あ!
私もそれ聞いた!
お父さん、お兄ちゃんにそう言ってた」
「僕も聞いた!絶対に言った!」
と健斗。
「お父さん
俺はお父さんと約束したとおり
この大学を受けて建築家を目指す。
今更やっぱり大学行くななんて
言いっこなしだよ。
それはないよ。
ちゃんと約束守ってよ」
と悠真。
「そうだよ。守ってよ」
と美織。
「そうだ!守れ!守れ!」
と健斗。
レコーダーの中で
兄弟が協力していた。
いつもはけんかばかりの
美織と健斗が
兄のために戦っていた。
私は泣いた。
思いもしなかった援護射撃が
嬉しかった。
そして申し訳なかった。
だから、泣いた。
レコーダーはまだ続く。
「お父さん!
噓つきはいけないんだぞ」
と健斗。
「親なんだから
子供にした約束はちゃんと守ってよ。
なんか今さら
そんなこと言うお父さん、超ダサ」
と美織。
「そういうの虐待っていうんじゃないの。
児童虐待は児童相談所って先生言ってた」
と健斗。
「なんだ
お前達寄ってたかって!
わかったよ。
じゃお前の好きに
受験すればいいだろ!」
と夫。
「ほんとに俺
この大学受けていいんだね?
ちゃんとお金出してくれるんだね?」
「しつこいな!わかったよ!
行っていいって言ってるだろ!
何度も聞くな!
ただし浪人は絶対にさせないからな。
わかったな!」
レコーダーの中の夫は
はっきりとそう言った。
その大学に行ってもいいと。
お金を出すと。
実は私はこの一言を
録音するために
夫を我が家に呼び出したのだ。
この録音が
果たして法的に有効か無効か
そんなことはわからない。
でもこれは
この先夫が
やっぱり進学費用は出さないと
言い出したときのための御守り。
こちらの切り札となるだろう。
今はこの切り札を
使わずにすむことを
心から祈るばかりだが。
よし
これで悠真を希望通りの大学に
進学させてやれる。
もう進学費用の心配はない。
その時はそう思ったのだ。
思ったのだった。