『田園に死す』雑記帳(1)
And life is like a dream
Dream
The dream I long to find
The movie in my mind
(ミュージカル「ミス・サイゴン/The movie in my mind」より)
◆
もし寺山が生きていたら74歳の誕生日となったであろう2009年12月10日に、流山児★事務所『田園に死す』(原作:寺山修司、脚色・構成・演出:天野天街、音楽:J・A・シィザー、企画・出演:流山児祥)が開幕した。寺山修司の監督した長編映画『田園に死す』(制作・原作・台本・演出:寺山修司。撮影:鈴木達夫。音楽:J・A・シーザー。美術:粟津潔。意匠:花輪和一。出演:八千草薫、春川ますみ、新高恵子、高野浩幸、菅貫太郎、他。制作:九条映子、ユミ・ゴヴァーズ。配給:ATG)が公開された1974年(昭和49年)12月28日からは、約35年後にあたるタイミングでもある。
映画『田園に死す』は、通常「寺山の自伝的映画」と紹介されるが、注意すべきは、けっして自伝映画ではないということだ。あくまで自伝「的」、あるいは自伝「風」映画である。「私」の過去を映画にしようとするものの、そこに真実を描かなかった現在の「私」が、過去の「私」に真実を伝えようとするメタ・ムーヴィーである。しかし、そこで語られる真実もまた、実は真実ではないということを、現在の観客たるわたしたちは知っている。
◆
「これは一人の青年の自叙伝の形式を借りた虚構である。われわれは歴史の呪縛から解放されるためには、何よりも先ず、個の記憶から自由にならなければならない。この映画では、一人の青年の“記憶の修正の試み”を通して、彼自身の(同時にわれわれ全体の)アイデンティティの在所を追求しようとするものである」(寺山修司/「『田園に死す』演出ノート」より)
◆
「終わったことは全て虚構に過ぎない」「歴史はどうにでも組み立て直すことが可能である」と考えていた寺山は、自身の過去も映画の中で組み立て直そうとする。しかし、組み立て直そうとしても完全に組み立て直しきれない「私」もまた、映画の「私」の中に、そして作者=寺山自身の中に潜んでいるらしい。
◆
「どこからでもやりなおしは出来るだろう。母だけではなく、私さえも、私自身がつくり出した一片の物語の主人公にすぎないのだから。そして、これは、たかが映画なのだから。だが、たかが映画の中でさえ、たった一人の母も殺せない私自身とは、いったい誰なのだ?!生年月日、昭和49年12月10日、本籍地、東京都新宿区新宿字恐山!!」(寺山修司/『田園に死す』シナリオより)
◆
この映画を通じて、あるいはこの映画のベースにもなっている彼の自伝的歌集(もちろん、これも自伝を装った自伝「的」歌集である)『田園に死す』において、寺山は、「私」の解体を試みる。では、なぜ「私」は解体されなければならないのか。それは、「私」=「自我」の重力に呪縛されていたからである。その背景には、「死」と隣り合わせの健康問題、母親との複雑な関係性、などなど、寺山ならではの特殊な事情が色々あったと考えられる。そんな「私」を解体し、自由になるために、寺山は、映画という表現媒体を夢のように機能させたのではないだろうか。
自身の欲望やら原風景やら幻視的オブジェやら現実的記憶やらを、フィルムの中に織り込んでみせた。フェデリコ・フェリーニの『8 1/2』や『アマルコルド』の手法をさらに過激に推し進めたともいえよう。これによって、たしかに「私」の解体は進められたのかもしれないが、本当に個の記憶から自由になったといえるのだろうか。そのことでますます「私」の内的な全体像が浮かび上がるというパラドックスが生じたとはいえないだろうか。かくして「私」はいよいよ謎を深めるばかりなのだ。
とはいえ映画『田園に死す』は、寺山修司があらゆるジャンルで繰り広げた表現活動の中でも、最高峰の作品と一般的に評されている。彼の思想や方法論さらには内面的主題が詰め込まれているうえ、ヴィジュアルも音楽も撮影も、すべて独特で完成度が高い。公開当時、キネマ旬報1975年日本映画ベスト10では、第1位『ある映画監督の生涯 溝口健二の記録』監督:新藤兼人(ATG)、以下、第2位『祭りの準備』監督:黒木和雄(ATG)、第3位『金環蝕』監督:山本薩夫(大映)、第4位『化石』監督:小林正樹(東宝)、第5位『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』(松竹)といった名作群のひしめきあう中、『田園に死す』は第6位につけている。尋常ならざる幻想実験映画としてはまあ健闘といってよいかもしれぬ(それにしてもATGの多いことよ)。
わたしは、公開から4年後、たまたま学校をさぼり観た。うぶで多感な高校生にとって、これほど圧倒された映画は他になかった。以来、現在に至るまで生涯のベスト1映画である(流山児祥氏に言ったら「変わってるねえ」と言われた)。この映画をきっかけに、寺山の他の映画や演劇(劇団天井桟敷)なども観るようになるが、『田園に死す』を超える衝撃はなかった。併せて、J・A・シーザーのことも、音楽の仕事を中心にそこそこ追っかけているが、わたしの中での最高傑作はやはり『田園に死す』の音楽なのだ(ジャパニーズプログレファンの間では御詠歌ロックの金字塔なども言われているらしい)。映画を観た頃には既にサントラ盤(アナログレコード)は入手不可能だったが、大学に入ると増山さんという先輩が所持していることを知った。そこで無理を言ってお借りし、テープにダビングさせてもらった。以来、2002年8月にデジタル・リマスタリングでCD復刻されるまで、20年近く、自分にとっては最も貴重な音源として大変役立っていた(親切だった増山先輩には改めて深謝!)。
【送料無料】田園に死す 【CD】

¥2,646 楽天 ※モバイル非対応
「2009年12月に流山児★事務所で天野天街が寺山修司作品を手がける」、しかもそれがわたしにとって最も愛着の強い映画、『田園に死す』だと知らされたのは1年ほど前のことである。わたしの心境は少々複雑だった。『田園に死す』は、過去にも幾度か舞台化されたことがある。わたしは、その中の1つ、劇団☆APB-Tokyoの上演を3年前に観たことがある。寺山への熱烈なリスペクト精神が、この難物に挑む心意気やよし、されど、戦略性の乏しい分、どうしても粗がめだってしまい、ノスタルジーの域を超えるものにはなりえてなかった。まあ、そういうものはまだ微笑ましい。しかし、天野が手がけるとなれば、微笑んでもいられない。というのも、天野天街は、わたしが最も強く興味を抱き続けてきた演劇作家だからだ。
天野天街。名古屋を拠点に、劇団少年王者舘を主宰。極めて独特な作風の舞台作品の劇作・演出を数多く手かげてきた。また、もともと自劇団のチラシのために始めた独自のコラージュ美術が注目され、数多くの演劇公演の宣伝美術や、書籍の装丁に起用されている。さらには、映像作家としても活躍。なかでも1994年監督作品『トワイライツ』はオーバーハウゼン国際短編映画祭で日本人としてグランプリ初受賞(ちなみに寺山修司は1975年のオーバーハウゼン映画祭において『迷宮譚』で銀賞)。このように、ハイブリッドな多面体というべき天野天街が、寺山という大いなるハイブリッド多面体の、集大成とも結晶体とも称せられる映画作品を、一体どのように扱うというのだろう。まず、そう思った。
【20%OFF!】トワイライツ(DVD)

¥2,940 楽天 ※モバイル非対応
天野はかつて、澁澤龍彦『高丘親王航海記』、鈴木翁二『マッチ一本ノ話』、しりあがり寿『真夜中の弥次さん喜多さん』の舞台化において、原作の風味を損ねることなく、大胆に自らの演劇ワールドへと移植/転換/翻訳させることに成功せしめている。とはいえ、今回の取り組み相手は、寺山修司の映画『田園に死す』という、相当に手強い難物ではないか。…しかし、である。天野の思考回路は、まるで「夢」の如し。作劇においても「夢」の技法を駆使することで、「夢」的な原作を、舞台上の「夢」として描くことを可能たらしめてきた。
もちろん天野のソレは、陳腐で凡庸な「夢」的表現とは一線を画す。フロイトは「夢」の仕事の例として、置換・圧縮・視覚化・象徴化などを挙げたが、これらはとどのつまり「夢」の「編集」作業と呼べるだろう。天野は、自らまるごとマルチな「編集」アプリケーションソフトと化して、ストーリー、台詞、美術、音、文字、身体、さらには時間、空間、記憶、演劇的決まり事に至るまで、あらゆるリソースを、編集可能なマテリアルとして扱うことで、大胆な「編集」作業を進める。そこでは時間を行ったり来たりさせることなど当たり前。一人の登場人物が複数に分裂するなども日常茶飯事だ。切ったり貼ったり読み換えたりひっくり返したりのコラージュ的「編集」作業の過程において、事物に潜む思いがけない本質が偶然浮かび上がってくる。それらをさらにつなぎあわせて、リアルな夢の感触を構築する。そうなるまで、たとえ「遅筆」の誹りを受けようと、天野は執拗なまでに、「編集」を繰り返すのだ。すなわち、彼こそは「夢の編集職人」であり「偏執狂的編集狂」なのである。
そこで思い出されるのは、寺山修司の諸作品もまた、コラージュ性ないし「編集」性に満ち溢れていることである。いまや国語の教科書にも載るほどに有名な「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国やありや」(第一歌集『空には本』「祖国喪失」より)という歌も、富澤赤黄男の俳句「一本のマッチをすれば湖は霧」「めつむれば祖国は蒼き海の上」をコラージュしたものではないかと言われている。そのため盗作問題にまで発展したこともあったが、結果的として圧倒的に強烈な印象を人々に刻印したのは寺山の「マッチ擦る…」の短歌のほうであって、つまりは卓抜した「編集」能力の勝利といえる。天野との違いといえば、寺山の仕事のほうが、諸局面において教養人・知識人としての意識的な力を感じる。天野のほうは幾分、無意識的な作業の中から思いがけない偶然の効果を生み出すことが得意のように見受けられる。
ともかくも、寺山という編集職人の仕事を、天野という編集職人がさらに「編集」すると、どうなるのか。しかも『田園に死す』は、寺山において映画=夢ともいえる。その夢の土俵で、夢職人たる天野はどのような戦略を描き、どのような仕掛けを発動させたのだろうか。
◆
昭和十年十二月十日に
ぼくは不完全な死体として生まれ
何十年かかって
完全な死体となるのである
そのときが来たら
ぼくは思いあたるだろう
青森県浦町字橋本の
小さな陽のいい家の庭で
外に向かって育ちすぎた桜の木が
内部から成長をはじめるときが来たことを
子供の頃、ぼくは
汽車の口真似が上手かった
ぼくは
世界の涯てが
自分自身の夢のなかにしかないことを
知っていたのだ
(寺山修司「懐かしのわが家」より)
◆
寺山修司は、映画『田園に死す』が封切られてから約8年半後の1983年(昭和58年)5月4日午後12時5分に、阿佐ヶ谷の河北総合病院にて死んだ。常に「死」と隣り合わせだった寺山にとって、それは「完全な死体」になることだった。その一方で、彼は「世界の涯てが自分自身の夢の中にしかない」とも書いた。そこで天野がまず企てたのは、寺山の夢=映画の内側に入り込み、「世界の涯て」=寺山の死の瞬間に時計の針をセットしたことだった。そうして、果たして本当に夢の中に「世界の涯て」があるのかどうかを問うたのではないだろうか。
…少々疲れたので、今日はここまで。思わせぶりなかんじで止めて申し訳ないが、続きは次回に。気分転換に、youtube動画をひとつ。八千草薫の「皇潤数え歌」にのせて、映画『田園に死す』の世界に軽く触れてください。
田園に死す 【低価格再発売】 [DVD]/菅貫太郎,高野浩幸,八千草薫
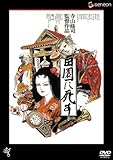
¥3,990 Amazon.co.jp
Dream
The dream I long to find
The movie in my mind
(ミュージカル「ミス・サイゴン/The movie in my mind」より)
◆
もし寺山が生きていたら74歳の誕生日となったであろう2009年12月10日に、流山児★事務所『田園に死す』(原作:寺山修司、脚色・構成・演出:天野天街、音楽:J・A・シィザー、企画・出演:流山児祥)が開幕した。寺山修司の監督した長編映画『田園に死す』(制作・原作・台本・演出:寺山修司。撮影:鈴木達夫。音楽:J・A・シーザー。美術:粟津潔。意匠:花輪和一。出演:八千草薫、春川ますみ、新高恵子、高野浩幸、菅貫太郎、他。制作:九条映子、ユミ・ゴヴァーズ。配給:ATG)が公開された1974年(昭和49年)12月28日からは、約35年後にあたるタイミングでもある。
映画『田園に死す』は、通常「寺山の自伝的映画」と紹介されるが、注意すべきは、けっして自伝映画ではないということだ。あくまで自伝「的」、あるいは自伝「風」映画である。「私」の過去を映画にしようとするものの、そこに真実を描かなかった現在の「私」が、過去の「私」に真実を伝えようとするメタ・ムーヴィーである。しかし、そこで語られる真実もまた、実は真実ではないということを、現在の観客たるわたしたちは知っている。
◆
「これは一人の青年の自叙伝の形式を借りた虚構である。われわれは歴史の呪縛から解放されるためには、何よりも先ず、個の記憶から自由にならなければならない。この映画では、一人の青年の“記憶の修正の試み”を通して、彼自身の(同時にわれわれ全体の)アイデンティティの在所を追求しようとするものである」(寺山修司/「『田園に死す』演出ノート」より)
◆
「終わったことは全て虚構に過ぎない」「歴史はどうにでも組み立て直すことが可能である」と考えていた寺山は、自身の過去も映画の中で組み立て直そうとする。しかし、組み立て直そうとしても完全に組み立て直しきれない「私」もまた、映画の「私」の中に、そして作者=寺山自身の中に潜んでいるらしい。
◆
「どこからでもやりなおしは出来るだろう。母だけではなく、私さえも、私自身がつくり出した一片の物語の主人公にすぎないのだから。そして、これは、たかが映画なのだから。だが、たかが映画の中でさえ、たった一人の母も殺せない私自身とは、いったい誰なのだ?!生年月日、昭和49年12月10日、本籍地、東京都新宿区新宿字恐山!!」(寺山修司/『田園に死す』シナリオより)
◆
この映画を通じて、あるいはこの映画のベースにもなっている彼の自伝的歌集(もちろん、これも自伝を装った自伝「的」歌集である)『田園に死す』において、寺山は、「私」の解体を試みる。では、なぜ「私」は解体されなければならないのか。それは、「私」=「自我」の重力に呪縛されていたからである。その背景には、「死」と隣り合わせの健康問題、母親との複雑な関係性、などなど、寺山ならではの特殊な事情が色々あったと考えられる。そんな「私」を解体し、自由になるために、寺山は、映画という表現媒体を夢のように機能させたのではないだろうか。
自身の欲望やら原風景やら幻視的オブジェやら現実的記憶やらを、フィルムの中に織り込んでみせた。フェデリコ・フェリーニの『8 1/2』や『アマルコルド』の手法をさらに過激に推し進めたともいえよう。これによって、たしかに「私」の解体は進められたのかもしれないが、本当に個の記憶から自由になったといえるのだろうか。そのことでますます「私」の内的な全体像が浮かび上がるというパラドックスが生じたとはいえないだろうか。かくして「私」はいよいよ謎を深めるばかりなのだ。
とはいえ映画『田園に死す』は、寺山修司があらゆるジャンルで繰り広げた表現活動の中でも、最高峰の作品と一般的に評されている。彼の思想や方法論さらには内面的主題が詰め込まれているうえ、ヴィジュアルも音楽も撮影も、すべて独特で完成度が高い。公開当時、キネマ旬報1975年日本映画ベスト10では、第1位『ある映画監督の生涯 溝口健二の記録』監督:新藤兼人(ATG)、以下、第2位『祭りの準備』監督:黒木和雄(ATG)、第3位『金環蝕』監督:山本薩夫(大映)、第4位『化石』監督:小林正樹(東宝)、第5位『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』(松竹)といった名作群のひしめきあう中、『田園に死す』は第6位につけている。尋常ならざる幻想実験映画としてはまあ健闘といってよいかもしれぬ(それにしてもATGの多いことよ)。
わたしは、公開から4年後、たまたま学校をさぼり観た。うぶで多感な高校生にとって、これほど圧倒された映画は他になかった。以来、現在に至るまで生涯のベスト1映画である(流山児祥氏に言ったら「変わってるねえ」と言われた)。この映画をきっかけに、寺山の他の映画や演劇(劇団天井桟敷)なども観るようになるが、『田園に死す』を超える衝撃はなかった。併せて、J・A・シーザーのことも、音楽の仕事を中心にそこそこ追っかけているが、わたしの中での最高傑作はやはり『田園に死す』の音楽なのだ(ジャパニーズプログレファンの間では御詠歌ロックの金字塔なども言われているらしい)。映画を観た頃には既にサントラ盤(アナログレコード)は入手不可能だったが、大学に入ると増山さんという先輩が所持していることを知った。そこで無理を言ってお借りし、テープにダビングさせてもらった。以来、2002年8月にデジタル・リマスタリングでCD復刻されるまで、20年近く、自分にとっては最も貴重な音源として大変役立っていた(親切だった増山先輩には改めて深謝!)。
【送料無料】田園に死す 【CD】

¥2,646 楽天 ※モバイル非対応
「2009年12月に流山児★事務所で天野天街が寺山修司作品を手がける」、しかもそれがわたしにとって最も愛着の強い映画、『田園に死す』だと知らされたのは1年ほど前のことである。わたしの心境は少々複雑だった。『田園に死す』は、過去にも幾度か舞台化されたことがある。わたしは、その中の1つ、劇団☆APB-Tokyoの上演を3年前に観たことがある。寺山への熱烈なリスペクト精神が、この難物に挑む心意気やよし、されど、戦略性の乏しい分、どうしても粗がめだってしまい、ノスタルジーの域を超えるものにはなりえてなかった。まあ、そういうものはまだ微笑ましい。しかし、天野が手がけるとなれば、微笑んでもいられない。というのも、天野天街は、わたしが最も強く興味を抱き続けてきた演劇作家だからだ。
天野天街。名古屋を拠点に、劇団少年王者舘を主宰。極めて独特な作風の舞台作品の劇作・演出を数多く手かげてきた。また、もともと自劇団のチラシのために始めた独自のコラージュ美術が注目され、数多くの演劇公演の宣伝美術や、書籍の装丁に起用されている。さらには、映像作家としても活躍。なかでも1994年監督作品『トワイライツ』はオーバーハウゼン国際短編映画祭で日本人としてグランプリ初受賞(ちなみに寺山修司は1975年のオーバーハウゼン映画祭において『迷宮譚』で銀賞)。このように、ハイブリッドな多面体というべき天野天街が、寺山という大いなるハイブリッド多面体の、集大成とも結晶体とも称せられる映画作品を、一体どのように扱うというのだろう。まず、そう思った。
【20%OFF!】トワイライツ(DVD)

¥2,940 楽天 ※モバイル非対応
天野はかつて、澁澤龍彦『高丘親王航海記』、鈴木翁二『マッチ一本ノ話』、しりあがり寿『真夜中の弥次さん喜多さん』の舞台化において、原作の風味を損ねることなく、大胆に自らの演劇ワールドへと移植/転換/翻訳させることに成功せしめている。とはいえ、今回の取り組み相手は、寺山修司の映画『田園に死す』という、相当に手強い難物ではないか。…しかし、である。天野の思考回路は、まるで「夢」の如し。作劇においても「夢」の技法を駆使することで、「夢」的な原作を、舞台上の「夢」として描くことを可能たらしめてきた。
もちろん天野のソレは、陳腐で凡庸な「夢」的表現とは一線を画す。フロイトは「夢」の仕事の例として、置換・圧縮・視覚化・象徴化などを挙げたが、これらはとどのつまり「夢」の「編集」作業と呼べるだろう。天野は、自らまるごとマルチな「編集」アプリケーションソフトと化して、ストーリー、台詞、美術、音、文字、身体、さらには時間、空間、記憶、演劇的決まり事に至るまで、あらゆるリソースを、編集可能なマテリアルとして扱うことで、大胆な「編集」作業を進める。そこでは時間を行ったり来たりさせることなど当たり前。一人の登場人物が複数に分裂するなども日常茶飯事だ。切ったり貼ったり読み換えたりひっくり返したりのコラージュ的「編集」作業の過程において、事物に潜む思いがけない本質が偶然浮かび上がってくる。それらをさらにつなぎあわせて、リアルな夢の感触を構築する。そうなるまで、たとえ「遅筆」の誹りを受けようと、天野は執拗なまでに、「編集」を繰り返すのだ。すなわち、彼こそは「夢の編集職人」であり「偏執狂的編集狂」なのである。
そこで思い出されるのは、寺山修司の諸作品もまた、コラージュ性ないし「編集」性に満ち溢れていることである。いまや国語の教科書にも載るほどに有名な「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国やありや」(第一歌集『空には本』「祖国喪失」より)という歌も、富澤赤黄男の俳句「一本のマッチをすれば湖は霧」「めつむれば祖国は蒼き海の上」をコラージュしたものではないかと言われている。そのため盗作問題にまで発展したこともあったが、結果的として圧倒的に強烈な印象を人々に刻印したのは寺山の「マッチ擦る…」の短歌のほうであって、つまりは卓抜した「編集」能力の勝利といえる。天野との違いといえば、寺山の仕事のほうが、諸局面において教養人・知識人としての意識的な力を感じる。天野のほうは幾分、無意識的な作業の中から思いがけない偶然の効果を生み出すことが得意のように見受けられる。
ともかくも、寺山という編集職人の仕事を、天野という編集職人がさらに「編集」すると、どうなるのか。しかも『田園に死す』は、寺山において映画=夢ともいえる。その夢の土俵で、夢職人たる天野はどのような戦略を描き、どのような仕掛けを発動させたのだろうか。
◆
昭和十年十二月十日に
ぼくは不完全な死体として生まれ
何十年かかって
完全な死体となるのである
そのときが来たら
ぼくは思いあたるだろう
青森県浦町字橋本の
小さな陽のいい家の庭で
外に向かって育ちすぎた桜の木が
内部から成長をはじめるときが来たことを
子供の頃、ぼくは
汽車の口真似が上手かった
ぼくは
世界の涯てが
自分自身の夢のなかにしかないことを
知っていたのだ
(寺山修司「懐かしのわが家」より)
◆
寺山修司は、映画『田園に死す』が封切られてから約8年半後の1983年(昭和58年)5月4日午後12時5分に、阿佐ヶ谷の河北総合病院にて死んだ。常に「死」と隣り合わせだった寺山にとって、それは「完全な死体」になることだった。その一方で、彼は「世界の涯てが自分自身の夢の中にしかない」とも書いた。そこで天野がまず企てたのは、寺山の夢=映画の内側に入り込み、「世界の涯て」=寺山の死の瞬間に時計の針をセットしたことだった。そうして、果たして本当に夢の中に「世界の涯て」があるのかどうかを問うたのではないだろうか。
…少々疲れたので、今日はここまで。思わせぶりなかんじで止めて申し訳ないが、続きは次回に。気分転換に、youtube動画をひとつ。八千草薫の「皇潤数え歌」にのせて、映画『田園に死す』の世界に軽く触れてください。
田園に死す 【低価格再発売】 [DVD]/菅貫太郎,高野浩幸,八千草薫
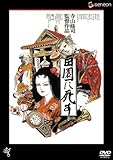
¥3,990 Amazon.co.jp