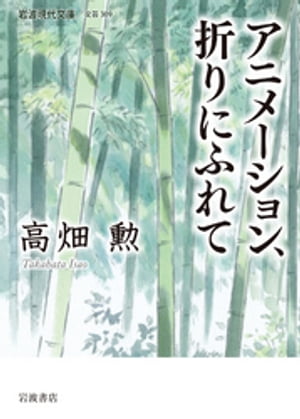昨日、不覚にも涙しながら観てしまいました笑
平成たぬき合戦ぽんぽこは、小さいころ、
えーそんなのジブリっぽくない、しかも団地の建設に反対する狸って、なんか説教みたい
なんとなくストーリーが想像できちゃう、面白くなさそう
という印象で1度も観たことがなかったし、
なんなら、昔よく放送されていた男はつらいよを避けるように笑
なんかしぶいし、古くさいし、と敬遠していたんです。
そして、なんと大人になってからもそれは変わらず(恥ずかしい)
最近ネットフリックスを外国のVPNにつなぎながら、ジブリを観ていたのですが
そのときにも、ぽんぽこは完全に優先順位が最後だったのです
先日、嫌々ゲド戦記を観たらとんでもない18年間の神経症笑 に気づくきっかけがかくれていたので
ちゃんと謙虚に、ぽんぽこも観ようということで
観始めたのですが、どうも最初の3分で見る氣が失せちゃう笑
いつも、パヤオさんの、あの恍惚感にひたれるようなうっとりとするような感じを求めていたので
それに比べちゃうと、あんまり食いつきが弱いのです
そして、やっと昨日もう一度みはじめたら、もう、脚本、ストーリーが凄すぎて、これは子ども向けの
おちゃらけたアニメの姿をした、強烈に大人向けの作品じゃないか、、と。。
以前の、脳内どころか全身ニューエイジ思想だった私だったら、こうやってネガティブなストーリーを見せて
民衆に、現実はそこそこにねって諦めるように洗脳しているんだぐらいに思っていました爆笑
まだ観ていない方は、高畑勲さんの「アニメーション、折にふれて」を読んでから、ぽんぽこを観るのがおすすめですが
なぜかと言うと、作中の、おかしさ、ばかばかしさの理由が、技術のなさからではなく
観客が、アニメはアニメ、現実は現実と、しっかり線引きできるようにという配慮からであることが判るからです。
たしかに、パヤオさん作品のように、没入感はありません、没入するあまり映画が終わってからまるで自分がその主人公本人になったような感覚がするようなこともありません、
ああ、アニメだな、という感覚はありつつも、アニメだからこそできる、キャラクターのタッチが急に変わったり、という表現を遊び心たっぷりで表現されているのはすごいと思いました。
しかも途中から、どんな展開になっていくのか、全く予想できなくなっていました。
相対評価に病的にこだわってしまっていた私は、つい、高畑勲さんが東大で学んだということを思い出しちゃうのですが
やっぱり、東大出身者の人がかつ、才能と鋭い洞察の人が本気でアニメを作るとこうなるんだなと
全体的にコミカルでありながら、たぬきのことを言っているんではなくて、まるで令和の日本人を言っているかのよう
しかもはっとしたのは
化けられるたぬきもいるけど、化けられないたぬきもいるという設定、、、
能力のある人間は都会で人間に化けて生き残っていけるけど、能力のない人間は、、、
たぬきのことを言っているようで、まさに現代の日本人や先進国の競争状態がぴったりあてはまる汗
切ないけれど、最後はやけになって、幻で、昔の緑あふれる情景を創り出す、
そのシーンは、予定外になんだか泣けてしまいました笑
どんどんテクノロジーが進んで、もうこういう自然溢れる世界は見えないかもしれないし
自分は、そういう自然溢れる世界で生きていたいのかもしれない