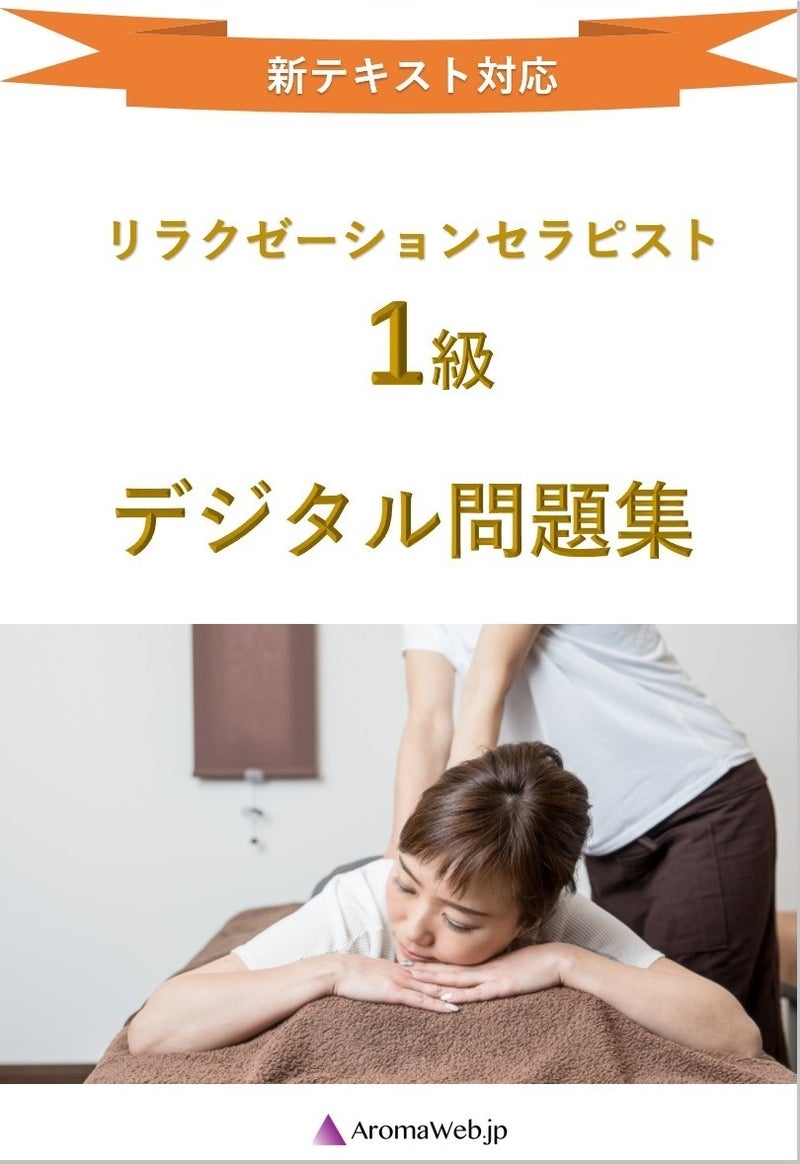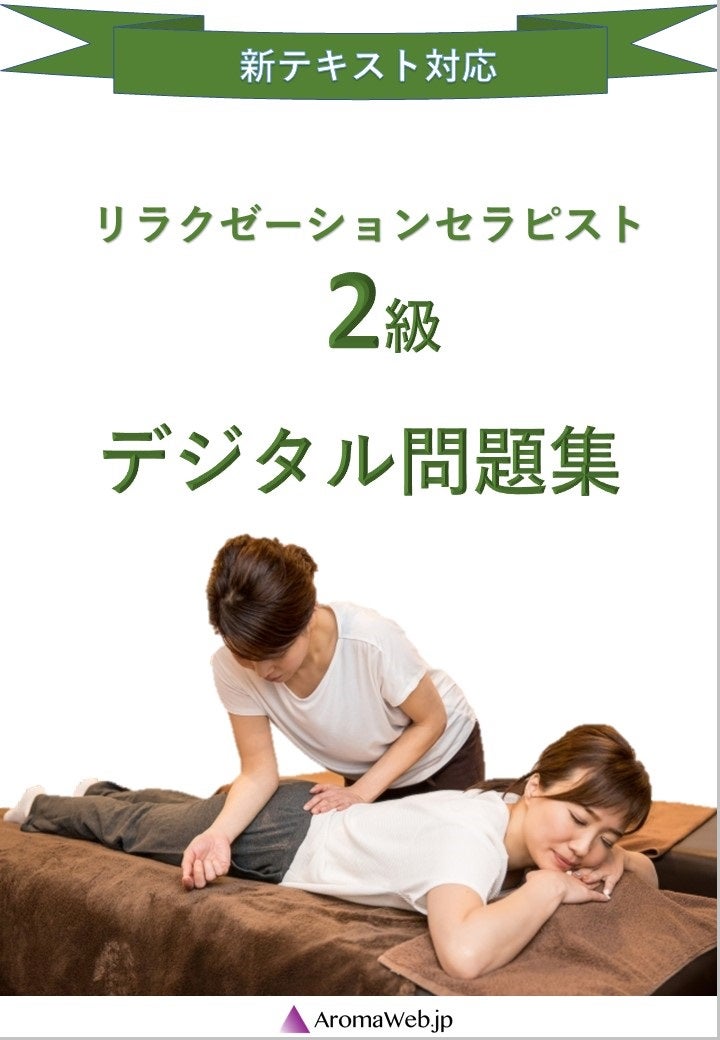1級試験で実際に出題された問題をレビューしています。27問目。
「第II章 スペースマネジメント」の第3節「リラクゼーションスペースの運営」からは3問でましたが、今日はその2問目です。

売り上げを構成する要素で(A)に入るものを選びなさい
売上 = 客単価 x 1日の来店客数 x (A)
1.固定費
2.利益
3.休日日数
4.営業日数

これは「8 資産管理」からの出題です。
客単価は、お客様が支払う平均金額。
それに一日のご来店客数の平均を掛けると一日の売上。
一日の平均売上に一年間の営業日数を掛けると年間の売上、一ヵ月の営業日数を掛けると月間の売上予想額になります。
当たり前ですよね。この問題自体はとくに解説はいらないと思います。

ですが、ちょっと変だな?と思ったのは、問題文の「売上」。
これ、何の売上でしょう?
「本日の売上」なら、平均値の客単価じゃなくて、日計表を集計すればいいですよね。
この問題文でいう「売上」は、実際の現ナマの売上ではなく、経営指標としての売上です。
こういうバーチャルな数字を駆使して、経営戦略を立てていくための会計を「管理会計」といいます。
一方でレジに出し入れする現ナマや在庫をカウントするのは「財務会計」。
財務会計は経理担当者の仕事で、管理会計は経営者の仕事です。
資産管理のセクションでこういうバーチャルな売上の計算式が設問に上がるのは、スタッフも経営者目線を持て、ということなんでしょう。
であれば、経営戦略を考えるうえで役に立つ数字、売上原価率とか販管費率とか、もう少し突っ込んでもよかったかもしれません。

もうひとつ、このセクションで気になったのは変動費と固定費について。
テキストでは、
・変動費=売り上げに比例して発生する費用。広告宣伝費、材料費、リネン費用など
・固定費=売り上げの増減に関わらず発生する費用。人件費、家賃、利息、水道光熱費など
となっていて、人件費は固定費になっています。
あれ?人件費って固定費なの?
新型コロナでお店は臨時休業中だけど歩合制だから給料はゼロ、セラピストの人件費は発生しないはず・・・
と思ったあなた、スルドイ!です^^;
人件費は給与として固定的に従業員に支払われる費用のこと。
多くのセラピストは業務委託契約を結んだ個人事業主なので、セラピストへの支払いは人件費ではなく業務委託費です。
同じ業務委託でも、清掃や産廃なら毎月の契約額は決まっているでしょうから固定費です。
しかし、セラピスト報酬は出来高での契約になっていれば変動費になります。

セラピストの費用はほぼ100%、労働に対して支払われるお金。
なのに人件費ではない。
ここは労基法上でもかなりなグレーゾーンです。
よく問題になる「偽装請負」という契約形態があります。
A社からB社に業務委託契約で仕事を発注しているのに、実際にはB社が自社の社員をA社に派遣、A社の指揮命令下で働かせるという労働形態を指します。
B社は自社の社員の面倒をみておらず、A社は社会保険料などの負担することなしにB社社員に指揮命令を行う。
これをやられるとB社の社員は自分の会社には守ってもらえず、A社からは雇用契約上のリスクなしにこき使われ、という状況になります。
A社の経営者もB社の経営者もどちらも人を雇うリスクを負わず、その結果、労働者が「奴隷」身分に落ちてしまうのが「偽装請負」です。
ひどいでしょ。でもよくあります。もちろん違法です。

業務委託費は、本来、労働の対価とイコールではありません。
委託を受ける側の独自ノウハウやら経費やら利益など、諸々が含まれる費用です。
しかし個人事業主への業務委託費は、現実には「労働の対価」と同じ。
個人事業主としての経営上の裁量(=独自の知恵と工夫で利益を増やす)もほとんどありません。
ここが「偽装委託」なのではないか?と思わせるポイントです。

ウーバーイーツっていうサービスをご存知ですよね。
ネットで注文を受けて「お持ち帰り」を運ぶ、いわば出前のクラウドサービスです。
これも実際に運んでいる人は従業員ではなく、業務委託の個人事業主。
運搬手段や運ぶ運ばないは個人の自由で会社に縛られているわけではありませんし、好きな時に好きなだけ働けるという形態が副業にマッチしていることで近年、脚光を浴びています。ちょっとかっこよく「ギグワーク」といったりしますね。
しかし、配達人が供給過剰になったと称して大幅な単金(運搬距離あたりの単金)の切り下げが実施され、問題になっています。
じつは、供給過剰であろうがなかろうが、発注側は配達人が足りなくなるギリギリまで、単金の切り下げができる。
不況で働き先がなくなると、安値でも請け負う人がどんどん出てきて、ほっといても賃金は下がる。
労働の対価を、市場価格に連動させようというわけです。

が、石油や株のように人件費を市場価格にダイレクトに連動させると、収入が不安定になり実生活が安定しません。
なにより、労働を市場で売り買いする、という形態は、そのまま「奴隷市場」と同じ構図です。
人間の生活は株のような投資対象ではないのに、「ギグワーク」はそういう状況を生み出しているように見える。
個人事業主とかいっておだてておいて、人間を株券と同じに扱おうとするのが「ギグワーク」というビジネス形態なのではないか、と疑っています。
発注側と受注側が一対一の対等な関係ならいいのですが、大資本対多数の個人事業主という関係は相当問題があるような気がしています。
ボディケア業界も、タクシー業界も、ウーバーイーツも、
・一定数の人間を確保してはじめて成立するビジネスであること
・画一的なサービス内容が要求されること
から、その実態はまぎれもなく労働集約型のビジネスモデルです。
たくさんの人を集めないと成立しないビジネスなら、ちゃんと雇用契約を結んで、社会保険等の負担をしないとダメですね。

セラピストにとって報酬は事業収益なのか、あるいは労働の対価なのか。
異論は多々あると思いますが、私は労働の対価、すなわち賃金であり給与だと思います。
長々と書いてしまい、失礼しました。
かえって混乱させてしまったかもしれません。
発注側にとって自社社員の人件費は固定費ですが、歩合制のセラピストへの報酬は変動費です。
お間違いなきよう。
あ、それから、テキストでは広告宣伝費が変動費に入っていましたが、たとえば、貸し看板の費用などは固定費です。
売上に応じて変動する広告宣伝費とは、たとえば割引券やおまけの粗品など、売上とともに発生する宣伝目的の費用があれば変動費ですね。
ということで、今日はこの辺で。
※実際に出題された問題は「重要問題」として、収録しました。