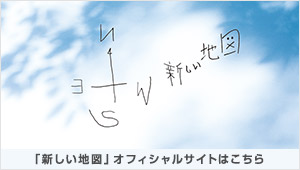不確実性の快楽のうしろめたさについて|中野信子「脳と美意識」
東京芸大・上野校地のすぐ隣に、京成電鉄の旧博物館動物園駅という、小さな廃駅がある。現在は、金属製の扉に施錠がされており、中に入ることはおろか覗き見ることもできない。利用者の減少により営業が停止されてから20年以上は経っている。
もしかしたら、これがかつて駅だったことを、知らない人のほうが多いかもしれない。
西洋風の、明るい色の小さな石作りの駅舎はどことなくやさしげで、愛らしい。動物園や博物館を見に来る家族や恋人たちを穏やかに出迎えるような、あたたかみのある佇まいだったのだろうと、往時が偲ばれる。開業は戦前の1933年のことである。
この前を通るたびに、中に入ることができないかなあ、とひそかに心をときめかせる人がたくさんいたはずだ。その思いの結実が、この駅の復元事業である。昨年から、期間限定でアートイベント時にここが開放されるようになった。事業についての短い解説は、駅舎の外側にあるブロンズ色のプレートに書かれている。
この記事を読んで初めてこの駅の存在を知った人も、今はもうない幻の駅に、期間限定で入ることができる、となったら行ってみたくなるのではないだろうか。
実は今、ごくわずかの間だけは(2019/10/18-11/17の金土日祝、10:00-17:00まで)、中に入ることができる。駅舎内で、スペイン出身の作家2名による作品展「想起の力で未来を:メタル・サイレンス2019」が開催されているからだ。このイベント期間中は、駅の扉は開かれていて、普段は見ることのできない駅舎の内部に入っていくことができるのだ。展示されているのは、クリスティーナ・ルカスの《Unending Lightning(終わりえぬ閃光)》という映像作品と、フェルナンド・サンチェス・カスティーリョの《Tutor(テューター)》という彫刻の2点。
ルカスの作品にはショッキングな映像も含まれていて、やや見る人を選ぶかもしれない。3つの大きなスクリーンにそれぞれ、 ビッグデータから可視化された世界各地の空爆の歴史(1911年の世界初の空爆から最新のものまで)、空爆の日付や場所、犠牲になった民間人の数や記録写真が順に表示される。
いずれの作品もインパクトのあるストーリーがあり、記憶の堆積のようなこの場所が、人類の重要な歴史を記憶に残そうという試みのアートと相和するとして使われるのもある意味自然なことかもしれない。
一方で、おそらくは日本人独特の、鉄道へのほのぼのとした憧れや郷愁は、戦争の記憶とはどこか混じり合わないようにも感じられる。廃駅になった理由は戦争や内乱等ではなく、少しずつ訪れた社会の変化による利用者の減少だからだ。
この駅は、修復を手掛けた人たちの粋な計らいで、落書きや壁の汚れなどもできるだけ当時の状態で大切に残されている。さながら、タイムカプセルのようだ。書き込みをされていた一人のお名前を調べてみたら、芸大の油画を卒業されている私と同年代の方で、現在は画家として活躍されているらしかった。そのほかに書き残されたメッセージも、この駅への愛惜の思いであったり、一緒に訪れた相手と愛を誓い合う言葉であったりと、どれもあたたかなものばかりだった。もしも私ならここにはもうすこし詩的な作品を展示したいなと素朴な感想を持った。
もちろん、反戦や人権などの社会的なメッセージを含むのが世界的なトレンドということもあるし、インパクトの強い作品で集客力をより高めたいという気持ちもよくわかる。また第二次世界大戦中、ヴァルター・ベンヤミンが、ナチスに対抗するために芸術家は社会主義と手を結ぶ必要があるという趣意の言説をとなえた。社会と芸術の問題はこれからも語られ続けるだろう。
ただ、個人的には、あまりそうしたセンセーションによって人の耳目を集めるというやり方は好みとはいえない。主張の是非は当然、別問題として切り分けるべきだろうけれど。
ルカスとカスティーリョの作品はさておき、ある主張の存在があまりに前面に押し出されると、美学的な問題は後回しにされることがある。それが現代アートというものだよと言われればそういうものなのだと頭で理解はできる。
一方、放っておいても目が行ってしまうような魅力があるか、シンプルにカッコいいかというと疑問が残るものもアートとして展示する意味があるかどうかと引いて考えてしまう観衆が多いというのはごく自然なことで、それを責めるのはむしろ呈示する側の力量の程度が露わになってしまっているということにほかならない。アートの専門家たちに「大衆はいまだにそんなことを言っている」という声が聞かれるのは残念なことのように思う。アカデミア側の主張や真意がほぼ理解されていないのを、大衆の責任として帰属するのはたやすいが、本質的には一体どちらの力不足なのかという問いが立つ。
イデオロジカルには私は極めてシニカルな態度を取り続けている。無論、アクティビストとアーティストの共通部分があってもいいし、双方をこなす人がいるのを否定しようとは思わない。腐るほど議論されて来ているところだろうから多くを語ることはすまいと思うが、アートと運動というのは少なくとも、局所的に重なりはしても、完全に一致するようなものではあり得ないだろう。
駅の階段の踊り場にはガラスの扉があり、かつての切符売り場とホームをガラス越しに見ることができる。きっぷうりば、というひらがなで書かれた文字を見るだけで、懐かしさでいっぱいになってしまう。この駅を愛していた人たちの落書きもひとつひとつの点や線すらいとおしいような感じがする。その感覚に静かに立ち返ろうとする心の動きをそっと支えるような空間こそ、むしろ平和を唱えるのなら根源的に必要なものなのではないだろうか。
「脳と美意識」 即身仏
ロボティクスや拡張現実を駆使してイマージュの可能性を探求するフランス人アーティスト、ジュスティーヌ・エマールと知り合う機会があり、しばらく前から親しくしている。ジュスティーヌは英語を流暢に話すけれど、私がフランス語を忘れないようにしたくてフランス人と見るとフランス語を使うようにしているので、それに付き合ってフランス語で話してくれる。適切な表現がわからないときは私の足りないところを補ってくれるし、気を遣って手加減してゆっくり話すということもないのでとても気楽に話すことができる。話の内容も、考えていることも面白くて、彼女といるとずっと昔からの友人のような感じがして楽しい。
今月、彼女が森美術館の展示「未来と芸術展」(2019.11.19-2020.03.29)に出展者として来日するというので、会おうという話になった。ただ会って食べたり飲んだりするだけではもったいないので、声を掛け合って都合をつけ、科博(国立科学博物館)で開かれているミイラ展を観に行くことにした。
彼女は池上高志・石黒浩・森山未來の各氏らと共に、2017年に《Reborn 生まれ変わる》というビデオインスタレーションを発表している。生と死の問題を直接扱っているのではなく、アルターエゴとしての人工物に出会った時、人はどうなるのか、というテーマの追求で、新しい自分の誕生、というのがこの作品の主眼であった。ただ、彼女も理系女子的なところが多分にあり、ミイラという存在そのものや、こうした葬送の様式には元々興味があったようだった。
展示の中で特に私たち二人が強い印象を受けたのは、第一会場の最後に展示されていた福島県浅川町の貫秀寺で普段は拝観することができる弘智法印宥貞の即身仏だった。
朱色を基調としたきらびやかな法衣を纏った宥貞が放つ、異様なまでの輝きに圧倒された。生命を終えてなお、見る者にただならぬ気迫を伝える姿は、ただそこに鎮座する仏の佇まいというよりは、衆生救済のために我が身を燃やし続けようとする修行者のそれであるように感じられた。
私が彼の来歴について説明すると、ジュスティーヌは息を呑んで、フクシマ……と呟いた(弘智法印宥貞が入定したのは福島県浅川町)。もちろん原発事故とは何ら直接の関連のない人物だが、それだけ福島という場所が、海外から見るとインパクトを持つ土地であるのだということを改めて感じた。
弘智法印宥貞は出雲国に生まれた、戦国時代末期から江戸初期の人である。青年期に諸国行脚の旅に出て、出羽三山の奥の院である湯殿山に立ち寄った際、衆生救済のための捨身成仏の風習に触れ、非常に大きな影響を受けたという。
のちに移り住んだ地(現在の福島県浅川町)では村人のために加持祈祷をして過ごし、人々に慕われたという。しかし、村でひとたび悪疫が流行すると、人々を救済しようと疫病治癒を祈願し、我が身を薬師如来と成さしめんという決意のもと、入定したと伝えられている。
即身仏について、ジュスティーヌは初めてその風習を知ったらしく、大きな衝撃を受けていたようだった。日本人としてごく表層的にではあっても知識を持っていた私ですら、かなりの動揺を感じるほどの力強さがあったので、それまで何も知らなかったのならなおさら、その印象は強く鮮烈であっただろうと思う。
3000年を一気に旅したね……と見終わった後の心地よい脱力感の中で感想を伝え合った。この長い長い時間の旅を、遠く離れたフランスと日本の人間が数時間でできるというのも科学の力だね、などと芸術と科学のこと、これからの人間のこと、ポストヒューマンの問題についても語り合い、何とも言えない充実した感覚を味わった。