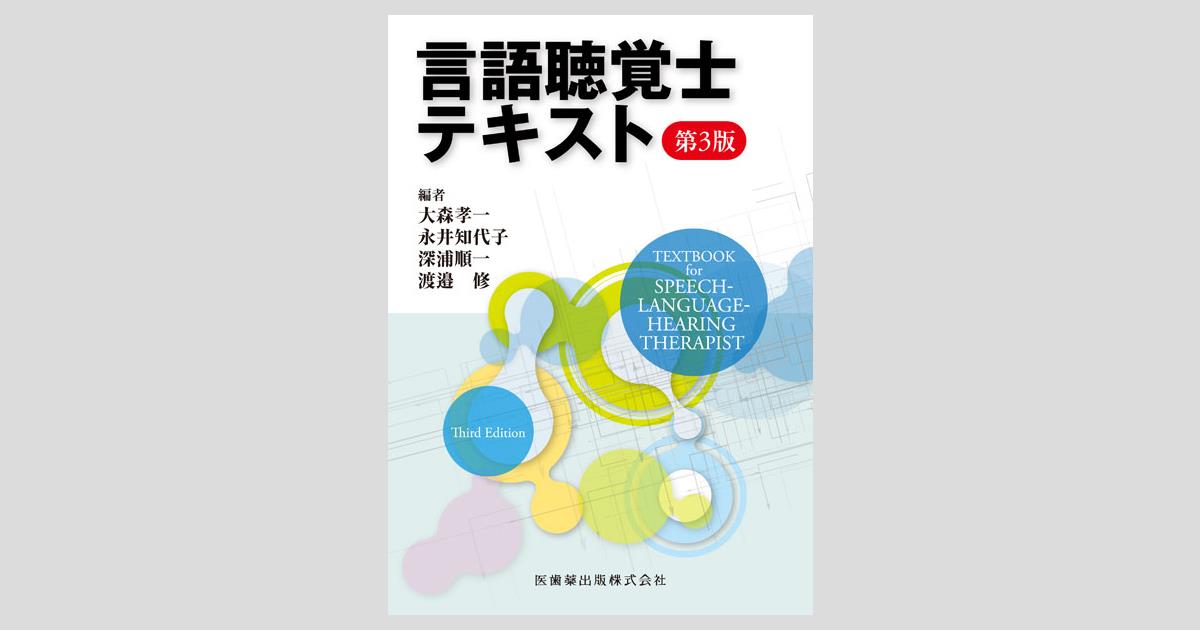言語聴覚士の資格試験用の教科書.
これはB5判と大判で2段組み,全437ページ.
目次は上のリンクから見れるが,
簡単には以下のよう.
ーーー
I 基礎医学
II 臨床医学
III 臨床歯科医学
IV 心理学
V ことばの言語学的基礎
VI 社会福祉・教育学
VII 言語聴覚障害学総論
VIII 成人言語障害学
IX 小児言語障害学
X 聴覚障害学
XI 発声発語障害学
ーーー
索引によれば,自閉症スペクトラム障害は,3か所.(p295,296,303)
一か所目(p295)は,簡単に,神経発達障害群のひとつとして自閉症スペクトラム障害を出しただけ.
2か所目は,13行で自閉症スペクトラム障害がDSMの最新版が古い版とどう定義が変わったか説明されている.
3か所目は,ここがこの本で一番詳しく載っているところだが,それでも53行.
内容はと言うと,TEACCH,応用行動分析,インリアルという指導方法が説明されているだけ.どれも浅い記述.まあ言語聴覚士名乗るなら,これらの言葉を聞いて初めて聞きましたなんて顔されちゃ困るよ,程度の知識.どれだけ効果があるか有効性などの話は無い.たんに存在してる指導方法を述べただけ.
言語そのものに学究的興味がある人なら読んで面白いことはたくさん書いてあるが,いざ言葉の遅れている自閉症児に役立つ情報は,となると,ほとんど書かれていない.
話すことが出来ていた大人がある時事故や老化などで話せなくなった場合の指導法が多い.
自閉症児の言語指導に役立つところを探すと,
IX小児言語障害学(p291-318)
XI発生発語障害学ー2.小児構音障害(p377-385)
XI発生発語障害学ー4.吃音(p396-403)
この程度だ.
最後の吃音は厳密には自閉症には入れないとすると,上の二つだけ.
その吃音にしても,メカニズムや理論は別にして,指導・訓練となると,
p401-403にあるだけ.
幼児期に対して23行,小学生に対しては15行しか記述がない.
吃音から離れて,自閉症児の言語指導をIX章から探すと,結局さっきのp303の自閉症53行の記述になる.TEACCHとABAとインリアルアプローチの用語説明だけ.